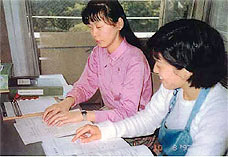印刷業での障害者の特性を生かした職場の開発事例
2002年度作成
| 事業所名 | 株式会社サンイチ工芸社 | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 千葉県松戸市 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | スクリーン印刷業 主要製品は商業印刷物、透明樹脂加工点字印刷物、スクリーン3D印刷物、その他の特殊印刷物 | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 27名 | |||||||||||||||||||||
| うち障害者数 | 4名
|
 |
1.事業所の沿革
|
2.障害者雇用の取組みの経緯
| 社長自身の障害者のボランティア活動の中で、障害者及び家族の苦しみに接し、障害者の職業的自立、社会参加の促進を決意した。以来各種障害者団体との接触により、社内で障害者にむいている仕事は何か、求めるものは何かを検討し、自立した障害者による、障害者及び社会に役立つ製品及び職場の開発、拡大に努めてきた。 昭和52年、全社的な検討の結果、印刷工程の機械作業以外の手刷り作業に、聴覚障害者を雇用することを決定した。公共職業安定所の紹介で初めて、他社の退職者を中途採用し、職場環境の整備を行い、健常者と変わりない戦力となることを体験した。その経験を生かして、全社の理解と協力を得て、現在までに3名の聴覚障害者の印刷工程の職場開拓に取組んできた。 また、平成5年に開発した透明性樹脂加工による点字印刷物が軌道に乗ってきたのに伴い、印刷版の校正及び製品の検査を点字が読めない健常者がやることの困難さがでてきたので、平成10年に視覚障害者を採用し、彼女が支障なく仕事を遂行できるよう校正、検査の重要な業務の環境を整備して、視覚障害者の特性を生かして、新事業の拡大を図ってきた。 |
3.取組みの内容
(1)聴覚障害者の受入職場の環境整備 |
| [1] 作業マニュアルの改善 健常者とのコミュニケーションがとりにくいため、眼で見て分かりやすい作業のポイントを作業現場に貼り付けて、聴覚障害者に分かりやすくした。 [2] 作業指示方法の改善 職場には手話の使用できる人がいないため、手話は使用せず、文書、身振り、手振りで間違いなく指示できるように指導者と本人と徹底的に摺りあわせを行い理解を深めて、仕事の指示に支障のないようにした。 [3] 報告・連絡方法の改善 筆談、身振り、手振りを主として、根気よく、コミュニケーションのルールづくりを行った結果、本人からも積極的な提言がでてくるようになった。 [4] 聴覚障害者の教育・訓練 指導者が筆談、身振り、手振りを交えて、現場、現物で、やってみせ、やらせてみせるOJT教育・訓練を行って、作業上のミスを防いだ。 最初は材料の移動、印刷版の洗浄、梱包作業等の補助作業に慣れさせてから、印刷工程の作業に就けた。 また、1回/週に職場の作業会議を開き、皆で問題点等の協議を行って、意思の統一を図っている。 |
(2)視覚障害者の受入職場の環境整備 |
| [1] 視覚障害者及び社会に役立つ新製品の研究開発 平成5年から各種障害者団体の協力を得て、視覚障害者及び関係者用の透明樹脂加工点字印刷物の新製品研究開発を行い、平成8年に販売を開始した。これは点字が透明であることから印刷製品には何の影響もでないため、調理の本、薬のパッケージ、行政のパンフレット等の市販されている製品に活用されている。 [2] 点字校正機の導入による視覚障害者の職場開発 視覚障害者の特性を生かして、点字校正機を導入し、上記新製品の生産に重要な印刷版の校正及び製品の検査業務を開発し、製品の品質向上に役立てた。さらに、視覚障害者の立場からみた製品の開発や生産上の留意事項のアドバイスを生産現場に行う等の生産管理上で重要な役割も担っている。 |
|
| [3] 視覚障害者の教育・訓練 点字校正機の操作については、経験者であったので特に研修を受けさせる必要はなかったが、新制度による国家資格として、点訳資格を受験させた。難関を突破して合格し、点訳の業務も手がけている。 [4] 通路、作業場等の安全の確保 本人の定位置は2階の事務所内にして、通路の確保、職場内の障害物の撤去等の整理・整頓を行い、本人の確認なしに物を移動しないように配慮した。 仕事の連絡は、現場の作業者が事務所に出向くことを原則とし、本人が現場に行く必要のある時のみ健常者が誘導することとした。 |
(3)全社的な障害者の受入環境整備 |
| [1] 障害者の採用 当社の該当職場に必要な技術、能力があり、職業的自立ができる人物を面接により選抜して採用している。 聴覚障害者の最初の採用時には、手話通訳者をボランティアでお願いして意思疎通を図った。 [2] 障害者の配置 障害者一人ひとりの適性を考慮して、配置を決定している。 一級聴覚障害者は、手作業の印刷を2名、手動の点字打刻を1名が職場内で孤立しないように、同一作業所内に配置している。 視覚障害者は、事務所内の入り口から直行10歩の位置で、視覚障害者にとって最適の印刷版の点字校正、製品検査の業務に配置している。 [3] 障害者の能力開発 障害者も健常者も共に生きる、育つことをモットーとして、1回/週の職場作業会議を通じて、お互いの能力開発を行っている。また、必要に応じて、外部研修に参画させて、レベルアップを図っている。 [4] 賃金・労働時間等の労働条件 障害者も正社員として採用し、賃金は月給制とし、その他の労働条件も健常者との差別はしていない。 [5] 定年・継続雇用 正社員の定年は、60歳である。 定年後の継続雇用は、本人と合意の上、実施している。 [6] 安全衛生・健康管理 安全については、1回/週の職場作業会議で注意事項を協議している。 職場内での事故はないが、通勤時の安全には留意し、万一の場合には携電話での連絡方法も知らせている。 健康管理については、全員2回/年の指定病院での定期健康診断の後に、保健婦が来社して面接指導を実施している。 [7] よい人間関係づくり 1回/月の全社の朝礼で、社長が社是である障害者の職業的自立、社会参加の促進と相手の身になって考えて、協力し合うことについての理解と啓発に努めている。 その他のコミュニケーションとしては、3階の食堂での毎日の会食や年2~3回の食事会やボーリング大会等を実施している。 |
4.取組みの効果
(1)聴覚障害者の新規な就労職場の開拓と拡大 |
| 作業の現状を把握し、聴覚障害者の就労の問題点を分析し、対応策を立案して、環境整備及び教育・訓練を実施したことで、品質・作業・安全面での問題を解決し、当社で初めての障害者の印刷工程での就労職場が開拓でき、この経験から、さらに聴覚障害者の雇用拡大ができた。 |
(2)視覚障害者の新規な就労職場の開拓 |
| 視覚障害者用の透明樹脂加工点字印刷物の研究開発を行い、視覚障害者の特性を生かして、印刷版の校正及び製品の検査業務を開発し、担当させた結果、製品の品質が向上し、顧客の信頼を得て、事業の拡大に貢献できた。 |
(3)全社的意識の改革 |
| 全社的な取組みにより、障害者も健常者と変わらずに自立して就労できることに成功して、全社的な障害者に対する理解と協力意識が高まった。 |
5.今後の課題・展望
|
6.まとめ
| 聴覚障害者については、職場に手話ができる人がいなくても、採用時はボランティアの協力を得て、職場では筆談などで意思の疎通を図り作業手順を確実に指導すれば、その後の工程での主要な仕事でも支障なく遂行できる良い事例である。 視覚障害者については、点字を活用した業務を効率よく進め、かつ、全盲であるにもかかわらず健常者によるジョブパートナーも移動するときだけ付き添う程度なので、それほど事業主の負担にならない良い事例である。さらに、透明樹脂加工印刷物の事業拡大により、視覚障害者が重要な役割を担う雇用の拡大に繋がることも期待できる。 |
| 執筆者:経営士・中小企業診断士・技術士 川崎 秀雄 |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。