関係機関の連携で支える障害者雇用
2002年度作成
| 事業所名 | 協越化学株式会社 | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 福井県坂井郡 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | プラスチック製造業 | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 20名 | |||||||||||||||||||||
| うち障害者数 | 16名
|
 (広びろとした敷地に工場が広がっている。) |
1.事業所の概要
| 日本経済の成長が鈍り、障害者の雇用にも大きな影響があらわれている。多くの現場で障害者がリストラにあっているが、そうした中で、重度障害者雇用に積極的な協越化学(株)の取り組みや背景を探ってみたい。 協越化学(株)は、福井県と石川県の境である坂井郡金津町熊坂に位置する。周辺は山林と田畑に囲まれたのどかな郊外であるが、福井県の主な幹線である国道8号線に隣接し、北陸自動車道金津インターに近い。協越化学(株)はプラスチック製造を主な事業内容とした企業であるが、昭和59年2月ごろから知的障害者の雇用を始め、平成10年頃までに16名の雇用を引き受け、現在に至っている。 |
2.取り組みの背景
 最初は、バブル期には一般の従業員が集まりにくかったことや、知り合いに頼まれたりしたことが、障害者雇用のきっかけであった。しかし、多くの困難や試行錯誤を乗り越え、今日では一人一人が製造ラインの大きな力となっており、障害者の多数雇用の現状に至っている訳である。 最初は、バブル期には一般の従業員が集まりにくかったことや、知り合いに頼まれたりしたことが、障害者雇用のきっかけであった。しかし、多くの困難や試行錯誤を乗り越え、今日では一人一人が製造ラインの大きな力となっており、障害者の多数雇用の現状に至っている訳である。社長の長谷川氏は、プラスチック日用雑貨は、外国から安価なものが大量に入ってくる時代であり、その製造業としての事業経営は大変苦しい状況である。しかし、少量・多品目でコツコツやっていけば、活路はあると述べておられる。 そして今後も障害者を解雇する方法は採らずに、ラインが止まれば、交代で出勤してもらうなど、工夫して雇用を継続させて行きたいと述べておられる。また、休日が多くなると勤労意欲がなくなるタイプや、動的な活動を好むタイプ、ゆっくりなら取り組むタイプなど、一人一人に合った形態も見極めながら、就労形態を工夫して継続して行きたいとも述べておられる。 |
3.取り組みの内容及び効果
 知的障害者を雇用することは、他の障害者の雇用と比べ、実践に結び付けるまでに時間がかかり、実際の配置までスムーズに行かないことが多い。また、生活指導(健康管理や金銭管理など全面にわたる場合もある)まで必要なケースもあり、他の従業員の協力を得ることも、困難なことが多い。そのような中で、協越化学(株)がどのように、多数雇用に結び付けていったのか、その現場に伺って考察してみた。 知的障害者を雇用することは、他の障害者の雇用と比べ、実践に結び付けるまでに時間がかかり、実際の配置までスムーズに行かないことが多い。また、生活指導(健康管理や金銭管理など全面にわたる場合もある)まで必要なケースもあり、他の従業員の協力を得ることも、困難なことが多い。そのような中で、協越化学(株)がどのように、多数雇用に結び付けていったのか、その現場に伺って考察してみた。 |
(1) 最初の取り組み(雰囲気作りがポイントになった) |
 障害者支援に対する特別な知識や支援体制があって最初の雇用が始まったわけではなかった。しかし、一般健常者が集まりにくい状況下では、ラインを動かすために障害者を特別視することなく、やれる仕事を必死でみんなが、探ってきたという感じであった。20名ほどの従業員であったし、社長自らやってみせるという姿勢が、障害者自身だけでなく、周囲の従業員にもよい影響を与え、障害者自身が溶け込みやすい雰囲気を作ったようである。 障害者支援に対する特別な知識や支援体制があって最初の雇用が始まったわけではなかった。しかし、一般健常者が集まりにくい状況下では、ラインを動かすために障害者を特別視することなく、やれる仕事を必死でみんなが、探ってきたという感じであった。20名ほどの従業員であったし、社長自らやってみせるという姿勢が、障害者自身だけでなく、周囲の従業員にもよい影響を与え、障害者自身が溶け込みやすい雰囲気を作ったようである。多くの現場で、雇用を決めた管理者の考え方が十分に現場に伝わらずに、障害者の雇用が失敗する例を見てきたが、協越化学(株)の場合、管理者自らが障害者に製品づくりの見本を見せ、共に汗を流し工夫をするという態度が、知的障害者雇用の定着をスムーズにしたようである。 |
(2)知的障害者を多数雇用して(他との連携を支えとして) |
 2名の知的障害者が力を発揮したことや、他の従業員が集まりにくい状況が続いたこともあり、周囲の福祉施設(知的障害者通勤寮)や養護学校等から知的障害者の就労希望が集中しだした。しかし、障害者の従業員が多くなるにつれて、トラブルも多発するようになった。知的障害者への支援体制も知識も十分でないまま、人数を増やしてしまったために起こったトラブルであった。こうしたケースで失敗し、障害者の雇用が止まってしまう企業を、筆者はいくつか見てきた。そこを協越化学(株)は、どう解決してきたであろうか? 2名の知的障害者が力を発揮したことや、他の従業員が集まりにくい状況が続いたこともあり、周囲の福祉施設(知的障害者通勤寮)や養護学校等から知的障害者の就労希望が集中しだした。しかし、障害者の従業員が多くなるにつれて、トラブルも多発するようになった。知的障害者への支援体制も知識も十分でないまま、人数を増やしてしまったために起こったトラブルであった。こうしたケースで失敗し、障害者の雇用が止まってしまう企業を、筆者はいくつか見てきた。そこを協越化学(株)は、どう解決してきたであろうか?例えば、不良品を大量に作ってしまった。(これは生産ラインの中で、チェック機構を作らないとか、作業導入をしっかりしなかった結果であった)女性の障害者がトイレにこもって出てこない。(生理の指導が、十分でなかった)障害者が無断外出してしまった。(職場や家庭でのトラブルや、人間関係のトラブル相談の体制づくりが、十分でなかった等)健常者は、作業ラインの管理以外に、知的障害者のトラブルの後始末に負われ、イライラした状態が見られるようになった。雇用が少なかった時代には、一人一人の能力や、性格の違いの状況を見極めることも可能であったが、それが不可能になってきた。場合によっては、生活の支援や指導まで、必要な事も起きてきた。そのため、健常者が障害者と共にと云う雰囲気も、薄くなってきた。そこで、こうした状況を解決するために、関係者の話し合いが開始された。 例えば、作業プロセスの失敗に対しては、担当者を決めて作業工程を点検する等と云うアドバイスを、関係機関の指導を受けて実施した。また、現場でのミーティングでも、チェック体制の確立などに努めると共に、障害者一人一人のパーソナリティ把握に努めた。そのため、家庭や福祉施設・出身学校の当時の担当者と情報を交換するなど、他との連携を強めてもいった。 つまり、トラブルを、企業の中で解決しようという姿勢から、他との連携をも使い解決を図っていくやり方に、変えていったのである。ハローワークや障害者職業センターばかりでなく、出身の学校や通勤寮などの福祉施設とのネットワークも、確立していった。家庭問題が日中の活動に影響していることもあり、保護者の見学会や懇談会も、アドバイスを受けて実施した。 精神薬や内科的な薬の投薬を受けている方の雇用例もあり、一企業の支援だけでは、とても支えられものではないと、島田工場長も述べられている。むしろこうした専門的なネットワークを使うことによって、障害者にも安心して働いてもらえると、述べておられる。プラスチックの形成は単純な作業の繰り返しでもあり、こうした雇用体制を作れば重度の知的障害者でも就労が可能な部分がたくさん見えてきたということであった。こうして現在の16名の雇用が成り立ってきた訳である。 もちろん平坦にスムーズに行ったわけではないが、社長以下分け隔てのない考え方が、障害者が働きやすい環境を作ったようである。障害者と直接接している従業員も、たまたま障害者が居ただけと言われるが、そこにたどり着くまでには、大変な苦労の連続があったように感じられた。そこを乗り越えてこられたのは、多くの関係機関の連携があったからだと感じられた。多数雇用のための努力は、たくさんあると思われるが、大きなポイントは以上のような点にあると考えられた。 |
4.今後の課題、展望等
| プラスチック製品の製造と云う業種そのものが、現在構造不況の渦の中にあり、経営状態も厳しい状況にあることが現場に伺い、ひしひしと感じられた。一般的に障害者だけでなく、一般健常者も労働時間の短縮や、賃金の低下に喘いでいる事が報道されている。しかし、一生懸命に働く障害者のためにも、経営基盤の強化が求められているところである。これといった決め手はなく、コツコツとやるだけだと、長谷川社長は述べておられたが、障害者の雇用安定のために、更なる経営努力に期待したい。 しかし、一方現場の従業員には、プラスチックの日用雑貨の製品作りに対する誇りは失われておらず、安価なものでも一生懸命よいものを作ろうという、労働の原点は失われていなかった。新たな設備投資や、異種産業への展開が必ず良いとは限らない。回り道でも培った実績と、連携のとれた社内人間関係、そして関係機関の連携で、障害者の雇用を支えていくことも、大切とも感じられた。 現場で働く障害者にインタビューしてみると、口をそろえて、給料よりも働く場の確保を希望しており、雇用の安定に関係機関がスクラムを組んでほしい。 なお、障害者の雇用状況のデータは、以下のとおりである。 |
| 執筆者:社会福祉法人 至誠福祉会理事長 高尾 誠 |
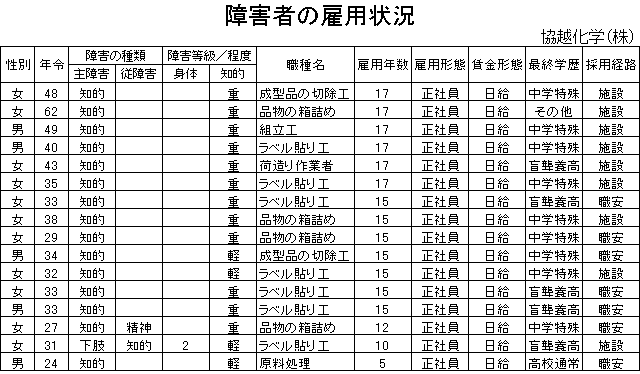 |
![]()
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











