障害者の働き易い職場環境特にソフト面の整備
2002年度作成
| 事業所名 | 株式会社スミセイハーモニー | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 大阪府大阪市 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 業務内容は住友生命の事務代行であり、(1)書類の点検・整理・保管・抽出(保全書類管理グループ)、(2)マイクロフイルム撮影(マイクログループ)、(3)福祉事務所からの照会対応とイメージ作成(サービス業務グループ)の3グループに分かれている。 | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 36名 | |||||||||||||||||||||
| うち障害者数 | 30名
|
1.取り組みの経緯、背景
| 特に、ソフト面の工夫として、 [1]お互いを助け合う風土の醸成、 [2]コミュニケーションギャップへの対応、 [3]本社各部門 との連携の3点が、設立当初より取り上げられており、今回事例収集させて頂く動機の一つとなった。 |
2.取り組みの内容及び効果
(1)募集・採用 |
| 設立と同時に25名の障害者募集を行ったが、担当者の心配とは逆に253名の応募、240名の受験があった。1次試験は簡単な筆記試験と面接を行い、2次で「本人の意欲と協調性」を中心に再度面接を実施し、最終的に3次で意思確認を行い、採用を決定した。5名増員の30名を採用することになったが、これほど応募者があったのは、大阪を中心に近県も含め20の公共職業安定所を訪ね、趣旨説明を行い、協力を求めて回った成果である。 |
(2)配置・定着・職場適応 |
| 業務開始後1年強なので、配置転換や定着にかかる特別の取り組みはしていない。ただし、就職当初は定時までに欠勤の連絡が無い、といった職業生活の「基礎の基礎」が不十分な者もいた。聴覚障害者がファックス操作をミスした等、やむを得ぬ場合もあったが、就業経験がない中で「会社のルール」がまだ充分身についていないことが原因の者もいた。そこで、当事者の置かれてきた状況をこちらが理解した上で、粘り強く説明していった。その結果、後者の理由による無断欠勤などは、1年たって無くなった。 |
(3)能力開発 |
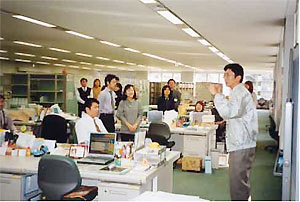 職員に必要な力を三階層に分けて考えている。[1]仕事をきちんとこなす力、[2]企業人として良識ある判断・行動のできる力、[3]社会に生きる人、あえて言えば人間として尊敬されうる考え方や行動のできる力、である。これらに対応する形で、例えば、[1]については3人のグループ長がOJTで仕事のノウハウを伝え、[2]については2人の部長(山口部長と、金山敏一取締役総務部長)が朝礼のスピーチや週間報告へのコメント記入によって指導を行い、[3]については社長が毎週メールで訓話を送っている。しかもメールに対しては返信を義務づけ、社長との対話を通じて、成長を促している。このように能力の三階層を、役割分担の上、開発しようと試みており、いずれ障害当事者の中からリーダーが生まれることを願っている。また、事業所の特長の一つには、「お互いを助け合う風土の醸成」がある。グループ編成・配席は障害部位を混在した形で考えられていて、車いす利用者が困難な荷物の上げ下ろしは聴覚障害者が行い、逆に電話応対は車いす利用者等がするなどの協力がなされている。これも、「他人のハンディに対する思いやりを共有していく」という、社会人、人間としての能力向上の一環である。 職員に必要な力を三階層に分けて考えている。[1]仕事をきちんとこなす力、[2]企業人として良識ある判断・行動のできる力、[3]社会に生きる人、あえて言えば人間として尊敬されうる考え方や行動のできる力、である。これらに対応する形で、例えば、[1]については3人のグループ長がOJTで仕事のノウハウを伝え、[2]については2人の部長(山口部長と、金山敏一取締役総務部長)が朝礼のスピーチや週間報告へのコメント記入によって指導を行い、[3]については社長が毎週メールで訓話を送っている。しかもメールに対しては返信を義務づけ、社長との対話を通じて、成長を促している。このように能力の三階層を、役割分担の上、開発しようと試みており、いずれ障害当事者の中からリーダーが生まれることを願っている。また、事業所の特長の一つには、「お互いを助け合う風土の醸成」がある。グループ編成・配席は障害部位を混在した形で考えられていて、車いす利用者が困難な荷物の上げ下ろしは聴覚障害者が行い、逆に電話応対は車いす利用者等がするなどの協力がなされている。これも、「他人のハンディに対する思いやりを共有していく」という、社会人、人間としての能力向上の一環である。 |
(4)安全衛生・健康管理 |
 健康管理については、生命保険会社の子会社なので、人間ドック施設の活用等、恵まれている面があり、車いす介助も看護師が行い、通常と同じ流れで検診を行っている。また、メンタルな部分での悩みの相談も重視しており、3か月に1回、部長が個人面談を行う他、3名のグループ長が日々の関わりの中で、変化を把握している。しかし、それでも、人間関係がうまくいっていないこともある。そういう場合、本人の元気がなくなってくるので、朝の朝礼で顔色を見て、気をつけるようにしている。一方、安全面についてだが、火災を想定した避難訓練を、本社総務部とタイアップして行っている。聴覚障害者用のフラッシュライトも、もちろん敷設している。なお、週1~2回、社長、部長、グループ長の6名で、[1]安全面、[2]健康面、[3]業務の遂行面について、職員一人ひとりの問題・課題を共有するためのミーティングを実施している。 健康管理については、生命保険会社の子会社なので、人間ドック施設の活用等、恵まれている面があり、車いす介助も看護師が行い、通常と同じ流れで検診を行っている。また、メンタルな部分での悩みの相談も重視しており、3か月に1回、部長が個人面談を行う他、3名のグループ長が日々の関わりの中で、変化を把握している。しかし、それでも、人間関係がうまくいっていないこともある。そういう場合、本人の元気がなくなってくるので、朝の朝礼で顔色を見て、気をつけるようにしている。一方、安全面についてだが、火災を想定した避難訓練を、本社総務部とタイアップして行っている。聴覚障害者用のフラッシュライトも、もちろん敷設している。なお、週1~2回、社長、部長、グループ長の6名で、[1]安全面、[2]健康面、[3]業務の遂行面について、職員一人ひとりの問題・課題を共有するためのミーティングを実施している。 |
(5)就業環境の整備 |
| コミュニケーションギャップへの対応としては、手話通訳士の配置(パート雇用)の他、小さなホワイトボードを筆談グッズとして活用している。また、本社の診療所(3F)や食堂(4F)といった福利厚生施設を活用させてもらえることで、作業面以外の就業環境の整備も充実させることができた。ハード面では、他に、駐車場の確保、身体障害者仕様のエレベータ・トイレの設置等を行った。一方、本社の人権担当・人事・教育部門と連携することで、本社の人権教育や障害者雇用へも貢献できているという面もある。 |
(6)その他 |
 「障害者は能力が劣るという既成概念の打破を示したい」という市川社長の言葉どおり、「障害者」と一くくりにすること自体無謀なことである。障害者一人ひとり、能力も意欲も異なるし、また障害者同士もかなりの程度補い合える。また、社会全体が、「障害のある人と共に」というとても良い方向に変わりつつあると思う。特に、公共職業安定所、障害者雇用促進協会、地域障害者職業センター、障害者雇用支援センター等の関係機関や、重度障害者多数雇用事業所、特例子会社等、先輩企業からいろいろ教えられ、また助けてもらえている。このネットワークは、本当に暖かいと思う。 「障害者は能力が劣るという既成概念の打破を示したい」という市川社長の言葉どおり、「障害者」と一くくりにすること自体無謀なことである。障害者一人ひとり、能力も意欲も異なるし、また障害者同士もかなりの程度補い合える。また、社会全体が、「障害のある人と共に」というとても良い方向に変わりつつあると思う。特に、公共職業安定所、障害者雇用促進協会、地域障害者職業センター、障害者雇用支援センター等の関係機関や、重度障害者多数雇用事業所、特例子会社等、先輩企業からいろいろ教えられ、また助けてもらえている。このネットワークは、本当に暖かいと思う。 |
3.ICF(国際生活機能分類)の視点からみた評価と展望
(1)ICF(国際生活機能分類)とは |
| ICF(International Classification of Functioning,Disability and Health)とはWHO(世界保健機関)が2001年5月に、総会で採択したもので、1980年に国際疾病分類の補助分類として発表されたICIDH (国際障害分類:International Classification of Impairment,Disabilities andHandicap)の改訂版である。障害者の活動や参加がなされている状態、もしくはそれらが制限・制約されている状態を、環境因子との関係でとらえようとした点が、大きな特徴である。環境因子とは、「人々が生活し、人生を送っている物的な環境や社会的環境、人々の社会的な態度による環境を構成する因子のこと」であり、それが存在したりしなかったりすることで、促進因子にも阻害因子にもなり得るものである。執筆者は、当該事業所の取り組みをICFの環境因子の視点から評価することとする。なお、本稿においては、「WHO(世界保健機関):ICF(国際生活機能分類),障害者福祉研究会編集,中央法規出版(2002)」から適宜引用・参考にさせて頂いた。 |
(2)ICF(国際生活機能分類)の視点からみた評価 |
| 本稿では、当該事業所における環境因子、すなわち「障害者が働き易い職場環境を整備する」促進因子の内、特にソフト面に注目したいと思う。障害者を多数雇用すること、それ自体も重要だが、当該事業所の優れた点は、設立当初から、人材育成に力を注いできた点である。それも、単に技術的な面で留まらず、社会人として、人間としての成長を願った重層的な能力開発がなされている。換言すれば一挙に30名の障害者を雇用するのであるから、「お互いを助け合う風土の醸成」という理念のもと、前述のような計画的・意図的な教育・能力開発をしていかなければ、現状のような円滑な運営は困難だったろうと推測するものである。また、そうした教育・能力開発がスムースに進んでいく背景には、両部長が3か月に一度個人面談を行うという緻密な人事政策もあるだろう。さて、ICFの視点だが、環境因子には、「態度」という大項目がある。ICFは、「態度」について「例えば、ある人への信頼や人間としての価値に関する、個人的あるいは社会的態度は、肯定的で敬意を示すふるまい、あるいは否定的で差別的なふるまい(ある人に対する烙印押し、決めつけ、排斥、無視)を動機づけうる。」と説明している。当該事業所でも、この「態度」、それも「同僚の態度(ICFのコード:e425)」「権限をもつ立場にある人々の態度(同:e430)」がともに、「(障害者への)肯定的で敬意を示すふるまい」につながり、障害者が業務を遂行する上での促進因子となっていると高く評価できる。さらには、そうした促進因子の背景に、企業としての理念・方針があることは言うまでもないことである。 |
(3)(2)への補足 |
| しかし、上記の点について、「ことさら肯定的で敬意を示すふるまいをしない限り、障害者雇用はうまくいかない」との誤解を招きやしないかという、貴重な示唆を、山口部長から頂いた。正鵠を得た指摘である。山口部長も指摘するように「あらゆる人間関係において、まずはお互いの存在を肯定しようとすることが大変重要」なのであり、あえて「障害者だから特別に『肯定的で敬意を示す』ことが必要」という訳ではない。後者の「態度」は、一歩間違うと「はれものに触る」ような関わりにつながり、結果として障害者に辛い思いをさせてしまう危険性もあるだろう。ICFの記述自身は、障害者に対する特徴的な二つの傾向を例示しているに過ぎないが、実際はもっと幅広く、深いものがある。ただし、ICFの言わんとしていること、つまり周囲の環境の重要性については、当該事業所の場合も、あてはまるものと理解している。また、私があえて(2)で「肯定的で敬意を示すふるまい」と記したのは、不況下においては、障害者に対する否定的な言動が起き易いが、当該事業所の実践は、それに対して説得力をもった反論を示していると感じたからなのである。しかし、当該事業所のめざしているところは、私の評価の視点をはるかに超えた「人間としての人材育成」の地平に到達していたのであり、改めて感服した次第である。 |
(4)今後の展望 |
| 本事例は、特例子会社のケースだが、一般事業所での障害者雇用にとっても有益なモデルとなるものである。一般事業所で障害者を受け入れた際、「関わり方が分からない」「能力が向上しない」といった声を聞くことがある。確かに、障害特性や業務遂行上の課題を把握することも大切である。しかし、今回の訪問及び山口部長とのメールを通したディスカッションを通じて鮮明になった次の点が、何よりも重要であると考える。すなわち、「障害者に否定的な態度で関わることが問題なのは言うまでも無いが、逆にことさら『障害者だから肯定的に接する』ことも、かえって当事者に辛い思いをさせかねない。むしろ他の者に肯定的に接する(あくまで、このことが大前提にあるが)のと同様に、障害者従業員に関わり、人材育成していく視点が必要である」ということである。市川社長の「障害者は能力が劣るという既成概念の打破を示したい」という言葉にも、このポリシーがよく表わされていると実感した。「既成概念」とは、まさに、スティグマ(烙印)に基づく障害者観であり、それを打ち破って、障害者の可能性、共に働く可能性を社会に示そうというスミセイハーモニーの試みに、強く共感するものがあった。既に多くの視察者への説明等で実施されているが、今後も、ぜひ、そうした成果を後に続く特例子会社や、一般事業所に役立つようお伝え頂きたいと願うものである。そのことが、前記の一般事業所の悩みに対する何よりの回答になるものと考えるものである。 |
| 執筆者:箕面市障害者雇用支援センター所長 栗原 久 |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











