養護学校との緊密な連携による雇用と定着
2002年度作成
| 事業所名 | 冨士建設工業有限会社 | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 徳島県徳島市 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 総合建設・生コンクリート製造及びコンクリートブロック製造販売 | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 37名 | |||||||||||||||||||||
| うち障害者数 | 5名
|
 (冨士建設工業(有)生コン製造プラント) |
1.障害者雇用の経緯と背景
| 昭和30年8月より建設業の他にコンクリート二次製品を徳島県下で初めて製造販売を開始した。昭和43年に視覚障害者用の点字コンクリートブロックの製造を計画したことが発端となり、社長から当社の製品で何か障害者に出来るものはないかと検討するように指示があり、県下の障害者施設をスペーサーブロック等5品目の製品見本や型枠を持参し、まずは実習教材として使えないかと訪問したが、当時は、設備費用や設置場所もなくやむなく断念する。 昭和51年に徳島大学附属養護学校(現在の鳴門教育大学附属養護学校)から実習教材を探しているとの問い合わせがあり、早速、学校側と協議を重ね学校敷地内にコンクリートスペーサー製造実習室を学校側が設置し、型枠等の機材とセメント・砂等の資材を会社側が提供することとなり、先生方に技術指導を行うことにより生徒に実習を開始することとなった。 昭和63年からは学校との連携が深まるなか、初めて工場実習を実施した。実習生の仕事ぶりを直接観察することが出来るようになり、また本人、家族の希望で学校から就職依頼があり、会社内では様々な意見があったが、検討を重ねた結果、職場適応訓練を実施後、平成元年にはじめて知的障害者(重度)を採用した。 以降、平成6年・11年・12年・14年に学校からの推薦があった知的障害者を各1名採用し、現在5名の者が全員定着している。また、校外実習指定事業所として雇用の拡大に努めている。 (参 考) 鳴門教育大学附属養護学校実習室 |
|
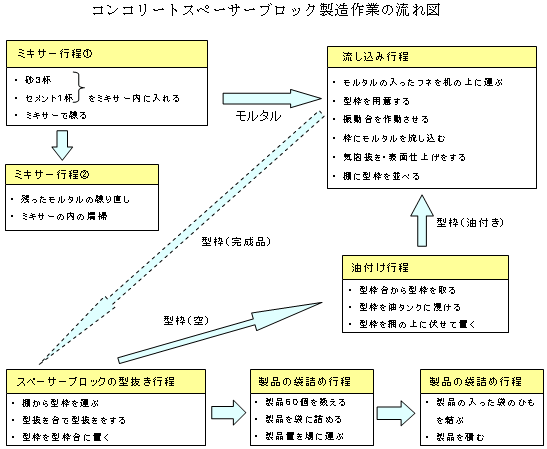 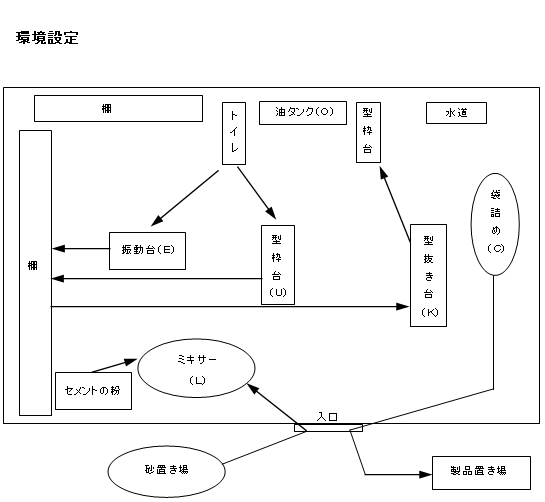 |
2.障害者雇用の現状と取組状況
(1) 障害者の就労状況 |
|
(2)職務内容 |
| コンクリートブロック・コンクリートスペーサー・車止めブロック・クーラー台等を製造するため、型枠組立・コンクリート注入・気泡抜き・表面仕上げ・乾燥・型枠バラシ・製品取り出し・型枠洗浄・製品整理等の作業を行うため、多少体力を要することから、各人の体力・能力・特性等から判断し、それぞれの職務を決めている。 (参 考) コンクリートブロック製品製造作業 |
|
(3)労働条件 |
昇給はアップ率・賞与は支給率によるが、他の従業員と同等にしている。 |
(4)職場定着連絡会議 |
| 月1回会社の定例会のなかにおいて、就労状況等の報告・確認等を行い、指導を要する事項がある場合には即刻対応している。また、職場推進チーム責任者・障害者生活相談員の専務取締役が毎日職場を巡回しながら声をかけて、就労状況、健康状態等を常時把握を行っている。 |
(5)仕事の指示・伝達 |
| 管理職が中心となり、口頭と行動によりやって見せて何回も繰り返し根気よく指導を行う。職域については当初変更を試みたが無理があったので、変更しないようにしている。 |
(6)安全管理 |
| 作業場・通路等の整理整頓、足元に物を置かない、物を立てかけない等についても繰り返し指導をした結果、整理整頓等は自主的に行うようになってきている。 |
(7)生活指導 |
| あいさつ・勤務時間の厳守・作業時の服装・職場離脱しない等について繰り返して徹底した指導を行うことにより遵守されている。 金銭管理面では、給与(現金支給)の支払日の翌日に必ず家族に渡したか本人に確認を行う(本人に自立を促すため家族への確認はしない)。また、職場に持参するのはお小遣いとして1日1,000円以内とし、更衣室に財布を置かず常時身につけておくように指導をしている。 |
(8)通勤指導 |
| 通勤方法は自転車2名・バス等2名・家族の送迎1名となっており、それぞれの通勤経路・所要時間を常時把握している。特に自転車通勤者には交通安全の指導をしている。また、遅刻、欠勤する場合には必ず会社に連絡するように指導している。 |
(9)従業員の意識改革 |
| 当初は「足手まといになるので雇わないでくれ」「それなら健常者を」との意見もあったが、数年経過するなかで勤務態度や仕事ぶりを見て自然に協力体制が出来上がっている。また、定期的に養護学校生徒の職場見学や職場実習・職場適応訓練生の受け入れなどによって自然に理解が出来てきた。 |
(10)家庭との連携 |
| 入社2年目位までは月1回程度の連絡を入れているが、3年目以降については本人の自立を促すため、特別な問題が生じない限り連絡しないようにしている。 |
3.関係機関との連携
| (1) 養護学校とは毎月2~3回実習資材の搬入、製品の引き取り等もあり訪問していることから緊密な連携が保たれており、毎年5月にはスクールバスによる生徒の職場見学の受け入れや校外現場実習指定校として職場実習も毎年実施している。 また、主要学校行事についても協力関係にある。 (2) ハローワークとは、定着指導・職場適応訓練生に対する指導・助成金申請手続き等で担当官・相談員と常時連携をしている。 (3) 障害者職業センターとは、職場実習や職場適応について、カウンセラージョブコーチ等と連絡を密にしている。 (4) 障害者雇用促進協会とは、専務取締役が障害者雇用情報誌「すだち」の編集委員として参画しているほか、協会主催のセミナー・研修会・講習会等には必ず参加し、職場定着推進チーム・障害者職業生活相談員等との連携体制ができている。 |
4.各種援護措置の活用
| 職場適応訓練費・特定求職者開発助成金・徳島県重度心身障害者雇用奨励金・トライアル雇用奨励金・報奨金等についてハローワーク・障害者職業センター・障害者雇用促進協会の指導のもとに、それぞれ該当する援護措置を活用している。 |
5.今後の課題・展望
| 長引く経済不況のなか建設関連産業も公共事業・民間事業も大幅に減少している。産業廃棄物処理費の負担増も重なり大変厳しい状況にあり、経費節減等経営努力に努めている。 現在、職場適応訓練により1名を受け入れており、3月で終了するため、ハローワーク・養護学校からその雇用について依頼を受け検討しているところである。 今後、障害者雇用の拡大については景気の上昇が見込めない限りは困難であり、現状を維持することが精一杯である。しかし、従来から実施している実習教材・資材の提供、職場見学、職場実習等については、引き続き養護学校との連携を保ち実施することによって、就職を希望されている障害を持つ生徒達を支援していくこととしている。 |
| 執筆者:(社)徳島県障害者雇用促進協会 障害者雇用アドバイザー 松田 知周 |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。

















