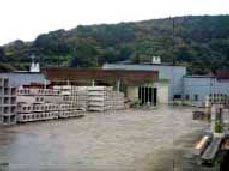積み卸し作業で雇用創出
2002年度作成
| 事業所名 | 有限会社平田工業所 | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 長崎県西彼杵郡 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 窯業・土石製品製造業 主にコンクリート製品の製造 | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 64名 | |||||||||||||||||||||
| うち障害者数 | 22名
|
1.事業所の概要
| (有)平田工業所は昭和28年4月に長崎市住吉町に石材業の個人企業として創業された。さらに昭和36年に住吉町にコンクリート空洞ブロック工場を、40年には時津町の砕石工場に砕石プラントを新設した。その後、拡大を遂げて、昭和43年2月には時津町に道路用コンクリート製品の製造販売開始、昭和44年7月に(有)平田工業所として法人となり、代表取締役に平田文次氏が就任した。昭和56年1月には雇用促進事業団の融資により身体障害者多数雇用事業所としてのモデル工場となり、昭和58年9月には、心身障害者雇用優良事業所として労働大臣より表彰を受けることとなった。そして平成6年7月にコンクリート工場を現在地に新築し本社も現在の時津町に移転した。 また、昭和34年近所の知人の頼みにより、初めて知的障害者を雇用。昭和52年頃から、社会福祉法人みのり会の依頼により徐々に雇用数を増加し、重度障害者を多数雇用している企業として評判となった。採用はハローワーク等からの紹介で行っている。 |
|
2.障害者の雇用状況等
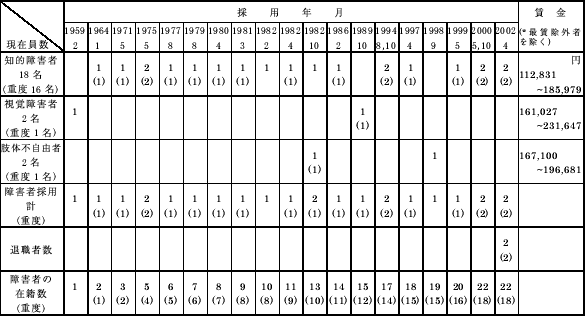 |
3.改善及び工夫の概要
(1)改善・工夫のテーマ |
| 不況でも障害者の雇用創出を図っている。 |
(2)改善及び工夫の概要 |
|
4.特記すべき事項
(1)リーダー(業務遂行援助者)による工場での業務指導 |
| [1] 担当課長または係長の指導により、知的障害者は2~3名で、ペアまたはグループで仕事を担当している。複数で作業する場合、古くから働いているベテランがリーダー格になって指導する。言葉で指導するより、実際に作業をして、見習わせるようにしている。 [2] グループでの作業に向かない社員の場合は一人で作業しても安全な部署に配置している。 [3] 個人の性格の見極めと適材適所の配置で、定着率を高めている。 (1) 塗油の作業工程 型枠に流し込まれたコンクリートが製品となった場合、コンクリート製品が型枠から容易に脱型するように、型枠の内側に脱型油を塗油する。その場合、型枠内側の油の塗りむらや油だまりがないように、予め油に浸したウエス(布)をよく搾ってから、型枠全体を拭きあげる作業を業務遂行援助者が手本を示しながら指導している。 |
|
| (2) 脱型の作業工程 コンクリート製品を脱型するにあたり、内枠・外枠を締め付けているボルトをスパナで弛めて外さなければならないが、対象障害者個々に専用道具をあたえ、脱型後のボルトの管理も含め業務遂行援助者が外すボルトの順序などの脱型方法の手本を示しながら指導している。 |  業務遂行援助者による 脱型作業 |
|
| (3) 型枠組立ての作業工程 製品を均一にずれなく製造するために、鉄製の型枠に目印をつけた。そこに合わせて型枠を組立て、スパナなどの専用道具によりボルトの締め付け作業を業務遂行援助者が手本を示しながら指導をしている。また、型枠組立て終了後、個々の専用道具は所定の場所に整理させている。 |
|
(2) 定着率の高さと欠勤率の低さの秘密 |
|
(3)雇用創出に向けての努力 |
|
|
5.評価
| 平田工業所の事例収集を通じて感じたことは、この企業がいかにして雇用の維持や創出に意を用いているかであった。建設関連、とくに公共土木関係の資材の供給を中心としている業態は昨今の状況下で、厳しい経済環境にあり、売上げ60%減の経営環境にもかかわらず、従業員や障害者の雇用の維持・確保に懸命に努力されていることである。 その秘密は、製品を作り、出荷するまでの動線を、あえて短くせず、あえて、省力化装置を使用せず、人海戦術で対応していることであった。そして新製品の開発や営業努力をそして仕事を、経営者をはじめとして全社員が活き活きと行っていたことが強く印象に残った。 |
| 執筆者:長崎大学環境科学部 教授 浜 民夫 |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。