企業グループ雇用率制度の導入
2003年度作成
| 事業所名 | 横河電機株式会社 | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 東京都武蔵野市 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 電気計測器、測定器、工業計器、科学・分析器。情報システムなどの計測制御及び情報処理に関する装置・システムの製作販売。航空宇宙機器並びにその他産業用機器の製作販売 | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 5,597名 | |||||||||||||||||||||
| うち障害者数 | 63名
|
1.取り組みの経緯、背景
| 平成3年の障害者雇用率は0.98%であり、法定雇用率の1.6%を大幅に下回っていた。当時、企業として障害者雇用促進法を遵守し社会的責任を果たすべきであるという機運があり、平成4年プロジェクトチームを発足し、障害者雇用を積極的に取組み1年間に25名の重度障害者を雇用した。その結果、同年1.22%であった雇用率が平成5年には1.66%と法定雇用率を一気にクリアし、本プロジェクトチームを解散した。 その後、平成9年障害者雇用促進法の一部改正(知的障害者が雇用率に算入、法定雇用率が1.6%から1.8%にアップ等)に伴い、平成11年に「横河ファウンドリー株式会社」を設立し、特例子会社に認定された。設立当初、知的障害者6名を採用、現在は14名に増え法定雇用率を上回った状態を維持している。 人事運営の基本方針は、次の4点で、現在も求人には全ての応募者に門戸を開いている。 [1] 性善説に立つ [2] 真の平等を目指す(性別、年齢、国籍、学歴、障害の有無等属人的なくくりはしない) [3] 長所を引き出す(美的凝視、減点主義を廃す) [4] 小事に拘らず大事を見据える 障害者雇用については、障害による制約は配慮するがその他の事項については障害の有無による区分けは無い。グループ企業全体としては、折からの分社、統合などの変革の時代にどう対応して行くかという課題と障害者雇用の啓蒙を図る為に平成14年10月の法改正「特例子会社を有する親会社は、認定要件を満たせば関係する他の子会社(関係会社)についても、特例子会社と同様、親会社と通算して雇用率制度を適用できる」と同時に、7社によるグループ算定の認定をうけ、平成15年4月には13社に拡大し法定雇用率1.8%の維持向上に取り組んでいる。 |
2.グループ算定導入の理由
| 当社の障害者雇用の基本は、企業の規模による障害者の雇用義務、努力義務に関わらずグループとして「法律遵守」が第一であると考えている。更に、株主オンブズマンから東京、大阪労働局に情報公開法に基づく障害者雇用状況表等の開示請求があり、従来グループ内では障害者雇用に比較的消極的であった企業もグル-プの方針に前向きに取り組むようになった。然し、一方ではグループ企業全体が分社、統合等により事業の再編成が活発に行われる中で工場移転などにより一部に障害者の継続雇用が困難になった企業なども発生している。以上の状況から冒頭の方針を達成する為に段階的にグループ算定を導入することとした。 |
3.グループ算定導入の経過
(1)グループ算定会社の選出基準 |
| 当面常用労働者301人以上(納付金対象の会社)とするが、最終的には全てのグループ会社を対象とする。 第一ステップにおいては、対象会社の中で既に法定雇用率を達成している会社で第二ステップからの算入を希望する1社を外し、その結果7社をグループ算定対象会社とした。 第二ステップでは、常用労働者301人以上(納付金対象)の全ての会社としたが、会社統合により急激に事業規模が大きくなり、人員も大幅に増えた会社も加わり、法定雇用率達成が危うい状況が予測されたので、将来算入予定であった小規模ながら障害者雇用に積極的に取り組んでいた会社を組み入れ、その結果13社をグループ算定対象会社とした。 第三ステップ以降については、事業連結の全会社をグループ算定の対象とする予定である。 今後、グループ算定の雇用率達成には、要件にのっとり親事業主である横河電機に配置した障害者雇用推進者を中心に、積極的に障害者雇用に取り組んでゆく方針である。 |
(2)関係会社のグループ適用の認定要件 |
| 関係会社の認定基準は、[1]「親事業主が関係会社の間に特殊な関係があること」については、親事業主が関係会社の意思決定機関を支配している(支配力基準)、[2]「関係会社と特例子会社との間の人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること又は関係会社が特例子会社に出資していること」については、関係会社から特例子会社に対し最低年間60万円程度の発注が行われている、と要件を満たしている。横河電機グループの内規として、関係会社に対し横河ファウンドリーへは少なくとも年間1名分の仕事量の発注を義務付けている。 |
(3)第一ステップ(平成14年10月1日) |
| 第一ステップのグループ関係会社の常用労働者数、障害者数、重度障害者数、雇用率は下表のとおりである。 (株式会社略)
|
(4)第二ステップ(平成15年6月1日) |
(株式会社略)
|
4.グループ算定に関わる機構
|
5.効果
(1)特例子会社「横河ファウンドリー」の新規品目及び既業務の受注量増大 |
横河電機及び関係会社の業務見直しにより、アウトソーシング化が進み、その受け皿としてグループの障害者雇用の核である「横河ファウンドリー」の事業拡大と受注量増大で、更なる障害者雇用に繋がっている。
|
(2)特例子会社「横河ファウンドリー」の社員のキャリアアップ |
| 上述の新規品目の受注に対応する為、下記の実務研修の強化を図っている。 [1] パソコン(ゴム印作成・銘板作成・名刺作成・経理資料・請求書入力等) |
|
| [2] 機器の分解作業 |
|
| 更に、実務教育だけでなく、経営に関する社長講話、健康教育、環境問題教育なども定期的に行われ、総合的な教育を実施している。 |
|
| 上記の教育により、社員のモチべ-ションが高まり、作業品目の拡大と効率化等個々人の意識及び作業能力の向上に繋がっている。 |
(3)雇用率について |
3、(4)項グル-プ算定企業(13社)の導入前と導入後の雇用率調査についての比較は下表のとおりである。この1年、グループ内の分社、統合、再編の変化にも拘らず、グループ各社に「法律遵守」意識が浸透し、一定の水準を維持している。
|
6.今後の課題・展望
| 会社としては、昨今の厳しい経済環境下で、企業の生き残りをかけた分社、統合化工場の再配置などの活動が更に活発化することが予測される。このような状況の中で、経済原則にのっとって障害者雇用の継続と新規採用をどのようにして推進してゆくことが出来るかが課題である。 会社の「遵法精神」をベースに、グループとして、知恵を出し合い、総合力を駆使し、創意工夫による業務の創出、現業務工程の抜本的見直しと再開発、又、在宅勤務などの多様な雇用・勤務体系の導入を検討するとともに、新規受注に対応できるよう社員の継続的なキャリアアップに努める必要がある。 |
7.まとめ
| 当社は、永年電機計測器、測定器、情報システム等の製品を産業界の幅広い分野に数多く提供し、限り無い技術革新が進む中で独自の技術を駆使し、業界において一定の地位を築いてきた。今後も、独自の技術力を更に高めるとともにITを活用した新規分野への進出を図ってゆく方針である。 障害者雇用については、「社会貢献」という意味合いよりは「法律遵守」という視点で捉えており、経営の中にしっかりと位置付けてゆく考えである。 ■資料[1] 【社 長 講 話】 1.2002年度のレビュー [1]経営状況の報告(売上、利益 等) [2]利益とは。利益を出すために。 2.2003年度の取り組み [1]6S 仕事中と退社時 [2]注意されたことを素直にうけいれる 注意をされるということは、「自分では気づけなかったことを、相手から教えてもらう」ということ。お客様、上司、同僚、からの注意は素直にうけいれる。 [3]目標を持ち、その目標を達成するために自分で努力する。 ア)YFD共通の目標は、相手(お客様、職場の仲間、他)の気持ちをよく考え、会社での生活が、お互いに気持ち良く過ごせるようにする。 イ)2002年度の研修の中で、それぞれ目標をたてた。その目標を達成できるように、自分なりの努力をする。 契約更改の面談に会社から提示された、ひとり一人の2003年度の課題・目標を提示されている。 [4]お客様へのサービス向上 納期・品質・コストは意識は2003.1月に話したとおり。 お客様への挨拶、言葉づかい、態度には日頃から常に気をつける。忙しい時やプライベートなことでイライラしている時は特に気をつける。 ■資料[2] 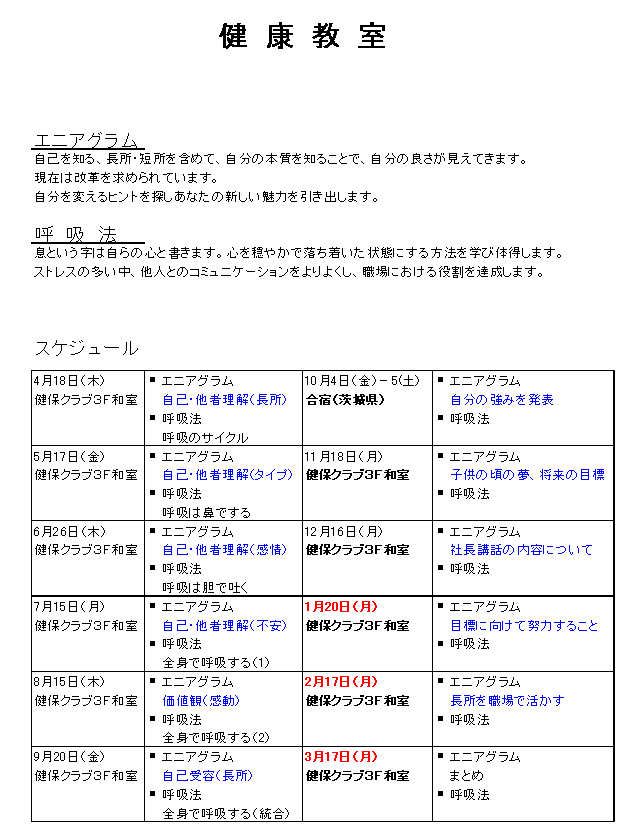 |
| 執筆者:株式会社オレンジジャムコ 代表取締役社長 小林 幸夫 |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。



















