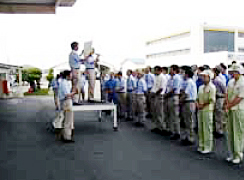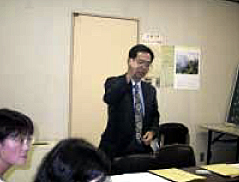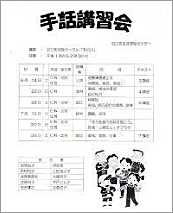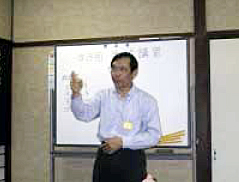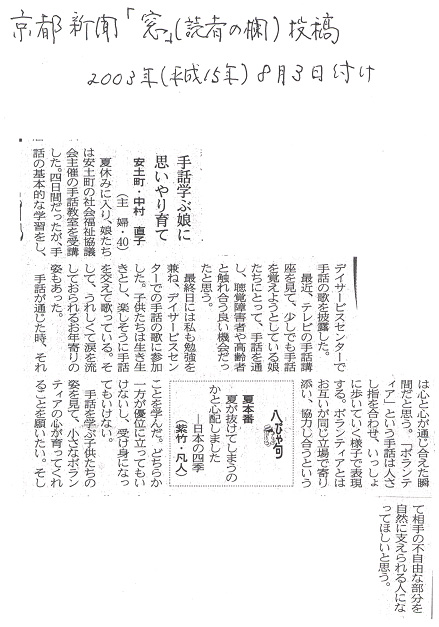聴覚障害者の技能レベルの向上と定着を目指す取組み、さらに企業内の取組みが地域社会へ拡がる
2003年度作成
| 事業所名 | 株式会社吉野工業所 滋賀工場 | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 滋賀県蒲生郡 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | プラスチックボトル製造 | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 370名 | |||||||||||||||||||||
| うち障害者数 | 8名
|
 (株)吉野工業所のロゴマーク |
1.事業所の概要
| (株)吉野工業所滋賀工場は、ペットボトル、洗剤、化粧品などのプラスチックボトル容器を環境保全と整合させつつ製造している事業所である。 同社の本社は東京都江東区にあって、現在、国内の工場は22ヵ所、海外工場はアメリカ、タイの2ヵ所、滋賀工場は同社の第4番目の工場として1966年(昭和41年)に立地した経緯がある。 同社の企業理念は「人とともに、自然とともに」をモットーに企業のロゴマークも「人の和」(結束と親和)としている。 滋賀工場の雇用管理は、立地以来、地元職業安定行政の助言と指導を基に緊密な連携を保ち、障害者の雇用・定着・技能形成・コミュニケーションの保持等の各ステージにわたり、きわめて活発であり、現在では企業内の手話教室が地域社会にまでひろがりをみるという希有な事例といえる。 |
2.障害者雇用の現状
平成15年(2003年)6月末日現在における、障害者雇用の現状(個別就業歴)は次表のとおりである。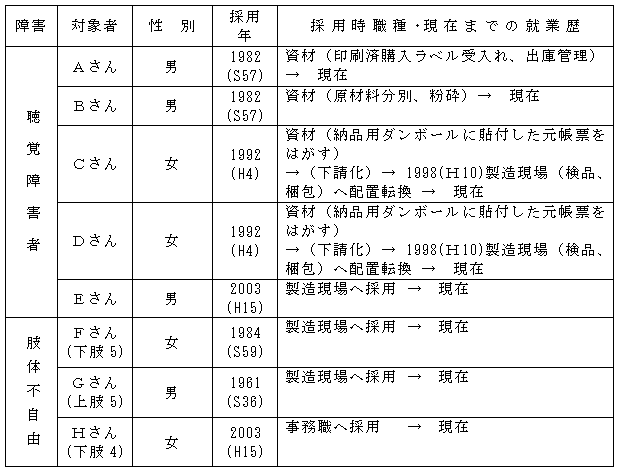 注 (1) 雇用形態は「協力社員」(1年間の有期契約で原則自動更新) (2) 「協力社員」契約による従業員は事業所でほぼ1割。原則として中途採用者に適用され自動更新。更新拒絶例(雇い止め)はない。 (3) 「肢体不自由」対象者欄の数字は障害等級を示す。 |
3.聴覚障害者(従業員)の技能形成
| 障害者雇用に関する企業の取組みのための最も重要なポイントは、障害者(労働者)の労働生産性が、同種・類似の仕事をこなす健常者(労働者)の労働生産性と比べてどの程度の位置にあると考えられるか、またその労働生産性が低い場合労働生産性の向上を目指す手段としての技能形成の方法・工夫をどのように行うかの問題である。 このため、この観点から、障害者(特に聴覚障害者)の製造業事業所における技能形成のありようと本事業所での「向上」への取組みについて [1] 生産現場の通常の操業状態下における技能形成、定着の現状と取組み [2] 生産現場の異常時(機器の故障、不具合、不適格品の生産、機械運転停止など)における技能形成の現状と取組み に分けて、それぞれを本事業所からの聞取りを中心に記述する。 (技能形成の程度と向上対策を検証する方法としてここでは通常操業時のありよう及び異常時の状況と取組みに分けて考える理由は、技能レベル(労働生産性の要因)が最も高いとされる状態とは生産現場における異常の発見・認知とその対応にある、とする考え方に立脚しているからである=その立場に立った先行実証研究は多くなされている=)。 |
(1)生産現場の通常の操業状態下における技能形成 |
| まず、通常の操業状態下における障害者(特に聴覚障害者)の技能形成・定着の現状と本事業所での取組みを述べる。 元来、個々の労働者(障害の有無にかかわらず)の技能形成と技能レベルを明らかにしうるとしても、それを摘記するのはきわめて困難である。なぜなら、人事考課とプライバシー保護の両面からの問題があるからである。 そこで、これを、作業者が通常の作業レベルをこなしうる程度までに習熟するための所要期間と現在到達しているその程度について、障害者と健常者とを対比する、という方法を採ることにした。 このための具体例として、障害者(特に聴覚障害者)にかかる通常作業日における通常作業時間ごとの就業等の状態とそれに対する本事業所での取組み(支援体制)を検証するため、典型例を、次に掲げる。 |
第2表 時間ごと通常作業の就業状況(典型例)と事業所の取組み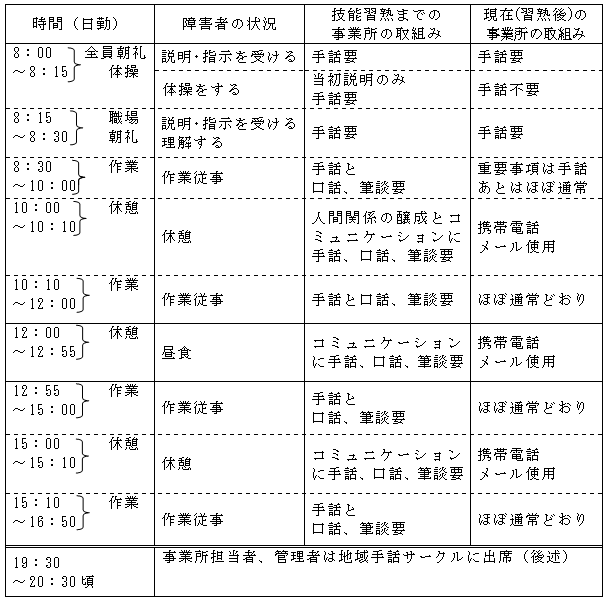 |
| ||||||
| この典型例をとりまとめた結果、障害者の習熟所要期間と現在の作業習熟レベルは、本事業所では障害者の職場の上司、管理者が手話の技術を習得して、障害者の技能習熟に不可欠な支援をくり返し行い、今も行っており、その結果、健常者(健聴者)の習熟所要期間と作業習熟レベルと比べてほとんど全く差がないことを確認できた。 よって、これにより通常の操業状態下における障害者の技能形成は、本事業所での取組みにより健常者(健聴者)のそれとほとんど差がないとの結論を得た。 また、全障害者が職場に定着していることも摘記しておく。 |
(2)生産現場の異常時における技能形成の現状と取組み |
| 製造業事業所における「異常」とは、設備機器の故障、不具合等の原因により、機械運転の停止、不適合品の継続的産出を生じたため、運転操作を一時的に停止のやむなきに至り、修復までの時間、従事労働者が作業を中断、手待ちになる状態を一般に指している。 いうまでもなく、生産を高めるために企業が取組むのは、この異常状態の発生を最少に押さえることである。このためこの方法は、生産現場における高技能レベルの労働者、現場管理者において、異常の予知・発見・認知・改善対応を即時に実行できる能力を保持することが求められるものである。 (生産現場における異常事態発生の頻度は、本事業所での発生頻度は別として、一般に意外に高いものである。ある実証研究では、従業員40人のセクションで異常事態発生による機械操作停止時間は月平均40時間、同セクションの全所定労働時間の2%に相当するとするものがあることを付記しておく。) 生産現場での異常事態の早い段階での認知は、設備機器の運転・操作時における異音、異臭、発光等の発生により、早期に予知し認知される。(つまり技能レベルの高い技能労働者、管理監督者ほど、その予知能力にすぐれており、予知、認知、対応により異常時間を最少にして手持ち時間を最少化することができるのである。) この見地から聴覚障害者の設備機器運転時の異音発生による異常状態の「予知技能」については、なお若干の課題があるのは否めない。このため機器が告げる機器の異常のシグナルは、音に加え光によるシグナルの構造となるような配慮が望ましい(この配慮の結果は、単に障害者雇用の改善取組みにとどまらず、機器異常の早期予知に多角的な手がかりとなるものといえよう)。 |
|
(3)意思伝達の手段 |
| ここで、聴覚障害者等に対する意思・情報伝達手段の多様化として携帯電話によるメール利用の活発化をあげねばならない。 現在のところ、携帯電話でのメール利用による伝達の場面は、従業員間の非公式接触の場(例:休憩時間でのやり取り等)が主体となっているが、特に必要な場合には公式接触(例:全社連絡事項、緊急指示等)においても、メールが使用されることがある。 携帯電話の利用は作業時間中禁じられているが、聴覚障害者に限っては必要な場合はこの取り扱いを弾力的に運用することが期待される(IT技術の進歩による「音声の視覚転換化」は、聴覚障害者のコミュニケーション手段を、手話に加えて多面化、重層化することであろう。ただし、フェイス・トゥ・フェイスの場面では手話による伝達手段に勝るものはない)。 |
4.肢体不自由者に対する配慮
| なお、肢体不自由者に対しては、採用当初は駐車場の特別区画を設ける支援措置を採ったが、現在では障害者の希望に応じ、区画を廃した経緯がある。 |
5.企業内の取組みが地域社会に拡がる
| 本事業所内部での、聴覚障害者に対する支援(職場での技能習熟とコミュニケーションの円滑化)としての高位技能者・管理監督者の手話技術の習得(企業内で手話教室の開催、教本の配布等)と活用は、企業内部にとどまらず、工場所在地の市町村などの地域社会や住民に手話教室の創設という形をとってひろがっていった希有な例となったのである。 すなわち、本事業所内の手話堪能な管理監督者の存在が事業所所在地の蒲生郡安土町や当該者の居住地・坂田郡近江町へひろがっていき、同地で手話教室、手話サークルがこれらの手話に堪能な従業員が講師になって順次開催(夜間・休日)され、企業内の障害者従業員に対する支援措置が地域の障害者福祉対策の充実と企業の地域社会への貢献に昇華していった、のである(別添・京都新聞投稿「手話学ぶ娘に思いやり育て」(安土町・中村直子氏)2003年8月3日付け参照) |
| ||||||||
6.まとめ
株式会社吉野工業所滋賀工場における障害者(特に聴覚障害者)雇用・定着の事例の聞取りによる結果を取りまとめると
|
| 執筆者:滋賀文化短期大学 非常勤講師 臼井 瑛 |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。