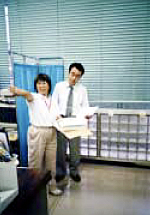「無限の可能性を拓く」という経営理念の実践~障害者の能力開発を促進する多面的取り組みから学ぶもの~
2003年度作成
| 事業所名 | 株式会社かんでんエルハート | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 大阪府大阪市 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 関西電力株式会社の特例子会社として、印刷・商事(ノベルティ包装等)・園芸・メールサービス・ヘルスケア・データサービス・電話対応サービス等の多彩な事業を展開 | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 130名 | |||||||||||||||||||||
| うち障害者数 | 84名
|
|
1.障害者職員の声でつなぐ現場紹介
| 「今日は、重度障害者雇用の人事管理に関するお話をお伺い致したく思いまして」、ご挨拶早々にそうお願いする私に対して、戸田幸彦顧問さんは、静かに次のようにおっしゃった。「どうぞ、現場の障害者自身からいろいろ聞いてみてください。その方がよく分かりますよ」 予期せぬ展開に、ふだん障害者と関わる仕事をしていながらも、やや狼狽しつつ、早速、現場をご案内頂いた。2時間で15人の障害者にインタビューすることができたので、まず、当事者の声をつなぎながらの現場紹介を行いたい。 かんでんエルハートは平成5年に設立、平成7年に業務を開始した関西電力の特例子会社である。また関西電力が51%、大阪府と大阪市が24.5%ずつを出資した第3セクターという性格も伴っている。 |
(1)業務課 |
| 会社概要をビデオで拝見した後、業務課の事務室へ。ここでは庶務全般と、関西電力の福利厚生施設利用に係る電話対応サービスをされている。「旅行先の宿舎を紹介した方から、『良かったよ』と喜んで頂けるのがうれしい」との声。インタビューするのが悪いくらい、電話受け付けが引っ切り無しに続く。関西電力の職員及びOBの方、一人ひとりとつながっている仕事なのだ。 |
|
(2)印刷課 |
| 続いて、印刷課のあるデザイン室と印刷・製本室へ。車いす利用者、聴覚障害者、知的障害者にお話を聞く。「印刷する量が多いと大変」とは、知的障害者職員の感想だが、関西電力の人事異動の時期である6月、12月には名刺印刷に夜中までかかることもあるという。しかし、こうした努力が後述の大きな成果につながってくるのである。なお、聴覚障害者へのインタビュー時には、車いす利用の方に手話通訳をして頂いたが、障害者同志の連携が盛んなのも同社の特長である。 |
|
(3)商事課 |
| 次に、商事課でノベルティ(記念品・贈答品)の包装実演を見せて頂く。これが、何とも鮮やかなのである。「かんでんエルハート」のロゴの向きなど、細かい点にも気を配り、かつスピーディに包む。 |
| 「デパートで、お店の人がしている包装が気になってしまう」と、日頃からプロの目で見ている知的障害者職員。壁には、「ボールペンのし袋入れ」の記録表が誇らしげに掲げられている。設立時には、5人で1日5,900本だったのが、最新記録では、14,100本である。なお、実際の業務で多くの量をこなすには、事前の仕事の段取りも重要になってくる。そこで、担当の身体障害者職員にコツを教えてもらう。「一人ひとりが得意な作業をうまく組み合わせて、納期に遅れないようにすることが大切」とのこと。ここでも、障害者同志の協力体制をもとにした、総合力発揮の精神がしっかりと根付いている。 |  壁には「ボールペンのし袋入れ」 の記録が |
|
(4)温室作業 |
| その後、外へ出て、温室を見学する。ここでは、業務受託している花壇へ植える花や、販売用の植物を種の段階から育成し、即売している。知的障害者職員が、パネルをもとに元気よく工程を説明してくれた。3人の知的障害者に「仕事をしていて楽しいとき」を聞いたが、いずれも「花を買いにきた地元のお客さんが喜んでくれたとき」との声が返ってきた。障害者を多数雇用している事業所は少なくないが、ともすると足元の地域との関係が希薄になってしまう場合がある。この点も、うまく工夫がなされているなと感心した。 | 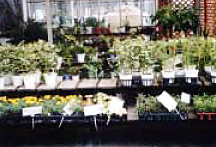 地域のお客さんにも好評な花苗 |
|
2.関西電力本店社屋にも、活躍の場が
| 以上が、住之江の本社の様子だが、引き続き、中之島の関西電力本店社屋内の職場である中之島ワークセンターを見学させて頂く。 |
(1)メールサービス部門 |
| ここでは、まず1階のメールサービス部門を拝見する。地上12階、地下3階の社屋を9名の知的障害者が行き来している。私は、この部門に、かんでんエルハートの真髄が最もよく現われていると感じた。社長さんをはじめ幹部職員宛も含め、毎日1万通余り来る郵便等を配送するという大変重要な任務を、知的障害者自身が担っている事実に、感動以上のものを覚えたのである。「言うは易し」であるが、誤配率を極力少なくするための工夫には、何度も何度も繰り返された試行錯誤があったのだという。配送先を書いた箱に仕切り板を入れ、その板より上は未チェックなので、分けた人以外が点検するシステム。配送袋の回収漏れをなくすための声を出しての照合と、表への記入、等々。紙幅上、書き切れないのが残念である。宛先が不明確だったり、書いてなかった郵便物の所属を調べる仕事も、知的障害者自身が担っている。「障害者職員の特性もうまく活用しながら工夫を重ねてきた」とは、担当スタッフの方の弁だが、「できて当たり前」とされるメールサービスを知的障害者の職場として開拓された先見性に、頭が下がる思いだった。なお、メールサービスは、大阪北、京都、神戸、姫路の各支店でも同様に実施されており、他の電力会社の特例子会社でも取り入れられたとのことである。 |
|
|
(2)ヘルスケア部門 |
| 最後に、7階にあるヘルスケア部門におじゃました。小鳥のさえずりのBGMが心地よい中で、マッサージを担当する視覚障害者職員の方に「やりがい」をお聞きする。 |
| 「病気で視力障害をもったとき、『自分は何もできない』と思っていた。それが、この仕事を通じて、人に喜んで頂けることができ、こんなにうれしいことはない」とのこと。ふと見ると、お客さんのデータが映るパソコン画面には、紙がかぶせてある。プライバシー保護のためであるが、見える側の立場に立って配慮をする点、サービス業と障害者雇用が両立するヒントのようなものを与えて頂いた瞬間だった。 時間の都合で、本店社屋の4階にあるデータサービス部門、高槻フラワーセンターへはお伺いできなかったが、障害者職員数だけみても、設立時の28名から3倍の84名へと、着実に広がっているのである。 |  ヘルスキーパーさんは中之島ワークセンターにはお二人おられる |
3.能力開発をするには、何が必要か、実践から学ぶ
| 前述の戸田顧問さんは創業時の代表取締役だが、現在の中井志郎代表取締役さんともども伺ったお話と、見学で得た実感をもとに、以下、「能力開発」の視点から、論じていきたい。「能力開発」は、どの企業も直面する課題だが、つい、障害者個人にばかり目がいって、「難しい」となってしまう。かんでんエルハートでは、殊更「能力開発」という文言は使われなかったかと思うが、その実、あらゆる実践が、「障害者の能力開発」を効果的に進めるために、集約されていっていると感じたのである。 |  中井志郎代表取締役さんの お話をお聞きする |
(1)意欲の喚起 |
| まず、障害者職員が前面に出て、まさに会社の主役として生き生きと働いている点に注目したい。いかなる能力も、やる気のわかない職場では開花し得ないが、当事者が見学対応の役割を積極的に担うことは、意欲の喚起に間違いなくつながっている。戸田顧問さんが、はじめに「障害者自身の話を」と言われた訳が、よく分った。 |
(2)活躍の場の確保 |
| 次に、意欲を持った障害者職員の活躍の場の確保が課題となるが、この点も実に貪欲に取り組まれている。平成14年度事業収入10億8千万円の内訳は、親会社受注80%、同関連会社受注13%、一般受注7%であるが、この7%に特に注目したい。周辺の他事業所の花壇管理や地元PTAの会報づくりなど、地域との共生と商売を、うまく融合させている。能力を発揮したくても、その現場が限られていては、結果として芽が出ないままになってしまうこともある。「準備段階から、印刷の注文取りに走っていた」という戸田顧問さんらの地道な取り組みあってこその現在である。 |
(3)改善の積み重ね |
| また、先述のメールサービスに代表されるように、知的障害者が作業を間違えないようにするための工夫の積み重ねも、能力開発とは不可分である。「うまくいっていない」事業所の場合、障害者にその理由を帰してしまいがちだが、今一度、考えてみたいのである、「サポート方法に改善の余地はないか」を。 |
(4)一緒に働く従業員の資質 |
| 更に、成功した秘訣として、一緒に働く健常者の資質の問題がある。かんでんエルハートでは、印刷なら印刷のプロの方を採用し、障害者のことを学んでもらい、業務を開始したという。この発想も、他企業に普遍化できる。何故なら、各企業とも、各々その道のベテラン社員はたくさんおられるからである。確かに、仕事を教える側が素人では、いかに障害者のことに精通していても、うまくいかないのである。授産施設や作業所で生産性が上がらない原因に、同様の指摘が行われていることを思い出した。 |
(5)成果に報いる会社の姿勢 |
| そして、能力開発と表裏一体の「成果に報いる会社の姿勢」も、また重要である。「黒字になったら海外旅行」とハッパをかけたら、平成9年度に累積赤字も解消し、黒字に転換したそうである。そして全社員そろってのグァム旅行となった由であり、これなら頑張りがいもあるというものである。日常的にも、顧客とのやりとりで、仕事の手応えを感じている話を、数多く聞くことができたが、これも能力開発を後押しする要因になっていると考えるものである。 |
|
(6)経営理念 |
| 以上、主役になることでの意欲喚起、活躍の場の確保、業務方法の改善の積み重ね、一緒に働く健常者の資質の高さ、成果に報いる会社の姿勢の5点を、「能力開発」を促進する周辺領域として挙げた。そして、これらに共通する考え方は、かんでんエルハートの経営理念である「無限の可能性を拓く」である。障害者雇用に取り組む企業の中で、かんでんエルハートが、常に光ってみえるのは、やはり、この理念があるからだろうと、今回、実感した。考えてみれば、とてつもない理念である。「無限」である以上、個々の障害者にとっても、会社にとっても、「これでよし」という限界はないのだから。しかし、だからこそ、メールサービスのような、傍から見て困難とも思われる業務にも取り組めるのだろう。そして、この理念は、会社の規模や形態(特例子会社か否か)にかかわらず掲げることができ、その実践も、規模と実状に応じて行うことは充分可能であると考えるのである。 また、「無限」は夢のある響きをもつ語彙でもある。現状を越えて、その先を求めたくなるキーワードである。例えば、数学で素数(2、3、5、7、11のように、1またはその数自身のほかに約数をもたない正の整数)というものがあるが、これは無限にあることが証明されている。だからこそ、より大きな素数を求めて、世界中の研究者がしのぎを削っているし、またそのプロセスで新たな発見も生まれてくる。かんでんエルハートでの「無限の可能性を拓く」実践は、特例子会社という枠を越えて、我が国における「障害者の能力開発」「職種開拓」の幅を広げていく役割をも担っていると考える。何度も例に出すメールサービスだが、この実践は、全ての官庁・企業で、知的障害者の業務が可能になることをも示していると言っても過言ではない。「無限の可能性」を追求する取り組みは、計り知れない波及効果をも生み出すのである。 今回の訪問は、障害者に関わって25年目になる私自身にも、新たな衝撃を与えてくれた。今後の課題は、戸田顧問さんのお話にもあった「花苗育成業務での精神障害者の雇用」「本店社屋の移転に伴うビジネスチャンスの獲得」「職員の親の組織である『自立を考える会』によるグループホームづくり」等と思われるが、これらにおいても「無限の可能性」が拓かれることを楽しみにして、報告を終えたい。 |
| 執筆者:財団法人箕面市障害者事業団 箕面市障害者雇用支援センター 所長 栗原 久 |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。