街ぐるみのリサイクル事業で企業就労と福祉就労の狭間を支える
2003年度作成
| 事業所名 | マルワ環境株式会社 | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 徳島県徳島市 (本社工場) 徳島県板野郡北島町 (北島工場) | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 環境コンサルティング、廃棄物コンサルティング、環境設計、リサイクル事業、廃棄物処理事業、建物解体工事事業、環境関連商品販売 | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 12名 | |||||||||||||||||||||
| うち障害者数 | 5名
|
1.事業所の概要と障害者雇用の状況
| 代表者 丸山 泰弘 設 立 1984年1月(2003年2月株式会社に組織変更/創業1958年) |
(1)雇用障害者数 |
| ||||||||||||
(2)紹介元 |
| 養護学校、知的障害者通勤寮、地域共同作業所、就業・生活支援センター、障害者職業センター、公共職業安定所 |
(3)仕事内容(主なものを記載) |
| [1] 古紙の選別と運搬車両への積み込み [2] 回収飲料容器の選別と運搬車両への積み込み [3] ペットボトルとプラスチックの選別、ベール品の梱包 [4] 瓦、ガラス、木屑、金属の仕分けと小運搬 [5] 工業用ウエスの製造 |
2.取り組みの概要と経過
| 本事例は、当該事業所が、総合的なリサイクルセンターの設立に向けて事業展開を進めている現段階の状況をまとめたものである。環境やリサイクルに関して手広く事業を展開している当該事業所は、2003年4月から、新たにペットボトルとプラスチックの再資源化作業を自治体から委託された。 これに伴い、当該事業所での障害者雇用の推進、職場定着・職場適応と障害者の能力開発にとどまらず、地元自治体や福祉機関、様々な関係機関と共に、障害者の社会的な自立を支える街/体制づくりが行われるようになった。 経緯について、以下の表に取りまとめた。 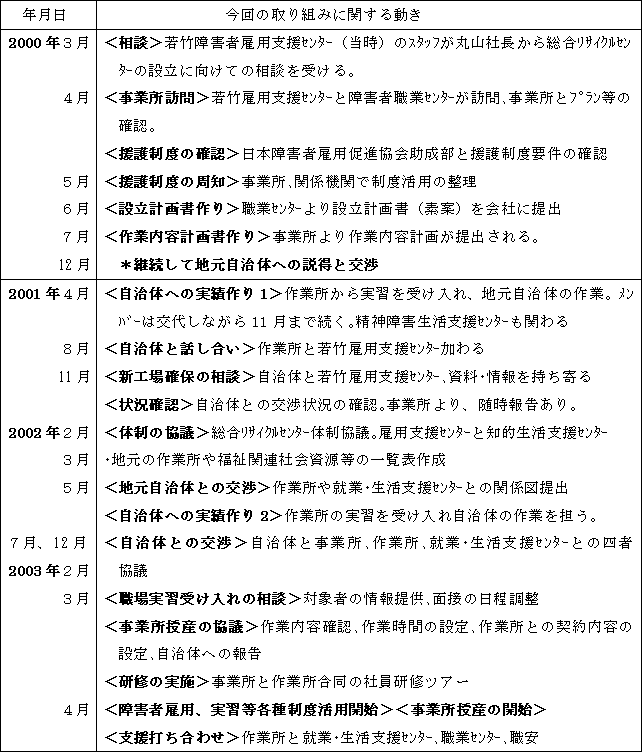 |
3.総合リサイクルセンターの設立と障害者雇用
| 当該事業所では、7年前から障害者雇用が始まっている。当初から総合的なリサイクルセンター設立プランの柱の1つに「障害者雇用の促進」が掲げられており、2003年4月にプランを前進させるペットボトルとプラスチックの再資源化作業の委託と北島工場の稼動が、始まった。これに伴い、2003年3月から現段階までに、2名の障害者雇用と5名の訓練・実習等各制度利用(5名は雇用を見据えている)が実現した。 リサイクル関連法が整備され、各地域においてリサイクルシステムの整備や充実が望まれてきており、今後、リサイクル関連法の整備に伴い、この業種で障害者雇用の促進が予想される。徹底した安全管理の元、この分野での障害者雇用の可能性を探ることは、雇用情勢の厳しい地方の取り組みとしても意味深いものと思われる。 |
4.これまで職場定着が困難だった人たちへの対応
| 2003年3月から受け入れが始まった7名は、それぞれに課題を抱えて、これまで職場定着が困難であった障害者が多数を占める。人間関係が原因でこれまで離転職を繰り返してきた人や生活面で様々なトラブルを抱えている人、重複の障害があり仕事をする上で困難さを抱える人、コミュニケーションが上手く図れない人などが働き始めた。そうした人たちの雇用の推進と同時に、職場定着にも力が注ぎ込まれている。 |
| 当該事業所での職場定着の大きなポイントの1つは、ひとりの障害者の就業と生活の両面を総合的に支援することに、事業所が大きな一翼を担って取り組んでいることである。就業面と生活面、それぞれの関係機関との連携は相当に綿密で、日常的に細かなやりとりをしている。事業所の障害者の就業と生活の両面を支えていこうとする視点が、様々な課題を抱えて職場定着が困難であった障害者の職場定着を進めていくことにつながっている。ちょっとした体調の変化、仕事の仕方やスピードの違いを生活面も含めた視点でもって原因を探り、的確な対応を行っている。 また、ポイントの2つめとして、個々の障害者にあった環境づくりに取り組んでいることが挙げられる。 |  袋がかけやすいように 改良されている。 |
| 個々の障害者の障害特性や性格にあわせて、個人が最大限の力を引き出せるように 使用器具や情報提供の仕方一つにしても工夫がなされている。また、障害のある本人や本人を支える関係機関と度々話し合いを行いながら、柔軟に職場内の配置転換が行われている。配置転換により、障害のある本人にとっては、仕事内容の変化がもたらされ、また、共に仕事をする人とのマッチングによって、人間関係の状況が変わる。この2つを障害者個々の日々の状況に応じて、個人の力がより発揮出来るような配置転換が行われている。また、個々の特性を把握して、それぞれの持ち味を仕事で発揮出来るような支援がなされている。 社長は「できることから探す」「いかなる困難さを抱えている障害者でも、必ず長所がある」と語ります。その根底には、事業所が本人と話し合うことに大変時間をかけていて、コミュニケーションを重要としていることと、障害のある本人の自発的な意見や積極的な姿勢、自己決定を尊重し、本人が自ら働く楽しみを見出していけるように事業所として努力していることがある。また、こうした支援は、職場内でのナチュラルサポートへと発展している。 |
|
5.企業就労と福祉の狭間を支える
| 当初、総合的なリサイクルセンター設立プランは、重度障害者多数雇用事業所を目指したものであり、事業所は、障害者雇用の推進を考えていた。ところが、地元自治体や各機関と話し合う中で、出てきた課題は、障害者雇用を進める前段階の取り組みがこの地元で行われていないということであった。この地域では、福祉的就労と企業就労の間に大きな溝があり、そこを埋める取り組みがあれば、今すぐに企業就労が難しい障害者も経験を積んで自信を持つようになり、将来的に障害者雇用の推進につながるということである。 当該事業所は、地元自治体や地元の地域共同作業所を巻き込む形で、今回の事業展開の半分を「福祉的就労と企業就労の大きな溝」を埋める取り組みに当てることにした。本当なら「自社で障害者を雇用した方が雇用管理を含めて会社としてやりやすい」という思いもあったが、それぞれの機関と地元の状況を含めて相談の上、あえて企業就労と福祉の狭間を支える取り組みを進めている。 2003年4月、ペットボトルとプラスチックの再資源化作業が委託され北島工場が始動すると同時に、地元の地域共同作業所のメンバーが当該事業所工場内で仕事を請け負う、事業所内授産活動に取り組み始めた。週4日間、作業所から就労予備軍である知的、身体、精神の障害者が6~9名程度、作業所のスタッフと共に仕事をしにやって来ている。作業所からすれば、働く体験が出来るし、作業所での工賃もこれまでの数倍になるということで万々歳のようである。 今回の取り組みにより、北島工場は、事業所の従業員や職場実習等の制度活用中の者、作業所のメンバー等、総勢20名程になり、皆でにぎやかにはたらいている。 |
6.働き始めた障害者と関係者のコメント
| 効果については、今回の取り組みにより働き始めた障害者や関係者からコメントを頂いたので、それを以下に記載する。 ●Aさん(マルワ環境(株)にて就労) 「今までの私の仕事は行きたくないことが多かった。でも、今の仕事に変わってから、いっしょうけんめいにすれば、人にみとめてくれるし、ほめられてうれしかったです。いつも仕事でひとりぼっちだったけど、なぜかひとりではないとおもい、あしたもがんばって行ける気持ちになる。今の仕事に行ってよかったと思います。これからもがんばって行きたいと思います。」 ●Bさん(マルワ環境(株)にて就労) 「マルワかんきょうにいきだして 仕事いぜんとちがっていそがしいです。これからもがんばっていまの仕事をつづけていきたいです。仕事をおぼえていきたいです。」 ●Cさん(地域共同作業所に在籍。マルワ環境(株)で事業所授産活動をしている) 「チューリップ(注:地域共同作業所の名前)とマルワのちがい。仕事がチューリップよりもきつい。チューリップは、マルワよりラクです。チューリップは、いろいろな事をする。マルワは同じ事をするのでラクな気もする。マルワのイイところ、きゅうりょうがチューリップより多い。早く終われば早く帰れる。きゅうけいもいっぱいできる。おかしもジュースものめる。話し相手がたくさんいる。いやなところは、誰かがいっつもおこられたりよくする、少しきびしいところです。いいところは、おもちゃ、ビデオ、CDをたまにもってかえります。」 ●Dさん(地域共同作業所に在籍。マルワ環境(株)で事業所授産活動をしている) 「楽しいです。プラスチックのせんべつをしています。作業しょとちがいます。しょくばがいいです。」 ●地域共同作業所・所長さん 「本人にとっては、はたらく喜び、チームワークの大切さ、お金が沢山もらえることなどがプラスになっていると思います。事業所内授産活動を進めるにあたっては、作業所は元々していた作業が残っているので、作業所に残るメンバーが少なくなってもなんとかしなければいけないという面があります。また、離れた場所(事業所内)で支援をするから職員同士のコミュニケーションの困難さもでてきます。 しかし、本人にとっては絶対プラスになっており、障害者にとって良い方向の活動であるのは間違いなく、企業も従業員さんにもプラスがあるはずです。他の福祉機関でも、事業所内授産の場を積極的に確保して欲しいと思います。障害者も企業の中で働いていけることを他のみなさんも実感してもらいたいです。障害者も自分のやる気があれば、働いていけるんだという実感を絶対持てるはずです。」 |
7.今後の課題・展望
| 今回の取り組みは、事業プランの最初の一歩といえる。総合的なリサイクルセンターの設立に向けた事業展開の中で、今後、更に幅広い障害者雇用やその他の取り組みが行われていくことと思われる。これからも、会社という枠組みの中で単に障害者を「労働力」として考えるのではなく、障害のある彼らが自分の夢をかなえたり、社会的な自立に向けて取り組んでいくことを関係機関と共有して、支えていくことと思う。 |
| 執筆者:就業・生活支援センターわーくわく 佐野 和明 |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。













