障害者雇用は我が社の誇り
~産学連携による機械の開発や海外進出のノウハウにつながって~
2003年度作成
| 事業所名 | 日豊製袋工業株式会社 | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 大分県中津市 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)コンテナーバッグ及び各種包装容器の設計及び製造販売 | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 90名 | |||||||||||||||||||||
| うち障害者数 | 22名
|
 日豊製袋(株)入口にて 社長友松と指導員山内 |
1.事業所の概要
| 代表取締役:友松研二 資本金:2,000万円 月販売高:60,000千円 |
(1)沿革 |
|
(2)主な取引先 |
|
(3)製造工程図 |
| 原料入荷→倉庫→*裁断→*印刷→*縫製→検査→*内袋挿入折りたたみ→*製品梱包 (* 障害者を配置している部所) |
2.会社の理念とトップの姿勢
| 障害者雇用のきっかけは、「創立間もなくのころ、従業員が『焚き火』をしている所に火を当たりに来る知的に遅れた少年がいた。毎日来るので、ある時、明日は薪を拾っておいでと言うと、翌日にはきちっと集めて持ってきた。火を消しておくように言いつけておくと、これもきちんと出来る。これは馬鹿にできんぞと言う訳で、メリケン袋の『糸を切ってごらん』と、やり方をして見せるときちんとできる。・・・『明日から君は社員である』こんなことから障害者雇用が始まった。」とのことである。胸が熱くなる話である。 そこで、障害者雇用についてどのようなお考えをお持ちかを伺ったら、説明資料として会社案内を戴いた。中身の一部が表-1及び表-2である。 「法人は国家社会に貢献することが使命である」の理念の基に、社長(友松研二氏)の決意として、障害者観が明確に銘記されている。「障害者は、障害者である前に人間である」こと、「障害者を納税者に育成する」ことの2点である。 また、「障害者職場指導要綱」(表-2)もユニークである。これが後述するマンツーマン体制に生かされ職場適応、生産性向上に寄与している。 同席の山内令子部長がいみじくも言われたように、「障害者雇用の促進も安定もトップの考えが大切」である。 |
3.中学校(障害児学級)卒業生を採用
| 当初は養護学校高等部卒業生も採用していたが、経験を重ねるうちに、中学校障害児学級の卒業生を採用し育成する方が即戦力になり易いと判断した。中津市内の障害児学級の生徒を実習で受け入れ、その内から採用を決定するシステムに切り替えたことが成功につながっている。鉄は熱いうちに打ての通り、入社初期の指導・教育の影響が大きいことを経験から得た。 |
4.障害者雇用についての一般従業員への理解・啓発
| 障害の有無に関係なく、最低賃金の保障(最低賃金適用除外申請者は最近雇用した1名のみ)と給料体系は一律でやってきた。障害者の数が増えて行くにしたがって、個々人の出来高と給与ベースの問題が必然的に出て来た。一般従業員の不満を解消するために、正しい障害者理解に立ち、会社の障害者雇用の意義を同僚に説明・説得できる力をもった人材の育成と出来高評価の見直しの必要に迫られた。 |
5.障害者雇用の経験が海外進出のノウハウに
| 障害者の雇用を促進安定させるために大学と連携して機械の改善・開発を行っているが、インドネシアへの工場進出を決断する際に、障害者のために改善した機械を持って行ってデモンストレーションした結果、機械が言葉の障害を乗り越えて契約成立に貢献した。 現在5か国(中国・台湾・タイ・韓国・インドネシア)6ヶ所に工場がある。障害者のために改善した機械が海外で評価され、海外からの受注が増えたことが、高齢者・障害者の雇用拡大・安定につながっている。 |
|
6.知的障害者の指導方法を見直すきっかけ
| 特性を捉えて指導すればよく働くこと、好きなこと・興味のあることであれば根気よく取り組むこと、かなり高度な仕事でも個の能力・特性を捉えて機械化を進めることで一つのことに対してはきちんと正確にできること等、障害者の可能性を実感している。 |
7.障害者職業センター、ワークトレーニング社の活用
| 採用決定後は、ワークトレーニング社で2週間の訓練を受けさせる。ここで作業の仕方、作業態度、会社の仕組み等の就労に必要な態度・心構えの指導を受けた後、出社と言うことになる。障害者職業センターとはその後も緊密な連携を取り合い、必要に応じて定期的な個別指導(カウンセリング等)をお願いしている。最近も、一昨年雇用したA君が、従来の指導要綱では手に負えないため解雇も辞さぬ思いで障害者職業センターに相談した。週に1度指導のため来社し、カウンセリングを続けた結果、物を言うようになり、仕事にも意欲を見せ始めたので、継続雇用を決定したとのことである。 |
8.徹底したマンツーマン指導で
| 当社の社員(障害者)教育の特色は、仕事は勿論、社員としての心得から日常の生活指導までを徹底したマンツーマン方式で教え込んで行くことにある。 一般従業員も指導する立場になったことで部下ができたことを喜び、誇りを持って仕事に当たるので、生産性の向上につながっている。今では新人が入社すると自ら新任育成係を希望するものが数名いるとのこと。「あれもこれもできなくてよい。何か一つの仕事のスペシャリストになればよい」と言う、友松研二社長の言葉が光る。 |
|
9.一般従業員(組合員)に障害者理解・障害者雇用の意義の啓発を図る(指導員の育成)
| 障害者を正しく理解する人が増えれば、不満は自然に解消されるであろうとの考えから、一般従業員を障害者理解のための各種講習会・学習会や県総合雇用推進協会主催の障害者職業生活指導員資格認定講習会等々に極力参加させ、障害者を正しく理解し、指導できる従業員の育成を積極的に推進した。障害者のことを知っている者が多数いるということは、例えば脊椎損傷の方には、周りの人が「そろそろトイレに行かんといけんのじゃないか」といった気配りができるなど、この障害の方にはどんなことに配慮がいるか等々、就労中でも障害者に対する細かい配慮が期待できる。 現在、指導教育の組織として、障害者雇用推進者1名、業務推進援助者2名、職業コンサルタント1名、障害者生活指導員3名を各ラインに適正配置し、多様な課題にその都度適切に対処できる体制ができている。 |
10.出来高を個人のノルマ制から、トータル方式へ改善
| 本日、今の時間の出来高予定のプラス・マイナスが、時間系列で従業員全員に見えるようにデジタル掲示板を設置している。その日の出来高が、総合してマイナスになっていなければよい。会社全体で今日一日の利益分がお互いで賄えればそれでよいという考えから、個人のノルマ制を廃止した。この結果、自主管理の姿勢、励まし合いの精神が生起した。 |  生産出来高表示板 この数字で自主管理を行う |
| 11.産学連携の成果 - 合理化は障害者雇用を拡大 |
| 国連の指定工場でもあり、例えば酷寒0度以下の気象条件にも耐えるオーダーメードの注文にも応じなければならず、常に技術開発が必要になる。またトップは技術進歩に敏感に反応する感性がなければならない。 そのため障害者のための能力開発、就業環境の整備、機械の改善・開発に資する研究を広島大学・日本文理大学・厚生労働省・県総合雇用推進協会と連携し実施している。障害者の能力・特性を見いだし、ボタン操作で仕事ができるように機械や操作方法を改善するのである。コンピューターミシン、超短波裁断機、超短波接着機などであるが、ボタン操作一つで、一般従業員の6~7倍も仕事をしてくれる。 「一般には、機械化すれば障害者雇用が減少するのではないか、リストラの対象にされるのではないかと考えがちであるが逆である。注文は営業努力次第でいくらでもとれる。事業が広がれば雇用は拡大する。」経験が言わせる、自信に満ちた言葉である。 |
|
| 12.今後の課題・展望等 |
(1)知的障害者の高齢化に伴う体力と能力の低下に伴う課題 |
| 加齢に伴い障害者の老化が急速に進み、8時間労働に耐えられなくなっている。表-2の障害者職場指導要綱で障害者指導のノウハウは完成したと思っていたが、高齢化対策が深刻な課題として生起してきた。再教育と継続雇用の問題、授産所や福祉工場等福祉施設との関わりをも考慮に入れた第二期(35歳以上)の指導の在り方を模索中である。 |
(2)知的障害者の能力開発に伴う課題 |
| 私学でもよい、知的障害者を税金を納める労働者として育成できる教育機関が早急に必要である。但し、そこでは(1)で述べた、再教育もできる能力開発センターであることが望ましい。 |  道場(居合道)兼娯楽室 (カラオケ及び室内スポーツ) |
表-1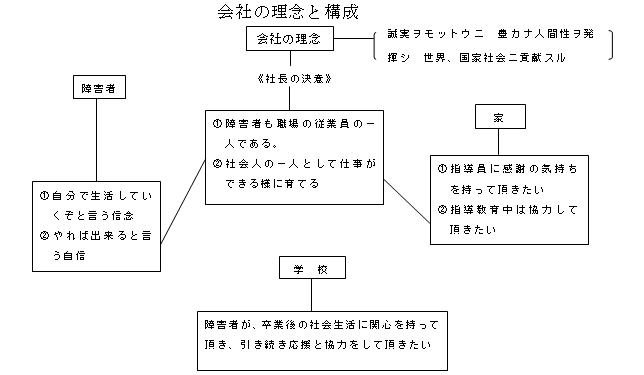 |
表-2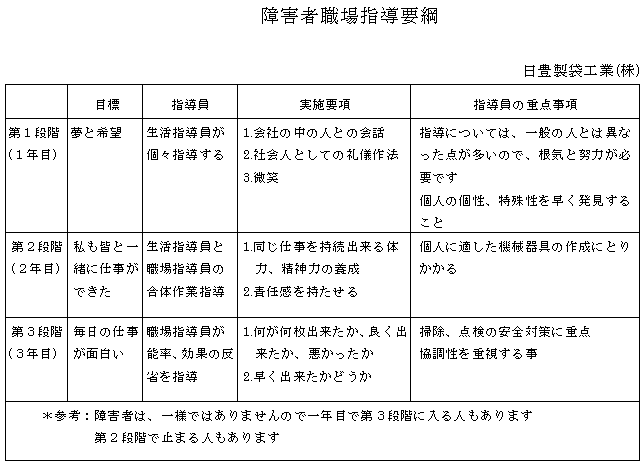 |
| 執筆者:別府大学短期大学初等教育科 佐藤 賢之助 |
11.産学連携の成果 - 合理化は障害者雇用を拡大
| 国連の指定工場でもあり、例えば酷寒0度以下の気象条件にも耐えるオーダーメードの注文にも応じなければならず、常に技術開発が必要になる。またトップは技術進歩に敏感に反応する感性がなければならない。 そのため障害者のための能力開発、就業環境の整備、機械の改善・開発に資する研究を広島大学・日本文理大学・厚生労働省・県総合雇用推進協会と連携し実施している。障害者の能力・特性を見いだし、ボタン操作で仕事ができるように機械や操作方法を改善するのである。コンピューターミシン、超短波裁断機、超短波接着機などであるが、ボタン操作一つで、一般従業員の6~7倍も仕事をしてくれる。 「一般には、機械化すれば障害者雇用が減少するのではないか、リストラの対象にされるのではないかと考えがちであるが逆である。注文は営業努力次第でいくらでもとれる。事業が広がれば雇用は拡大する。」経験が言わせる、自信に満ちた言葉である。 |
|
12.今後の課題・展望等
(1)知的障害者の高齢化に伴う体力と能力の低下に伴う課題 |
| 加齢に伴い障害者の老化が急速に進み、8時間労働に耐えられなくなっている。表-2の障害者職場指導要綱で障害者指導のノウハウは完成したと思っていたが、高齢化対策が深刻な課題として生起してきた。再教育と継続雇用の問題、授産所や福祉工場等福祉施設との関わりをも考慮に入れた第二期(35歳以上)の指導の在り方を模索中である。 |
(2)知的障害者の能力開発に伴う課題 |
| 私学でもよい、知的障害者を税金を納める労働者として育成できる教育機関が早急に必要である。但し、そこでは(1)で述べた、再教育もできる能力開発センターであることが望ましい。 |  道場(居合道)兼娯楽室 (カラオケ及び室内スポーツ) |
表-1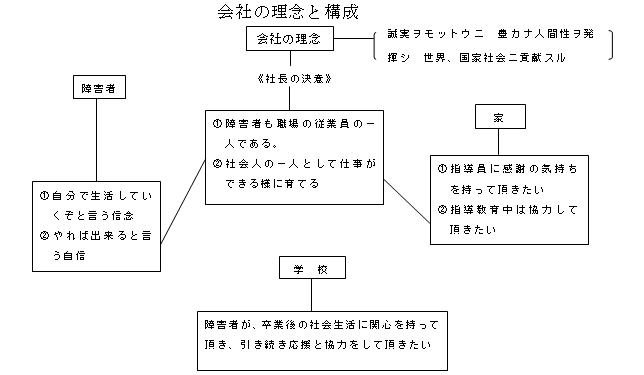 |
表-2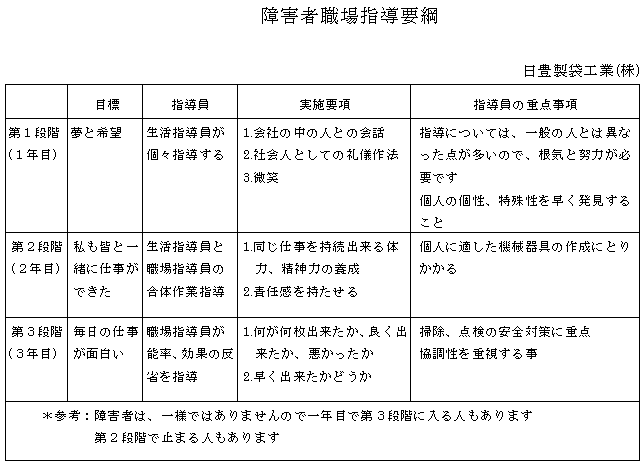 |
| 執筆者:別府大学短期大学初等教育科 佐藤 賢之助 |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。

















