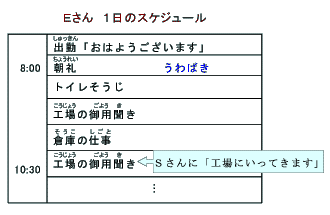できることを見つけて~ジョブコーチ支援を活用した職場適応~
2003年度作成
| 事業所名 | 山形大光株式会社 | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 山形県寒河江市 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | プラスチック成形加工 | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 85名 | |||||||||||||||||||||
| うち障害者数 | 2名
|
1.事業所の概要
| 山形大光株式会社は、昭和60年創業、資本金4,600万円。現在本社工場、パック工場、そして上海にも工場を構え、プラスチック製品の製作・成形・加工を中心に益々業績を伸ばしている。 平成15年9月には、障害者雇用への寄与に対し、社団法人 山形県障害者雇用促進協会長表彰 障害者雇用優良事業所として表彰された。 |  代表取締役社長 久家 勇喜 氏 |
2.障害者雇用の経緯
(1)Eさんの採用 |
| Eさん(男性)は軽度の知的障害があり、以前は社会福祉法人牧人会(まきびとかい) 寒河江共労育成園に通所していたが、就労意欲が高まったのを機に求職活動を始めた。職業安定所からの紹介で障害者向けの合同面接会に参加したところ、その面接会場で当社社長の目にとまり、2ヶ月間の実習(この間山形障害者職業センターの生活支援パートナーが支援)を経て正式雇用となった。この実習前に、仕事に向かう意識づけと事前練習を兼ね、園で下請けをしていた当社の箱作り作業の特訓や、バス通勤の練習等を行っていたため、就業にはスムーズに移行できた。現在は在勤5年目になる。 |
(2)作業面の工夫 |
| 当初は箱作り、製品箱詰めなどの補助作業を行った。社員の皆さんが様々な梱包作業をEさんに与える中で、以下のような工夫と心くばりがなされていた。 [1] 図示、ガイド 製品の箱詰め方法は製品によって違う。それぞれイラストで箱内の並べ方を示したり、印に合わせて製品を乗せていけば完成するような「ガイド」と呼ばれる表示を作ったりした。 [2] モデリング 正しい並べ方を1セット作ってモデルとして提示したり、また2種類の製品を分別する際にはそれぞれの箱の上部に1つ入れるべき製品を貼り付けて示したりした。 [3]チェック体制 箱詰めされた製品はお客様の元へ発送されるわけなので、間違いがあってはいけない。他社員による二重・三重のチェック体制が確立されている。 しかしEさんに向いている作業内容がなかなか掴めず、またEさんが作業を途中でやめる、何もしていない時間がある、といった課題も徐々に挙げられてきた。そこでジョブコーチ支援を開始することとなり、山形障害者職業センターの計画のもと、社会福祉法人愛泉会 向陽園地域生活支援センターの深瀬ジョブコーチと筆者で3ヶ月間の支援を行った。 ジョブコーチ支援事業は、障害者の職場適応に関する様々な課題に対し、人的支援によって雇用の安定と促進を図ることを目的としている。ジョブコーチが事業所を訪問して、実際の現場で障害者本人の特性に応じた指導助言を行い、また家庭との連携も進めていく。今回は事業所の取り組みに協力する形での支援となった。 |
3.ジョブコーチ支援の中から
(1)駐車場草とり、会社前歩道の掃き掃除 |
| 環境整備の要望があったため、ジョブコーチ付き添いにより行ってみた。 ○ブロック分け 特定の範囲だけを掃除し続けたり掃き残しが多かったりしたので、掃除する範囲を細かく分割し(イラストで示す、アスファルトの境目で分ける、棒を置いて境界線を作る等)、そのブロック毎に掃除するようにした。すると視線の範囲が狭くて済むので掃き残しのチェックも行き届き、順序良くブロックを次々掃除していくと全範囲がきれいになった。 “どこからやればよいか”“前回どこまでやったか”“どの程度までやればよいのか”といった点は、意外とわかりにくいことだったようである。 |  会社前の歩道。山のようにあった落ち葉もだいぶ掃けるようになりました。 |
(2)御用聞き |
| [1]新しい仕事の創出 社員の皆さんから最も多く挙がった要望が「箱運搬等の雑務をしてもらえると助かる」ということだった。そこでEさんには1日4回定期的に工場内に入り、各社員に用を聞いて回る“御用聞き”という仕事を設定してみた。 工場内では射出成形機から常時製品が作り出されコンベアで運び出されてくるので、社員には製品を入れる箱を倉庫に取りに行く余裕がなかなかない。そこへEさんが行き、指示された箱や材料のプラスチックペレットを持ってきたり、完成品を次の部署へ運んだりする。 箱、箱に入れるパット、製品を包むマットは何十種類とあるが、Eさんはその時使われている箱を一瞥で覚え、同種の箱類を間違いなく持ってくることができる。社員の皆さんから「ありがとう」「助かるよ」という言葉をかけてもらえるこの仕事で、Eさんは大きなやりがいを得ることができる。 |
| [2]スケジュール表 最初のうち、1日4回の御用聞きに行き忘れることが度々あったので、Eさん用に1日のスケジュール表を作成し、ここで御用聞きの時間帯の意識づけを行った。 [3]居場所表示 仕事を頼みたい時にEさんがいないという事態を防ぐため、Eさんが自分で現在位置を示すボードを準備した。しかしスケジュール表で定期的に工場内に行くことが定着してくると、社員はEさんが来たときに頼めるようになり、今では居場所ボードはあまり活用されていない。 |  指示された箱を車で運んでいます。 |
|
(2)倉庫内整備とトイレ掃除 |
| [1]あなたの仕事 以前から行っていた倉庫内の作業として、使用済み箱の現品票をはがす作業や、運び込まれた箱を所定の位置に戻して整理する作業があるが、空いた時間だけ行うようになり途中でやめてしまうことも見られた。改めて「これはあなたの仕事」「やってくれると皆が助かる」と伝え、責任感をもてるように支援している。 |  倉庫は大量の箱。 整理は至難の業ですが大事な仕事です。 |
| [2]できたことを褒める また社員Wさんの提案で、Eさんに工場内男子トイレの掃除を任せた(トイレ掃除は毎朝女性社員が交代で行っていた)。Eさんは手順をすぐ覚えてきれいに掃除でき、社員に大変好評だった。その点をWさんから褒められるとEさんは自信がつき、責任感をもって掃除を毎日継続し、時々スリッパが揃えられていないことを嘆くまでになった。更に、以前Eさんは下履きのまま工場内に入る・トイレを下履きで汚すということがあったが、それもなくなり、下履きと上履きの区別をしっかりつけられるようになるという効果もあった。 |
4.今後の展望~射出成形機を任せられて
| このように1つの部署に固定所属するのでなく、横断的な仕事をする場合、時には複数人から指示が同時に出されることもある。仕事の優先順位づけというものは、会社全体の仕事の流れが把握できていないと適切な判断ができない、かなり難しいことである。そこで一般的には、障害者の仕事をマネジメントする立場の者に、指示系統を一本化するのが望ましいと言われている。 |
| そんな中ついに、A製造部長から、Eさんに1台の成形機を担当する機会が与えられた。このラインは箱詰めの際、決まった並べ方はなくて入れるだけでよく、微細な製品チェックは次の工程で行われるので、Eさんも過度なプレッシャーを負うことなく行えた。周りで見ていた社員も「心配だったけど、やってみるとできるものだね」との評価。この経験でEさんは、今まで以上に「会社のために働いている」「自分にもこれだけできる」という達成感を味わうことができ、Eさんの仕事の幅もグンと広がった。 今後も新たな仕事を任されることがあれば、それに付随する新たな課題が生じるかもしれない。しかし社員の誰もがEさんに気を配り、声をかけ、様子をみる体制ができあがっているので、その都度きめ細かな指導をされることにより、課題に対処していけることと思う。 |  ラインにて。 ゲートから製品を外して箱に入れます。 |
5.障害者雇用の道程を照らす大きな光
| 支援開始当初にあった「仕事を途中でやめる(現品票はがし・箱の整理)」「一部しか行わない(掃き掃除・草とり)」「何もしていない時間がある」といった課題は、周囲の人から見ると「仕事に対する意識・社会人としての自覚が足りない」と映る。これはむしろ当然のことでもある。しかしEさん本人は「この仕事は途中でやめよう」「今は何もしなくていい」などと考えていたわけではない。この両者のズレの原因を考えると、周囲の人には“今は○○をやってほしい”“ここまでやってほしい”という期待があり、一方で本人は“今何を期待されているのか、やるべきことがわからない”“どこまでやる、という目標がわからない”と困惑していたのかもしれない。このズレは放っておくと、雇用主側と障害者との間に溝を作り、両者にとって憂慮すべき事態になりかねないことである。 そうなる前に当社では手を打った。勿論人は誰でも、突然変わったり急激に改善したりすることなどないが、「放っておいてはいけない」「何かしよう」と思った時点から何かが変わっていく筈である。 「本人に向いている仕事がわからない」、これは障害者を雇用する多くの事業所が直面する問題である。しかし山形大光(株)では社員の皆が「とりあえず試しにやってもらって、それから考えよう」というスタンスでいた。「どうせできないからやらせない」「できなくても無理にやらせる」ではなく、Eさんができる仕事・できそうな仕事をあれこれ探して、時には作って、与えたのである。 その過程の中に、[1]本人の仕事の範囲を明確にして、ここまでやるという目標を示す、[2]本人の任務であることを明確に示して責任感を養う、[3]できている点を褒めることで達成感を生み、次への意欲につなげる、といった心くばりがあった。障害者雇用に際して行われる工夫の殆ど全てがユニバーサル・デザインであると私は考える。障害者にとってわかりやすい詳しい指示・明確な指示は、障害のない者にとってもやはりわかりやすく、障害者が社会人としての可能性を広げられる会社は、障害のない者にとっても才能を発揮できる、可能性という光のある会社なのだ。だから障害者に対するものと同じ心くばりが会社全体で誰にでも行われれば、全員が働きやすい会社になるのではないだろうか。決して面倒で大がかりなことではなく、会社の連帯感の中で自然に生まれてくるちょっとした心くばりでよいと思うのである。 山形大光(株)の皆さんの温かい見守りの根底には、障害の有無にかかわらず、同じ社員として・仲間として受け入れる心があることは言うまでもない。Eさん自身が「みんなに気をかけてもらい、いろいろ教えてもらえることは本当にありがたいと思っている。俺は本当に良い会社に入れてもらった」と、常々口にする。この言葉に、山形大光(株)の姿勢の全てが表れている。 私もジョブコーチとして、このように温かく理解ある会社に関わらせていただき、学ぶところが多くあった。深く感謝いたします。 |
| 執筆者:山形県社会福祉事業団 西村山精神障害者地域生活支援センター ジョブコーチ 小竹 由子 |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。