やる気を育てる障害者雇用
2003年度作成
| 事業所名 | 株式会社 きものブレイン | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 新潟県十日町市 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | きものアフターケア・きものガード加工・きもの縫製・きものリサイクル事業及び全国各地の有力呉服店と提携し、「きものらんどりー」のブランドで受注等の事業 | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 234名 | |||||||||||||||||||||
| うち障害者数 | 23名
|
1.障害者雇用の状況と理念
(1)障害者雇用の理念 |
| 「障害を持つ人にも安心して働ける職場を提供する」という理念のもと、障害者の人格を認めて共に成長できる社内体制を作り障害者の雇用を推進している。 働いている障害者は、視覚障害を除き障害の種別も多岐にわたっており、本社及び工場は、重度障害者(車いすの人)が容易に働けるバリアフリーの建物である。 また、障害者雇用で特定の職種にかかわる人だけでなく、委員会活動などを通じてより多くの社員が共にかかわる社内体制を作っている。 |
(2)雇用及び離職の状況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] 障害者雇用の増加と離職者が少ないことから障害者の定着率は高い。 [2] 職域拡大により障害者雇用の増加が続いている。 [3] 企業の工夫等により重度障害者の増加及び重度障害者の雇用比率が高い。 [4] 離職した者の理由は、体調を崩した者・結婚による転居・高齢等、本人の都合によるものが殆どである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)就労場所・作業部署別配置状況 |
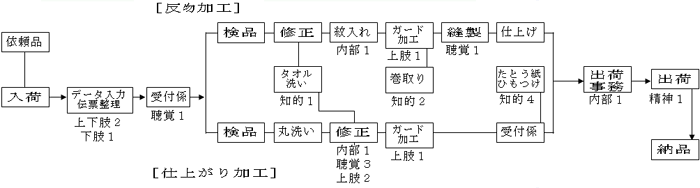
(4)障害者の作業内容 |
|
2.障害者雇用のための仕事の確保
| 従来、「たとう紙」(和服などをたたんでしまっておく厚い包み紙)の完成品を購入していたが、製造元が人手不足等よりの納期が遅れてきた為、職域開発としてこれの半製品を購入し、ひも付け作業を知的障害者の仕事とした。 | 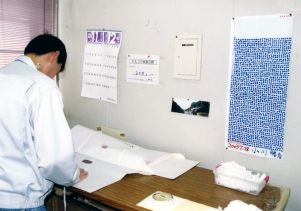 たとう紙ひも付け |
| ※ひも付け枚数目標を1日200枚と自分でたて、3万枚に挑戦 |
| 車いすの障害者対策として、データ入力できるようにシステム改善を行っている。また、修正デザイン担当は、美的センスを求められることから、個々の静かな環境の職場を用意している。 |  データー入力 |
| ※両手首の機能障害により両手に突起物のついた手袋を付け、キーボードを操作しパソコン入力 |
3.雇用継続のための工夫
(1)連帯感、帰属意識を養う |
| 障害者・健常者共に職場内では、明るく挨拶をすることを徹底し、職場の活性化を図っている。 「社員全員参加」の理念を持ち、会社行事に参加するよう働きかけ体験させている。 毎週行われる部門内の朝礼において、1分間スピーチを順番に行い、知的障害者にも連帯感をもってもらう。また、懇親会や旅行などにも積極的に参加してもらい、他の職員との交流を深め、帰属意識を養っている。 |
(2)目標の設定 |
| 毎日の目標を自分自身で設定し、1日の終わりに作業日報に記入の上指導員に報告させる。そしてその成果を相互に確認することにより、責任感を養っている。 知的障害者にあっては、働く目的を明確にする為、個々人の目標数を設定し、作業状況や成果の確認をすることで「やる気」を起こさせている。 |
(3)障害者推進委員会 |
| 健常社員にも理解と協力を促し、「障害者推進委員会」(職場定着推進チーム)を機能させ、障害職種毎にチームを作り定着をはかっている(下記参照)。 チームの委員は、各部門からの他に障害者の委員も入れ、委員会の開催は3カ月に1回であるが、問題がある場合はチーム毎にその都度招集し対処している。 なお、副社長は、オブザーバーという形でいつでも支援している。 〈チーム名と役割〉
|
(4)成果の評価 |
| たとう紙のひも付け作業が、3万枚達成後、全体朝礼において表彰状と記念品を授与し、本人からスピーチをしてもらう。社員から大きく評価され、自分の成果をかみしめることとなる。 目標が達成すれば周囲から評価され、達成されなければまた次回に挑戦するという方法を用いることによって、職場内に「やる気」が醸成されている。 |
4.今後の課題、展望
(1)課 題 |
|
(2)展望等 |
|
5.まとめ
| 本事業所は、障害者雇用において、さまざまな工夫をしており、いずれも高く評価できる。特に高い雇用率を達成している要因を分析すると、以下の3点にまとめることができる。 第1に、「障害を持つ人にも安心して働ける職場を提供する」という企業理念を実際に具現化できるよう、さまざまな取り組みがなされている。たとえば、障害者と健常者の双方がメンバーとなって、「障害者推進委員会」を設立している。そこでは、下位組織として5つのチームが編成され、職場における安全面・健康面等様々な問題に対処できるように工夫されている。これによって、障害者の職場定着が推進されていると考える。 第2に、障害者のための仕事(作業)を新たに作り出すことによって、障害者雇用のための職域を拡大している。たとえば、知的障害者のために「たとう紙」に関わる作業を新たに作るとともに、それを知的障害者の教育訓練の場として活用している。また、車いすの障害者でも作業できるコンピュータを利用したデータ入力作業を設けている。 第3は、障害者雇用にあたって、健常者と同様、「配慮はするが特別扱いはしない」、つまり「本人ができることは本人にやらせる」、そして、「各自が目標を達成したら、全社員でほめて、共に喜ぶ」という姿勢(取り組み)を大事にしている。そういう中から、障害者も健常者とともに働く意欲が高まり、雇用継続も図られていくのだと考える。 |
| 執筆者:新潟大学教授 松井 賢二 |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











