老人福祉施設における障害者雇用の取り組み
2003年度作成
| 事業所名 | 社会福祉法人H 老人福祉施設 | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 石川県金沢市 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 老人福祉施設・通所介護(デイサービス)・訪問介護(ホームヘルプサービス) | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 30名 | |||||||||||||||||||||
| うち障害者数 | 3名
|
1.障害のある人の採用に至った経緯
| 障害のあるなしに関わらず、同じ職場の仲間として一緒に働くことを理念としている。 平成11年より障害のある人の就労支援を行っている金沢市社会福祉協議会(以下、「金沢市社協」とする。)に、「この施設に適した障害のある人がいれば、すぐにでも採用したい」と相談をした。 そこで、金沢市社協を窓口とし、事業所及び金沢公共職業安定所、石川障害者職業センター(以下、「センター」とする。)と話し合った結果、職員としてすぐに採用する前に仕事に慣れ、事業所側も本人の適正を見極めるために職場実習制度を活用することになった。 金沢公共職業安定所の紹介により、男性3名、女性1名(のちに自己都合により退職)が実習生として選ばれ、平成14年12月から平成15年3月までの間に職務試行と職場実習制度を活用し、実際の職場で実習を行うことになった。 まず最初に、障害のある人の職業適性及び職業能力を把握することを目的に、センターのカウンセラーによる約2週間の職務試行を行い、その評価に基づき、事業主に障害のある人の職業能力等について、さらに理解を深めてもらうことを目的として、石川県障害者職場実習制度(石川県の独自制度)による実習を1ヶ月間行った。 この結果、4人は日常の挨拶等も礼儀正しく行なえ、また作業効率も今後伸びると期待されることから、更に1ヶ月間のトライアル雇用(試行雇用事業)を経て、平成15年3月、職員として正式に採用されることとなった。 |
2.職務の内容
| 障害のある人を採用するにあたり、新たに「環境衛生員」という職種を設けた。 その職務の内容は、施設内外の掃除、物品の整理整頓、公共図書の整理、電球や蛍光灯の交換等が主である。 |
3.3人のプロフィールについて
|
4.職場実習を行う際に決めたこと
| 初めて障害のある人と関わるため、不安なことや分からないことが多くあった。しかし、障害のあるなしに関わらず働きやすい環境を整えようと考え、事前に以下のことを決めた。 |
(1)他の職員と同じように対応する |
| 障害のあるなしに関わらず、他の職員と同じように対応した。これは、労働条件や服務規定についても同じである。 |
(2)日常のあいさつをしっかりとする |
| 円滑な人間関係を築くために、お互いに気持ちよく「あいさつ」をすることを心がけている。 毎朝、玄関 ⇒ 職員ルーム ⇒ 事務所の順番で、大きな声で「おはようございます」、仕事が終わって帰宅する際も同じように大きな声で「お先に失礼します」と、あいさつをした。その際、他の職員は例え仕事中でも必ず手を止め、しっかりした姿勢であいさつを返すようにした。 この基本的なコミュニケーションがあって、初めて職員相互の理解につながるのではないかと考えている。また、最初はAさんをはじめBさんやCさんも自信なげなあいさつであったが、徐々にはっきりと笑顔であいさつが出来るようになり、それに伴って仕事にも自信を持って臨むことができるようになった。 |
(3)就労支援機関へのホウ・レン・ソウ(報・連・相)をする |
| 職場内のことなので、基本的には職員同士で障害のある人のサポートを行なうが、仕事の指導方法(新規の仕事の指導方法など)や職場生活など、事業所だけでは解決が困難なことや解らないことがあれば、積極的に金沢市社協をはじめとする就労支援機関と打合せを行なうことにした。その結果、様々な変化(本人・職場・サポート体制)にもすばやく対応ができた。 |
(4)担当者を配置する |
| 指示や作業内容にばらつきがない様に、同じ作業は同じ担当者が指示を出し、報告を受けることにした。これにより、障害のある人が混乱して、次に何を行なえば良いか、職場の誰の指示に従えば良いか等が解り易くなった。 |
(5)目的を持って障害のある人に関わる |
| 職場実習を進めて行く中で、次にどのようなことを身に付ける必要があるのか目標を決め、段階を踏んで、仕事内容の質を向上していく計画を立てることにした。 →短期目標を「環境に慣れる」、長期目標を「指示を待たずに、自立して一日の作業をこなせるようにする」ことと決め、目標を一つずつ上げ、達成していった。
※現在は第4段階を達成し、第5段階に入っている。(平成15年11月現在) |
(6)業務の内容を事前に伝える |
| 仕事の内容を事前に決めておき、一日のスケジュールを表に表して、各自に持たせた。 「次に、何を、どこで、いつまでするか」を事前に伝えることで、障害のある人の仕事が急になくなったり、不安やストレスを軽減することに非常に役立った。 |
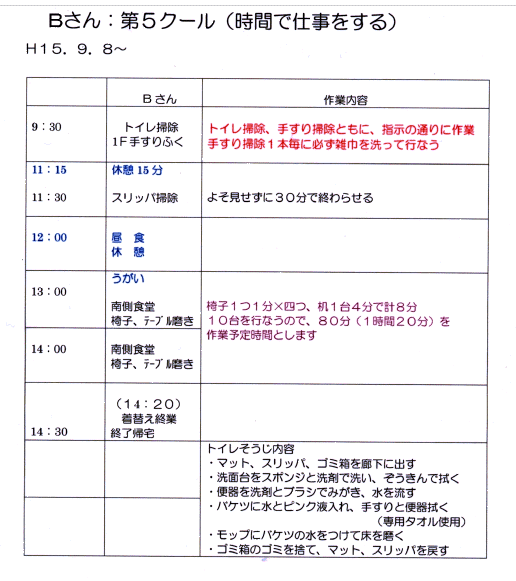 |
5.仕事を通じて工夫したこと
(1)仕事の指示をする際に、曖昧な説明をしない |
| 例えば、洗面台の掃除では、「ここを掃除してください」や「洗面台を掃除してください」という指示では、実行できなかった。 具体的に、「このスポンジにこの洗剤をつけて、この順番でこすってください」と、担当者が一緒に例を示しながら説明をすると、作業手順通りに掃除をすることができた。 |
(2)指示書を作り、指示を受けなくても自分でできるようにした |
| 一度覚えた作業であっても、途中で声を掛けられたり、大きな物音に気を取られたりすると、次の作業手順が解らなくなることがあった。そこで、作業手順を書いた指示書を作成し、次の手順が自分で確認できるようにした。 (作成した作業指示書) 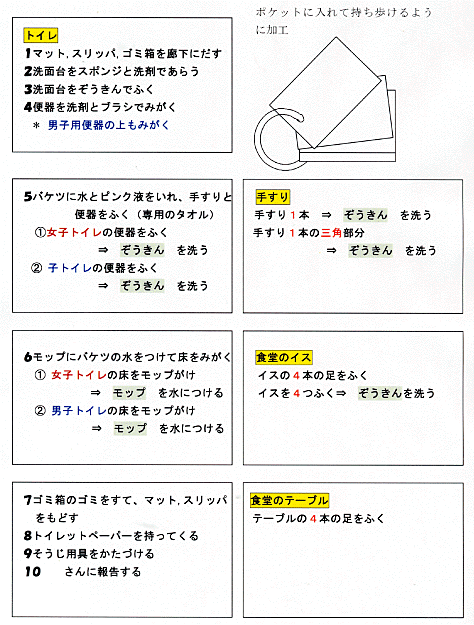 |
(3)仕事の意味を伝える |
| 職務の中心となる館内の清掃について、「綺麗にする」という仕事の意味を伝える難しさがあった。 ある日、Aさんに「床を拭いて綺麗にしてください」と指示をした。しかし、Aさんはただ、担当者の動きを真似して、モップで床を撫でるだけであった。 そこで、担当者は「Aさんにも汚れとはどんなもので、どのように綺麗にするのか分かるように説明しなければならない」と考え、ある方法を試してみることにした。 それは、小麦粉を用意し、食堂の床に撒いて「これが汚れだよ、床を撫でるだけでは綺麗にならないよ」と説明しながら、一緒にその小麦粉をモップで掃くというものであった。 この手法は、Aさんにかなり有効で、これ以降、自分で汚れを見つけ、綺麗に掃除ができるようになった。現在では、窓に張ったクモの巣も自分で見つけ出し、綺麗に取れるようになった。 |
6.今後の課題・展望
| 彼らに自立して生活できるようになって欲しいと考えている。 現在は家族と同居し、支援を受けながら生活しているが、いずれ自分の力で生活しなければならなくなる。そのためには昇給も必要であるし、そうなれば、事業所として今以上に仕事の質や量を求めることになる。 特に、今一番の課題は、作業を時間どおりに遂行することである。これを乗り越えると、仕事の幅が増え、昇給の可能性も出てくる。そのためにも作業中に必要に応じて声を掛けることができれば良いのだが、それでは事業所としての負担が大きくなる。そこで、新しい仕事を増やす時などには、就労支援機関と相談をしたり、ジョブコーチ制度を活用する等を行なって、効率的に職務内容を充実することが求められる。 |
| 執筆者:社会福祉法人金沢市社会福祉協議会 主事 上田 浩貴、主事 川守 祥央 |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











