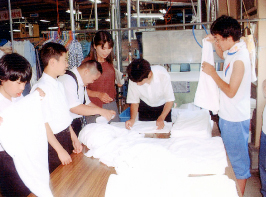現場教育による能力アップと生活支援の取り組み
2003年度作成
| 事業所名 | 株式会社チャームランドリー | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 島根県浜田市 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 一般クリーニング業、ホテル向けシーツ、バスタオル。ユカタのレンタル事業 | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 52名 | |||||||||||||||||||||
| うち障害者数 | 12名
|
1.障害者雇用の経緯
| 昭和51年、3名の障害者を含む従業員と共に操業開始し、56年には国の特別融資を受けて工場を整備、本格的に障害者雇用に取り組む。景気動向に伴う変遷はあったが、生産性の向上に重点を置いた経営により雇用の安定を維持している。 |
2.採用、教育訓練について
(1)会社としての採用方針と職場実習の受け入れ |
| 障害者の特性や適性、経験等を考慮して採用配置することを方針としている。欠員が生ずれば即補充の考え方に立っている。 地域の養護学校等から依頼のある生徒の職場実習に対しては、毎年受け入れ職場体験の学習に極力協力実施している。平成12年/2名、13/2名、14/1名、15/1名の実習生を受け入れた。過去5年間に実習生1名を含め、障害者3名を採用している。 障害者の障害の状況により、ハローワークの指導による職場適応訓練を実施している。これによる採用は4名である。 県の健康福祉センターの事業である「精神障害者社会適応訓練制度」を受け入れ、現在1名の実習生がいる。 |
|
(2)採用前の職場実習 |
実習期間中に知的障害者各人の職務適応能力や可能性、また職場における融和、人間関係などについて良く把握承知することに努めている。
|
(3)ジョブコーチによる支援と職場適応への取り組み |
| 地域障害者職業センター及びハローワークの指導・援助により、平成14年度より開始された職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業をいち早く検討して、会社として積極的に、ジョブコーチの派遣をお願いしこれに取り組むこととした。 これまで、仕上工1名(雇用前の支援)、プレス工1名(雇用後の支援)に対してジョブコーチによる支援を受けている。 まず始めに取り組んだのは、知的障害者で職場適応訓練を実施したが、仕上げ作業で職場適応が思うように進まない人に対して、ジョブコーチに支援を受けることとし、同時に家庭への助言を求めて長い目で実施した。 次いで仕事の能率面で困っている人への支援指導を受け現場責任者と一緒に取り組んだ。 その成果として1人は職場適応が進み、他の一人は確実性が増し生産性が従来より向上した。 ジョブコーチの派遣期間は、雇用前1名が6か月、雇用後1名が3か月であった。 |
(4)業務遂行援助者の配置と指導 |
| 知的障害者のうち重度障害者7名の各職場での作業の円滑化を図るために、作業方法、作業手順、その他必要事項の指導等を行えるよう、障害者雇用促進協会の指導支援のもとに、業務遂行援助者2名を配置している。配置転換となるユカタプレス機は1か月交替で作業転換を実施。仕事の内容の変更などについても、随時指導を行っている。 指導員の配置部署は、シーツロール部で、障害者3名につき指導員1名、ユカタ・タオルたたみ部で、障害者4名につき指導員1名を配置している。 指導員の配置により、確実性が増し、出来上がり枚数のチェック精度向上により生産性の維持、向上に結びついている。 |
3.労務管理・問題への対応
| 関係機関との連携を取りながら、職場定着を図り、かつ生産性の向上に極力取り組んでいる。 |
(1)S就業・生活支援センターとの連携 |
| 雇用障害者の中で、これまで勤務・生活に問題はなかったのに、ふとしたことで仕事が手に付かなくなったり、出勤しなくなったり、当人がトラブルを抱えるに至るようなことが発生する場合がある。 こうした場合、まず社内の職業生活指導員はじめ総務関係者で話を聞き、経緯を聴くようにしているが、関係者でも解決が困難な場合は、S就業・生活支援センターの生活支援ワーカーに連絡を取りアドバイスを得ると共に相談に応じてもらっている。また、必要に応じて来所願って直接本人と面談の上、問題の解決のための相談助言を得ている。 これまでの相談状況は、相談件数が毎月平均2~3件、年間では細かいものを含めると約60件に及んでいる。 |
(2)家庭との密接な連絡・対応 |
| 通常は、休日の変更や勤務に関するものを主として連絡している。欠勤が続く、何か問題が起きて休んでいる、通院が必要になった場合の通院の調整、あるいは昼食を取らないなど問題が生じた場合には、即座に生活相談員が独自に、あるいは普段連携を取っている就業・生活支援センターの生活支援ワーカーの協力を求めて、家庭訪問をして保護者とよく話し合って、問題の早期解決に向けて努力している。 |  相談は話し合いから始まる |
(3)障害者職業生活相談員の活動状況及び職場定着推進チームの活動状況 |
|
|
4.職場改善の実施
| 障害者の働きやすい環境、職場における安全確保のため、設備の改善、整備を行ってきた。 |
(1)2階への階段昇降機の設置 |
| 食堂休憩室がある2階への昇降のため、平成9年に階段昇降機を設置した。これにより、体幹障害者や視力低下の障害者の昇降がしやすくなった。 |  階段昇降機の利用 |
(2)安全設備の改善=ユカタプレス機用パトライトの設置(6台) |
| 従来は作業者の勘に頼っていた仕上げ部門のユカタプレス機に安全装置を付けることにより、作業の安全性と事故防止を図った。これは、作業者が両手でプレス機のボタンを押すと、同時に上部のパトライトが点灯する仕組みとなっている。この改善により安全が確保され、同時に作業に集中することができる。 |
|
(3)工場の出入り口の段差の解消 |
| 歩行上の安全確保のため、工場2カ所の出入り口の段差の解消を行った。 |
5.安全衛生、健康管理
| 安全衛生、福利厚生の取り組みは、従業員の日々の安定的労働を維持する上で不可欠な事項であり、意欲の向上やひいては生産性を追求する重要なファクターである。 |
(1)労働安全衛生の取り組み |
| 安全委員会の部会を開催して、最近の事例に基づき事故原因の解明、月間の目標の決定と安全意識の高揚を図るとともに、月1回職場のミーティングを開いて工場内の安全歩行の励行と安全ルールの遵守徹底を行っている。 また、昨年春の第2土曜日には、協会のビデオを借用して、「働く人の健康管理」や「こんな仕事だってできるんだ」を上映して、研修をおこなって意識と意欲の向上に役立てている。 |
(2)送迎バスの運行と安全意識 |
| 通勤者のうち9名(内3名はグループホームから)に対して、朝夕、会社バスにより最寄りの駅まで送迎している。 併せて、駅から自宅間においての安全面の呼びかけによって意識を高め、通勤途上の事故防止について指導している。 |
(3)健康管理 |
| 疾病の早期発見、健康管理のため、年1回の定期検診を実施(保健公社の来社)している。 |
(4)通院に対する配慮 |
| 疾病の早期発見と適切な治療のため、風邪等で通院を余儀なくされる場合、そのために遅刻・早退にいたる場合は、賃金カットをしないこととしている。(現在2名通院中) |
(5)福利厚生 |
| 二階の休憩室には、リフレッシュのためマッサージ機を設置しており、自販機も利用できる。 |
(6)会社行事 |
|
 カラオケ大会の風景 |
6.まとめと今後の課題
| 会社創立以来、長年にわたって障害者雇用と職場定着に取り組み、特に近年の受注量の減少を抱えるなか、労使一体となった生産問題への取り組みによる生産性の向上に努力し、障害者の雇用維持に努めていることは、優れた雇用管理と経営理念によるものであろう。 障害者の雇用面、特に外部の学校や施設からの教育実習に対しては積極的に受け入れ協力していること、社内の職場教育については計画的、一定期間をかけての現場実習により職場適応がスムーズに行われ、労使双方のミスマッチを少なくする努力が伺える。 特に知的障害者が抱える日常的な生活問題やトラブルへの対応に対しては、会社幹部でもある職業生活相談員が中心となって解決に当たり、かつ地域生活支援センターとの連携により迅速に問題解決に当たっておられることは、なにより心強く大切なことである。 今後の課題としては、高齢化がある。 就業者の年齢構成は、20歳以上30才代7名、40代以上(内55才1名)5名となっているが、20歳代と30歳代において谷間が見受けられることが今後の人員構成上の課題といえる。一方、勤続年数と加齢による定年退職等を考えるとき、いかに対処していくかが大きな課題となりつつある。障害者の場合いわゆる加齢による職務適応能力の低下と言う問題に直面する。 会社としては、このため、将来展望として高齢障害者への対応として、例えば小規模事業所として集約的に働ける職場構想について考えているが、企業単独では困難な課題であり、関係機関や行政等とのタイアップが必要である。 |
| 執筆者:(社)島根県障害者雇用促進協会 障害者雇用アドバイザー 須山 光弘 |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。