保育所における知的障害者雇用の取り組み~支援機関の協力体制~
2003年度作成
| 事業所名 | 社会福祉法人靖美福祉会 きらら保育園 | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 徳島県板野郡松茂町 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 保育所 | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 18名 | |||||||||||||||||||||
| うち障害者数 | 1名
|
1.事業所の概要
|
2.障害者雇用の状況
(1)障害種別及び人数 |
| 知的障害者 1名 |
(2)紹介元 |
| 公共職業安定所&障害者就業・生活支援センター&地域共同作業所 |
(3)仕事内容 |
| 保育所内の用務 [1]洗濯物の洗濯、干し、たたみ [2]掃除 [3]準備(食事の配膳、昼寝のふとん等) *タイムスケージュールや細かい内容については、資料1~3参照 |
3.障害者雇用の経緯
| これまで、徳島県内の保育所では、知的障害者を雇い入れする事例はなかった。2年前、県内にあるあっせん型障害者雇用支援センター(現 障害者就業・生活支援センター)が障害者の「はたらくくらすネットワーク会議(関係機関の連絡調整会議)」を開催していた。その会議の中で、県内でモデルとなるような知的障害者の保育所就労、「児童福祉施設(児童家庭局所管施設)における入所児童(者)処遇特別加算費」を有効活用して知的障害者の職域拡大を図ることについて、話し合いがもたれた。その時に、養護学校と障害者職業センターが主となり、県内のある保育所での職場実習を行うことになった。結果として就労には結びつかなかったが、関係機関の担当者は徳島県内でモデルとなる雇用事例を待ち望むようになった。 2003年4月、きらら保育園は開園した。「元々、保育園を開所したときから障害者も共に働ける保育園にしたかった。」「保育園は、こまごました業務がたくさんある。たくさんすぎて、どこの保育所でも保育士さんが片手間ではやり切れない。」「片付けや運搬、色んな業務があるから、そこで障害のある人が働けるのではないか?」と、園長の葉田さんは考えていた。ただ、葉田さんは「どういう風に受け入れをしたらいいかは分からなかった。」と言う。 2003年9月末、きらら保育園で用務員の補充が検討された。障害者の雇用について、葉田さんは主任の吉岡さんと相談をし、吉岡さんも「障害者と共に働ける保育園」という想いが心の片隅にあったので、すぐに賛成をした。 2003年10月、葉田さんたちは「障害者の雇用を進めたい」と思ったものの、どこへ相談してよいのか、どういう風に雇い入れしてよいのか、全く見当がつかなかった。県内にある児童施設や県の社会福祉協議会に問い合わせてみたが、詳しいことは分からない。最終的に、地元のハローワークへ問い合わせをして、担当官と相談をすることになった。きらら保育園のあるエリアには障害者就業・生活支援センターが存在し、担当官と相談する際に、たまたま、そこのスタッフとも顔合わせをすることができた。 2003年10月末、きらら保育園は、障害者雇用へ向けて地元のハローワークと障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター等と相談をはじめた。 |
4.知的障害のあるAさんへの支援とその経過
| 徳島県内では初めてとなる保育所における知的障害者の雇用について、雇用に至るまでの経過や支援の内容(活用された資料)、雇用後の定着支援の内容等を以下にまとめた。 |
(1)仕事内容の整理(職務分析→職務設計) |
| 2003年10月末、障害者就業・生活支援センターのスタッフがきらら保育園を訪ねた。その際、保育所で働いている他県事例の資料や県内のある保育所で行われた職場実習の資料がきらら保育所に提示された。具体的な資料に目を通した葉田さんは「よそでもやっているなら、うちの所でもできるわ。」「うわー、こんな事までできるなら、本当にいいなあ!!」と感激したと同時に、障害者雇用への不安が軽減されたそうだ。 障害者就業・生活支援センターは、まず最初に、障害者雇用に向けて用務業務の仕事内容を整理することを提案した。葉田さんと障害者就業・生活支援センターのスタッフは協力して、勤務時間内にどういう仕事内容を設定するのがよいかを考えていった。考えられた内容を障害者就業・生活支援センターが簡単に取りまとめ、仕事内容の素案が表になった(資料1)。 2003年11月初め、障害者就業・生活支援センターと障害者職業センターが合同できらら保育園を訪問した。10月末にできた仕事内容の素案を元に、保育園と2つの機関が共同して検討を重ね、仕事の内容表が完成した(資料2)。葉田さんは「感激ばかり。こんな風にしてもらえるんやなあ。世の中捨てたもんじゃないなあ。」と感じたそうだ。 |
(2)採用予定者の選定と制度の活用 |
| ハローワークと障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターが保育園での就職希望者を募った。仕事内容を説明するだけでは分かりにくいので、支援機関は希望者と保育園の見学をした。最終的には、知的障害のある女性1名(Aさん)が対象となった。雇用に向けた支援内容や支援体制をAさんと保育園、支援機関とが話し合った。 その結果、1つは、雇用にむけてジョブコーチ支援事業を活用することにした。知的障害への支援について、保育園には具体的なノウハウがないため、他の保育士のためにも、人的なサポートはとても有効だと考えた。もう1つは、「児童福祉施設(児童家庭局所管施設)における入所児童(者)処遇特別加算費」の制度活用を進めた。 |
(3)支援機関やジョブコーチによる支援(雇用まで) |
| Aさんは、養護学校卒業後、一旦は仕事をしていたが、就労を継続することはできなかった。Aさんは支援機関に相談をして、一時、地元の地域共同作業所に通いながら、次の就職先を探しているところだった。支援機関は、Aさんが通っていた地域共同作業所と連絡調整を行い、地域共同作業所とも就職に向けた段取りを進めた。保育園が心配していたAさんの通勤は、支援機関が通勤路の確認から通勤方法の検討までAさんと相談を進めた。複数の機関が関わりながら、1つの方向へ向かって支援体制はスムーズにつくられていった。 Aさんは恥ずかしがりやで、仕事を行う上では、周囲とのコミュニケーションが課題だった。また、仕事内容をしっかりと覚えていくためには、多少時間がかかる。仕事内容を整理した表を活用し、ジョブコーチによる人的なサポートが入ることで、Aさんはスムーズに仕事を覚えていくことができた。 Aさんの生活面(両親とのやり取り等)は、支援機関がサポートをしているので、事業所としては安心だった。Aさんが仕事をする上で生活面の影響があれば、ジョブコーチや障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、ハローワーク等へ相談できる支援体制がある。葉田さんは「身内に障害のある人が生まれても大丈夫だなあ、と。そういう気持ちがしました。」と言う。 |
(4)職場定着へ向けた支援、ナチュラルサポートへの支援(雇用後) |
| Aさんの仕事ぶりは大変良く、吉岡さんも「最初からずーっとコツコツ仕事をこなしてくれている」と言う。「児童福祉施設(児童家庭局所管施設)における入所児童(者)処遇特別加算費」の制度活用との関係で、雇用前の期間は短く、雇用後に継続した支援を必要とした。Aさんがする仕事の内容は、臨機応変に仕事の順番を組替えたり、新しい仕事内容に取り組んでみたりで、日々変化がある。その都度、支援機関と相談をして、仕事内容の変更等を行った(資料3)。 また、最近は、用務の業務だけではなく園児と関わる時間が持てるように業務内容の工夫をはじめた。支援機関と相談をしながら、給食の配膳や昼寝用布団の準備等をAさんの仕事内容に加えた。昼寝用布団の準備は、全ての布団の組み合わせ(敷布団や掛け布団)を覚えないといけないので、ジョブコーチがする支援に習って、事業所が主体となってAさんの支援を組み立ててみることにした。Aさんに分かりやすく、仕事がしやすくなるような情報提供の仕方を保育園が行った(写真2)。当初、Aさんは判断がつかずに布団を持って立ったままのこともあったが、今では、布団の準備をスムーズに行えるようになった。 |
|
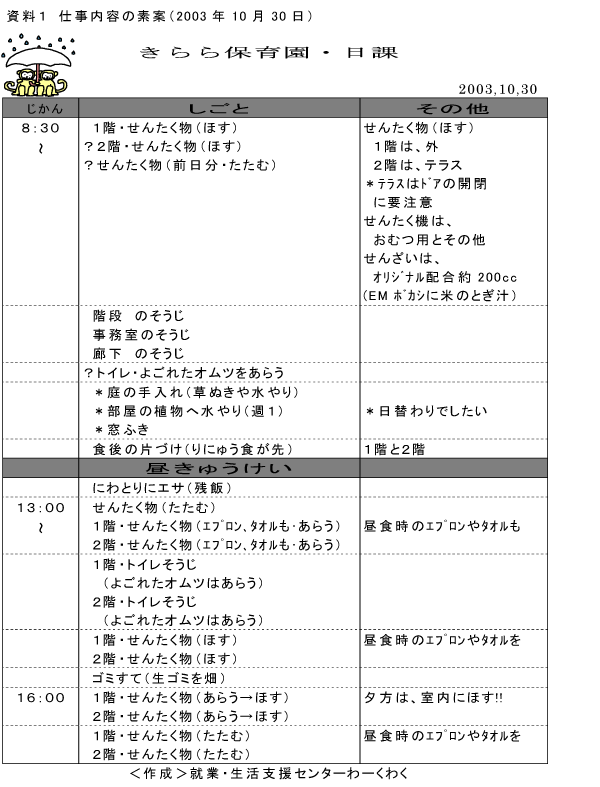 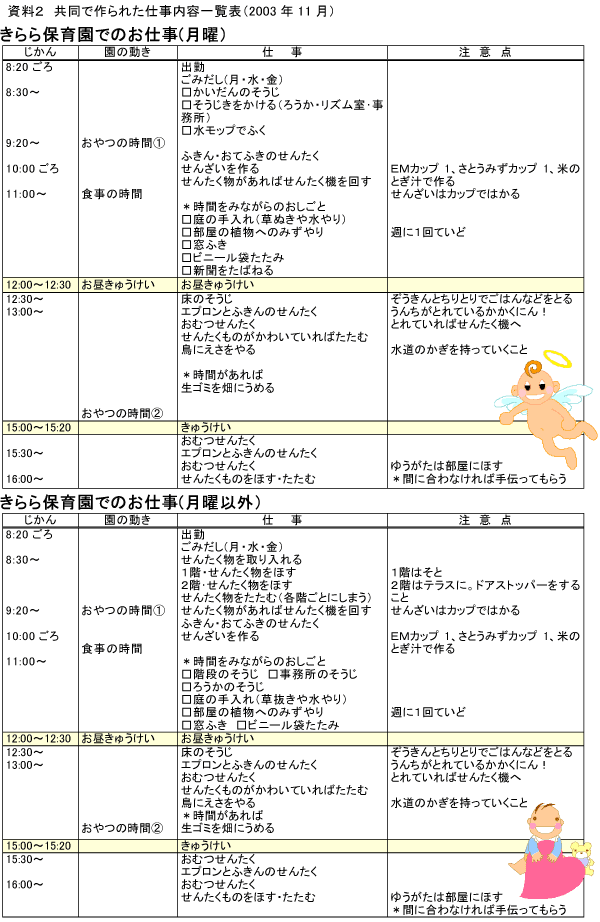 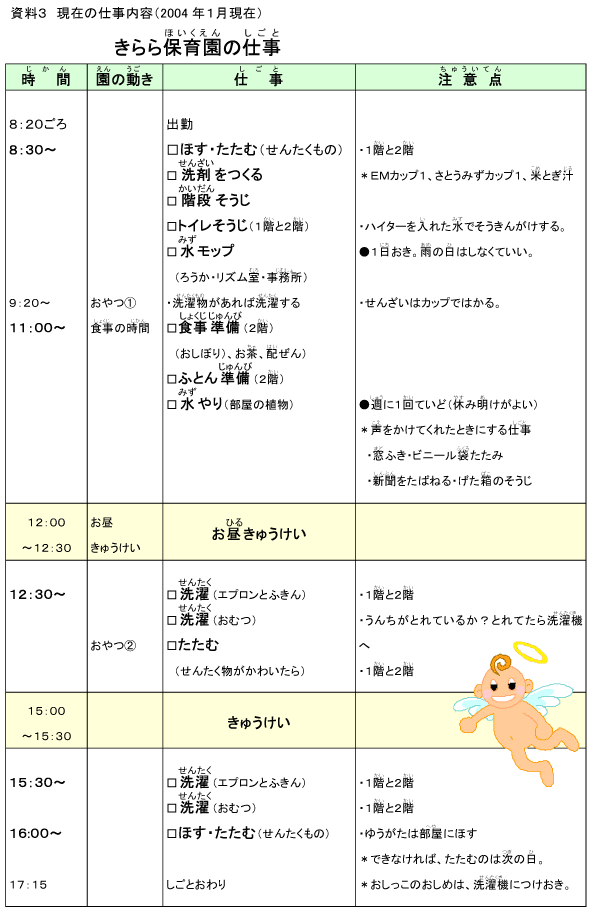 |
5.取り組みの効果
(1)知的障害のある本人にとって |
| Aさんは仕事を始めたころを振り返って「不安やった。」「仕事ができるかなぁと思った。」「(初日は)とても緊張しました。」と言う。今現在の気持ちを聞くと「仕事は楽しいです。」「洗濯しながら子どもを見るんが楽しいです。」と答えてくれた。避難訓練の時、園児の手をひいて避難をしたり、乳幼児を抱かせてもらう機会があって、Aさんの心の中で何かが変わり始めたようだ。そんなAさんの様子をジョブコーチは「Aさんの引込み思案なところが、子どもと関わることでクリアーにされていく。コミュニケーションの課題をうまくフォローしている。」と捉えている。 2004年2月には、Aさんの出身校でもある養護学校の在校生が、様々なはたらく場を学ぶ授業の一環として、きらら保育園を見学している。どの学生も、用務の仕事をしながらも園児とふれあうAさんを見て、目を輝かせていた。また、見学した学生は、卒業後就職がうまくいかなくなったとしても、再就職にむけた取り組みが支援機関と相談をしながら行われていることを目のあたりにしたのだった。 |
(2)保育所にとって |
| 葉田さんと吉岡さんは「職員は洗濯物の心配をしなくてもよくなった。時間外の仕事になってしまうところが解消された。」「食事の前後は、保育所で一番忙しい時間帯。 |
| 給食の配膳、おしぼりの準備、昼寝用の布団敷き。どれをとっても本当に助かる。」「みんなの雑務が少なくなるので、保育士はその分、子どもに時間をあてれるようになった。」と話す。「普段、障害者と接する機会すら少ない。そうなると構えてしまうことが多くなる。保育所がそういうことをなくしていく場になれたらいい。」「これだったら、よその保育所でも絶対に良いと思うだろうから、私たちも事あるごとに宣伝します!!」とも話してくれた。 |  洗濯物を干しているところ。 これらの用務をAさんがすることで、 保育園全体の業務遂行がスムーズになった。 |
(3)支援機関にとって |
| 徳島県では初めてとなる保育所での雇用事例であったため、仕事内容の表(業務分析表)や「児童福祉施設(児童家庭局所管施設)における入所児童(者)処遇特別加算費」制度の資料などが、関係機関に周知された。今後、徳島県内においても、この分野で更に障害者雇用が進むことが期待されている。 |
6.今後の課題・展望
| 今回の取り組みは、これまで他県での事例はあったが、徳島県においては初めてとなる取り組みである。今後、徳島県内に限らず、福祉分野等の対人サービスの業種にも障害者の職域が拡大されていくことと思われる。今回の取り組みも、各地の事例を紹介することで事業所側の不安が解消されているし、支援内容についても各地の事例を参考にしている。障害者雇用の促進を考えると、それぞれの支援機関がもっている情報や各地での取り組みがより一層共有化され、今回の取り組みのようにそれぞれの支援機関が協力して支援の体制をとることがとても大切なことであると痛感させられる。色んな要素を含んだ大きな効果が、この事例にはあるように思われる。 |
| 執筆者:就業・生活支援センターわーくわく 佐野 和明 |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。













