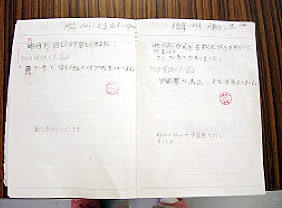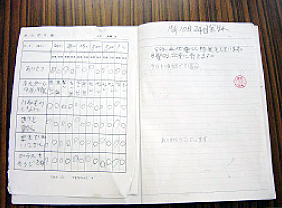精神障害者・知的障害者が成長する日々
2003年度作成
| 事業所名 | 株式会社エコシティ | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 軽重量発泡骨材の製造 | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 23名 | |||||||||||||||||||||
| うち障害者数 | 2名
|
|
1.事業所の沿革及び事業概要
| 環境保全を目的として、平成11年11月会社の創業後、循環型地域社会構築への貢献を理念とし、我々に最も身近に発生する廃棄物であるガラスびんとアコヤ、カキの貝殻を有効活用したネクストワン(軽重量発泡骨材)の製造を開始した。それとともに、リサイクル事業とその取組み、ならびにリデュース・リユース・リサイクルの大切さを多くの人に知ってもらうためにゼロエミッション活動(環境教育活動)も行っている。 |
2.障害者雇用に対する企業の考え
| プラント設立当初から、地域社会への貢献の一部として障害者雇用は考えていた。自らが参加することで勉強となる、そういう機会として全員で取組み、障害者は社会生活の勉強、我々は心の勉強をさせてもらう。 『Face and face,Mouth and mouth,Heart and heart』 |
3.知的障害者雇用の経緯
| 「僕、就職が決まったら新しい自転車を買ってね、これはお母さんにあげるんよ」「どうして」「お母さんの、ペダル壊れているから」。知的障害をもつ彼と初めて会った日の会話である。 ハローワークに障害者の雇用で相談に行ったところ、ジョブコーチの制度と共に一人の青年を紹介して下さった。同伴してこられた方は、素朴で仕事着のままの姿で彼を見守っている優しい眼差しを持つお母さんだった。3日間できるかどうかやってみようか、ということでスタートを切った。 |
| 彼が頑張ろうと意気込んだのは、ガラスびん再生処理プラントでのいくつかの仕事である。 掃除、作業の補助、そして現在、日本でも当社だけと思われる作業をしてもらっている。家庭から排出されたガラスびんのリサイクルによって生まれる軽重量の発泡骨材の製造過程において、原料となる廃ガラスびん破砕後に発生する残渣の分別作業が、彼らの担当である。 見学に来られた方が一同に「ここまでするのですか」と聞かれるほど細かく根気のいる作業である。キャップの隙間に残ったガラスの除去、廃プラ、金属キャップいくつかの残渣を最終まで分別して次のリサイクルへ。普通に考えれば最終処分場にて処理した方が早いと考える物ばかりである。でもこのように見えないところでの彼らの作業により、当社の理念は支えられている。 |  分別作業に従事している知的障害者の 高橋 充さん |
4.精神障害者雇用の経緯
| 2人目もハローワークからの紹介、ジョブコーチ制度で出会った精神障害を持つ彼。会った日は表情もなく「はい」「いいえ」という言葉の繰り返しであった。彼をケアする方は体力のない事をしきりに気にしていたのだが、私から見れば保護することばかりを考えているようにしか見えず、「貴方達は、彼が死ぬまで面倒をみれますか」という私の問いに、「出来ません」という答えが返ってきた。じゃ、何故保護しようとするのか、明日への勇気や希望を与えていくのが彼の周りにいて彼をケアする人達の仕事ではないだろうかという思いで、日々彼と共に取組んでいる。 問題であった労働時間は、最初は毎日4時間午前中だけ、その後季節の変わり目の前に30分ずつ時間を延ばしていった。ただし、疲れたらいつでも帰っていいという条件を付けて。ジョブコーチに来ていただいた期間を含めて、約9ヶ月の月日が過ぎていった。彼の努力を伴いながら、すこしずつ確実に労働時間は安定してきている。現在は6時間45分の労働をこなせるようになった。彼とは1日8時間労働をクリアすることを年内目標にしている。 今は服用している薬の量は減り、通院回数も減った。顕著に確信を得ることのできない症状に苦しまれていたご両親や周辺が、その変化に驚いている。 「責任」という二文字の重圧がかかった彼の社会人としてのサイクルが、今少しずつ戻り始めているように思う。現在は、班長さんとして、作業中は知的障害を持つ彼のフォローもしてくれている。養護学校の生徒さんを実習で受け入れた時も、面倒を見たり彼も負担なく対応してくれて、意見などくれるようになった。 |
|
5.今後の課題
| 現在障害者の雇用賃金は、関係機関等に相談に行ったところ健常者の最低賃金をもって一般的と聞かされている。雇用サイドにとって、賃金は、作業能力に応じた設定を前提に考えるので、当然健常者に比して彼らは不利になってくる。 「給料などたいした問題ではないのです」と彼らのご両親から言われた。障害者を抱える親にとって、社会参加は大きな課題である。当たり前のことが出来るようになってほしい、朝「行って来ます」と出かけられる職場がほしい。しかし、たとえ親と言えども年はとるもの、いつまでも障害を抱えた我が子を腕の中で守っていてはやれない。ある程度の年齢に達した時、彼らなりに自立をしてもらいたい。 |  部署長 尾崎淑子さん |
| そのためには、雇用の機会と同時に、賃金のあり方についてもう一度見直す必要があるのではと思う。 「私の手を見てください」と差し出す赤く腫れた母の手、「昨日も叱ったのです」と、口で言っても理解できない知的障害の我が子に、親は手を上げてしまうこともしばしばとのこと。 痛む手を見た時、この母の手を二度と腫らしてはいけないと思った。これがマイナスに働くこともあるのだ。彼の意識の中では誉められることが生き残ることの全てになり、その為に、して良いこといけないことの判断などは漠然としてしまい、嘘をつくという行為に変わるのだ。二度とさせてはいけないと、何度も胸に手を当てさせ理屈ではない心のありかを捜すのに苦労した。 今でも毎日、職場、家庭とノートでの連絡帳を欠かさず続けている。もう三冊目になった。必要があれば電話でも話している。○がついても誉めない、×がついても叱らない、これを2ヶ月程お母さんの協力を得て続けた。今は出来ていないこと、悪かったことを、きちんと受け止められるようになった。 障害者を雇用すること、これは一人の人間の人生を預かることである。職場、家庭、公的機関全てが同じ意識で取組んでいかなければ、彼らの成長はありえないと思っている。 |
| ||||
6.知的障害者を持つ母親からのメッセージ
| 障害のある子を持つ親にとって、学校を卒業して一番心配する事は就職のことです。 仕事に行けるところがあるか、どこまで受け入れ体制が出来ているかと言うことです。 事業主さんに理解があっても、周りの人すべてに理解をして下さいと言うのも勝手な要求であって、本人がどこまでついて行けるかが心配です。 |
| 就職しても毎日、子供の顔を見て何かを訴えてくるかと心配な思いで話していると、嬉しかった事などを笑いながら、ころげるような言葉で話してくれると、今日までの苦労も洗い流す思いです。 息子は三度目の就職ですが、今回はハローワークからのお世話で、初めて耳にする愛媛障害者職業センターの「ジョブコーチ」の方に色々と職場定着についてお世話になり(2ヶ月間を2回計4ヶ月)有り難うございました。 これからは、ジョブコーチ制度を活用して障害者でもたくさんの方が就職できるようになっていくと思います。 私の息子は、会社の皆様方からご理解を頂くと同時に、ジョブコーチの方のお世話により就職が出来ました。 現在、親子ともに頑張っていられるのも皆様方のお陰です、ありがとうございます。 障害者を持っている皆さん方も、負けないで、ハローワークに相談をして是非頑張って欲しいと願っております。 |  高橋さんのお母さん |
7.精神障害を持っている親子からのメッセージ
(1)本人からのメッセージ |
| 発病して会社を辞めるしかなくなり大阪から帰ってきました。 治療を受けながら仕事をさがすために、ハローワークに何度もいきました。 仕事をさがす方法は、病気を隠すか、隠さないかしかなかったので、最初は隠してさがしました。 |
| 仕事は見つかりましたが、8時間労働は体に負担がかかり、なかなか続きませんでした。 体の調子も悪くなり、次の仕事にはなかなかつけませんでしたので、次は病気を隠さないで仕事をさがしましたが、電話口で断られてしまい面接もしてくれませんでした。 気持ちも落ち込み体調も悪くなりどうにもならないでいるとき、一カ所だけ(株)エコシティという会社が、ジョブコーチの制度を利用して採用してくれる事になりました。最初は労働時間を短くしてもらい体の調子を見ながらうまく仕事をさせてもらっています。労働時間も少しずつ延ばしていっています。 体調が悪くなって休んでしまうようなこともなくなり本当にうまくいって良かったと思っています。 |  高石研二さん |
(2)母親からのメッセージ |
| 息子が現代病の「ウツ病」と診断されてから、我が家の生活が一変しました。 私もある程度は、新聞とかその他の事で知っていたつもりですが、いざ自分の子供の事となるとどうすればいいのか、色々悩みました。 しかし、現代医学は進歩していて薬もいいのがあり、少しずつよくなって行きました。 |
| そうすると、本人は先ず仕事に就く事を考え色々探しているようですが、病気が病気ですので、企業側はどうしても二の足を踏みます。 私も、病院のケースワーカーさんに相談したり、本人も働きたいのに、なぜそれが出来ないのか調べても見ました。 その時、松山市にある「愛媛障害者職業センター」の事を聞き、そこから新居浜市内にある(株)エコシティという会社が面接に応じて下さり、ある期間実習に行けることとなり、上司である、尾崎さんが色々と面倒を見て下さいました。実習期間も無事終わり、今は社員として働かせて頂いております。働く時間も無理のないように少しずつ延ばすとかの配慮をして下さり、常に本人の体調を気にかけて下さっています。 障害者でも、仕事をしたい人は他にも沢山いると思います、給料よりもまず先に(株)エコシティのような企業がもっと増えて下されば、障害者の子を持つ親としてどんなに有難いことかと思います。 |  高石研二さんのご両親 |
| 執筆者:株式会社 エコシティ部署長 尾崎 淑子 |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。