未来を開発するやさしさ・つよさ・創造~車いす障害者にハンディキャップはない~
2004年度作成
| 事業所名 | 株式会社オーエックスエンジニアリング | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 千葉県千葉市 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 車いすの開発・製造・販売 障害者作業環境改善器具開発 | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 37名 | |||||||||||||||||||||
| うち障害者数 | 13名
|
 本社全景 |
1.事業所の概要
| (株)オーエックスエンジニアリングの本社所在地は、政令指定都市である千葉市の6行政区のうち、最大の面積を有し北西部に位置する若葉区にある。 県都千葉市は首都圏の一角を担い、都心から約40・と交通の利便性が高い地域であるが、会社設立当時、この地域は「田舎」と形容される緑に囲まれた純農村地域であった。現在もなお、各企業、団体等が所有する各種スポーツ施設に隣接した緑深い中に当社はあり、江戸創設期に徳川家康によって一夜にして作られたといわれている「江戸と東金の狩猟地」を結ぶ御成街道(別名、一夜街道とも言う。)沿いに所在する。まさに、当社のロゴマークにある「未来を開発する」にふさわしい土地といえよう。 |
(1)事業所の沿革 |
| 昭和51年(1976年)、都内江戸川区でヤマハオートバイの製品・同部品の開発に携わっていた現会長が独立し、オートバイの販売店「スポーツショップ石井」を創立。 昭和53年(1978年)、株式会社スポーツショップ石井を設立。 昭和63年(1988年)10月、千葉市中田町に(株)スポーツショップ石井より分離独立し、別会社 (株)オーエックスエンジニアリングを設立(オートバイ・同部品の製品開発)。 平成元年(1989年)4月、車いすの製造に着手。
|
(2)車いす製造を始めた経緯 |
| 昭和59年(1984年)4月、(株)スポーツショップ石井の社長であった石井氏は、モーターサイクルレースのテストライダー兼ジャーナリストとして活躍していたが、開発製品の新車に試乗中、不慮の事故により脊髄を損傷し、車いすを必要とする身体障害を負った。 同氏は当初、既存の車いすを何台も使用したが、その機能・デザインに飽きたらず、翌60年(1985年)、社内に個人的プロジェクトを作り車いすの制作・改良を重ね使用していた。 平成2年(1990年)9月、ドイツで開催された世界最大の「自動二輪車・自転車展」視察時に、使用していた車いすを現地記者から称賛され、製造会社を聞かれた。自社製である旨説明したところ、「何故売らないのか」と言われたことがきっかけで事業化を決意した。 なお、会社を千葉市中田町に設立した背景には、土地の価格ということもあるが、新製品の開発ということから、製品化までの「秘密保持」が重要であったことである。 |
(3)事業の展開 |
| 車いす障害者が参加するスポーツ種目の広がりから、その需要は増加傾向にあり、各種の専用車の開発や、日常用として高齢者等が使用する「病院仕様」の車いす等もその需要は好調である。 一方で、日常用に代表されるが、国内での製品のだぶつき等で海外への寄付行為が増加しているものの、送り出されるものが即使用出来るものばかりではなく、現状では、修理・補修が必要なものも送られており、修理・補修の技術者がいないと単なる廃棄物と化してしまうこととなる。 そこで、当社では、タイ国から研修生を受入れ技術者として養成(9月末修了)し、現地で「リサイクル会社」を設立することとしている。 |
2.障害者の採用・配置
(1)募集・採用 |
 社員として初めて障害者を雇用したのは、奇しくも千葉市が政令指定都市となった平成4年(1992年)に採用した車いす使用者であった。 社員として初めて障害者を雇用したのは、奇しくも千葉市が政令指定都市となった平成4年(1992年)に採用した車いす使用者であった。その後、順次障害者が増加し、現在は従業員37名中1・2級の下肢障害者が12名となっているが、求人にあたって障害者のみを募集の対象とはしていない。 募集ルートはいろいろな方法を活用しているが、主としては、公共職業安定所・折り込み広告によっている。 採用のあり方も、特に特別な要件は何もなく、健常者との差別・区別もせず「仕事が出来るか」ということのみで採用している。 |
(2)配置 |
車いす使用者が営業に回ると、それだけで有利に展開しているのが現状である。 また、健常者より障害者の定着率が圧倒的によいという。 従業員の意識も「仕事をもらっている」ではなく、「仕事をしている」の感がひしひしと感じられる。 |
|||||
3.ハンディキャップのない職場環境
(1)施設や制度での細かな配慮 |
| 会社全体で職場内の段差をできる限り無くし、段差の大きいところはリフトやエレベーターを取り付け、トイレを広くしているだけで、障害のある社員の存在を意識して行っている訳ではない。 スポーツ仕様のオーダーメイド車いす製造という業務の性格から、車いす使用者の来客もあり、通路上に車いすを通すのにはどうかという荷物が置かれるなど工場内も雑然とは見えるが、細かな配慮が感じられた。 イベント等におけるメンテナンスを行うためのバスも、下肢障害者も運転できる仕様となっているなど深いところでの配慮が感じられた。 配慮といえば、会長の工作室といわれる部屋は、ドア式の入り口もあるが、敷地から直接入れる電動シャッター付の広々とした出入り口が設置されており、工作機械の台や机は車いすに合わせた高さ等に加工してあった。もちろん、従業員用も同じことが言えるが、会長用工作室という名の先導的施設の試作品ではないだろうか。 また、障害者に対する住宅の借り入れや駐車場の確保等、通勤への配慮は当然のごとく行われている。  |
(2)健康管理 |
| 健康管理においても、障害者であるからといって、特別なことはしていない。個々に病気対応として定期的に通院をしているので、自己管理が徹底しているといえる。 あくまでも自然体というか、障害者であるということを意識の外に置く空間を作り出している。 |
4.まとめ~「障害者」という意識はない
敷地内でのバリアフリーは徹底されており、取材に当って車いすを使用している広報室長は「社内で行かれないところはない」と明言し、言葉どおり隅々まで案内してくださった。 一方で、建物内では、荷物も高いところにあるし、床に荷物を置くことも、車いす社員や車いすのお客様が来ることも全社員が意識していない。 一方で、建物内では、荷物も高いところにあるし、床に荷物を置くことも、車いす社員や車いすのお客様が来ることも全社員が意識していない。車いすのみならず、障害者が雇用されているという考えが意識の外にあるという感覚である。 現会長が、社長時代から「車いす障害者にハンディキャップなんか無い」といい、これが浸透しているためか。とにかく全てにおいて差別・区別がされていない。車いす使用の広報室長曰わく「車いすの人が転んでも誰も手を貸さない。本人が助けを求めれば助ける」と。 健常者、障害者を区別する意識が無く、まさしくノーマライゼーションの世界を作り出しているといえる。 健常者、障害者とも生き生きとして働き、職場はとても明るく感じられた。 最後に「社訓」を紹介して閉じることとする。 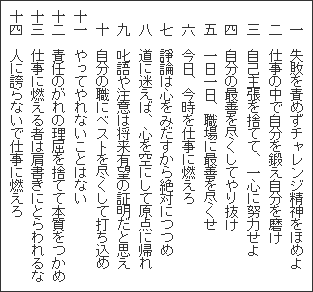 (執筆者:元千葉公共職業安定所所長 黒川志朗) |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。













