さまざまな従業員が、適材適所で働く~多様性を生かした特例子会社~
2004年度作成
| 事業所名 | 伊藤忠ユニダス株式会社 (伊藤忠商事株式会社の特例子会社) | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 神奈川県横浜市 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | クリーニング、印刷、写真 | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 64名 | |||||||||||||||||||||
| うち障害者数 | 40名
|
|
1.事業所の概要
(1)沿革 |
| 伊藤忠ユニダス株式会社(以下「ユニダス」とする)は1987(昭和62)年7月、総合商社の伊藤忠商事株式会社(以下「親会社」とする)の特例子会社として横浜市に設立された。同社は神奈川県で最初に設立された特例子会社で、1988(昭和63)年3月に特例認定を受けた。資本金は、5,000万円(伊藤忠商事(株)100%出資)である。 2004年11月時点の従業員は64名、うち障害者は40名である。障害者の内訳は、身体障害者27名(うち重度18名)、知的障害者13名(うち重度9名)である。 |
(2)設立の経緯 |
| 親会社では、ユニダスの設立前から身体障害者を雇用していたが、法定雇用率の達成が困難な状況であった。そこで特例子会社を設立し、障害者の法定雇用率達成を目指すこととした。 業種については、親会社直轄の独身寮・単身寮寮生の衣類のクリーニングと、人事管理・海外駐在・海外出張に必要な証明写真が社内の需要として取り込めることから、ユニダスはクリーニングと写真を主体にスタートした。その後社内需要として取り込め、設備投資が比較的少ないことなどからプリントサービス部が新設され、現在に至っている。 ユニダスが設立された1987(昭和62)年は、身体障害者雇用促進法(1960[昭和35]年制定)が障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」とする)と改められ、知的障害者を障害者雇用率に算入できるようになった年である 。当時の障害者雇用は身体障害者が中心であり、ユニダスも設立当初は身体障害者のみを雇用していた。その後1990(平成2)年から知的障害者も雇用するようになった。 |
(3)特色 |
| ユニダスの大きな特色の一つは、従業員の多様性である。身体障害者と知的障害者の双方を雇用している上に、従業員の身体障害の種類も聴覚障害、肢体不自由、内部障害とさまざまである。従業員の年齢層も、20代から60代と幅広い。同社ではさまざまな従業員が適材適所で働いている。 また伊藤忠グループ外からの受注比率が高いことも、他の特例子会社にあまり見られない特色といえるだろう 。ユニダスではクリーニングの売り上げが全体の約65%を占めており、このうち約90%が伊藤忠グループ外からの受注である。 |
2.採用と配置
| ユニダスは従業員の採用を、部門別・職種別に行う。採用にあたっては何ができるかを重視するが、素質や適性のある人、訓練すれば作業ができる人を採用する。一旦特定の部門で採用されると、部門内で担当作業の変更はあるが、他部門への配置転換はほとんどない。障害特性から、配置転換が困難な場合があるためである。 例えばクリーニング工場部で採用された従業員は、工場内で複数の作業を担当したり、担当作業を変更することはあるが、営業部、プリントサービス部、写真部への配置転換はない。またクリーニング工場内の機械は、片手でなく両手で使用する設計になっている。このため片麻痺の従業員は他の適した職務を担当する。身体障害のため立ち仕事が困難な従業員は、座って行う作業を担当する。身体障害者の管理職も5名いる。 障害の種別では、身体障害者が中途採用で年齢層も幅広いのに対し、知的障害者は養護学校の新卒者が中心で、年齢も20代から30代と若い。またユニダスには定年後再雇用制度があり、それを適用して勤務する従業員もいる。 なお同社における近年の新規採用は、欠員の補充が中心である。 |
3.主な作業工程と障害者の配置-クリーニングと印刷-
| ユニダスは、クリーニング、印刷、写真を事業の柱としている。このうちクリーニング部門と印刷部門を本事例で取り上げることとする。 なお写真部門については、東京・青山の伊藤忠商事本社内で、2名の身体障害者の社員が担当している。 |
(1)クリーニング |
ア クリーニング部の仕事
クリーニング部は更に営業部と工場部に分けられる。営業部の従業員は集荷、配達及び仕上げ済み衣類の整理、配達準備を担当し、工場部の従業員は衣類の洗濯・乾燥・プレス・仕上げを担当する。営業部では、身体障害のある従業員が自動車を運転して集荷や配達にあたる。またユニダスに勤務する知的障害者のほとんどが、工場部に所属している。 クリーニングの作業工程及び従業員の配置は、図表1のようになっている。工場の従業員は、採用後工場内で一通り仕事を経験してから、担当職務が決まる。 |
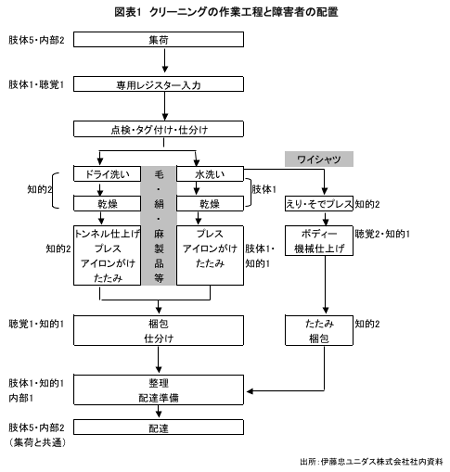 イ 技能の習得 機械やアイロンの使い方といった、作業に必要な技能は、OJTにより習得する。作業上の注意事項は、壁に掲示されている。プレス機のスタートボタンは事故防止のため、両手で押さないとスタートしない仕様にしてある。 このように視覚的要素をもたせ、実技に重点を置いた方法は、コミュニケーションに難のある知的障害者や聴覚障害者に有効といえるだろう。聴覚障害者とのコミュニケーションは、主に簡単な手話と筆談で行う。
ウ 営業部の仕事  営業部の集荷・配達担当者は、決められた曜日に決められたコースを回って仕事を行う。 営業部の集荷・配達担当者は、決められた曜日に決められたコースを回って仕事を行う。例えば週3回月曜・水曜・金曜に集荷・配達を行う場合は、月曜に集荷した衣類を水曜に配達、水曜集荷分は金曜に配達、金曜集荷分は翌週月曜に配達する体制をとっている。 営業部では、自動車の運転ができる肢体不自由者や内部障害者が集荷・配達を担当している。また知的障害者は一般的に顧客サービスに適さないとする向きがあるが、ユニダスには営業部に所属し、クリーニングが済んだ衣類の整理や配達準備を担当する知的障害者がいる。このように工場部だけでなく営業部でも、適材適所で従業員が働いている。 エ 勤務体制 クリーニング部は従業員を4つの班に分け、月・火・水・金曜日は4班体制、木・土曜日は3班体制で稼働している。木曜日を3班体制にするのは、他の曜日に比べて業務量が少ないからである。従業員は毎週日曜を休日とするほか、月に一度木曜日と土曜日を休日とする。但し4月と5月は繁忙期のため、土曜日は全て出勤日となる。 ユニダスの就業時間は午前9時から午後6時までであるが、クリーニング工場は8時30分には仕事ができる状態になっている。営業部の集荷・配達担当者は受注量や交通状況に応じて、所定の始業時間より早くから仕事を始めることがある。またその日の業務が終わり次第終業としており、1時間程度早く終わることが多い。 オ 顧客開拓 クリーニング部の主な顧客は、親会社や他企業の独身寮の寮生、及び伊藤忠グループが建設したマンションの住人である。会社設立当初は親会社の独身寮を対象に業務を行っていたが、収益をあげるために、親会社の独身寮の沿線にある他社の独身寮を顧客として開拓した。更に伊藤忠グループのディベロッパーが建設したマンション、あるいはグループ企業が管理会社となっているマンションでは、入居説明の際にクリーニングのPRを行う。 この顧客開拓が、現在ユニダスの主要な部門となる基盤を築いたといえるだろう。 カ 品質の確保 クリーニング部では納期だけでなく品質も重視している。受付時には、ポケットの中やボタンを調べる。ポケットの中に物が入っていたら、出してから洗濯に回す。ポケットの中の物は、納品時に洗い上がった衣類と一緒に顧客に返却する。ボタンについては、取れかかっていたり、欠けていたり、ひびが入っていたら付け替える。その際、縫い糸は衣類の色に合わせる。ボタンが無くなった場合は、似たようなボタンを付けるようにしている。 事故や紛失があった場合は、社内規定及び業界規定に基づいて対応する。 キ 夏場の熱中症対策  クリーニング工場には多くの機械が設置され、大量の熱を発生する。このため工場内ではエアコンが利かず、夏場の熱中症対策が大きな課題となる。 クリーニング工場には多くの機械が設置され、大量の熱を発生する。このため工場内ではエアコンが利かず、夏場の熱中症対策が大きな課題となる。対策方法として、水分とミネラル分を補給するために、工場内に麦茶と梅干しを置いて、自由に飲食できるようにした。工場内にある飲物の自動販売機も、自由に使ってよいこととした。また正午から45分間の昼休みと午後3時から30分間の休憩に加えて、午前10時にも休憩を取るようにした。 更に2004年夏には、熱中症予防のため、従業員が相互に監視を行った。監視に基づいてある従業員が他の従業員に休憩を勧めることもしばしばあったとのことである。 |
(2)印刷 |
| 印刷はプリントサービス部が担当する。そこに所属する従業員は、身体障害者7名、知的障害者1名、健常者2名の計10名である。 取り扱う品目は、封筒、名刺、挨拶状、年賀状、ちらし、パンフレット等である。プリントサービス部の売上はユニダス全体の25~30%を占めており、このうち約8割が伊藤忠グループ内からの受注である。受注の際、グループ会社から顧客の紹介を受けることがある。身体障害者の割合が多い点と、親会社グループ内からの受注が多い点が、クリーニング部と異なる特色といえるだろう。 プリントサービス部における作業工程及び人員配置は、図表2の通りである。 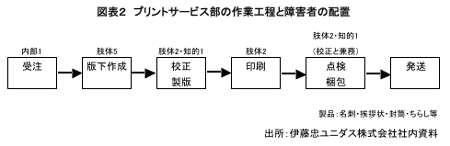 プリントサービス部でも、適材適所の人員配置が行われている。例えば車いすを使用する従業員は、コンピュータで版下制作を行う。知的障害のある社員は自閉症で、独特のこだわりといった特性を、校正や点検の作業に生かしている。コンピュータや印刷機の改造は特に行っていないが、麻痺のある従業員が難なく印刷機を使いこなしている。健常者は印刷機による印刷を担当している。 印刷の作業場では紙埃やインクのにおいが発生するため、作業中は窓を開けて換気を行う。これによって作業環境の向上を図っている。
|
4.従業員への配慮 -労働条件・社屋・通勤-
| ユニダスには身体障害者が多く勤務するため、労働条件や社屋の設計といった面においてさまざまな配慮を行っている。 同社は、身体障害者には無理をさせず、一定の余裕人員を確保する方針をとっている。身体障害者は無理をすると翌日の仕事に支障をきたすからである。更に産業医と連携して、従業員の健康管理にも努めている。 労働時間や休日についてはある程度柔軟に対応している。ユニダスには半休制度があり、それを利用して通院と仕事を両立させている従業員もいる。毎週通院が必要な場合は、通院日を公休日とし、土曜日に出勤するといった方法を取ることもある。 社屋については、2002(平成14)年、プリントサービス部及び総務部が現在の建物に移転したことを機に、レイアウトを変更した。プリントサービス部及び総務部が入っている建物(事務所・印刷工場)は、身体障害のある従業員に配慮した設計となっている。 例えば通路は、車いすの人がすれ違えるように、幅を広めに取ってある。トイレは個室を広めに取り、手すりを設けている。玄関以外の扉は全て引き戸を用い、床面にはレールではなく溝を用いて、扉を開閉しやすく、かつ段差をなくすようにしている。但し玄関だけは、建物の構造上引き戸を設置できなかった。車いすの従業員が玄関を出入りするときには、他の従業員がドアを開閉することがある。 事務所・印刷工場とクリーニング工場は、交通量の多い道路を隔てて斜め向かいにある。しかし2つの建物の間には横断歩道がないため、両者間を移動するときには多少遠回りになっても横断歩道を利用し、交通法規の遵守と安全の確保を徹底している。(図表3) 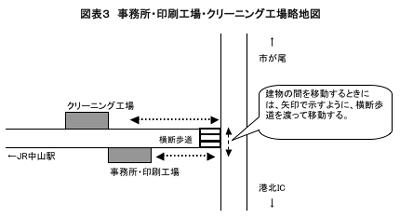 プリントサービス部及び総務部は移転前、クリーニング部と同じ建物(クリーニング工場)で業務を行っていた。クリーニング工場の建物の階段には、車いす用の昇降機が設置されている。 通勤や住居についても、配慮が行われている。身体障害のある従業員の中には、自動車通勤が認められている者がいる。会社の駐車場は、社屋の近くに確保してある。また障害者が個人で住居を探すのは往々にして困難が伴うため、会社が住宅を借り上げ、そこに住む従業員もいる。 |
5.特例子会社とグループ適用をめぐる問題点
| 親会社の伊藤忠商事における2004(平成16)年6月1日時点の障害者雇用率は2.4%で、法定雇用率の1.8%を大幅に上回っている。この数値は親会社とユニダスの常用雇用労働者数に基づいて算出されており、グループ適用は行っていない。近年、親会社のリストラの影響で分母となる常用雇用労働者数が減っているため、障害者は増えないのに雇用率が上昇する傾向にある。 企業のリストラや合併・分割再編に対応する有効な方法としてあげられるのは、特例子会社制度のグループ適用である。これは、特例子会社を保有する企業が関係会社を含めて障害者雇用を進める場合、一定の要件の下に、関係会社に雇用されている労働者も特例子会社に雇用されている労働者と同様に親会社に雇用されている者とみなし、実雇用率を計算するもので、2002(平成14)年の障害者雇用促進法の改正により可能となった。 しかしながらグループ適用について、ユニダス代表取締役社長の笠井敦夫氏は次のように問題点を指摘している。 「グループ適用は企業の合併や分割再編には有効だが、そうでない場合、障害者を雇用していない企業の意識低下や無関心につながりかねない。もしグループ適用を行うなら、何らかの条件を付けて、障害者雇用への関心が薄れないような仕組みを作る必要がある。また、傘下に多数の企業を擁するグループでは、どの企業を障害者雇用率のグループ適用の対象にするか、選択が難しい。」 障害者雇用率のグループ適用は施行から2年余りと日が浅く、効果や問題点がさほど多くあがっていないのが現状である。そのような状況下で、笠井氏の指摘は、障害者雇用率制度について新たな問題点を投げかけているといえよう。 |
6.まとめ -特例子会社のメリット-
| ユニダスは、さまざまな従業員が勤務する特例子会社である。 「多様性」というと、女性やパートの多い職場をイメージする向きがあるかもしれない。しかしさまざまな年齢層で、さまざまな障害を持つ従業員が、それぞれの適性を生かし、ある程度柔軟性を持たせた労働条件の下で仕事をこなすことは、「多様性」そのものといえる。既に述べたように、この「多様性」が、ユニダスの大きな特色である。 「特例子会社」は障害者の雇用促進の上で大きな役割を果たしており、そのメリットの一つとして、従業員の特性や必要性に応じて独自に処遇や労働条件を設定し、柔軟に運用できる点があげられる。しかし他方で、特例子会社は障害者の隔離や差別につながり、ノーマライゼーションに反する、という考え方もある。 障害のある者もない者も同じ職場で共に理解・協力しながら働くというのは、一つの理想型であろう。とはいえ障害のある者の就労にあたっては、障害ゆえに配慮すべきこともある。もし障害者だけを特別扱いすると、管理が煩雑になる上に、従業員間の公平性が損なわれる恐れも否定できない。逆に障害者も健常者も対等に扱おうとして、前者に必要な配慮がおろそかになってはならない。個々の必要性に対応し、かつ公平性を保つ上で、処遇、労働条件や就業規則を独自に設定できる特例子会社は、非常に有効といえるだろう。 ユニダスは特例子会社のメリットを生かして、さまざまな従業員の就労を可能にしている。 (執筆者:明治大学講師 青木 律子) |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。



















