障害者の自立と職場定着の取り組み~先輩障害者による指導体制と社員寮での生活支援~
2004年度作成
| 事業所名 | 株式会社 新潟プレスセンター | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 新潟県長岡市 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 紳士服、婦人コート及びワンピース・ジャケット等既製服のプレス仕上げ作業 | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 22名 | |||||||||||||||||||||
| うち障害者数 | 19名
|
 事業所(左側)と社員寮(右側) |
1.事業所の概要と障害者の雇用状況
(1) 経営方針 |
| 「各種機械と手作業の組み合わせを丁寧にわかりやすく反復継続指導を行い、製品の品質を高め、メーカーの信頼度を第一にして、安定経営をめざしつつ、企業と従業員の和をもって前進する」を経営方針としている。 特に、知的障害者の職場適応指導は、長期間の反復継続指導が必要であり、流れ作業に組み入れるには約3年の歳月を要するため、業務遂行援助者(工場長)の補助として先輩知的障害者を後輩の指導に当たらせており、先輩障害者には自立心と優越感を醸成し、両者の職場定着に効果を成している。 また、作業工程の見直しを行い、できるだけ障害者の働く場の確保に努め、障害者ひとり一人の有する能力を正当に評価し、丁寧かつ的確な指導によって作業能率の向上を図り、人間尊重の理念に基づき良き職業人・社会人に成長するよう苦楽を共にして、企業と従業員の発展をめざすことを念頭に企業経営を行っている。 社訓は、礼儀、信義、尊さと反省である。 |
(2)障害者雇用の経緯 |
| 障害者雇用のきっかけは、昭和40年代の高度経済成長期の人手不足を補うことから、公共職業安定所の勧めにより、知的障害者を1名雇用した。その後、年々雇用を増やし、現在は、従業員22名中、障害者を19名(重度10名)雇用している。 |
(3)障害者の雇用状況 |
障害者の雇用状況 障害者の年齢構成は、50歳台5名、40歳台5名、30歳台5名、29歳以下4名で、最高年齢は58歳である。
障害者の勤務年数は、最長29年、最短6年、平均18、9年である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)障害者雇用の表彰 |
| 昭和50年、心身障害者雇用優良事業所として新潟県知事表彰を受賞した。 昭和55年、心身障害者雇用優良事業所として労働大臣表彰を受賞した。 |
(5)助成金の活用 |
| 昭和55年、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を活用し、工場を建設した。 |
2.作業工程と障害者の配置
(1)作業内容と配置 |
| 健常者2名(50歳代女性)は点検とボタン付けなどの修正に従事している。 障害者は、プレス機操作に7名、アイロン作業に12名従事している。プレス作業者は検針、ハンガーアップ、包装・袋掛けを兼務している。
|
取扱品目は、紳士・婦人のコート・ワンピース・ジャケット・パンツ・スカート等の既製服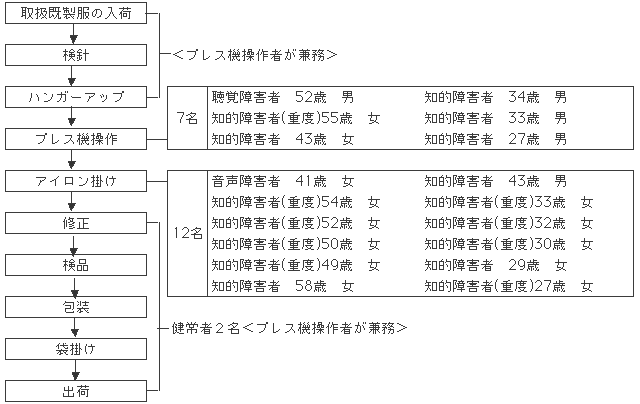 |
(2)プレス工の作業内容 |
| 受注した紳士服・婦人コート・ワンピース・ジャケット・パンツ・スカート等をプレス機によって、袖、襟、見ごろの部分をプレスして仕上げる。 |
(3)アイロン工の作業内容 |
| プレスの終わったコート・ジャケット等の裏地をアイロンで仕上げる作業及びスカート・ズボン等の全体的な修正をアイロンで行う。 |
3.障害者の自立と生産性向上への取り組み
(1)募集方法、採用条件 |
| 募集方法は、知的障害者総合援護施設「新潟県コロニーにいがた白岩の里」から就労可能者の推薦を受け、3ヵ月間の職場実習の後、採用している。 面接時、採用条件として、「あいさつがキチンとできる」「はっきり返事ができる」かどうかの2点と「性格の明るさ」を最重点におき、採否を決めている。 このことを守ることができれば、これまでの障害者雇用の経験から障害の程度に関わりなく積極的に採用してきた。 |
(2)やる気を起こさせる工夫 |
| 障害者の多くは、経験年数による技能の向上は期待できず、毎日同じ作業の繰り返しで ある。このため、業務遂行援助者である工場長と部長(社長の妻)が常に作業場を巡回して「早くなったね」「上手になったね」と褒め、自信と意欲を起こさせるための声かけをしている。 |
(3)組織と指導体制 |
| 知的障害者に対する指導は、連日同じことを根気よく反復しないとなかなか理解しにくい。特に取扱製品が変わった場合は、最初からわかりやすく丁寧に作業手順を説明し、先ずその作業をやってみせてから、実際に作業をやらせてみて、慣れるまで根気よく何度も繰り返し指導しなければならない。 また、直接指導していると、指導している方は苛立たしくなることも多々あるが、障害者はその状況を敏感にとらえ緊張し、更に作業習得を遅らせてしまう恐れがある。 このため、時には先輩障害者に簡単な作業指導を行わせてみると、お互いに緊張を解きリラックスした状況の中で作業習得が容易になる場面もあり、このことが比較的両者の信頼関係にいい結果をもたらし、職場定着に繋がっているのではないかと工場長は分析している。 |
(4)健康管理、社員寮 |
| 健康管理においては部長が中心となって、毎朝、ひとり一人に声を掛けて確認している。体調の思わしくない者には無理をさせず休養を取らせ、ひどいときには主治医に連絡してできるだけその病気が長引かないよう配慮している。 また、部長は、以前に前述の「コロニーにいがた白岩の里」の児童指導員の経験を有し、健康管理面や障害者間のもめごと、障害者家族との連携においても事細かに行っており、障害者家族からも信頼され、障害者には隔たりなく親身になって対処しているため、母親のように慕われている。
現在、入寮者は8名で、朝・夕の食事の準備は自分たちで話し合い、自主的に買い物に行かせて好みの料理を作らせるなど時折指導をしながら、将来自活ができるよう配慮している。 このため、休日になっても家族のいる自宅に帰る者は少なく、みんなでテレビを見て談笑したり、手芸や読書したりして楽しく過ごしている。 |
(5)労働条件 |
| ア 勤務時間 9:30~18:15(1日の労働時間7:30)、休憩時間 1:15 イ 休日 日曜・祭日・第2土曜日 ウ 賞与 年2回 エ 定年 満60歳、再雇用制度有り(年齢制限なし) オ 退職金制度 有り カ 健康・厚生年金・雇用・労災保険加入 キ 賃金 基本給(知的障害者は、全員労働基準監督署に最低賃金の除外申請・承認) ク 基本給以外の手当 通勤手当・皆勤手当・家族手当・残業手当 |
(6)福利厚生 |
| ア 定期健康診断 年1回 イ 慰安旅行 年1回(1泊2日)、 ウ 納涼会・忘年会・クリスマス大会 エ その他 障害者職場定着推進チーム(月1回開催) |
4.取り組みの効果と課題
(1) 効果~定着率のよさ |
| 最近3年間で離職した者は3人で、離職理由はいずれも病気と体力の喪失である。現在、働いている者は全員定年まで勤めたいと希望している。 また、生産性の向上には、安定した受注と信頼される製品加工が必要であるが、日本の縫製業界は中国製品に押され非常に厳しい状況下にある。特に単価が低く抑えられ、かつ短期納期を迫られることが多い。このようなときは全員残業で切り抜けているが、その状況を理解して不平不満を言う者はいない。 |
(2)課題~高齢化 |
| 最大の課題は、従業員の高年齢化に伴う作業能率の低下と将来の生活支援である。 障害者の年齢加齢による作業能率の低下は、一般的に健常者より早く35歳頃から始まり、それは体力と視力の低下である。視力の低下は眼鏡によって補足できるが、体力の減退による作業能力の低下は防止がむずかしい。 定年後の生活は、厚生年金と障害者年金で、ある程度の生活はできるものと考えられるが、更に将来のために貯蓄を奨励している。また、部長はこれからの定年者や離職者には一生ケアすべく話しており、将来に不安を抱かせることのないよう配慮している。 |
(3)今後の展望 |
| 当社は、東京の縫製メーカーと地域商社のための中堅プレスセンターである。今後もこの地位を維持すべく、更に業界から信頼され、必要とされる地元企業として発展していかなければならない。 前述のとおり従業員22名中障害者19名で、殆どの生産は障害者によって成されていると言ってよい。このことは、事業主の障害者ひとり一人に対する心温かい継続的な指導と障害者の気持ちが一体となり企業運営がなされていることにある。 現在は、日本経済の停滞により、特に縫製業界は厳しい状況にあるため、障害者の雇用増は望めないが、健常者、若年者を雇用すれば能率も向上し、少数の人員で経営も成り立つ。しかし、当社としては、これまでの障害者雇用のノウハウを生かし、地域の障害者雇用模範事業所として、さらに発展・躍進して行きたいと考えている。 |
(4)感想と評価 |
| 知的障害者を多数雇用して事業を経営することは並々ならぬ努力が必要であり、苦労を伴う。社長はじめ工場長、部長は、障害者の特性を深く理解しており、働く障害者の笑顔を見るたびに疲れを忘れ、天職を感ずると言う。誠に尊敬するに余りある信念である。 このように障害者雇用に対する前向きな企業が増えることを念願したい。 (執筆者:元三条公共職業安定所所長 長沼 宏) |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。














