外注清掃業務を障害者の職域に転換して雇用を進め、障害者雇用率達成間近となった事例
2004年度作成
| 事業所名 | 一正蒲鉾株式会社 | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 新潟県新潟市 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 蒲鉾等練り製品製造業 | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 1,081名 | |||||||||||||||||||||
| うち障害者数 | 12名
|
 会社全景 |
1.事業所の概要と障害者雇用の状況
(1)事業所の概要 |
| ア 創立年月日 昭和40年1月22日 イ 資本金 9億4千万円 ウ 経営方針 ・価格競争から価値競争へ ・消費者の目線に沿ったマーケティング戦略の展開 ・ISOに沿った業務活動の推進 ・幅広い情報の活用ができ先見性を持つ人材の育成 ・ユーザーニーズと社内体制のバランスをとった業務用商品の開発 ・様々なリスクから会社を守るための総合的リスク管理を目指した取組み |
(2)障害者の雇用状況及び推移 |
表1 障害者雇用状況(平成16年12月1日)
表2 年次別障害者雇用率の推移
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.障害者雇用率を高めた経緯
(1)障害者雇用が進まなかった状況と社内での検討 |
| 障害者雇用によって社会に貢献するという理念は、以前から強く意識していたが、蒲鉾製造現場は作業内容の特殊性から健常者並みの体力が必要なため、これまでは聴覚障害者を受入れる程度で、遅々として進まない現状にあった。 人事の総括責任者(人事マネジャー)は、これまでの障害者雇用に対する考え方では、公共職業安定所の障害者の受入れ要請・指導等に応えることができず、強く認識はしているものの、近々のうちに障害者雇用率を達成することは難しいと考えた。そのため、同業他社の工場見学、雇用開発協会の「障害者雇用リファレンスサービス」の雇用事例情報の入手のほか、「障害者雇用推進セミナー」等へも積極的に参加するなど、職域開発や特例子会社の設立等の手掛かりを得るべく情報収集を行い、社長を中心とした幹部会議に報告し検討を行った。しかし、昨今の厳しい経営状態及び予算面から具体的な方策を見出すことができなかった。 また、人事マネジャーは、幹部会議で障害者雇用は会社全体が一丸となって前向きに取組まなければ前進は望めないことを説き、もう一度、社内全体(製造棟、厚生棟)で、障害者の受入れが可能な職域開発について総点検を行ったが、現段階では以前同様、障害者を受入れる職域開発は望めないとの結論に至った。 |
(2)外部委託作業の検討 |
| しかし、外部に委託している清掃作業であればこれを自社で行うことにより、障害者雇用に生かすことができるのではないかとの提案があったため、これを社長に進言して障害者雇用の職域開発の足がかりとして取組むこととした。 これまで、清掃作業の外注費と雇用率未達成のために納付している障害者雇用納付金を合わせると年間かなりの金額に上る。当然、利益の追求なくして経費増は認められず、また経費節減は社の至上命令である。 人事マネジャーは、外部に委託している清掃作業を障害者の職域開発とするため、年間の清掃外注費と雇用納付金額から、自社雇入れによる清掃作業とした場合の経費の試算を行った。経費的にはある程度の負担増は覚悟をしなければならない、果して清掃作業を何人の障害者に任せたら採算が合うかわからない、また実施した場合うまくいくかどうかなど、多くの不安があった。 しかし、社長から「とにかく実施して見ることが前進に繋がる。」との強いことばがあり、以下の組織(図1)でスタートすることにした。 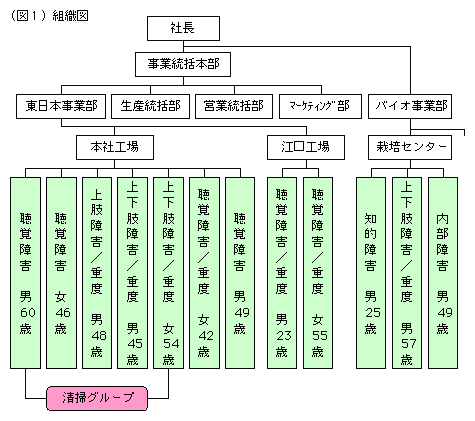 |
(3)障害者の採用 |
| 公共職業安定所の助言により、早速、清掃員求人の申込みをすることにした。折よく公共職業安定所の障害者集団面接会が予定されていたのでこれを機会に参加し、3名採用した。また、平成15年後半から16年後半にかけて公共職業安定所の紹介により更に2名採用して、この1年間に合計5名採用した。 |
(4)清掃グループの発足 |
| 外注業者では健常者3名で清掃作業を行っていたが、障害者の場合、一般的に若干は作業能率が低下することを考慮して、障害者5名のメンバーで清掃業務に従事してもらうことを企画した。配置転換による1名に、新規採用の肢体不自由者3名と聴覚障害者1名の計5名で清掃グループを発足させた。 |
(5)取組みの効果 |
| 清掃業務で障害者を順次採用したことに伴い、障害者法定雇用率(1.8%)の2分1にも満たなかった雇用率が、表2のとおり平成16年6月1日現在では1.59%、平成16年12月1日現在では1.67%となり、雇用率達成まであと1人となった。 なお、障害者の部位別状況は、表1のとおりである。 |
3.障害者の採用、労働条件及び雇用管理
(1)採用条件と能力の把握 |
| 公共職業安定所から紹介を受けた障害者の面接においては、障害の部位よりも「やる気と忍耐力、協調性」を重視して行い、そのほかに「会社の規律を守れること」「長期勤務が可能なこと」などを考慮して採用した。 |
(2)労働条件 |
| 社員の身分は、正社員と準社員に分かれ、準社員はさらにパート社員と臨時社員に区分されており、1年更新の雇用となっている。 準社員は、給与が時間給であることと、退職金制度が適用されないことが正社員との差異 となっているが、一日の労働時間(8時間)、休憩時間(60分)、年間休日(105日)、賞与(年2回)、定年年齢(満60歳)、社会保険(健康・厚生、労災・雇用)の加入についての差異はない。 今回採用した清掃チーム要員の身分は準社員で、勤務時間は特別に7時30分から16時30分となっており、時間給は700円となっている。 |
(3)作業内容 |
イ 最初のうちは工場管理者が朝のミーティング時に処々指示・点検していたが、清掃作業に慣れてくるに従い、効率よく委託清掃よりも綺麗にしてくれると他の従業員から感謝されている。 また、現在は厚生棟の清掃のみ担当してもらっているが、今後は順次製造棟の清掃も担当してもらうよう検討中である。 ウ 清掃グループは、人事課の直属とし、リーダーには以前に倉庫業務に従事していた60歳 定年後の聴覚障害者(6級)を雇用継続して任命したが、このリーダーが的確に作業配分して くれるので、各人の受持ちは当然のことお互いに協力し合い作業を行っている。 |
(4)社員食堂までの階段手摺の改善 |
| 厚生棟は、1階が事務所、2階が社員食堂となっており、食事のときは当然階段を利用しなければならない。このため、障害者が上り下りしやすいように階段の左右に手摺をつけたが、そのほかの改善は行っていない。 |
(5)障害者職場定着推進チームの活動 |
しかし、人事マネジャー(職業生活相談員)は、当時よりも障害者が5名増えたことから、障害者の職場環境整備のための意見収集、個々人の健康状態の把握は職場定着を図るためには絶対に欠かせないことを認識して、推進チームメンバーを正式に任命した。平成16年10月に、工場長、各現場主任指導員、障害者代表3名を加えて、安全・衛生の遵守をも含めた日常就労上の問題点や自己の健康管理等についての会合をはじめてもった。 |
4.今後の課題と評価
(1)課題 |
| ア 当面、障害者雇用率の完全達成が喫緊の課題である。平成17年6月1日までに1名以上 雇用したいと考えている。 イ まもなく定年(60歳)を迎える障害者がいるので、定年後の継続雇用を図って行きたいと考えているが、本人が希望しない場合は補充を早くから検討しなければならない。 ウ 清掃作業は、危険の伴う箇所が存在する。現在のところ事故等は皆無であるが、障害者職場定着推進チームの会合の定期的な開催及び事故未然防止のための専門家による講習会の開催が必要と思われるので早急に検討しなければならない。また、障害者の離職防止を図る必要がある。 エ 女子トイレの清掃を男子が行うことに女子社員から抵抗感があるため、女子が専門にするよう配置を考える必要がある。 |
(2)今後の展望 |
| 障害者雇用は、会社とりわけ人事担当者の重要な職務であることを常に認識して、障害者の求職情報の把握と職業安定機関との密接な連携を保持しながら、更に障害者雇用等に貢献して地域社会に溶け込んで行きたい。 また、今後は情報機器部門の職域確保について検討するとともに、まいたけ栽培センターに知的障害者(現在は1名)を配置できるよう検討を進める。 |
(3)まとめ |
| 人事総括責任者(人事マネジャー)は、障害者雇用について深く認識し、会社のトップと社員に対して繰り返し説得して、雇用率達成まであと間近としたことに対して心から敬服したい。今後はできるだけ早く達成して雇用調整金支給対象事業所となり、地域の模範事業所となられることを期待する。 また、社長の「有言実行のことば」は、障害者雇用を進める担当者には大きな励み・支えとなったものと考えられる。 (執筆者:元三条公共職業安定所所長 長沼 宏) |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。













