ホテル業における障害者の職域拡大
2004年度作成
| 事業所名 | 有限会社大光観光 (氷見グランドホテルマイアミ) | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 富山県氷見市 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | ホテル業(宿泊、日帰り、寿、法要等) | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 100名 | |||||||||||||||||||||
| うち障害者数 | 6名
|
 ホテル全景 |
1.事業所の概要と障害者の雇用状況
(1)事業所の概要 |
イ 代表者 代表取締役 大石 正徳 ウ 障害者雇用推進者 総務部長 京本 淳一郎 |
(2)障害者雇用の経緯 |
| 社長の信条による部分が大きく、「社会・地域に何か役に立つことをしていきたい。困っている人に手助けが出来る方法、社会貢献が出来る方法として、自分は障害者の雇用を受け入れていきたい」という気持ちを持ち続けているのが今日に繋がっている。 最初は、地元の障害者雇用から始まっている。また地域(氷見市)では障害者雇用をしている企業が僅かということもあり、その中でも多くの障害者を雇用している実態があるので、近隣の市町の養護学校からの強い要望を受け入れて6名までになった。またそれ以外にも、障害者福祉施設から働くことの体験学習も受け入れてきた。 |
(3)障害者の雇用状況 |
|
2.仕事の内容と分担
(1)配置 |
| 障害者5人は洗い場作業、同じ部署での仕事である。 もう1人の障害者は、事務所で予約受付や従業員のシフト勤務管理などを行っている。 |
(2) 洗い場作業 |
作業の流れとしては、(1)宴会・朝食後の食器等の後片付け、(2)その食器等の運搬、水洗い、乾燥、点検、収納、(3)食堂(朝食)のテーブル上の調味料の点検、配置である。 |
(3) サポート体制 |
「援助者」として健常者1名が職場で一緒に作業をしたり指導したりしながら、目の届く範囲でサポート役として働いている。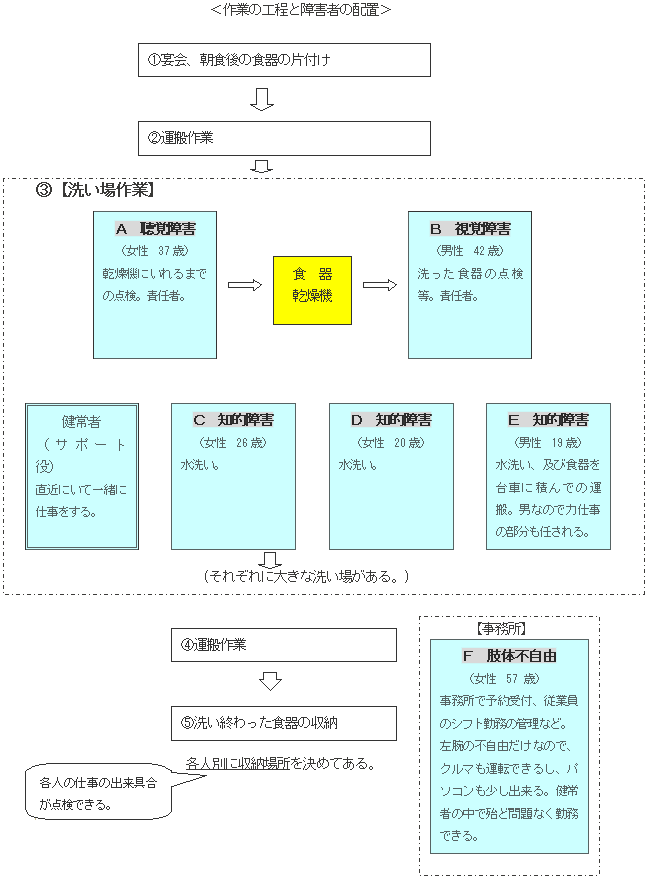
|
3.雇用管理と指導面での配慮
(1) 業務上の管理 |
| 多忙な時は、障害者に休んで貰うことにしている。 何故なら、宿泊客が多いときは400名とすれば、食器類が一人8枚として3200枚も洗うことになる。作業スピードが健常者の半分では、時間的に間に合わなくなってしまい、次の食事の準備にかかれなくなる。そんな時は、近所のパート・アルバイト従業員に時間延長などで対応してもらっている。 |
(2) 教育訓練等 |
| 誰でも、最初の頃に一度は、食器を入れた箱を幾つも積んだ台車で運搬する時に、廊下の勾配などの関係で台車から箱を落とし、何枚もの食器を割ってしまうことがある。台車の取扱いに慣れていないので、感覚がつかめずバランスをくずしてしまうようだ。 注意を促す時に重要なことは、怒らないこと。怒らないで忍耐強く注意、指導を続けることである。怒ってしまうことで、本人が意気消沈してしまい、結果として逆効果になることを体験上理解されている。現状は日常的なOJTで足りている。 また、日常的に心がけていることは、いつも障害者に会うごとに「声かけ」をすることである。それが信頼につながり、心の支えとなっていると思える。 身体障害者は、通常は問題なく作業できるし、それなりに責任を持たせるようにしている。知的障害者の場合は、説明が理解できなかったり頑固な面もあったりして、思い通りに指導できないことがある。そんな時は部長に申し出て注意・指導してくれるように頼むことも時々ある。 |
(3) 労働条件 |
| 労働時間は、個別的には1~2時間程度の差があるが5~6時間勤務。一部交替制も組み込んでいる。休憩時間は他の従業員と同じ。 |
(4) 通勤 |
| 肢体不自由者1名は車を運転して通勤している。他の5名は家族が送り迎えをしている。やむを得ない場合は、会社で送迎することもある。 |
(5)職場定着の状況 |
| 今までに離職者はいないので、勤務年数も10年、20年以上と長くなっている。今では働くのが楽しいと言っている。食事はいつもグループで一緒に取り、そのグループの中で当番を決めたりして、自主的に楽しくしている。 |
(6)施設等の改善 |
| 作業環境や福利厚生(食堂、トイレ、床の段差、照明など)については、障害者対策としての特別の施設は設置していない。現在雇用している障害者には、その必要性はないため。 |
4.今後の課題と展望
(1)ホテル業での障害者雇用の可能性 |
| 実際に障害者雇用推進者である総務部長よりお話をうかがい、現場を見てみると「一定規模以上のホテル宿泊業における障害者雇用の職域拡大は今後可能ではないか」と思われた。勿論、解決すべき課題は多いが、一定の範囲の障害者であれば可能ではないか。 当社においては、車いすの障害者はいないので、床の段差をなくすなどの施設や設備そのものの改善はさほど必要がない。また、現状の作業については、安全確認の施設整備や教育訓練のための特別な施設も必要なく、受け入れることができている。 食器洗い部門のチームとしての業務は、順調にこなしていけるようになれば、作業スピードをカバーするためにも、少しずつ体験的に試行錯誤しながら作業を増やしていけるのではないか、職域の拡大に繋がるのではないかと思われた。 しかし、それらは「理屈からはそういうことが十分可能な筈」というだけで、現実の雇用には幾つものハードルがあるだろう。 |
(2)具体的な課題 |
| 以下の課題を、時間をかけて整理して理解が得られれば、一つの成功例として他の同業者に働きかけるよりよいモデルとなっていくと思われる。 ア 知的障害者の作業効率(健常者の半分程度)の改善。これは雇用する側からすれば、早急に改善をしていかねばならないことである。 イ 障害者雇用の限度。社長の理解だけでは限度がある。効率的な経営が求められる中では、法定の障害者雇用率に達することが目一杯ではないか。また、障害者を一人だけ雇用すると、職場の人間関係から長続きしない確率が高くなる。だからといって、数人も雇用することは更に経営効率に影響を与えることになる。 ウ 従業員の理解。一般の従業員にしてみれば、障害者雇用は大事なことと理解はしているが、いざ職場で同僚として働くとなると、作業ミスや作業能率の悪さには、なかなかいつまでも寛容な態度はとれなくなってしまう。また、リストラの時代に作業能力の低い者を雇用して賃金抑制に繋がるのではないか、障害者も大事だが自分達の労働条件の向上を優先してほしいといった会社に対する不満も出ると思われる。 |
(3)課題解決の方法 |
| これらの問題は、施設・設備というハードの対応ではなく、精神的とも言えるソフト面の問題がむしろ大きいといえる。つまり「理解と協力」。日常生活、営業活動の中では満ち溢れているこの言葉が、障害者雇用においては真剣味を帯びた特別の重みを持ってくる。「理解はあっても協力はなかなか出来ない」という高い壁がある。性急に法整備を楯にとってしまっては、短期的な数字は改善できても継続雇用とならない確率も高く、結果的には良い結果にならないのは明白である。 従って、これらの課題解決に向けては、会社の方針の中に盛り込んだり社長の強い信念を前面に出していかない限り障害者雇用は進展していかないという厳しい現実がある。そうなると障害者雇用に理解を示す社長か、または特例子会社の対応ができるような大会社でしか雇用が進まないことになってしまう。名案はなく、僅かの理解ある社長の行動を地道に一歩ずつ、一つずつ積み上げていくことが必要である。 |
(4)社会全体の動向 |
| しかし、社会全体としては各種団体の前向きな取り組みが、一昔前からの結果として確実に実を結び始めているのも事実である。また、追い風として、少子高齢化による就労者人口の減少につれて障害者雇用が進むことも期待できる。これは前向きな成果ではないかもしれないが、結果として社会に必要な面が改善されるのであれば、「少子高齢化による就労者の減少というマイナス面を、障害者の雇用が進むというプラス」で少しでも補う結果になればそれも可ではないか。 いずれにしても過去においては、リストラ等により折角の障害者雇用の減少はあったが、10年前、5年前、昨年、今年、来年、5年後と、着実に障害者自身の働きたいと言う意欲と事業主側の理解、社会的な認識の向上により、一人ずつ働く障害者が増えてきていると思うし、更に増えていくべきである。 |
(5) 現場担当者のことば |
| 最後に、障害者雇用推進者からの言葉を、現場で直に接している実感があったので紹介しておく。 『いつも声掛けをする』、『怒らない』、『障害者は礼儀正しい』。 とかく、世の中の若者の行動や礼儀がとやかく言われるだけに、実感として受取れるものである。また、健常者だけの職場であっても重要なことである。私たちは、ついつい設備や処遇面に捉われがちだが、根本的なやる気、元気を導くために必要なことは、どの職場どの組織であっても同じということが常日頃忘れかけているだけに改めて感じた。 |
(6)まとめ |
| 社長の雇用の決断と、職場の推進者の努力と苦労があってこそ、障害者雇用が一歩ずつ進む。そのために、行政、関係機関、同僚、社会が、それぞれの立場で応援することを続けなくてはならない。 (執筆者:岡野社会保険労務士事務所社会保険労務士 岡野 満) |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。















