農業協同組合の小売店舗における知的障害者雇用~職場実習と専任担当者の配置による職場定着の取り組み~
2004年度作成
| 事業所名 | JAいずも「ラピタ」 | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 島根県出雲市 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 小売業 | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 365名 | |||||||||||||||||||||
| うち障害者数 | 5名
|
1.事業所の概要
(1)事業の内容 |
| 昭和39年、JAいずもの生活資材販売部門として現在地に「出雲生活センター」を開設、平成元年に名称を「ラピタ」と改名し、本店を新築オープンした。現在は出雲市内及び周辺地域(平田市、佐田町、多伎町、湖陵町、大社町)に本支店合わせて9店舗を展開している。店舗購買事業の他に、結婚式場など生活文化活動の拠点としての機能も有している。この地域は穀倉地帯として知られ、農業協同組合(JA)の存在・影響力が大きい地域と言える。 |
(2)経営方針 |
| 名称の「ラピタ」は『快適な暮らしを提供したい』という気持ちが込められたネーミングであり、これが店舗全体の方針である。 |
(3)組織構成 |
従業員365名(うち知的障害者5名)で人事管理は店舗管理課が所掌し、店舗管理係長が障害者の実習対応から採用までを担当しており、最も障害者雇用数の多い施設係においては、専任の現場担当者1名を配置している。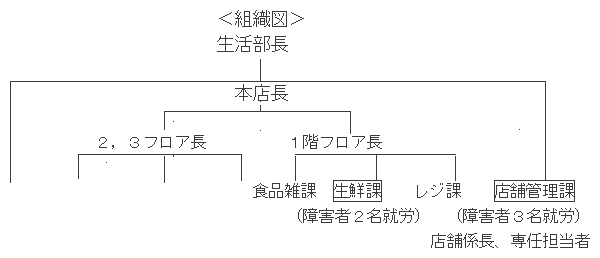 |
(4)障害者雇用の理念 |
| 出来るだけ多くの障害者の方に「職場体験」の場として提供し、その中で業務内容に合致した方がいれば、採用していきたい、という積極的な姿勢を持っている。 |
2.障害者雇用の経緯と職場配置
(1)障害者雇用のきっかけ |
| 障害者受け入れのきっかけは、平成元年、職業安定所の雇用率達成指導であった。障害者の雇用にあたっては、一人一人の障害者の能力・適性・特性を理解した上で、就労する業務を設定し配置する事の必要性が生じた。 そこで、地域の障害者授産施設と連携し、施設利用者の職場実習から受け入れ、雇用を開始した。 また、バックヤードでの商品作り作業等に適さない方のために、店舗管理部門の施設係を新たに設定し、知的障害者向けの作業とすることで雇用数の増加を図った経緯がある。 こうして流れの中で、雇用した障害者の職場定着のための取り組みを行った。 |
(2)職種の設定と配置 |
現在雇用している障害者の業務は次の通りである。
職場実習を経て、就労可能だと判断された本人の能力・適性によって採用時に職種を設定する。障害者雇用を開始した当初はほとんどの障害者が施設係の業務であったが、ここ数年は生鮮課のバックヤードでの実習を経てそのまま生鮮課業務につくことが多い。 生鮮課での業務は単純な下処理作業から本格的な処理、パック詰めまで多種の作業があり、少しずつステップアップを図ることが出来る長所がある。 一方、施設係の担当業務は単純な作業が多く、そのような単純な作業を繰り返すことによって仕事を覚えていく障害者にとっては、必要な作業職種であり、雇用障害者の適性により設定ができる利点がある。
|
3.職場実習の実施
(1)実習生等の受け入れ |
| 地域の養護学校から依頼のある職場実習生を毎年受け入れ、職場体験としての実習に極力、協力している。 実習生の受け入れは主に本店で行う(実習生の住まいとの関連で、他店舗に配置する事もある)。 (直近3年間の実習受け入れ数)
また、県の健康福祉センターの事業である「精神障害者社会適応訓練制度」も受け入れており、現在1名が実習中である。なお、この事業の実習生は今後も積極的に受け入れていく予定である。 |
(2)職場実習の内容・期間 |
| 実習内容は、現在、施設管理作業部門は配置数としては充足しているため、主として生鮮食品の部門を中心にバックヤードで商品作りを行う作業に設定し、実習・雇用を進めている。この業務は、接客業務はないが、挨拶・返事・指示への理解が出来、より速い動作が求められる業務である。 期間は2週間とし、評価は各部門のチーフが行い、担当者に報告する。ここでの実習は、学校も就労が可能かどうかの見極めとして行うため、評価も厳しく行うことになる。実習期間中には、所属学校と担当者が連絡を密に取り合い本人の特性・能力理解に努めるようにしている。また、家族との連携もこの時点で開始するようにしている。 現在、生鮮課の雇用障害者は2名ともこの職場実習を経て引き続き就労している。 |
4.担当者の専任による問題への対応
(1)トラブルの発生 |
| 雇用障害者の会社組織に対する理解、業務内容の理解については、現場でただ指示するだけではうまく進まない。また理解が不十分なことによって、お客様とのトラブルや同僚とのトラブルが発生する。 例えば、社員の上下関係、それぞれの役割が理解できず、指示ばかりする人(現場上司)に「自分ばっかり仕事をさせて」と不満をもち、働かなくなってしまった事例がある。また、買物カートの整理の際、折角並べたカートをお客様に乱され、怒ってしまいトラブルになったこともある。 |
(2)社内体制~担当者の専任 |
| 障害者指導を専門に行う担当者を1名配置し、教育・作業指導・助言・相談に当たる体制をとった。特に、施設係は買い物カート整理、買い物かご洗い、清掃業務とお客様に接する事も多い仕事のため、細かい配慮が必要であり、担当者配置によって日常的にかかわる事が出来、成果を挙げている。 また、この専任担当者の役割としては店内業務に留まらず、通勤練習・見守り(バスの利用)、生活面のフォロー(雇用障害者が生活しているグループホームとの連携や家族との連携)、出身施設との交流など、生活支援面での活動も多く、最近は精神的な支えを必要とする障害者もおり、その相談に当たるなど「ジョブコーチ」+「生活支援ワーカー」的な役割があり、障害者の職場定着への取り組みとして大変重要であると言える。 |
(3)専任担当者の支援ポイント |
| ア 作業を「指示・命令」するのではなく、常に「共業」体制でのぞむこと。 まず、会社の同僚としての姿勢を持って押し付けをしない。 その中で、組織(上下関係)をじっくりと教えていく(性急には理解できない事が多い)。 イ 休憩を出来るだけいっしょに取り、日常的なコミュニケーションをとるようにする。 家庭や友人関係などの事が原因で仕事に支障が出ることがあるため、フォローできる関係を持っておく。 生活面での特性も理解しておくことで、現場での問題に対応し易い。 |
5.一般従業員の障害理解
| 施設係に配置された雇用障害者の重要な業務として、朝一番の「店周の清掃業務」「溝掃除」がある。これは、他の社員の通勤時間に店舗周囲の清掃を行う業務であり、定期的に溝掃除も実施する。 この業務は、地味ではあるが毎日必ず行わなければならない。この業務を行う彼らの姿や障害者雇用についても、当初、一般社員は余り関心を示さなかった。しかし、毎日必ず目にすることで、雇用障害者の存在と仕事振りが理解されるようになり、同時に店周囲の美化も進んでいった。 このことは、障害者理解のための社内研修を何回も行うよりも社員教育として効果があり、また障害者への理解が「自然に」浸透したと言える。 職場定着を継続させる環境として、一般社員の理解は不可欠であり、この作業は地味ではあるが大変重要な取り組みである。
|
6.まとめと今後の展望
(1)「新職種の創造」への取り組み |
| 現在、本・支店に5名の障害者雇用があるが、今後雇用増を考えるとき、現在の職種だけでは人員は充足しており展望がない。また、現在働いている障害者にとってもレベルアップの職種が必要であると考えられる。 そのために、現在、店内各部門毎に「新しい職種の創造」を提案している。知的障害者の仕事イコール単純作業という発想からの脱却を図り、現在の雇用障害者のレベルアップを行い、様々な適性を持つ新卒の障害者に職場提供を図るという積極的な取り組みである。 また、最近になって長期就労していた障害者の方が、足の故障により立ち仕事が難しくなって退職した。同一職種しかない状況では継続して雇用していくことが困難であり、このことも新職種創造の必要性を痛感させた。 |
(2)各機関との連携 |
| 今後、障害者の雇用を進めていくためには、就労・生活支援の充実がますます必要となってくる。現在の専任の職場担当者1名の取り組みだけでは対応しきれない。 現実に、新しい障害(ADHD、学習障害等)への対応や家族との関係調整、生活面での対応について、地域の就労・生活支援センターの生活支援ワーカーや障害者職業センター、職安担当者に支援、調整を委ねて継続したケースもあり、今後連携を強化していく方向である。 |
(3)まとめ |
| 当社の各種取り組みから、下記の通り総括して評価する。 ・実習生の積極的な受け入れで、障害者の適性・理解力等を現場で確認することによって、担当職種の設定が確実に出来ること、また関係者(学校・機関・家族)との連携を早期から行えることは、職場定着への取り組みの基本であるといえる。 ・会社で専任の担当者を設置し、上からではなく一緒に働きながらじっくりと、仕事を取り巻く環境について理解させていくと言う取り組みは、特に職場適応力の不足している(社会経験の少ない)障害者にとって頼もしい職場であると言える。 ・出雲市内は、大規模なショッピングセンター、スーパーが次々と出店し、競争が激化している。そのような状況の中で、新たな「受け入れ職種の創造」を課題として掲げ、取り組みを開始しているという積極的な障害者雇用への頼もしい姿勢がうかがえた。 ・この地域における農業協同組合(JA)の存在・影響力は大きく、その意味でこの企業での障害者雇用は、他の地域企業や地域住民の意識に良い意味で影響を与えるのではないかと期待している。 (執筆者:社会福祉法人四ッ葉福祉会障害者地域生活支援センター「ハローネット」生活支援ワーカー 吉岡直子) |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。















