知的障害者の「個性」を活かした雇用創出
2004年度作成
| 事業所名 | 有限会社山下陶苑 | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 長崎県東彼杵郡川棚町 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 茶碗や皿等の食卓・厨房用陶磁器製造業 | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 15名 | |||||||||||||||||||||
| うち障害者数 | 6名
|
|
1.事業所の概要
| (有)山下陶苑は、長崎県の北部に位置し、有名な「有田」や「波佐見」の陶磁器の産地と一帯となったところに所在し、農村の田園地帯に、ひっそりとのんびりとしたところにある企業工場である。全敷地面積は1400坪で、そのうち本工場が400坪、第2工場が120坪を占めている。 (有)山下陶苑は、昭和56年の創業で、「治兵衛窯(じひょうえがま)」と称しているのは、現会長の父親の名前からとっている。 業界事情は厳しく、ピーク時の30%程度の出荷量なので、「生地(きじ)屋さん」も10社に減ってしまった。しかも最近は安い物と高い物に2極分化しており、安い物では中国製品に追い上げられている。中国製で安く売られているものは、工程数が少ない。日本製とくに波佐見では形状と絵柄などの質で対抗している。 焼きだけでも3回行うことがある。ここで出荷している製品は、2回焼が90%、3回焼が10%のシェアである。 ・素焼窯(900-940℃、ガス)6時間程度 ・本焼窯(1250-1300℃、ガス)13時間程度 ・電気窯(850-900℃)5時間半程度 *色物の場合なので上絵窯ともいう。
|
2.知的障害者の雇用状況
(1)知的障害者雇用のいきさつ |
| 山下会長は知的障害者の雇用のいきさつについて次のように語る。 昭和58年に創業したが従業員を採用することが難しく、必要数を採用できなかった。それはこの業種の製造工程が重筋労働でかつ熱いこと、単純な工程が多いことなどが原因であった。その時に知的障害者の自立更生を支援する施設から障害者の紹介を受けたことがきっかけとなった。 最初は養成期間(試用期間)を設けて働きぶりを見て、良ければ正社員として採用する、ということから始まった。その頃は、景気も良くて大量に同じものを生産していたので、知的障害者の活躍の場も多かった。 現在、従業員は15名で、6名の障害者を雇用している。障害者の全員が知的障害者で、そのうち5名は重度の知的障害者である。平成12年度より報奨金対象事業所となっている。 |
(2)知的障害者の採用の経過 |
| 知的障害者の採用については下表のように順次行い、ヒアリングを行った平成16年12月現在で6名の知的障害者が雇用されている。 採用、退職状況経過表 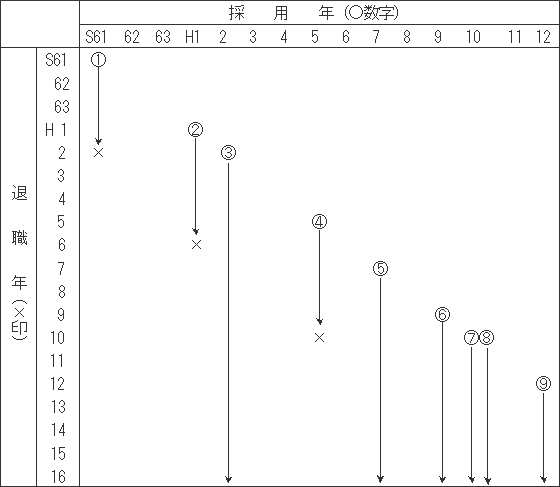 |
3.生活面や障害への対応と助成金の活用
(1)通勤 |
| 6名の知的障害者の事故防止、通勤時間の管理、作業能率の効率化を図るために通勤用ワゴン車を購入し送迎を行っている。 そのうち5名は知的障害者の自立更生施設の通勤寮から、1名は自宅から通勤している。 ワゴン車の買い替えを機会に、「重度障害者通勤対策助成金」を活用して、通勤用自動車を購入した。
|
(2)てんかんのある障害者への対応 |
| てんかんの症状を持つ2名の障害者については重度障害者介助等助成金等を活用し、業務遂行援助者を配置して、次のような指導を行っている。 ア 作業方法、手順等見本を見せながらきめ細かな指導を根気強く繰り返し行う。 イ 機械の使用についての危険性の指導を行い事故防止の徹底を図る。 ウ 人間関係等雇用管理面での指導を行い雇用の継続を図る。 てんかんで服薬を有する障害者においては、通勤寮が通院や薬の管理を行っており、通院日を考慮して出勤日の調整が必要であるため、通勤寮の支援員との連携も欠かせない。 なお、てんかんの症状を有する重度の知的障害者の一人については平成12年度に始まった障害者緊急雇用安定プロジェクトの「トライアル雇用」を利用し、障害者職業センターによる支援を受けて採用した。 |
(3)職場定着推進チームの設置 |
| 障害者の職場定着を図るため、平成13年度に事業主や現場指導員等による「障害者職場定着推進チーム」を設置している。 |
(4)仕事づくり |
| 近年は多品種で少量生産となり、工程が短期間で変わるので、覚え込みの苦手な彼等にとっては不都合であるが、その都度、健常者が付いて、「新」工程や「新」作業を教え込んで作業に慣らしている。慣れたら作業効率が上がる。 今は、いろいろな作業をやってもらうので、覚えるのは難しいが、指導員をおいて教育訓練に当たっている。怒ったり、しかったりすると、来なくなってしまう。彼等の個性を知り、仕事になるように教え込み、彼等ができるようにすることで「仕事づくり」をしている。 会社にとって役に立つように使うことは当然のこと。上手に使うことが会社にとっても本人たちにとっても生産と雇用に結びつくので、必要なことである。仕事に貢献させるように、工程や作業を工夫して段取りをしてやることが大事であり、社会奉仕の気持は無い。 他の仕事をさせた後、昼休みの後とか翌日には、仕事内容を忘れるという特性があるので、そのことを承知しておくことが大切である。それを教え込むのは、今は業務遂行援助者でもある社長や会長が当たっている。 |
(5)採用と退職 |
| 知的障害者の更生施設出身者からの採用を続けているが、欠員がでた時に、一定のテストをして、良ければ採用している。 退職はこれまで3人いたが、結婚等自己都合によるもので会社の事情によるものは無い。 |
(6)休憩時間 |
| 障害者と健常者は和気あいあいの雰囲気である。懇親会等にも利用している食堂で昼食も一緒に食べている。 |
4.知的障害者9名の採用と現在の状況
| 9名の採用とその経過は次のとおりである。雇用上の留意事項に配慮しながら雇用創出を図っている。 |
(1) Aさん |
| 男性、重度知的障害。 ハローワーク紹介により、S61年10月15日採用。 H2年6月9日退職。 |
(2) Bさん |
| 女性、重度知的障害。 ハローワーク紹介により、H1年6月1日採用。 H6年2月28日退職。 |
(3) Cさん |
| 男性、重度知的障害(障害者職業センター判定)。簡単な字は読め、数も少しは数えられる。与えられた仕事はあまり速くはないが出来る。 ハローワーク紹介により、H2年10月1日採用。 職種は、陶磁器製造補助。作業内容は、釉薬をかける作業や、素焼の積み降ろし作業。 賃金は、時給制。 通勤寮に入寮しており、マイクロバスによる送迎を行っている。 重度障害者通勤対策助成金を活用。 雇用上の留意事項としては、作業の順序や釉薬の種類等が判らなくて、間違わないように、その都度確認しながら作業するように指導している。 |
(4) Dさん |
| 男性、重度知的障害。 ハローワーク紹介により、H5年4月1日採用。 H10年3月31日退職。 |
(5) Eさん |
| 女性、軽度知的障害。簡単な読み書きはでき、数も少しは数えられる。与えられた仕事は、遅いができる。 ハローワーク紹介により、H7年3月1日採用。 職種は、絵付工。作業内容は、簡単な絵付けや、素焼を掃いたり釉薬をかけた後の高台を拭く作業。 賃金は、時給制。 自宅から、マイクロバスによる送迎を行っている。 重度障害者通勤対策助成金を活用。 雇用上の留意事項としては、集中力にかけるため、周りの者が注意して見守っている。 |
(6) Fさん |
| 男性、重度知的障害(障害者職業センター判定)。読み書きが出来ないし、数も全く数えられない。 ハローワーク紹介により、H9年3月1日採用。 職種は、陶磁器製造補助。作業内容は、釉薬をかけた後の高台を拭いたり、窯から上がった製品をおろす作業。 賃金は、時給制。最低賃金除外申請をしており、短時間勤務。 通勤寮に入寮し、通勤はマイクロバスで送迎を行っている。 重度障害者通勤対策助成金を活用。 雇用上の留意事項としては、重度の知的障害者で、読み書きも出来ず、数も判らないので、本人が出来る作業を見つけさせている。出来ることが限られているので、仕事が途切れないように心掛けている。 |
(7) Gさん |
| 男性、重度知的障害(障害者職業センター判定)。読み書きが出来ないし、数も全く数えられない。自閉症のため自ら話はしない。 ハローワークの紹介により、H11年4月1日採用。 職種は、陶磁器製造補助。作業内容は、素焼の積み降ろし作業。 賃金は、時給制。 通勤寮に入寮し、マイクロバスによる送迎を行っている。 重度障害者通勤対策助成金を活用。 雇用上の留意事項としては、自閉症のため本人から話をすることがないので、なるべく周りから話し掛けるようにしている。作業が途切れないように指示するように心掛けている。 |
(8) Hさん |
| 女性、重度知的障害(障害者職業センター判定)でてんかんもある。読み書きは出来ないし、数も全く数えられない。説明についても、判ったようでいても理解できない。 ハローワーク紹介により、H11年10月5日採用。 職種は、素焼はわき。作業内容は、生地を一度焼いて絵付けする前に、埃を取り除いて準備する作業。 通勤寮に入寮し、通勤はマイクロバスで送迎を行っている。2ヶ月に1回通院(朝夕服薬)。 賃金は、時給制。最低賃金除外申請をしており、短時間勤務。 重度障害者通勤対策、重度障害者介助等(業務遂行援助者の配置)助成金を活用。 雇用上の留意事項としては、重度の知的障害なので業務遂行援助者を配置して、常時指導できるようにしている。数が判らないので、援助者があらかじめ数を揃えておくようにしている。 |
(9) Iさん |
| 女性、重度知的重度の知的障害(障害者職業センター判定)、てんかん。読み書きが出来ないし、数も全く数えられない。自閉症のため自ら話はしない。 ハローワーク紹介により、トライアル雇用を活用してH12年5月1日採用。 職種は、陶磁器製造補助。作業内容は、釉薬をかけた後の高台を拭いたり、窯から上がった製品をはずす作業を行っている。 賃金は、時給制。最低賃金除外申請をしており、短時間勤務。 通勤寮に入寮しており、通勤はマイクロバスで送迎を行っている。月に1回通院(朝夕服薬)。重度障害者通勤対策、重度障害者介助等(業務遂行援助者の配置)助成金を活用。 雇用上の留意事項としては、重度の知的障害で判断力に欠けるため、業務遂行援助者を配置して、常時指導できるようにして、作業が途切れないように指示を出している。自閉症のため本人から話をすることがないので、なるべくまわりから話し掛けるように心掛けている。 工場内作業風景
|
5.まとめ
| 近隣にある知的障害者の自立更生を支援する社会福祉法人長崎慈光園との連携により、知的障害者通勤寮「復帰寮」から知的障害者は通勤バスで通勤している。そして、この通勤バスを運転しているのは会長の山下さんである。 山下会長は、会社は当然にして、「利益」を出すために会社や工場を経営しており、「社会貢献」とか「社会奉仕」のためではない。そんなことをしたら会社がつぶれてしまう、と言う。 ごく普通に共生が業務運営で行われ、「力」が入らずに、全く意識せずに行われている。彼等には、出来ることをやってもらっている。陶器の製造工程における、「清掃(高台ふき)」、「さや入れ」、「さや外し」、「釉薬かけ」、「窯入れ時の積み込み、窯出し後の降ろし」などである。 (有)山下陶苑が、高い障害者の雇用率を可能にしているのは、陶業の製造工程における「下支え」業務を「近隣施設」からのマンパワーの供給にあることを理由に挙げている。しかし障害者の潜在能力を教育訓練により開発して、その能力を活用しよう、雇用創出しようそして会社の経営に活かそう、という経営者の普段着の理念がそれを可能にしていると拝察した。
(執筆者:長崎大学環境科学部教授 浜 民夫) |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。



























