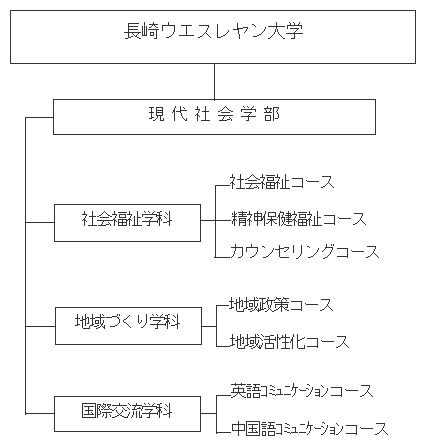キャンパス内で実現された共生社会
2004年度作成
| 事業所名 | 学校法人鎮西学院 長崎ウエスレヤン大学 | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 長崎県諫早市 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 大学 | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 121名 | |||||||||||||||||||||
| うち障害者数 | 4名
|
|
1.大学の概要
(1)はじめに |
| 「ウエスレヤン」のネーミングは、キリスト教の大きな流れのひとつであるメソジスト教会の創始者ジョン・ウエスレーにちなんでいるとのことである。 2004年の12月のある日、私たちは長崎ウエスレヤン大学(学長:森泰一郎教授)を、長崎県は諫早市の栄田町のキャンパスに訪ねた。キャンパスは、元ゴルフ場跡地だけあって、ゆったりとしたスロープの緑豊かな地にあった。副学長の内村公義先生(教授)、開浩一先生(助手)そして、事務局長、総務課長からお話を伺ったり、キャンパス内をご案内いただいた。 |
(2)組織及び教職員数(2004年5月1日現在) |
鎮西学院
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.障害者雇用の概況と施設改善
(1)障害者雇用率 |
|
(2)障害者雇用の経緯 |
| 常勤3名の障害者を採用年別にみてみよう。 1990年の4月1日に、腎臓に1級という重度の障害を有する女性(当時31歳)を図書館司書として採用したのが初めてのことであった。 2002年に長崎ウエスレヤン短期大学から4年制大学に移行した時期には、2人の両下肢機能障害者(いずれも障害等級1級、車いすを使用)を、教員(講師ならびに専任助手)として採用した。この時、現代社会学部福祉コミュニティ学科が創設された。2005年4月より社会福祉・地域づくり・国際交流の3学科になった。 この2人の教員のうち、開浩一さんの事例について次の章で詳しく紹介することにする。 一方、もう一人は、2002年4月1日、長崎ウエスレヤン大学開学に伴い教員を公募し、財団法人全国精神障害者家族連合会に勤務していた千葉市在住の方を、精神保健福祉担当の教員(講師、現在は助教授。学生委員長の重責も担う)として採用した。 そのため、当初は大学に近い駐車場付きの住宅を借り上げ提供し、加えてスロープや手すりも取り付け、和室を洋室にする等の改造も行った。 なお、重度障害者通勤対策助成金(重度障害者用住宅の賃借)が、2002年4月分から対象者が住宅を購入し賃借住宅を退去する2003年7月まで活用された。 |
(3)施設の改善 |
| 車いす使用の障害者2名については、現在、自家用車で通勤しているが、雨天時等の乗り降りの際には濡れるため、屋根付駐車場の2台分の新設と出入口の改修等を行い雇用の安定を図られている。施設の新設・改修にあたっては、次の障害者作業施設設置等助成金(第1種)の活用が図られた。 ア 障害者用屋根付車庫 現状屋根なしの車庫を利用して、雨天時のために新設。 イ 車いす用通路の設置 既存花壇及び植込み撤去、既存側溝撤去、既存縁石撤去、新設縁石工事、新設アスファルト舗装。 ウ 自動ドア新設 車いす使用の障害者2名に通行の利便のため、車庫から校舎に通じる手動式ドアを自動ドアに改修。 エ スロープ改修 既存のスロープは勾配がきつく車いすによる通行の基準に適合してないため全面改修。
|
(4)長崎ウエスレヤン大学の理念 |
| このように、長崎ウエスレヤン大学が障害者の雇用に積極的に対応しているのは、次のような理念に表現されている。 「わが国ではいま、『福祉』は時代のキーワードになっています。そもそも福祉とは、社会に暮らす一人ひとりが幸せに生きることをさす言葉。だからその対象は高齢者や障害をもつ人たちだけにとどまりません。私たち自身も福祉の主役なのです。この福祉の輪を自分の家族へ、学校の仲間へ、さらには同じ街に暮らす人々と広げていくと、最後には世界につながっていきます。つまり、世代間、地域間、そして地域と世界といったさまざまな関係の中で福祉は必要とされているのです。」 |
3.助手として勤務する開浩一さんの例
| この章は、開さんからのヒアリングと大学の「研究紀要」での開さんの論文等を参考に構成した。 |
(1)開 浩一(ひらき こういち)さんのプロフィール |
| 1970年生まれ。兵庫県生まれの長崎育ち、長崎ウエスレヤン短期大学教養科社会福祉コース卒業後、アメリカ留学を果たした。 現在は、久留米大学大学院で比較文化研究科博士課程に在籍しながら、母校である長崎ウエスレヤン大学の現代社会学部福祉コミュニティ学科のグローバル教育センターで助手をしている。 |
(2)開さんの思い |
「長崎ウエスレヤン短期大学との出会いは、10数年前のことです。19歳で交通事故にあい、車いすの生活を余儀なくされ、東京の大学を3年で中退し、福祉を学ぶために長崎ウエスレヤン短期大学の教養科社会福祉コースに入学したのです。事故にあった経験は、人のあたたかさと障害というものについて考えるきっかけになりました。そしてもっと福祉を学び、自分の道を切り拓きたいという思いから、アメリカのシュライナー大学へ編入留学しました。 シュライナー大学へ行ってまず驚いたのは、私が住むことになる寮のシャワー室とトイレを改造してくれたことです。この出来事は、まさにカルチャーショックでした。しかも、障害者のために施設を整えることは、法律で義務付けられているというのです。障害者を受け入れる社会が、そこにはありました。 アメリカでは、障害をもった医者や弁護士も数多くいます。障害が自分の道を進むうえで妨げにはならないのです。だから日本とは違ってアメリカでは、障害者をよりアクティブなイメージでとらえています。そんな環境のなかで私もプロフェッショナルな知識と技術を身につけたいと思い、シュライナー大学卒業後はアワーレディースオブザレイク大学院でソーシャルワーク(社会福祉)を学びました。 そして1999年に帰国しました。2001年度は長崎ウエスレヤン短期大学の社会福祉コースで、カウンセリングを担当し、授業では、私がアメリカで学んだマイノリティに対するカウンセリングについて取り上げました。マイノリティとは、たとえば、同性愛者やエイズの人、障害者など、社会のなかで少数しかいない人々のことです。日本人だってアメリカではマイノリティです。これを日本におきかえてみると、不登校の子どもたちもマイノリティのひとつと考えられます。 アメリカのようにマイノリティが当たり前のように社会で活躍できる日本をつくっていきたいですね。 現在は、グローバル教育センターの助手として、主にコミュニティサービスの職務を担い、また、心理学の講義の通訳も務めています。」
|
4.ウエスレヤン大学における障害学生受入れのための取り組み
| ウエスレヤン大学の副学長の内村公義先生のお話やご提供頂いた「研究紀要」等の資料によると、次のような段階を踏んで、障害を有する学生の受入れを進めてきたということであった。 |
(1)車いすを利用する学生への支援体制の整備 |
| 本学の前身である短大時代は、創立以来、毎年のように軽度の機能障害(歩行・言語障害等)を有する学生を受け入れてきていた。しかし、その内実は、いずれも施設設備の改善や支援者などを特に要しない、その時々の構造で学生生活が十分可能な軽い障害を有する学生に限られていた。 1991年になると、車いすを利用する、いわゆる重度の学生を初めて受け入れた。それが開さんであった。多くの課題を残しながらの受け入れ決断であったために、合格判定後も大学関係者の間からは「何か事故が起きたときには責任がとれない」「そもそも毎時間ごとの2階や3階への教室移動はどうするのか」などの不安や当惑気味の意見が噴出していた。そこで入学式までの間に、保護者と本人と大学関係者による懇談会が数回重ねられることになり、その中で支援の要領が明らかになるにつれ、学内も平静さを取り戻していった。施設面の不備を少しでも補おうと当時高額だった階段昇降機をいち早く購入してはみたものの、入学後は学友たちの支援の手にとって代わられ、殆ど使われなくなってしまった。在学生による支援組織が課題を補う上で大きな支えになることがあらためて知らされることにもなった。以後、大学は身近に生起する様々な課題に学びながら、トイレ、スロープ、ドア等の施設面の改善を漸次行うことになった。
|
(2)視覚障害を有する学生への支援体制の整備 |
| 1996年度には、新たに全盲の学生を含む3人の視覚障害を有する学生を受け入れた。当時、九州でも全盲の学生を受け入れている大学は数少ない状況の中(長崎県下では皆無)、様々な議論が噴出した。しかし、(1)受験したいという受験生の意志に対して、大学は、受験の機会を平等に与えなければならないこと、(2)障害があることで入試や就学を拒むことは、建学の理念であるキリスト教精神や社会福祉コースの看板を裏切るものであること、(3)入学した学生に対し、大学が自らの責任において就学環境を整備することは、すべての学生に平等な教育機会を保障する意味で当然のことであり、しかも、そこにこそ大学自身の学びや成長があること。こうした考えのもと、当時、すでに当たり前の風景となっていた車いす利用学生の就学例に習い、点字受験を手配するなど受け入れ準備が進められた。すべてが初体験のことばかりで、むしろ大学は、多くを学ぶことになった。 点字入試を無事パスした学生は、その後、歩行訓練を理由に1年間休学した。この間、大学では学内にバリアフリー委員会が発足し、その基本方針に基づき、当面、視覚障害のある学生の就学環境の整備を中心に全学的な取組みが開始された。 そこで、障害学生(視覚障害にかかわらず)が、通常の学生生活を営むうえで最低限保障されなければならない点として、「読む」「聴く」「書く」「歩く」の4項目に対してどう支援していくか、という点に絞りながら対応策を検討していった。 以下は、当時、整備を終えた項目の概要である。
この他、教科書や試験、配布資料等の点訳体制の確保や実習時の配慮、教師への協力依頼、学生寮への優先的入寮、点字辞書のソフトがインストールされたノート型パソコンや点字(ピン)ディスプレイ等の貸与申請、代読者の雇用体制等がマニュアル化されたことで、受け入れ体制はほぼ完了した。 1年後、学生は復学した。そして在学期間、特に支障もなく、無事2年間で卒業していったのである。 |
(3)全介助を要する学生への支援体制の整備 |
| 短大にとっては最後の入学式にあたる2001年4月、新たに車いすを利用する学生を1名迎え入れた。車いすを利用する学生については、すでにハード・ソフトの両面で実績を重ねていたが、その学生は脳性麻痺による言語障害と強い緊張のために全介助(移動、食事、代筆介助等)も必要としていた。これまで積み上げてきた障害学生に対する一貫した姿勢は、新たな課題を前にしても維持していった。このとき、支援を要すべき項目を細かく特定するために31のチェック項目からなる「障害者就学のためのアセスメント票」がバリアフリー委員会の手で新たに作成され、支援体制のために役立てられた。こうして、当該学生は短期大学最後の卒業生の一人として、無事2年間で卒業し大学に編入、現在4年生として在学している。 |
(4)日本における障害学生支援 |
「全国障害学生センター」は、毎年、すべての大学に障害学生の受け入れ状況を調査して「大学案内障害者版」として発行している。その2005年版によると、アンケートの回収率は52.02%(373大学)だが、障害者の受験が可能か不能かは、次の表のようになっている。
(出所:大学案内2005障害者版より。うち、外国籍障害者も含む全ての障害者が受験可の大学は59校。)
|
5.まとめ
(1)車いす先生の教員としての採用~共生社会がキャンパス内に |
| 施設、教育体制の整備は、一気に行ったのではなく、本論にあるように、下肢障害者の入学試験、授業、卒業、職員として採用という段階を踏んで行われた。 また、受け入れる障害の種類に関しても、下肢障害者、視覚障害者、全介助者、とステップを踏んで行われた。 この大学のキャンパス内では、障害者・マイノリティと健常者の共生社会が実現されている、と思った。キャンパス内では、7カ国からの留学生たちで、学生達は、世界は多様であることを体験している。共に生き共に暮らす社会をどこにでもある風景にしたい、という大学経営者の想いが伝わってくる。 障害を持った者が学生として受け入れられ、卒業後、教員としての資格を取得したとき、母校において教員として採用され、学生を指導する立場に変わる、という夢が実現されている。 このような事例が増えることにより、障害者の雇用が促進されることが期待される。 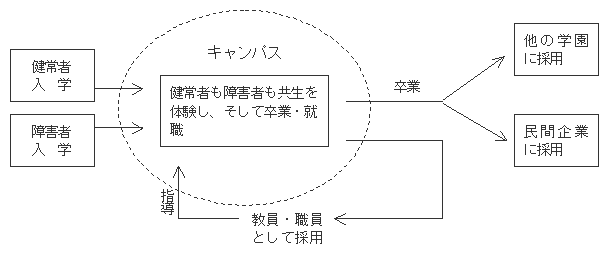 |
(2)学生に与える影響 |
| 障害のある先生が、障害があることに臆せずに教室で授業をしている姿を学生に見せることで、学生の心に変化や勇気を与えているものと思う。障害のある先生が、ありのままの姿を見せることで、学生たちが授業を通じて、チャレンジ精神を養い、可能性を追求する、学生の心の中に思いやりの心を育て、視野の広い、心の広い学生を育んでいると思われる。 我々の社会には障害者もおり、障害者と健常者は共生することが必要といわれ、障害者のいる風景の方が当たり前と思うが、実際には我々の近くには健常者だけの世界が多々見られる。 人は様々、我々の社会は多様な個性をもった人たちで構成されている、ということをこのキャンパスでは、自然に学ぶことを可能にしているのでは、と思った。そしてヒアリングを終えてご協力いただきました大学関係者に感謝をしながら、明るい気持ちで長崎ウエスレヤン大学を後にした。 |
(3)学校における障害者雇用のあり方 |
| 一般に「学校」における障害者雇用率は低い、と思われる。あるべき姿をこの事例から模索してみたい。 ア 大学の教員養成課程などで障害者を入学させ、教員免許を取得できるようにする。 イ 養護学級のみならず、普通学校においても教員として採用する。 ウ 障害を持った教師が健常な生徒に授業を行う。 エ 勿論、一般学部でも、障害を持った学生の受入れを図り、障害者と健常者が共学できるようにする。 このようにすることで、受験第一主義や教育の効率性のみを追及することなく、子供の時から、障害者と共生することにより、後に、「障害」は個性であると考えられる大人に成って、企業人に成りあがり、雇用率を達成する企業人、社会人になるのでは、と思っている次第である。 <参考資料> 1.長崎ウエスレヤン大学地域総合研究所「研究紀要」2巻2号(2004年3月) 2.長崎ウエスレヤン大学「2005年大学案内」 3.長崎ウエスレヤン大学「2002 CATALOG」 4.全国障害学生支援センター「大学案内2005障害者版」 (執筆者:長崎大学環境科学部教授 浜 民夫) |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。