厳しさと緩やかさを併せ持つ
~品質と納期を重視しつつ、自主性を活かしノルマのない企業~
- 事業所名
- リコーエスポワール株式会社
(株式会社リコーの特例子会社) - 所在地
- 神奈川県海老名市
- 事業内容
- 親会社商品のアフターサービス用部品の包装・梱包、複写機ユニットのリサイクル業務
- 従業員数
- 23名
- うち障害者数
- 18名
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 2 現場事務、リサイクル作業指導員 内部障害 0 知的障害 16 部品の包装・梱包、複写機ユニットのリサイクル 精神障害 0 - 目次
1. 会社概要
リコーエスポアール株式会社(以下「エスポアール」とする)は、OA機器メーカーである株式会社リコー(以下「親会社」とする)の特例子会社である。親会社は「人を愛し 国を愛し 勤めを愛す」という創業の精神に基づいて、早くから身体障害者の雇用に取り組んだ実績があり、特例子会社もこの精神の下に平成6[1994]年4月に設立された。以後身体障害者は親会社で、知的障害者は特例子会社で雇用する方針をとっている。
平成17[2005]年6月1日時点の親会社における障害者雇用率は2.05%で、法定雇用率を上回る水準を示している。平成17[2005]年9月1日時点のエスポアールの概況は、以下の通りである。
| 設立 | 1994年4月 | ||
|---|---|---|---|
| 特例認定 | 1994年5月 | ||
| 資本金 | 2,000万円 | ||
| 株主構成 | (株)リコー90%、パーツコンポーネントシステム(株)10% | ||
| 従業員構成 | 知的障害者 | 16名 | 男性11名、女性5名 重度障害4名 |
| 身体障害者 | 1名 | 女性、重度障害 | |
| 指導員 | 4名 | 男性1名(身体障害者) 女性3名 |
|
| 管理者 | 2名 | ||
| 計 | 23名 | ||
同社は部品の包装を主な業務の一つとしている。その包装数は1か月に50万~60万点にのぼり、全世界のサービス拠点を出荷先としている。
エスポアールは設立から10年以上経過し、作業の流れ、行動規範や社員に対する支援体制が確立している。このため他社や養護学校の見学も多く、ある意味で模範的な役割を果たしている。
2. 業務内容と作業上の工夫
(1)グループ制による変動業務
エスポアールでは、社員を4つのグループに分けて仕事を行っている。各グループの担当業務は固定制ではなく、その日の作業量や社員本人の希望と適性に応じて担当業務が決められる。それぞれのグループには指導員が1人ずつ付く。
適性やグループ内の人間関係を見ながら、半年から1年位の周期で社員を4グループ間でローテーションさせ、品質を維持するとともに社員の育成を図っている。
(2)手作業による包装
ア 作業の流れ
手作業による包装は、伝票に基づいて図表1のように進められる。

まず包装する部品と必要な包材を準備する。包装前の部品は所定の場所から作業場へ運び、所定の場所から必要な包材を必要数だけ取り出す。包材を取り出したときには、出庫日・出庫数・在庫数・出庫者を棚札に記録する。
包装作業は、まず部品を小さい単位で包装し、次に小さい単位で包装したものをまとめて大きい単位で包装し、最後に大きい単位で包装したものをまとめて箱に詰める。
端数が出たときの対応方法は、伝票に表示されている。マイナスや不良品が発生した場合は、掲示で知らせる。
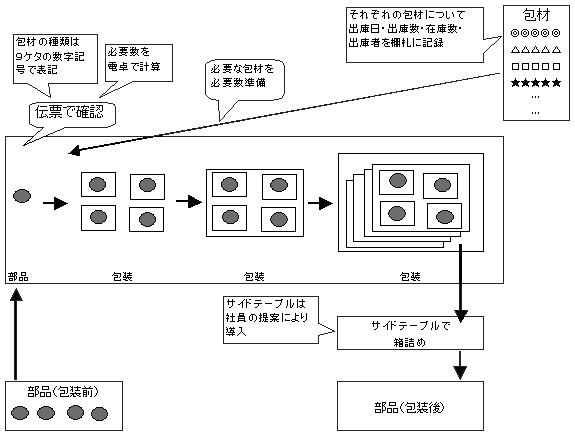
イ 作業の習熟
現在のような作業の流れが確立するまで、約2年かかった。エスポアールの立ち上げ当初は、指導員が包材を準備し、社員は包装作業だけを行っていた。しかも社員の作業量は調査時ほど多くなく、漫然と作業に取り組むこともしばしばあった。そこで空き時間に、伝票に記載されている記号の意味や、電卓の使い方を学習し、必要な包材の準備も全て社員だけでできるようになった。一旦作業の流れが確立した後に入社した社員は、短期間でスムーズに適応している。
また作業の流れが確立するにつれて、作業量が増加したり、作業にジグを必要としていた社員がジグなしでもできるようになるなど、社員の作業能力の向上も見られた。
(3)機械を用いた包装作業
ア 作業内容
エスポアールでは、一定多数の部品の包装に機械を用いている。機械は2台あり、導入の際に助成金を活用した。2台のうち1台はコロと呼ばれるゴム製のローラーの包装機で、1日12,000個の包装ができる。もう1台はブレードと呼ばれる細長い板・棒状の部品の包装機で、1日8,000本の包装が可能である。機械は、安全のため可動部に手が入らないようにする、不具合が発生したときには自動的に停止する、操作パネルはシンプルにし表示をわかりやすくする、スイッチは正常・異常のシール・サインを貼るなど、知的障害者が使いやすいように設計されている。自動包装機の導入及び活用のプロセスは、平成7[1995]年、日本障害者雇用促進協会(当時)主催「第3回障害者雇用促進のための職場改善コンテスト」(※注)で優秀賞を受賞した。
包装作業は、(1)箱を組み立てる、(2)部品を箱に入れる、(3)箱に封をする、(4)バーコードラベルを貼る、(5)部品番号を照合する、(6)包装済みの部品を箱に詰める、という順序で進められる。(2)と(6)は手作業で、他は機械が行う。機械による包装も伝票に基づいて進められる。なお一例として、ブレードの包装作業の流れを図表2で示す。
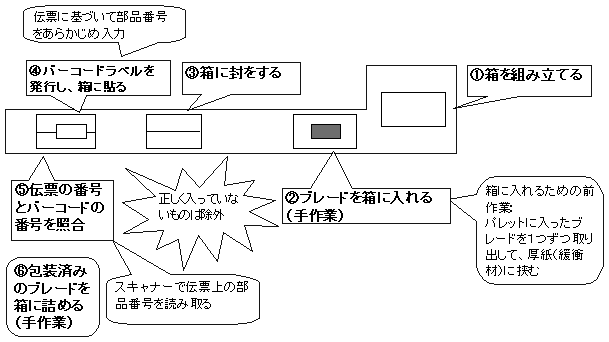



イ 作業の習熟
機械を導入した当初は、操作を担当する社員を2人配置していた。やがて操作に習熟すると1人だけで担当するようになり、もう1人は他の作業を担当するようになった。
また指導員の指示や経験の蓄積を通じて、社員は機械の始動や停止だけでなく、点検、消耗品の交換、部品番号の入力、小さなトラブルへの対処などもできるようになった。機械に不具合が生じると、自動的に停止する。次にスイッチ、更に他の場所を見て原因を突き止め、不具合を直す。機械は3年に1度くらいの頻度で、業者による点検を受けている。
(4)複写機ユニットのリサイクル作業
ア 作業内容
複写機ユニットのリサイクルは、(1)開梱、(2)解体、(3)再利用可能な部品と処分する部品の分別、(4)リサイクル部品の洗浄、(5)作業実績を伝票に記録、(6)3階の作業場から1階へ部品を移す、という順序で進められる。(エスポアールは、4階建てのビルの3階にある。他の階には関連会社が入っている。)

解体作業は機種ごとに決められたブース内で行う。作業の際には、危険防止のため手袋を二重にはめるようにしている。
部品の分別には判断を要するが、その基準として、処分する部品のサンプルを提示することで、再利用可能な部品を区別できるようにしている。このような方法を取るのは、再利用可能な部品の例があまりにも多すぎるからである。また間違いやすい部品もサンプルを提示し、注意を促している。
部品の洗浄は、汚れの軽いものは手で、ひどいものは超音波洗浄機で行う。包装機だけでなく、この洗浄機の導入にも助成金を活用した。洗浄作業でも仕上がり具合を見るために判断を要するが、納品先からの苦情、サンプルの提示、作業の実演や社員自身の経験の蓄積により、ある程度可能になった。
イ 関連会社社員との関わり
この作業は、建物1階の関連会社のスタッフとともに行う。作業量が多いときには、社員が所属・利用する福祉施設に応援を依頼することもある。
特例子会社は障害者を集中的に雇用するため、差別や隔離につながり、ノーマライゼーションの観点から好ましくないとする見方がある。しかし特例子会社の従業員と、親会社・関連会社・関係機関等の従業員が共に仕事をすることは、差別や隔離といった見方を是正し、障害者に対する理解を深める上で最も有効な方法の一つである。
(※注 「障害者雇用促進のための職場改善コンテスト」は2002[平成14]年より「障害者雇用職場改善好事例」と改められた。)
3. 行動規範と提案制度
(1)来客への挨拶
エスポアールでは、社員は立って作業を行う。座るよりも立つ方が作業に集中でき、かつ、作業中に発生するさまざまな問題等に対応しやすいからである。立って作業をすることは、初めのうちはつらく感じることもあるが、1週間もすれば慣れるとのことであった。
作業場に来客が入ったときには、目が合ったときに目礼をする程度にとどめる。知的障害者を多数雇用する事業所の中には、来客があると従業員が一斉に挨拶をするところもあるが、エスポアールではそのようなことをせず、作業に専念する。挨拶をするとそのために作業を中断しなければならないからである。挨拶は基本的な対人コミュニケーションの一つであるが、それをしないからといって礼を失するわけではない。
(2)定物定位
包装前の部品、包装後の部品、伝票、包材、パレット等作業で扱う物は、全て所定の位置に置く(図表3参照)。置き場所を視覚的にわかりやすくするために、床に線を引く、「○○置き場」という表示を設ける、といった工夫も行う。包装前の部品は納期順に並べる。パレットは搬送先によって置き場所を定めている。
このように定物定位を心掛けることで、作業の効率化、品質の確保及び納期の厳守につなげている。
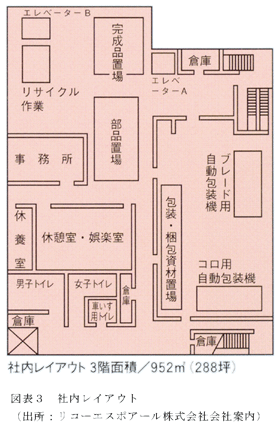
(3)創意工夫
品質や納期に厳しい反面、作業の進め方についてはある程度社員に創意工夫の余地を持たせている。エスポアールでは作業指示書やマニュアルの類を用いない。工程が比較的短く、作業時の基本動作が決まっている一方で、部品の点数が多く、入れ替わりが激しいためである。また社員の中にも、他の人が取る方法の模倣を好む者もいれば、それを嫌う者もいる。作業上の癖やこだわりを持つ者もいる。
知的障害のある従業員が作業を容易に習得し、かつ一定の品質を確保するために、マニュアル等を用いて作業の標準化を図る事業所は少なくない。しかしエスポアールの場合、仕事と社員の双方の特性から、方法を統一するよりむしろ社員に工夫や改善の余地を持たせる方が適当といえる。
(4)目標と評価
エスポアールでは、標準作業量やノルマを設定せず、終業時に当日の作業実績を個人レベルで日誌に記録するといったこともしない。その代わり、社員全員で努力して、要求される品質・納期・コストを満たせば良しとしている。多種多様な部品を扱う、部品の数量が一定ではない、グループで作業を行うときには個人の貢献度が正確に把握しにくい、といった理由からである。
仕事は親会社から固定費で受注し、実績は伝票で把握する。作業は、固定費と実績を比較した上で、費用に見合うように進めることとしている。社員の技能の向上度合いは、月間数値など中長期的な指標を判断材料の一つとしている。
以上のようにエスポアールの行動規範は、作業に集中することを優先し、品質・納期・コストを重視する一方で、ノルマを設定せず、創意工夫を奨励するなど、厳しさと緩やかさを併せ持っていることが大きな特色といえるだろう。
(5)提案制度
社員の自主性や創意工夫を仕事に生かすための仕組みが、提案制度であり、1999年に始まった。
提案にあたって、社員は従来の作業方法と自ら新規に考案した作業方法を所定の用紙に記入する。記入の際には、指導員の支援を受けることもある。その後、社員は上司と面談し、提案内容の評価に応じて200円から10,000円の報奨金の支給を受ける。提案件数は、業務の繁閑や重点的に取り組む項目の変化により波があるが、多いときには1名の社員が月に7~8件提案することがある。また提案は個人だけでなく、グループで行うこともある。提案内容は社内に掲示され、これによって更なる工夫や努力を引き出すようにしている。
提案制度の導入以来、5年間で出来高(部品包装単価に数量を掛けた値)が150%上昇した。作業に用いる機械が動く速度は一定なので、提案制度の導入後に出来高が上昇したということは、大きな変革を伴わない小さな工夫によって作業効率が改善したことを示している。
社員による提案の例としては以下のような内容があげられ、日常の業務に活かされている。
社員による提案の例
(出所:参考文献1) |
4. 職務遂行・就労継続のための支援体制
(1)指導員について
エスポアールは、知的障害のある社員の職務遂行を援助するために、指導員を4名配置している。指導員の役割は、仕事の大まかな段取りを組むことと、社員による対応が困難な変化や問題に対応することである。指導員は一旦指示を出すと、その後は原則として社員に手や口を出さず、自身の作業を行う。その傍らで社員の動きを観察し、何かおかしいところを察知すれば対応にあたる。また指導員と管理者は週に1度ミーティングを開き、問題提起や意見交換、情報共有を行う。
(2)関係者との連携
知的障害者は、学習、適応や状況理解に難があるという特性から、心身の自己管理が総じて不得手である。そこで、エスポアールでは家庭、福祉施設、医療関係者、地域資源、他企業等と連携し、社員が就労を継続できるように努めている。
家庭とは年に2回交流を持つようにしている。社員の家族には年に1度来社してもらい、社員の仕事ぶりを実際に見たり、スタッフと話し合う機会を設けている。また年に1度の社員旅行には家族も招待する。
医療関係者とも連携し、社員の心身の健康管理に努めている。親会社の他事業所の医務室から看護師が月に2回来て、健康上の相談に応じる。また精神科医によるカウンセリングが月に1度行われる。
社員が所属・利用する福祉施設とは、社員の仕事と生活に関する情報を共有し、持ちつ持たれつの関係を築いている。作業量が多いときには、施設に応援を依頼することがある。これには納期に間に合わせることができるだけでなく、施設のスタッフが社員の仕事ぶりを理解できるというメリットもある。他方で施設には社員の心理面・生活面の相談に応じてもらい、問題が発生したときに対処できるようにしている。
また障害者雇用に対するセミナーやイベント、NPOの活動等を通じて、他企業や教育、行政、各種団体とも連携を図っている。
(3)採用と実習
採用は、原則として、養護学校や職業能力開発校等の生徒を対象としている。実習、面接、保護者及び出身母体(学校、福祉施設等)の確認を通じて、手先の器用さ、根気、注意力、作業遂行能力、社会適応能力などを総合的に検討した上で、採用を決定する。なお近年の採用は、欠員の補充が中心となっている。
このほか、採用を前提としない実習については、養護学校の生徒及び教員、職業能力開発校の生徒等をそれぞれ年間数人ずつ受け入れている。
(4)今後の課題
エスポアールは設立から10年以上経過し、勤続10年を超える社員もいる。しかも近年採用を抑制していることもあり、社員の平均年齢は上昇傾向にある。したがって、社員の加齢に伴う体力・作業能力の低下にいかに対応するかが今後の重要な課題である。
5. おわりに
エスポアールでは、就業時間中は作業に集中することを優先し、品質・納期・コストを重視する一方で、作業自体については社員の自主性に任せ、創意工夫を奨励している。これは「厳しさと緩やかさの両面を同時に持つ」ことそのものといえるだろう。
「厳しさと緩やかさの両面を同時に持つ」というのは、1980年代のビジネス書のベストセラー『エクセレント・カンパニー』(ピーターズ&ウォーターマン著、※参考文献4)において、アメリカの超優良企業に共通して見られた8つの基本的特質の一つである。同書の主張には支持もあれば批判もある。1980年代に奨励されていたことが、現在では通用しなくなっている場合もあるだろう。
とはいえ実際に働く上で、厳しさばかりでは意欲を失い結果にも悪影響を及ぼしかねない。だからといって緩やかさばかりでも、規律が乱れて仕事が成り立たない。したがって人を仕事に動機づける上では、厳しさと緩やかさのバランスが重要となる。特に学習や理解、適応に難のある知的障害者にとって、優先すべきこと、奨励すること、禁止することを明確に区別し、意欲につなげていくことは、尚更重要である。
現在の作業体制や行動規範は、約2年にわたる試行錯誤の結果確立されたものである。その確立と継続の背景には、家庭、福祉、教育、医療、その他関係者との連携があった。
エスポアールが仕事を通じて「厳しさと緩やかさの両面を同時に持つ」ことを10年以上にわたって実践したことは、同社が他企業の模範となり、更に漫画のモデル(※参考文献5)とされた重要な要因といえるだろう。
| 1) | リコーエスポワール株式会社会社案内 |
| 2) | 青木 律子 「知的障害者に対する提案制度の適用例」『職業リハビリテーション』第18巻1号 2005年 34-40頁 |
| 3) | 本間 修 「当社の知的障害者の雇用 -自動包装機器の導入を通して-」『労働の科学』53巻6号 1998年 16-19頁 |
| 4) | T. J. Peters & R. H. Waterman Jr., In Search of Excellence, Harper & Row, 1982(大前研一訳『エクセレント・カンパニー』[上][下] 講談社[文庫] 1986年) |
| 5) | 戸部けいこ『光とともに・・・』第7巻 秋田書店 2004年 |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











