個々の特徴を生かした職務配置により、社員の半数が知的障害者
~ジョブコーチとの連携と職務の工夫~
- 事業所名
- 有限会社鴛谷豆富店
- 所在地
- 石川県金沢市
- 事業内容
- 豆腐・揚げ製造販売
- 従業員数
- 10名
- うち障害者数
- 5名
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 0 内部障害 0 知的障害 5 豆腐製造補助、洗浄 精神障害 0 - 目次

1. 障害者雇用の経緯と障害者雇用の状況
(1)障害者雇用に取り組むことになった経緯
当社は、昭和60年4月設立であり、経営理念は「よい材料を使い、よい商品を作る」である。現在の代表取締役社長は鴛谷一男氏。
障害者雇用のきっかけは、先代の社長が、取引先の病院から頼まれて精神障害者を受け入れたことからである。しかし、その人は調子が悪くなると欠勤することが度々あったため、継続雇用には至らなかった。会社は少人数で多くの商品を製造するために、安定した労働力を求めていた。その後、知的障害者を雇用。欠勤が少なく、また指示したことは素直に聞くという真面目な勤務態度が評価され、その後の継続した障害者雇用につながった。
現在雇用している知的障害者5名を採用していく過程で、2名の精神障害者の実習受け入れや雇用を行ったが、安定した労働力を得ることはできず、現在は知的障害者のみの雇用となっている。
この会社における多数の障害者雇用は、金沢市社会福祉協議会(以下、金沢市社協とする)ジョブコーチとの連携などにより進められてきた。
(2)雇用している5名の知的障害者について
| Aさん | Bさん | Cさん | Dさん | Eさん | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年 齢 | 26歳 | 23歳 | 53歳 | 18歳 | 38歳 |
| 障害程度 | 軽度 | 軽度 | 重度 | 重度 | 軽度 |
| 最賃除外 申請の有無 |
無 | 無 | 有 | 有 | 無 |
| 勤務期間 | 5年3ヶ月 | 3年2ヶ月 | 8ヶ月 | 4ヶ月 | 1ヶ月 |
| 職 務 | 豆腐の加熱殺菌処理、冷却処理 | 配送箱の洗浄 | 豆腐、揚げ製造時に使用する道具類の洗浄 | 薄揚げ製造機の洗浄 | 豆腐製造機の洗浄 |
| 配送先毎への仕分け | 揚げ機の清掃 | 薄揚げ種の冷却 | |||
| Bさんの補佐 | 社長の補佐 | 社長の補佐 | |||
| 豆の補充 | |||||
| 勤務時間 | 8:00~14:00 | 8:30~14:00 | 7:30~13:00 | 8:30~12:00 | 8:30~14:00 |
2. 注意事項ファイルを作成して支援したAさん
(1)雇用の経緯
平成12年4月にハローワークの紹介で石川県障害者職場実習(以下、県実習とする)を始めたが、うまく仕事を覚えることができず、会社からハローワークに相談。石川障害者職業センターを経由して金沢市社協に依頼があり、ジョブコーチ支援が行われた。
その結果、会社の望む職務がこなせるようになり、採用となった。
(2)ジョブコーチ支援
ジョブコーチがAさんの課題になっている部分を分析したところ、豆腐の種類が多いことで混乱を招いていることが分かった。ジョブコーチは、豆腐のパッケージと注意事項を記入したファイルを作成し、Aさんはそれを手がかりに職務をこなせるようになった。
また、ジョブコーチ支援が一段落した後も、そのファイルの活用は会社の方にも引き継がれ、Aさんに覚えてもらいたいことを紙にまとめ、ファイルに入れるようになった。
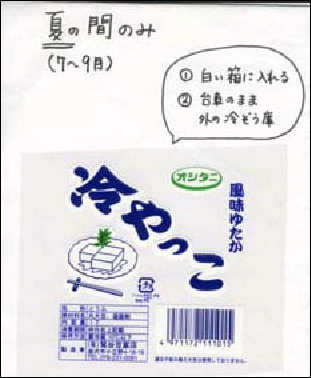
(3)職務配置
Aさんは、人とコミュニケーションを取ることが苦手であり、これまでもそれが原因で離職を繰り返していた。鴛谷豆富店で働くにあたり、できるだけ人と関わらなくてもできる職務を割り当ててもらった。そのことで、Aさんは集中して自分の職務をこなすことができるようになった。
(4)現在の様子

今ではジョブコーチが作成したマニュアルも必要とせず、完全に1つの作業工程を任されている。周りからの信頼も厚い。
仕事を覚えたことで自分自身に自信が持てるようになり、苦手だった他の従業員との関わりも出来るようになってきている。
3. 手順書を作成して支援したBさん
(1)雇用の経緯
平成14年4月にハローワークの紹介で県実習を始めたが、作業に時間がかかっており、採用が望めない状態であった。Bさんの入所する通勤寮を通じて金沢市社協に依頼があり、ジョブコーチ支援が行われた。
その結果、30分程の時間短縮が出来るようになり、採用となった。
(2)ジョブコーチ支援
ジョブコーチがBさんの課題を分析したところ、『洗浄機と手洗いを交えながら洗う』という流れが理解できていないため時間がかかっていたことが分かった。
そこで、従業員に手順の確認やコツの聞き取りを行い、Bさんがわかりやすいよう文字と写真を組み合わせた手順書を作成した。
| 5 | 手洗いの前に機械で洗浄します |
 |
| 6 | 機械が動いている間に箱を洗います |
 |
| 7 | スポンジに洗剤をつけて洗います |
 |
| 8 | 洗剤を流します |
 |
(3)職務配置
Bさんは自己主張が強いため、他の従業員と一緒に仕事をしていくことが困難と思われた。そこで一人で行える配送箱の洗浄を職務とした。他の従業員と離れた位置での洗浄業務であったが、Bさんは真面目な性格であるため、手を抜くことなくコツコツと仕事に取り組むことができている。
(4)現在の様子

洗い残しもなく、配送箱の洗浄は完全に任せられている。包装担当者から「急ぎで○箱欲しい」という指示を受けても、すぐに対応することもできるようになった。
4. 文字のない手順書を作成して支援したCさん
(1)雇用の経緯

平成16年10月、ジョブコーチによる定期訪問時に会社が「薄揚げを揚げる職務をしていた従業員が退職したため、代わりに働ける障害者はいないか」と相談した。ジョブコーチとハローワークが連携し人材を選出したが希望者がいなかったため、社会福祉施設に話を持ちかけた。会社から近い場所にある知的障害者更生施設のグループホーム入居者だったCさんが、働くことを希望したため、ジョブコーチの支援を受け、県実習が行われた。
その後、少々の不安は残るものの、本人にやる気があったため、採用となった。
(2)ジョブコーチ支援
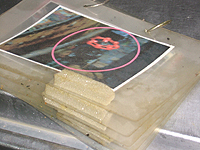
Cさんの仕事の柱の一つとなる「揚げ機の清掃」を教えるにあたり、ジョブコーチが手順を分析し、手順書を作成した。この手順書には、Cさんの文字を読むのが苦手、数が数えられない、手先が不器用という3つの欠点をカバーする以下のような特徴がある。
- 写真のみで構成する
- 順を追っていく形ではなく、順にめくっていく形にする
- めくりやすいように隙間を作る
また、正式雇用になった後、集中力に欠け、洗い残しが続いたことがあった。ジョブコーチと施設の職員と話し合った結果、Cさんが「働く楽しみ」を見出せていないことが原因とわかった。そこで、給料を使う喜びを感じられるよう、ガイドヘルプサービスを利用し、買い物やボーリングなどに出かける機会を作った。また会社側も、Cさんが楽しく働けるような雰囲気作りを心がけた。
(3)職務配置
Cさんは、言葉でのやりとりは可能だが、文字の読み書きや、5以上の数字を数えることはできなかった。
募集のあった職務は薄揚げを揚げる業務全般であったが、機械の微調整など難しい作業が多かったため、揚がってきた薄揚げを箱に並べていくという職務中心で行うことにし、実習を開始した。しかし、「1列7枚で3列」と数えることに時間がかかってしまい、機械のスピードについていくことができなかったため、この職務もできなかった。
そこで、薄揚げを揚げる仕事を社長がすることになり、代わりに社長や従業員が片手間で行っていた道具等の洗浄をCさんの柱となる職務とした。
(4)現在の様子
採用当初は、こなせる職務が限定され問題も多かったが、除々に様々な職務を遂行することができるようになり、会社の戦力になっている。
5. 勤務時間と職務内容の調整について支援したDさん
(1)雇用の経緯

平成17年2月、ジョブコーチによる定期訪問時に会社が「薄揚げ製造機の洗浄をしていた従業員が退職したため、代わりに働ける障害者はいないか」と相談した。ジョブコーチとハローワークが連携し人材を選出したが希望者がいなかったため、養護学校に話を持ちかけた。高等部3年生だったDさんが働くことを希望したため、ジョブコーチと教員(実習サポーター)の支援を受け、現場実習が行われた。
この実習で内定をもらい、卒業後採用となった。
(2)ジョブコーチ支援
薄揚げ製造機は複雑な仕組みになっていたため、社長に洗い方のコツを聞き、その手順を整理し、Dさんに伝えた。
また、Dさんは「P所(小規模授産施設)に行きたい」という思いと「鴛谷豆富店で働きたい」という思いが交錯している状態であった。Dさんの精神面の安定にP所は重要なポイントであったため、両方の思いが叶えられるよう、午前中のみの勤務にしてもらい、午後から余暇活動の場としてP所に行けるよう調整をした。
(3)職務配置
Dさんの思いを叶えて午後からP所に行けるよう、4時間程度の仕事量である薄揚げ製造機の洗浄に職務を限定した。
(4)現在の様子
「午後からP所に行けるように午前中に仕事を終わらせる」という目標を持ちながら、集中して働いている。
6. 実習中の職務転換により採用されたEさん
(1)雇用の経緯
平成17年6月、出来上がった揚げ類の包装の職務の募集をしていたところ、ハローワークからの紹介があり、金沢市社協のジョブコーチ支援を受けながら、県実習が行われた。募集をしていた職務については採用とならなかったが、真面目な仕事ぶりが評価され、別の職務に配置転換することで採用となった。
(2)ジョブコーチ支援
包装作業は、注意しなければならない点が多く、ジョブコーチが周りの従業員にポイントを聞き、整理しながら本人に伝えた。
(3)職務配置
実習中は包装作業を行っていたが、包装時の温度チェックなど商品の良し悪しを左右する責任の重い職務だったため、完璧な職務遂行能力を求められた。実習中に数回、うっかりミスがあったため、会社は採用に消極的であったが、真面目に黙々と働く姿を会社は評価していた。そこで長所を生かした豆腐製造機の洗浄を中心とする職務に配置転換をした。
(4)現在の様子

豆腐製造機の洗浄は、隅にこびりついた豆腐を取らなければならないなど非常に根気のいる職務だが、大変きれいに洗浄している。また、他の職務もこなすことができるようになり、大きな戦力になっている。
7. まとめ
これまで述べたように、鴛谷豆富店では従業員の半数という多数の障害者を雇用し、それぞれが戦力になっている。しかし、現在に至るまで障害者雇用がすべてうまくいったというわけではない。生鮮食品の製造のためにまとまった休日もなく、小規模企業のため1つの職務を複数で行うことができないので個々の責任が大きい。今まで、精神障害者の実習受け入れや雇用をしてきたが、長く続かなかったのは、精神障害者にとって「休みにくい」「責任が大きい」ということが負担になっていたのではないかと思われる。
同じ業種・職種でも、障害の種類や状態、個々の特性によって向き不向きがある。事業主や支援機関は、障害者が最も能力を発揮できるような職務配置を考えていく必要があると考える。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











