ことばでのコミュニケーションが難しい知的障害者の雇用
~養護学校の実習制度と個別指導の活用~
- 事業所名
- 株式会社セイツー
- 所在地
- 石川県能美郡川北町
- 事業内容
- 飲食料品加工卸売業(青果流通販売業)
- 従業員数
- 128名
- うち障害者数
- 9名
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 1 食品製造 肢体不自由 0 内部障害 0 知的障害 8 食品製造 精神障害 0 - 目次

1. はじめに~養護学校卒業生の就職~
今日の養護学校高等部進路指導における最大の課題は、一人一人の生徒の進路先確保と卒業後の生活支援体制の確立である。
そのため、石川県立明和養護学校(以下「本校」という)では、高等部3年間の学習カリキュラムの中で、計画的・継続的に進路学習や就業体験実習(以下「実習」という)を行うことにしている。在学中から石川県障害者職業センター、金沢・こまつ両障害者就業・生活支援センターなどの関係機関と連携しながら進路指導に当たっており、卒業後の生活がよりスムーズに移行ができるようになっている。
実習は4週間に及ぶものもあり、在学中に本校の実習サポーターや障害者就業・生活支援センターのジョブコーチと共に就労現場における問題点の発見と解消に取り組むことが出来るようになっており、企業側にとっても即戦力として採用出来るというメリットがみられるようになっている。
今回の報告は、株式会社セイツーのご理解のある取り組みによる成果が大きいものではあるが、養護学校からの就労にあたって、特に実習のメリットがより強く反映されたものでもある。
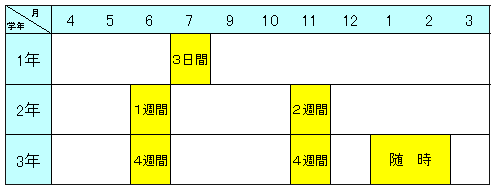
2. 事業所の概要
(1)障害者雇用の状況と考え方
株式会社セイツーは「土、野菜、人間」をキーワードに、土壌とそこでとれる野菜の品質の相関関係を科学的に分析し、契約農家に直接栽培方法を指導してつくる「高品質野菜」の生産を行っている。企業理念は「人間性豊かな食文化、生活文化の創造に貢献」、行動指針は「自然への感謝、社会への感謝を忘れません」であり、特色のある経営方針を打ち出している。
障害者雇用に対しても大変積極的であり、平成16年度には知的障害者9名、聴覚障害者1名の計10名が勤務している。最近では、平成12年度卒業生3名、平成13年度卒業生2名が本校から雇用に至っている。本校の「現場実習協力企業」にも平成12年12月に登録いただいている。
代表取締役の奥村晃氏は、「障害のある人が社会で働いて認められることと、その報酬が得られることを知ることは大変重要だ。障害のある人でも会社の中で適切な仕事をコーディネートしていけば十分働くことが出来る。・・・」と熱く語られている。
(2)職場での対応
株式会社セイツーにおいて、障害者に対しての具体的な支援については以下のとおりである。
- 現場に業務遂行援助者を配置し、仕事の手順、職場の人間関係などに配慮している。
- 金沢障害者就業・生活支援センターおよび石川障害者職業センターからのジョブコーチ支援により、日常生活における問題解決も行っている。
- 安全管理には特に配慮し、仕事の前と後で刃物の本数を点検するなどしている。
現場の方々は、障害のある方のこだわりからくるトラブルにも極めて普通に接していただいている。「理由が解れば、特に問題はありません。」という声が現場の方々から聞こえてくる。
3. 知的障害のあるRさんの雇用までの経緯

平成16年6月、本校高等部3年生2名が野菜のカット作業で実習を行うこととなった。そのうちの1名が、知的障害のあるRさんである。実習中は本校の実習サポーターおよび金沢障害者就業・生活支援センターのジョブコーチが支援にあたることとした。
実習の結果、Rさんについて、作業遂行能力に大きな問題はなく、素直で明るい性格と評価していただいたが、体力的な面およびコミュニケーションの問題から雇用については「保留」という結果となった。そこで、自立活動という学習活動でRさんのコミュニケーションについて個人指導を行い、その指導の中からRさんへの配慮事項を確立した。
平成16年11月から、再度セイツーにて実習を行った。その実習では大きな変化はみられなかったが、作業内容のモデリングの徹底と現場の業務遂行援助者の理解によって、大きなトラブルがみられなくなり、その後も実習を重ねた。
その結果、平成17年3月にRさんは採用となった。
採用後も、金沢障害者就業・生活支援センタージョブコーチおよび本校の卒業生相談員とも連携を図り、問題があった場合に備えながら現在に至っている。
4. Rさんの特性・課題と在学中の支援
(1)Rさんの特性・課題
ア コミュニケーション
Rさんは、日本語だけでなく、家庭内で使用されている言語にも困難がある。つまり音声言語による指示は伝わらないことが多い。
友人との関係は良好であるが、何を言われてもニコニコしているので、友人から誤解されることがあるなど、言葉が通じないために小さなトラブルが起きることがある。
イ 作業能力
手先の巧緻性などに問題はない。普段から家庭で行っている皿洗いなどの家事は、障害のない人と同等以上の作業遂行力がある。
作業に対する姿勢は至ってまじめであるが、コミュニケーションに問題があるため、作業中にトラブルや不調を自ら訴えることができない。
複雑な作業についての理解はモデリングで示す必要がある。
(2)在学中の支援の取り組み
養護学校では、児童生徒の障害に基づく様々な困難を改善、克服し、自立し、社会参加する資質を養うための指導である自立活動という学習がある。平成16年に学級担任とこの自立活動担当者が協力し、Rさんが将来職場や地域社会で生活する上で必要なコミュニケーション能力を身につけるための取り組みを行った。
ア Rさんのコミュニケーション能力についての把握
聴覚認知、音声言語の理解度、本人の発声、文字などの視覚情報の理解度、身振り表現、作図等、幅広く行うこととした。特に視覚情報については、簡単な絵カードを用いた取り組みを行った。(表1参照)
絵カードを見て、意味を理解することはそれほど難しいことではない(絵カードによる正答率8割程度)が、サ・タ・ハ行など発音が難しいものが多数あるため表現が難しい場合、本人なりの「言い換え」を行おうとしてうまくできない場合が多い(絵カードによる評価は5割程度)。「言い換え」には時間的・心理的な余裕が必要である。頭で理解していても、音声言語は、周囲が感じている以上に困難であることがわかった。
コミュニケーションに関しては急激な改善は難しく、意味は理解していることが多いことから判断すると、言葉で指示するよりも、「やってみせることの方が大切である。」と周囲が共通理解できた。
| 絵カードの内容 | 発音 | 備考 |
|---|---|---|
| 足 | あし | 問題なし |
| ゾウ | じょうさん | 「ぞ」→「じょ」 |
| ゼリー | ちゅむもの | 「のむもの」? |
| 大根 | だいこん | 問題なし |
| 階段 | かったん | 聞き覚え違い |
| ネギ | しゃんちょん | 母国語? |
| 布団で眠る | おやすみ | 言い換え |
| スイカ | しゅいか | 「す」→「しゅ」 |
| 穴に落ちる | ぼとんいたいよ | 言い換え |
| 郵便ポスト | ・・・(無言) | ? |
| ちりとり | じょうち | 「そうじ」 |
イ 実態を把握した上でのソーシャルスキルの向上
平成16年6月の実習で「無表情になり、突然泣き出す」といった状態が見られたこと等から、不調・困惑を訴えられるようになることが最優先の課題となった。具体的な取り組みは、「いや」「わからない」という拒否の表現の練習を行い、学校生活でのそういった場面で、学級担任を中心に指導をしていくこととなった。また、絵カードを使用したコミュニケーションの指導などをとおして、広い意味でのソーシャルスキルトレーニングを積み重ねた。
その結果、徐々にではあるが、スムーズに表現ができるようになっていった。卒業間際には、ちょっかいを出す男子生徒に向かって「やめて、○○(生徒名)キライ!」と表現するまでに至った。
5. 採用後の支援についての話し合い
平成17年3月、採用にあたって、企業と支援機関である金沢障害者就業・生活支援センターと学校の三者で、卒業後の支援について会議を設けることとなった。これは全国の養護学校で平成16年度より試行されていた「個別移行支援会議」と呼ばれるもので、どの機関がどういった支援をするかという役割を明確化させようとするものである。(表2参照)
| 本人・保護者の将来の希望と課題、および関係する支援機関(連絡先) | |||
|---|---|---|---|
| 将来の希望 | 具体化のための課題 | 関係支援機関(連絡先・担当)と役割 | |
| 職場での作業 人間関係 |
・野菜の下処理のみならず、前処理等いろいろな仕事を行う。 ・職場の人たちに、自分の思っていることが言えるようになる。 |
・仕事の段取りを覚え、自分の判断で動けるようになるまで、一つの仕事を継続する。 ・初めはキーパーソンとの円滑なコミュニケーションをはかり、それをつなげていく。 |
・金沢市社会福祉協議会 金沢障害者就業・生活支援 センター 就業支援担当:Mさん ・(株)セイツー 担当 :T氏 |
| 家庭生活 | ・ある程度の家事も行う。 ・買い物等一人で外出できるようになる。 |
・家庭での自分の役割を明らかにし、継続して行う。 ・支援者と共に外出することを繰り返し、一人で外出する方法と自信を身につける。 |
・金沢市社会福祉協議会 金沢障害者就業・生活支援 センター 就業支援担当:Mさん ・卒業時担任:Y教諭 |
| 余暇活動 | ・公共交通機関を利用して、行きたい所に一人で出かけられる。 ・友達と余暇を楽しむ。 |
・支援者と共に外出することを繰り返し、一人で外出する方法と自信を身につける。 ・携帯電話等で友達と連絡をとることを覚える。 |
・金沢市社会福祉協議会 金沢障害者就業・生活支援 センター 就業支援担当:Mさん ・卒業時担任:Y教諭 |
平成17年6月には、Rさんの様子について、(株)セイツーの業務遂行援助者より金沢障害者就業・生活支援センターおよび本校へ相談があった。その内容は「作業面・生活面においても問題はないが、本人がどのように思っているかわからない。」といったものであった。そこで本校の元学級担任・進路担当者から以下のような回答をした。
- 言葉によるコミュニケーションが難しいために、主語述語のある文章で返答しなければならない質問に対しては、生返事をするだけになってしまう。質問の方法は「はい」「いいえ」で示されるものがよい。例えば「足は痛いか?」「○○さんとお話できる?」など。
- コミュニケーション以外については体力的なことが課題と考えられる。
- 体力面として初めに出てくる問題を腕や足の痛みとして言い換えると思われる。
その後、巡回相談を行うこととし、平成17年8月現在、金沢障害者就業・生活支援センターとともに支援を継続している。
6. まとめ
今回は養護学校での取り組みを中心に報告したが、(株)セイツーでは、重度障害者介助等助成金による業務遂行援助者を活用することによって、より細やかな指導ができていることや関係機関との連携がスムーズに行われていることが、障害者の雇用を支えているといえる。
今後は、企業・支援機関・学校が連携して支援することにより、Rさんが自分自身の力で、自分なりの人間関係を築き上げることが望まれる。
また、奥村社長は、会社のそう遠くない場所に住居を確保するなど、生活面においても自立できるような設備が必要であると考えている。その時には障害者支援費制度による居宅支援事業や施設利用など福祉的なサービスを併用し、グループホームなどが造られるのかもしれない。奥村社長の話から、障害のある人たちの社会的な自立について大きな夢が感じられる。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











