自主性を重んじた職場運営と独創的な人材育成
~9つの委員会制度、業務改善提案運動、知的障害者の事務業務での能力開発~
- 事業所名
- 株式会社ニッセイ・ニュークリエーション
(日本生命保険相互会社の特例子会社) - 所在地
- 大阪府大阪市
- 事業内容
- 印刷・製本(営業から各種製本加工までの全工程)
一般事務(日本生命の事務代行)
・生命保険関係事務処理
・印刷発注管理事務 - 従業員数
- 94名
- うち障害者数
- 80名
障害 人数 従事業務 視覚障害 1 総務、経理事務 聴覚障害 35 印刷・製本、一般事務の全領域 肢体不自由 39 印刷(プリプレス)、一般事務の全領域 内部障害 2 一般事務(生命保険関係事務処理)、印刷(製本) 知的障害 3 一般事務(生命保険関係事務処理) 精神障害 0 - 目次
1. 事業所の概要と障害者雇用の状況
(1)特例子会社設立の経緯
平成4~5年頃に、親会社である日本生命で、「重度障害者の積極的雇用を通じた福祉に先進的な企業イメージの向上、障害者雇用率の安定的確保」を主眼に特例子会社の設立検討が進められた。
平成5年4月に特例子会社であるニッセイ・ニュークリエーションを設立、同年11月より業務を開始し、平成6年3月に特例子会社認定を受けた。
創業時よりノーマライゼーションを積極的に推進する観点から、親会社の営業部(営業拠点)と同一ビルに同居し、社内外に障害者雇用の必要性を訴求した。
現在は障害者雇用の拡大に伴い、執務スペースを最大限活用するため同社のみの単独入居となっている。
(2)助成金の活用
創業時、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金、重度障害者等通勤対策助成金等を活用。
現在の助成金の中心は、手話通訳派遣(平成16年度実績延べ101人)、特定求職者雇用開発助成金となっている。
(3)組織
主な業務は業務課と印刷課が担当している。その他、社内の経理・福利厚生等を担当する総務課がある。
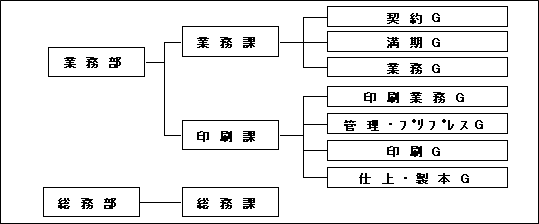
(4)業務内容
業務の中心である印刷課と業務課について下記に述べる。
ア 印刷課
・ 営業活動(車いす使用者の営業車を駆使している。)
・ 製版・平版オフセット印刷・各種製本加工の全工程
・ 印刷発注管理事務(印刷物の価格査定、価格交渉、支払管理事務等)
イ 業務課
事務代行部門として、親会社である日本生命保険相互会社より業務委託を受けている。業務は、生命保険関係事務処理であり、親会社のオンライン端末を駆使している。
・ 生命保険加入者の住所確認業務
・ 満期保険金書類の点検・区分
・ 個人年金関係書類点検等
(5)経営方針
創業時より、「明るく・正しく・強く」という行動指針を定め、それをもとに会社の風土作り及び社員の育成を行っている。また、経営理念として次の3点について定めている。
・ 障害のある者が能力を発揮できる強い職場作りを通じて継続的に雇用を進める。
・ 常に高い業務品質を追求してお客様の信頼に応え日本生命になくてはならない会社になる
・ 社員とはお互いに協力し合い健康でいきいきと働くと共に良き社会人として行動する
(6)社員構成
構成員 96名(プロパー社員82名、出向者14名)
| 部位 | 人数 | 内 重度 | 内 軽度 |
|---|---|---|---|
| 視覚障害 | 1 | 0 | 1 |
| 聴覚障害 | 36 | 36 | 0 |
| 肢体不自由 | 40 | 37 | 3 |
| 内部障害 | 2 | 2 | 0 |
| 知的障害 | 3 | 1 | 2 |
| 合計 | 82 | 76 | 6 |
重度障害者の割合が多く、9割以上となっている。
(7)障害者雇用の理念
経営理念にあるように「障害のある者が能力を発揮できる強い職場づくりを通じて継続的に雇用をすすめる」ことを重視。能力発揮できる雇用管理と定着の推進が進められ、ここ数年間は定着率95%以上(年始在籍/年末在籍)を維持している。
2. 社員の自主性を重視した職場運営~委員会制度を中心に~
(1)委員会制度とは?
「明るい職場づくり」「正しい業務遂行」「仕事への強い挑戦」を理念として、社員全員参加に基づく委員会制度を実施している。具体的には、3つの推進グループ傘下に9つの各種委員会を擁し、各委員会とも障害ある社員をリーダーとした運営を実施し会社経営を側面から支えている。
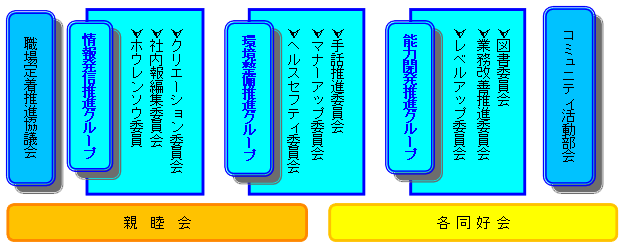
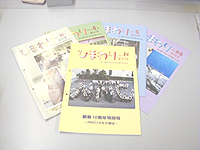
活動時間は、週一回の時間中の一斉活動の他、本来業務に支障のない限り時間内の個別活動も認められている。具体的な活動内容としては、ホウレンソウ委員会では、全体朝礼の運営や掲示板の管理等、社員間に情報がスムーズに流れるよう様々な取り組みや工夫を行っている。また、クリエーション委員会では、ホームページの作成・会社案内の作成を、手話推進委員会では手話教室の開催・NNC手話ハンドブックの作成等といった具合である。このような活動が、ホームページの作成、機関紙「ひまわり」の発行、独自の手話手帳の発行、同社オリジナル災害時避難用車いす用担架の開発などの成果物として結実させている。また地域の福祉協議会と密接な連携のもと、学校への「車いす体験講座」等への出張講演も委員会活動のなかから産み出されてきたものである。
(2)委員会制度に対する経営側の取り組み
ア アドバイザー、相談役制度
委員会の上部組織である「各推進グループ」に管理者層がアドバイザーとして参画し、社員との闊達な議論を通じて活動を検証、取り組み内容の進め方を確認している。また、経営判断を要することについては常勤の役員を中心に配置した「相談役」の判断を仰ぐシステムを用意している。
イ 年3回の「委員会リーダー会議」(社長以下役員等経営幹部と委員会リーダーで構成)を通じた委員会活動の進捗状況相互確認、経営幹部による活動評価と方向性の助言。
ウ 社員を巻き込んだ優秀委員会表彰制度の導入
(3)委員会制度の効果
結果として次のような波及効果を産み出している。
・組織横断的なメンバー編成による部門間コミュニケーションの円滑化
・本来事業では培いにくい基礎能力の涵養
・委員会リーダーを通じた組織マネージメント能力の向上
・会社経営への参画による従業員満足度(ES)の向上
・経営側による新たな人材発掘
3. 精緻な人材育成体系
(1)人材育成体系
経営理念に「能力を発揮できる強い職場つくり」とあるように、同社が最も力を入れているのが人材育成である。
障害のある社員が主役となり、職務能力面でも普通の会社と同じように力を発揮できる就労環境を整えるため、創業時より社員育成に努力を重ねてきた。その結果、現在は次表にあるような精緻な人材育成体系を築き上げている。研修、OJT及び自己啓発が大きな柱となっている。
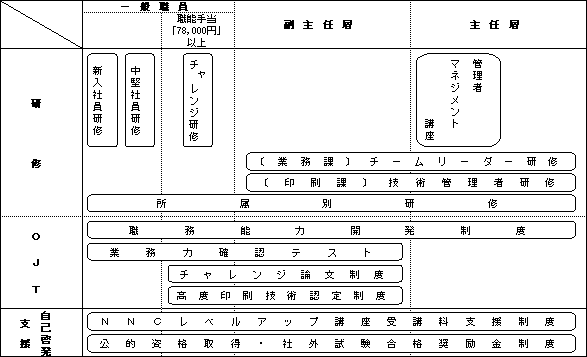
ア 研修
研修は層別に分けて行われる。研修資料の作成からインストラクターによる受講生の研修指導に至るまで、障害ある社員が担当している。勿論、聴覚障害者には、専門の手話通訳を配置している。
イ OJT
OJTの中軸をなすものは職務能力開発制度である。これは、目標管理を行うシステムであり、年始・年末には上司と面談し、目標のすり合わせ、達成度のすり合わせ、及び評価が行われている。ツールとして「職務能力開発表」を使用するが、委員会活動状況、業務改善提案状況なども項目に採り入れられている。このツールも社員で作られたとのことである。
ウ 自己啓発
自己啓発は社外の通信講座受講が中心である。優秀賞を獲得すると受講料の全額を会社負担とする支援措置が施されている。受講者は社員の80%に及び、フォークリフト免許や第一種衛生管理者・有機溶剤取扱主任者等、様々な分野にわたる資格取得者を出している。このことからも、自分を向上させようという意欲を如何に会社が育んできたか垣間見ることができる。
(2)人材育成体系の効果
ア 管理職への登用
こうした社員教育の取り組みもあって、障害のある社員の管理職への登用が増えている。平成17年4月現在、課長代理1名、主任6名、副主任11名となっている。
同社の昇格システムは人事考課に加え、一定の職能段階に達すること、論文審査に合格すること等、客観的な公平性を確保した運用を行っている。このため、周囲の認知度の高い者が必然的に昇格する結果を招来し、組織の融和性を維持することにも役立っている。
イ 独自の自己啓発制度の構築
平成16年度から「社内ワープロ検定制度」を導入している。これは、社員のIT能力向上を目的に導入されたものであり、社員全員が自分の目指す等級にエントリーし、社内ワープロ研修を経て、検定試験の結果により「等級」が付与されるシステムである。
一見何の変哲もない仕組みであるが、ユニークなところは、等級を10段階設けて、手指に障害ある者でもどこかの等級レベルに達するように設計されており、さらに上位等級を目指せるように意欲を喚起するため下位等級認定者程きめ細かな区分に従った「奨励金」を支給していることである。この制度も社員自らで作り上げたとのことであり、社員の能力開発に対する意欲の強さを伺うことができる。
4. 知的障害者の事務職としての能力開発
(1) 知的障害者の事務職での採用
平成16年度より、知的障害者の事務職での採用を行っている。現在、3名の知的障害者(重度1名、軽度2名)が在籍している。
業務の内容も、書類の点検、オンライン端末の操作、工程管理システムへのデータ入力等、他の社員と同様である。事務職の知的障害者については、能力開発に工夫をしている。
(2)アドバイザーの配置
入社後3ヶ月はアドバイザーを配置している。初めは隣について教育するが、慣れるにつれ、徐々に単独で仕事に取り組めるようにし、入社後3ヶ月目で、ある程度単独で仕事に取り組むことができることを目指す。また、教育には、同社独自のマニュアルを使用し、手順を一つ一つ時間をかけて何度も教えることにより、他の社員と同レベルの成果が期待できるようになっている。
入社3ヶ月を経過後も、入社時のアドバイザーが引き続き教育・相談役となることにより、スキルアップ及び職場適応へのフォローを行っている。
(3)独自のマニュアルの開発
同社社員が手作りのマニュアルを作成している。これは、業務の委託元から手交された執務解説書を解読し、全ての社員にもわかりやすいようにと、写真・図解等を豊富に取り入れた特製版である。
当初は、必ずしも知的障害者を想定して作ったものではなかったが、これが知的障害者の教育にも役立ったそうである。現在、担当したアドバイザーはこのマニュアルをさらに改訂し、自分の経験を踏まえ、様々な資料を研究した上で、知的障害者用のマニュアルを作成中である。今後の完成が待たれる。
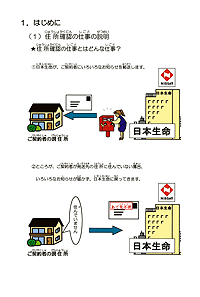
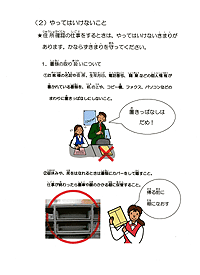
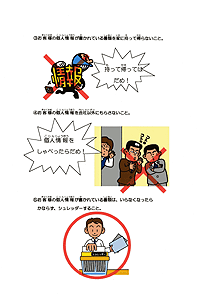
イメージしやすいイラストを活用、注意事項を分かりやすい記号(×・○で示す)、ルビをふる、色の統一化を図る等、分かりやすい工夫が施されている。
5. 業務改善提案運動
最大の社内イベントともいうべきもので、テーマエントリー(6月)から優秀作品発表会(12月、翌年4月)に至るまで、提案内容を検証し、データ採取等、半年以上の期間をかけて遂行される。
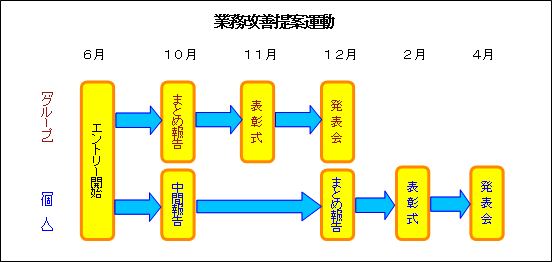
非役員社員のほぼ全員が提案を行い、優れた作品は表彰され発表会を通じて全員に披露される。コストが比較的かからないものであれば即採用ということで、社内を歩くと、こうした提案運動の成果が随所に散見され、業務遂行あるいは、障害ある者の就労に役立つツールとして日常業務の遂行にごく自然に生かされている。
また、必ずしもベテラン社員の提案が優秀作品として選ばれるというものでもなく、新人の提案であっても着想の斬新さが買われることもあり、経営層による選考の柔軟性が窺われる。
6. 今後の課題・展望等
「日生グループの一員として一層障害者雇用率の向上及び安定化を図るため、親会社とも連携しつつ更なる障害者雇用の拡大をいかに図るのか」というのが中心テーマになっているとのことである。
同社は平成17年4月現在で96名の社員が在籍し、更なる発展を図るため、当面の課題として、入居ビルのレイアウト変更、新たな職務開発等の課題があるそうだ。さらに、同社常務取締役益永氏は今後の課題と展望を以下のように語っている。
・一層の職場定着に向けた業務領域の拡大及び職務能力の開発・向上
・中高齢層占率の拡大への対応(組織体力の増強、障害態様に応じた職務の組替等)
・知的障害者の増員(既述したマニュアルの整備を図る他、彼らの一層の職務能力開発について)
・精神障害者の雇用についての研究
また、同社が全国最大規模の特例子会社であることもあり、障害者雇用管理ノウハウの伝播、コンサル機能の発揮、障害者雇用に対する政策提言への活動についても、積極的に携わっていきたいとのことであった。
7. 障害のある社員のコメント
西山典子(同社主任)さんの声を紹介。
「NNCでは、通常業務以外にも委員会活動や業務改善の取り組み、研修会の運営、グループ運営等、いろいろな事をやらせて頂きました。今までこのような取り組みをしたことがなかった私にとっては、これらのことは苦手な事ばかりで、順風満帆には進みませんでした。しかし、必ず周りの上司、同僚、部下に助けられながら、今までやって来ることができました。それは、この会社にはお互いの障害を理解し、それぞれの工夫でお互いに力を合わせて仕事をしていく風土、社員自らが中心となって提案改善できる社風や様々な取り組みに挑戦出来る機会が沢山あったからです。
今では一つの目的に向かって皆で力を合わせて行けば、苦手なことに挑戦しても楽しく活動でき、持っている以上の力が出てくることを実感しています。
NNCにある人材育成制度、委員会制度は、自分への挑戦の場であり、自分を磨く成長の場です。自分を振り返って以前より成長できたのはこの会社のおかげだと感謝しています。
これからも『自分に負けない気持ちを持ち、助け合い団結して、活き活きと輝いている職場』を目指し、みんなで頑張っていきたいと思います。」
8. 考察~障害を理解し力を合わせて仕事をする企業風土~
(1)お互いの障害を理解したきめ細かな対応
同社の取り組みのすばらしさは、ハード面(車いすトイレの設置数完備、パトライトの設置等)は勿論であるが、社員の西山さんの言葉にもあるとおり、「お互いの障害を理解し、それぞれの工夫でお互いに力を合わせて仕事をしていく風土、社員自らが中心となって提案改善できる社風や様々な取り組みに挑戦出来る機会」に代表される。
同社では、お互いに協力して仕事に携わることができるよう、まず互いの障害や配慮事項を理解することから始まる。入社すると、各々の社員の持つ障害についての研修がある。勿論、研修で使う資料も社員自身による手作りによるものである。
また、社員全員が手話と口話を併せて使用している。それは、上肢障害のものであっても、知的障害のものであっても同様である。たとえ細部まで手話で美しく表現できなくても、それぞれがそれなりの方法で手話を使用している。その様子に全く違和感はなく、自然体なのである。
このように、お互いの障害を理解することから始まる会社のシステム、障害の垣根を越えてお互いに力をあわせようとする社風が、同社の基礎となっていると思われる。また、このような風土だからこそ、前述した委員会制度や人材育成制度に代表される活動が、より一層効果的に運営され、社員が中心となった会社運営につながっているものと感じられる。
(2)地域社会への波及
このような社風、及び委員会制度をはじめとした社内の取り組みは、様々な成果を生み出している。

例えば、その代表例として、独自の自己啓発制度の構築・手話手帳・ツールの開発等をあげることができる。特に、同社の業務改善提案活動で開発されたツールは素晴らしいものがあり、大阪市職業リハビリテーションセンターでもその一部を借りて使用している状況である。
一方、これらの活動は社会貢献活動にも及んでいる。コミュニティ活動部会では、地域交流の一環として小・中学校での講演活動や車いす体験学習を社員が中心となって自主的に行っている。
それぞれの委員会や同好会等の活動の成果物は、各種表彰制度で賞を受賞する等、社会的にも認められるものとなっている。
・「大阪市防火標語」(大阪市消防局主催)
・「防火管理に関する意見・体験談」(大阪市消防局主催)
・「障害者雇用促進月間ポスター原画」
(高齢・障害・求職者雇用支援機構主催)
・「人権啓発ポスター・標語」
(大阪市人権啓発推進協議会主催)
このように社員を中心とした活動が、社内だけに留まらず社外にも及び、相応の評価を受けていることは特筆すべきことであり、社員の意識・意欲の高さを伺い知ることができる。

(3)経営者層の意欲
経営者層も、社員に負けじと社会活動への意欲をにじませている。
とりわけ障害者雇用に対しては、同社が最大規模の特例子会社であり、先駆的な役割を担うべきとの考えから、見学・体験実習の受け入れ、全国重度障害者雇用事業所協会の活動、各種講習会への講師派遣等、様々な活動に取り組んでいる。
(4)終わりに
前述した様々な活動は、社会的にも高い評価を受けている。特に、大阪府が行っている障害者雇用貢献活動顕彰制度(通称、ハートフル企業顕彰)では過去2回分野賞を受賞し、能力開発に向けた人材育成体系、障害のある社員が会社運営に参画できる仕組み、障害者雇用の雇用啓蒙活動等が高く評価された。
今後の課題・展望として「中高齢化」への対応や、精神障害者の雇用に向けた研究等が挙げられていたが、同社の「障害を理解しお互いに力を合わせて仕事をしていく風土」が堅固なものである以上、解決の道も早いと思われる。例えば、同社は数年前まで本格的には知的障害者の雇用に取り組んでいなかったが、現在では、事務職としての採用だけでなく、その能力開発・研修の手法まで一貫したカリキュラムが構築されているのである。
このような素晴らしい社風を備えた同社の障害者雇用への先駆的な取り組みに今後とも期待したい。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











