従業員の障害体験を福祉機器ビジネスに活用する
- 事業所名
- 株式会社ジェー・シー・アイ
- 所在地
- 宮城県黒川郡大和町
- 事業内容
- 福祉用具の製造、販売、レンタル等
- 従業員数
- 128名
- うち障害者数
- 6名
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 5 企画、業務総括、営業事務、電算管理 内部障害 0 知的障害 1 レンタル品の消毒 精神障害 0 - 目次

1. はじめに~国際生活機能分類(ICF)について~
国際生活機能分類(ICF)は、生活機能を心身機能・構造、活動、参加という3つの次元に分けて、それらの相互作用関係を理解するものである。そして、それらの生活機能に支障がある場合について、機能障害、活動制限、参加制約というように障害を構造化して考える。
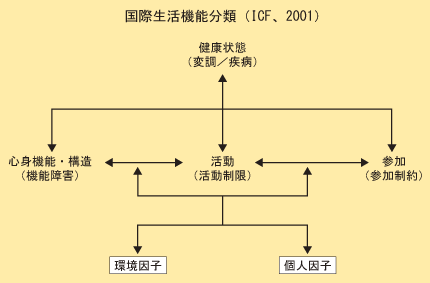
例えば、脳卒中によって左半身麻痺になった場合、変調・疾病にあたるのが脳卒中、機能障害が左半身麻痺である。活動制限として歩行障害が生じる。その場合、適切な補装具や福祉機器を用いると活動制限も少なくなり、平坦な場所ではある程度歩けるようになったとする。ところで平坦な場所では多少歩けるが、職場に復帰する場合には、バスの乗り降りの段差や列車を利用する場合の駅の階段、会社の職場までに階段があるために移動に大きな障害がある。参加制約だ。この参加制約もノンステップバスを利用し、エレベーターが使えれば解消できる。また使いやすいトイレの整備も必要だ。環境因子とは種々の福祉用具、補装具、乗り物、建物のバリアフリー化や専門的なアドバイスなどを指す。適切な機器、支援、社会環境条件などのいわゆる環境の因子を十分に活用できれば、活動制限や参加制約を少なくすることが可能となり、日常生活又は社会生活の制限を少なくできるのである。
当社は、ここでいう環境の因子に関するさまざまな福祉機器と専門的なアドバイスなどを提供する事業所である。
今回はICFの考え方をもとに、当社の障害者雇用の経緯、理念とともにそこで働いている身体に障害のある2人の社員の就職の経緯や職務内容について考える。
2. 事業内容と経営理念
当社の業務は、レンタル用品の取り扱い、自社オリジナル商品の開発、住宅の改修、コンサルティング活動、研究活動などである。これらの活動は、ICFに照らし合わせると環境因子の改善のための業務活動であり、これらの改善によって活動制限や参加制約をできるだけ少なくすることができれば、障害があっても高齢であっても一人一人がより充実した日常生活や社会生活に取り組むことが可能になるのである。
佐藤隆雄社長は、福祉系大学卒業後、身体障害者授産施設に勤めたほか、重度障害者を多数雇用する企業の設立計画に関わった経験をもつ。
その後、昭和51年、福祉機器、車いすや介護用品などの販売のため当社を設立した。たった1人で設立した事業所も高齢者社会を目前に社会福祉の制度改革などをもとに次第に需要が伸び、家族に障害のある人がいた人や施設で働いていた目的意識を明確にしていた人たちが入社した。やがて、介護保険の導入、また福祉用具のレンタル事業や相談活動の充実に伴って、当社は大きく成長した。
佐藤社長によると、当社はノーマライズ提供事業会社である。車いすを売っていくらの世界ではなくて、車いすを売ることを通してその車いすを使う人の自立を促すんだということをはっきりと、繰り返し、繰り返し、社員に伝えている。
次に示す三つの【経営】が当社の掲げる経営理念である。本報告では、当社に就労している2人の身体に障害のある社員を取り上げて紹介し、当社の経営理念に照らし合わせて紹介する。
①福祉事業を通して、お年寄りや障害のある人々の自立を支援し、思いやりのある企業を目指す【科学性のある経営】、
②福祉事業を通して、明るく朗らかで健康的な福祉社会の実現に、夢を持って貢献する【社会性のある経営】、
③力を合わせ、感謝と感動と創造する心を持ち、豊かで潤いのある生活と活力ある職場を作る【人間性のある経営】
3. 障害のある社員の勤務状況
(1)今野業務部統括マネージャー ~障害・高齢分野の専門家~
両下肢障害のある今野さん(男性、40歳)は大学卒業後、なかなか就職先がみつからなかったが、福祉事務所で出あった車いすを常用している当社の営業マンの話をきいたことをきっかけに18年前に入社した。高齢社会が目前に迫り、福祉機器を活用して地域で充実した生活をおくることの重要性について言われてきた頃であった。
事務職を5年間経験してから、営業を担当することになったが、このときは水を得た魚のようにとても充実した仕事ができたという。両下肢障害のために、数多くの困難に直面し、様々な工夫を重ねてきた今野さんは、自分自身の経験をもとに、顧客のかかえる困難や悩みについて顧客とともに考え、的確に分析してニーズを明確にすることができた。今野さんの言葉を借りれば、得意技を生かして自分の営業マンとしてのスタイルを違和感なく創りあげることができたのである。ここでは障害のあることはデメリットではなく、障害者としての経験をメリットとして生かすことができた。「障害を持っていて、よくやっていますね」といわれたことも数多くあったが、これもプラスのイメージととらえ、自分の体験を仕事に生かすことができた。
5年間営業を経験した後、企画の仕事を担当することになった。介護保険導入にあわせたレンタル事業の拡張など、忙しい毎日を過ごしたが、このときも、今野さんの体験と工夫を重ねて培った営業経験は、企画立案や達成に大いに役立った。そして、事業が拡大するに従い、コンピュータの更なる導入による企画や営業サポートの占める割合が大きくなった。現在、今野さんの仕事の内容も管理職としての役割が大きくなり、本部・工場の業務部統括マネージャーの要職を務めている。
 今野業務部統括マネージャー |
(2)石川さん(システム管理) ~相談に応えることによって自分も成長~
石川さん(男性、31歳)は、13年前に大きな怪我をして、頚髄損傷のため車いすを常用している。受傷後、1年半は入院生活を余儀なくされ、リハビリなどに励んだ。その後、障害者職業能力開発校で1年間、商業デザインを学び、障害者合同面接会を通じて8年前に入社した。介護保険導入直前で、事業拡大に伴いITシステムの構築が急ピッチで行なわれていた頃である。
入社後の石川さんは、システムエンジニアから参考書などを借りて、ほとんど独力でIT業務について勉強した。頚髄損傷による手指の動きが不自由なため、入力デバイスを活用し、さらに様々な工夫を重ねた。そのような努力を経て、石川さんは現在、システム管理に従事している。
同僚によると、ITに関してわからないことがあると石川さんに聞くことがとても多いという。質問されたり、相談を受けたりした場合などで、すぐに的確な応えが見つからない場合には、石川さんはしっかり学び、自分自身で理解を進めてから応える。教えることは、自分自身で学ぶことでもあり、教えることを通して知識も技術も身についてきたと石川さんは言う。これが石川さんの仕事力の向上である。
 今野業務部統括マネージャー(左) と石川さん(右) |
4. 個人の成長と事業所の成長
「モノと人とのフィッティング」を心がけ、誰もが暮らしやすい社会を目指し、一人一人の顧客にあったサービスを提供することが当社のモットーだ。そのためには、コミュニケーションをたいせつにして、顧客の立場に立ったサービスの提供や現場のニーズを把握した商品開発が重要となる。単にモノを提供するだけでなく、それを使う人に本当に合ったものか、常に考え、工夫し、改善していく必要がある。
今回の今野さんの事例をもとに考えると福祉機器の販売や開発を行う場合には、障害による生活上の制限を受けてきた経験自体が、仕事に大きな力を発揮する原動力となる。今野さんの言葉を借りると、個人の成長が当社の成長につながり、また当社の成長は更なる個人の成長を導くことになる。
ところで、視点を変えると、今回紹介した身体に障害のある今野さんも石川さんも適切な環境因子によるサポートがえられるので、やりがいのある仕事を行なっているのである。これは、当社が掲げる3つの経営理念のうちの1つである【人間性のある経営】そのものに他ならない。
そして、この【人間性のある経営】が基盤となって、【科学性のある経営】、【社会性のある経営】が実現するのであろう。
5. さいごに~福祉ビジネス分野における障害者就労の大きな可能性~
今回の事例は、障害者としての体験をもとに行なってきた工夫や努力が、そのまま事業所の業務に生かされている成功例である。
当社での障害者雇用の実践をみると、そこで働く障害のある人々にとって、障害のあることはマイナスの要因ではなく、障害を体験していること自体が仕事を遂行するための大きな資源となっている。日常生活や社会生活において大きな制限を受け、困難を体験してきた障害者だからこそ、障害をもたらす環境の諸因子の存在に気づきやすく、顧客とともにそれを改善するための福祉機器の活用をはかることができるのである。
わが国では今後さらに福祉ビジネスに関する需要が高まってくると考えられる。このように考えると、福祉関連ビジネス領域には障害のある人々の就労のチャンスが限りなくあると考えられる。
これまでの社会は、働き盛りの男性に基準を合わせた社会であったといわれ、これからは障害者を標準とした社会になることが大切であるといわれる。そのための福祉ビジネスにとって、障害のあることはマイナスではなく、プラスの大きな資源になると期待される。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











