適性を把握し、スペシャリストを育成
1. 事業所の概要
(1)沿革
株式会社渡辺リネンは、株式会社渡辺ドライを母体としたクリーニング業を中心に展開するワタナベグループの一社である。
当社の開業については、明治36年に日本のドライクリーニング業界の先駆けとして創業した渡辺西洋洗濯店であり、歴史は非常に古い。
昭和37年にリネンサプライ部門を新設し、病院基準寝具の専用工場を設置。
昭和40年にリネンサプライ部門を独立させ有限会社渡辺リネンを設立。
その後事業拡張に伴い、昭和61年株式会社渡辺リネンと変更。
(2)組織
ワタナベグループが雇用する1,100人を超える社員のうち、当社は220人の社員が勤務している。
施設は本社に隣接する工場のほかに新潟工場ほか4工場と2営業所を有する。

(基準寝具・ダイアバー)


組織図
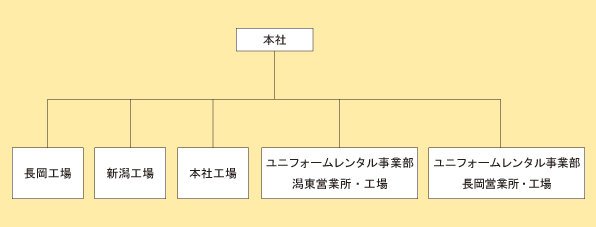
2. 障害者雇用の経緯
(1)経緯
昭和37年に病院のリネン工場を設立してから、取引先の医療施設から障害回復者の職業訓練の受け入れ先として依頼を受けたことがきっかけであり、その後も県内の養護学校等から職場実習の依頼を受け、昭和40年代から職場実習からの雇用に至った。
昭和63年から平成元年にかけて職安からの雇用要請を受け、障害者雇用に積極的に取り組むこととなった。
平成2年に新潟市に進出、新潟工場の設立に当たり、知的障害者を3人雇用した。
平成6年から7年にかけて障害者雇用を更に進め、平成7年には助成金を活用し重度障害者多数雇用事業所施設を設置した。
平成8年9月には、障害者雇用の優良事業所として「労働大臣表彰」を受賞。
平成18年1月現在、ワタナベグループで雇用している障害者39人のうち当社で勤務する障害者数は25人で、グループ全体の64.1%を占める。
なお、障害のある社員の中には、10数年前に雇用し現在も継続して勤務している社員も多い。
(2)障害のある社員の内訳
視覚障害者 1人 (工場作業員)
聴覚障害者 3人(重度1、重度短1) (工場作業員)
上肢障害者 1人 (工場作業員)
下肢障害者 1人 (工場作業員)
内部障害者 1人(重度) (配送係)
知的障害者 18人(重度6) (配送係1、工場作業員17)
なお、25人のうち約3分の2である16人は、新潟工場で勤務している。
3. 具体的な取り組み
(1)募集・採用
障害者はハローワーク経由で採用している。採用に際しては3週間以上の職場実習を行い、その後本人と親の様子を見るほか、保護者との面接を重視し採否を決めている。
本人については、健康で明るく、挨拶や返事ができるか、一人で通勤できるか、身の回りのことが自分でできるか、働ける体力があるかなどを確認する。
保護者からの確認では、家庭環境が生活態度や性格に影響を及ぼすこともあるため、家庭内で自立できているかに重点を置いている。
(2)労働条件
勤務時間は午前8時から午後5時までであり、そのうち1時間15分休憩をとる。
給与は時給制の社員が多い。最低賃金適用除外申請はしていない。社員全員が業務に必要な戦力として雇用している。
好成績を残すと正社員となり月給制として雇用する場合もある。正社員登用の基準には障害の有無は関係ない。
(3)障害者職業生活相談員の選任
本社工場に1人、新潟工場に3人の相談員を選任し、所定の講習を受講させた。
各相談員には、当社が障害者を雇用する理念を理解してもらうとともに、障害者に適切に対応するよう指示している。
(4)作業
1)工程の細分化
障害者の主として従事するリネン作業の主な作業工程は、入荷、点検・仕分け、洗濯・脱水、乾燥、仕上げ・たたみ、検査、結束・包装、出荷に分けているが、うち彼らが多く従事する工程は仕分け、洗濯及び仕上げである。

種類別に振り分ける


2)知的障害者に対する配慮
従事作業については、洗濯前の仕分け作業や洗濯後の振り分け作業部門に重点的に配置するなど、作業をできる限り単純化、定形化し、反復作業になるよう工夫している。
その後、一旦職場に配置したが人間関係や職場に馴染めない社員が出た場合に配置換えするとともに、1年または2年のスパンで配置部署を変えている。
3)スペシャリストの育成
新潟工場では何箇所かの作業を経験して職場が決まるとその仕事のスペシャリストを目指す。
多能工よりもスペシャリストに重点を置く方針により、一旦覚えた作業は確実にこなす、一つの部署のリーダーを勤められる、仕事の段取りがすべてわかっているなど、スペシャリストが育ってきている。

(5)聴覚障害者とのコミュニケーションにおける配慮
聴覚障害者とのコミュニケーションについては口話が中心であり、上司がゆっくり発声することで支障なく会話することはできるが、詳しい内容については筆談でやり取りし、必要に応じてハローワークから手話通訳を派遣してもらう。家庭との連絡にはFAXを使用する。
(6)社内研修
新入社員研修には大卒や高卒と共に養護学校卒業生も参加し、グループの研究会や新年会には、障害者も全員参加する。
(7)関係機関との連携
新潟市役所の福祉関係部門やハローワークの障害者担当職員との協力体制ができているほか、地域障害者職業センターの障害者職業カウンセラーのアドバイスも適宜受けている。
(8)健康管理・福利厚生
定期健康診断は全員実施している。また、毎朝の朝礼で声かけをする中で顔色や様子に注意するほか、服薬が必要な社員に対して服薬管理の状況を確認している。
また、福利厚生については、新年会、勉強会、社員旅行など全員参加している。
(9)グループにおける助成金等活用状況
障害者雇用調整金(平成17年)
障害者雇用報奨金(平成17年)(当社)
重度障害者介助等助成金(平成17年)(当社)
重度障害者多数雇用事業所施設設置助成金(平成17年)(当社)
4. 取り組みの効果
(1)社内表彰等で受賞
日々、陽の当たらない部署においてこつこつと頑張っている社員を表彰する方針に基づき、当社は社内表彰制度を取っている。全社員の前で年間3人から7人ほど選ばれる優秀模範社員に対して行う会長表彰については、これまでに知的障害者を含む2人の障害者を表彰した。
また、知的障害のある社員1人は、新潟県障害者雇用促進大会で優良勤労障害者として表彰された。
(2)保護者会の開催回数の減少
新潟工場の立ち上げに際し知的障害者を多く採用し始めた頃に、保護者会を作ってもらい、月1回会合を開いた。保護者から多数寄せられた「本人が果たして満足に仕事が出来ているのだろうか」との心配の声に対し「自信を持ってくださいと」と伝えた。
保護者会を開くことによって、家庭での様子などを知ることができたことと併せて、保護者には本人の仕事の様子や職場環境を知ってもらうことができた。また、保護者間の交流や情報交換も進んだ。
保護者会は次第に四半期に1回と回数を減らし、現在では知的障害者が安定した作業をしているため、1年に1回情報交換会として開催している。
なお、従来から保護者がいつでも職場を見学できるよう職場は対応している。
(3)連絡ノートによる家庭との情報交換回数の減少
知的障害者に対して、最初はその日の作業の様子や家庭での状況などを書いた毎日交換ノートにより、家庭と職場との情報交換を行っていたが、次第に作業について書く必要がなくなったため、週1回、月1回と間隔は空いてきているが継続して実施している。
5. 今後の展望
当社の新潟県内の工場施設における人員体制は整っており、当面は欠員補充の際に障害者雇用を検討する状況であるが、グループとしては、今後とも事業拡大の際には、障害者の雇用を構想に入れることについても考えている。金子 芳三郎
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











