「サラダほうれん草」生産の主役は知的障害者

(上部のライトは遠赤外線照明)
1. 事業所の概要
(1)沿革
| 設立 | 平成12年3月23日 | |
| 操業開始 | 平成12年7月 |
(2)主な設備
| 鉄骨ビニールハウス | 24m×9m×6棟 = 1,296m2(393坪) | |
| 育苗ベンチ | 15m×4列 =60m | |
| 水耕栽培(定植)ベンチ | 20m×1.2m×30列 = 720m2(54,000株) | |
| 発芽室 | 3m×3m = 9m2 | |
| 暖房温風器 | 2基 | |
| ボイラー | 1基 | |
| 保冷庫 | 3m×3m | |
| 出荷調整室 | 5m×7.5m=37m2 |
(3)障害者雇用数
知的障害者(重度) 6人(障害者雇用率 171.4%)
障害者の年齢構成 20代・・・5人、50代・・・1人
(4)事業の内容
障害者を働き手の主力にして、農薬に頼らない水耕栽培による「生食用野菜サラダほうれん草」をハウス栽培し、年間21万袋(1袋100グラム)を生産・販売している。食の安全性の確保と高い品質、気候に左右されずに安定供給ができることなどへの評価を得て、県内の大店舗販売店ほか40社余に供給している。
2. 障害者雇用の経緯
当社は、障害者が通年安定して働くことができ、かつ働くことで障害者が社会的に自立できる活動の場を提供することを目的として、平成12年に現社長の宇治稔さんが設立した。
宇治社長は、創業当時には建設業を営んでいたが、その傍ら中小企業経営者同友会に参加し、その部会で障害者の雇用に関する研究や啓蒙活動を続けていた。
社長自身も知的障害者の子供を持ち、養護学校のPTA会長も務めていたが、彼らが就業できるチャンスが少ない現状を憂慮し、自分たちで彼らを雇用する企業経営ができないだろうかと考えた。その末「障害者が通年安全に働ける仕事」をテーマに追求していった結果が「生食用野菜サラダほうれん草の栽培」であった。
中小企業経営者同友会部会の会員諸氏の出資を得、農園の土地は会員から借用し、その他幾多の場面で会員の協力を得て、平成12年3月に「有限会社野菜ランド立山」を設立した。また、建設会社を経営していた経験を生かしてハウスの基礎工事や配管などは自ら施行した。
同年6月にハウスが完成し、早速種まきが行われた。定植、育成し、7月に初収穫した。その後、従業員への訓練、生産に係るノウハウの習得、生産効率の向上、販路の安定・拡大などの経営安定策を進め、第3期目にして経営の黒字化を実現した。
特に彼らへの訓練・指導に当たっては、社長の妻の宇治悦子さんが取締役施設長として、また業務遂行援助者として社長を補佐している。障害者の子をもつ親としてその経験を生かし、一緒に作業をしながら彼ら個々人の長所を引き出し、適材適所に配置し定着させた結果、現在全従業員7人のうち6人が知的障害者の職場となった。
ちなみに、障害者が通年継続的に安定して就業できる場所として、当該事業がふさわしいとして選定した理由は次のとおり。
①通年栽培ができることによって安定雇用が可能であること
②ハウス内で作業することによって気象変化の影響を受けにくいこと
③製品や道具に重量物がなく、作業の安全性が高いこと
④栄養価が高く価格も高価、かつ、傷みが速いので輸入品との競合が少ないこと
⑤無農薬によって食材として安全安心であること


3. 具体的な取り組み
(1)障害者の能力を最大限に引き出すために
当企業の起業目的そのものが障害者の就業場所を創出し、就業を通じて障害者が社会的に自立できるよう支援すること。また、障害者が労働力の補助的存在ではなく、労働力の主力として働くことができるようにするための訓練・作業条件・作業環境の整備及び改善を行い、また、国の障害者雇用に係る支援事業を活用しながら、結果として事業が永続できるよう経営の安定を図ることが必須であった。具体的な取り組みについては、以下のとおり。
ポイント
●障害者が力を発揮できるための訓練及び作業条件・作業環境の改善
●労働力の100%が知的障害者でも採算の取れる仕組みの構築
(2)社内の組織・人員配置
下図は主な役割分担を示したものであり、社長以下9名が就業している。社長は液肥や工場内の温度管理その他設備の維持保全を行い、社長婦人の悦子さんは取締役施設長として社長を補佐するとともに、総務・経理ならびに業務遂行援助者を兼ねている。もう一人の業務遂行援助者の田中知子さんは通勤バスの運転手を兼務している。
3人とも障害者の就業時間中は業務遂行援助者として、障害者と一緒に現場作業に従事しているのが通例である。
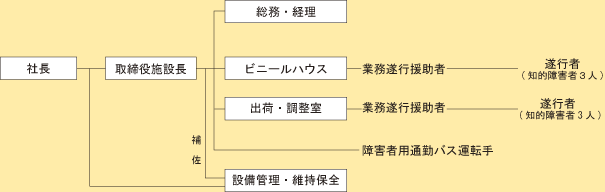
(3)障害者の勤務時間
季節による収穫サイクルが異なるため、春・夏・秋期は9:00~16:30、冬期は9:00~15:30(いずれも昼休1時間)に設定し、1時間の時間差を設けている。
操業当初は、終了時刻を17時30分に設定していたが、後日、緊張感を持続できる理想的な時間の選択肢として1時間短縮した経過がある。
(4)障害者雇用に関するノウハウの習得
宇治社長自身が、創業期前後以来、妻の悦子さんとともに全国各地で開催される障害者就業支援の様々なセミナーに出席。
また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の「働く広場」、全日本手をつなぐ育成会の「手をつなぐ」、その他各支援機関の機関紙に目をとおし、障害者雇用に係るハウ・ツーの習得に努めてきた。
なお、近年は各所から講演や現場指導を依頼されることが多く、「少しでも障害者雇用拡大のステップになれば」との願いや、「観るも勉強、教えるも勉強」と考え、多忙な日課を割いて可能な限り引き受けるようにしている。

業務遂行援助者
(右から宇治さん、田中さん)
(5)障害者が事業所の主要な労働力の主体となるために
障害者の受け入れにあたっては、選別は原則として行わない。その人の能力を予見するのは困難である。3か月の試用期間中に、やってみせて、やらせてみて判断する。
しかし、障害者が主力としての戦力(労働力)となることを目指すことが目的である限り、次の3つの要件を満たせる見通しの者を採用した。
①就業の意欲・・・継続して勤務してもらいたいため、家族などからの強制ではなく、自分の意思で、働きたいという意欲があること。
②独力で通勤ができる・・・就業意欲の堅持、継続性、安全確保、コミュニケーションなどをはかるために、他の人の力を借りないで、自宅又は養護施設から公共交通を利用して通勤できること。
③一定程度の協調性があり、複数人での同時並行作業に順応できること。
(6)役割分担及び担当工程の決め方の工夫
下図は、サラダほうれん草の育苗から出荷までの工程、及び障害者の主な配置状況である。
障害者の配置人数は当該工程の作業に着手する場合の人数であり、常時着手しているわけではなく、したがって、障害者雇用数と各工程の配置人数の総数とは一致しない。
例えば定植から収穫までの期間は、春・夏・秋の期間(14日間)と冬期間(24日間)とは異なるので、その季節の1サイクルあたりの育苗ベンチ数及び水耕栽培ベンチ数を定め、それぞれ工程ごとに一定の期間を置いて着手する仕組みにしている。
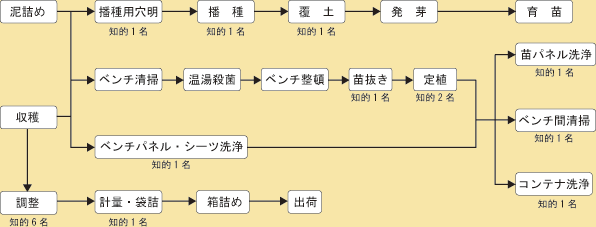
役割分担を定める場合には、経験に基づき、次の2つのことを基本にしている。
①一通りの工程を経験させること
②本人の自主性を尊重し、本人に選択させること

経験することによって自分にできる、できないを障害者に会得させる。一般的に自尊心が強いので、自分で選んだ役割には他人に負けまいとして熱中する。
例えば、「播種」工程は発泡スチロール製パネルに泥詰めされた直系15ミリの144個の穴に、直径1ミリに満たない種を5個づつ均一に入れるという実に微細で根気が要る作業であるが、正確にできる人(継続できる人)と、できない人(継続できない人)との差が顕著に表れるという。
実習によって、適性の可否を判断した上で、工程の分割や集約あるいは段取りを変更するなど人の能力に見合った工程設定を行うようにした。
(7)家族的な職場の雰囲気夫
当社では、業務遂行援助者と障害者が、いとも鮮やかに、かつ、実にタイミングよくコミュニケーションが図られている。特徴をいくつか挙げる。
1)工場のレイアウト
作業場は「育苗・収穫」をするビニールハウス棟と「調整」する建物との2棟で構成されているが、各棟の内部には仕切りフェンスがないので、どの位置からも全体の動きが把握できる。
2)作業の進め方
上の2つの建物でのそれぞれの作業時は、社長以下全員が同時に移動して作業する。「さあヤルゾ!」という一体感が伝わる。
3)業務遂行援助者の指導
2人の女性の業務遂行援助者については、注意するとき言葉は鋭くても、最後は母親のように優しさと慈愛に満ちた空気で包み込む雰囲気が漂う。障害者からの返事も歯切れが良く、業務遂行援助者への信頼の度合いの大きさがうかがわれる。
4)通勤バスの効用
事業所は農村部に位置するので、車で約30分の距離にあるJR滑川駅までの出退勤時には通勤バスを運行している。駅までは、公共交通などを利用して従業員が集まってくる。現在6人中5人が利用している。
運転は業務遂行援助者の田中さんが担当している。車中では田中さんから、例えば「きんのの晩のおかずなんだったがけ?(昨晩のおかずは何でしたか?)」といったみんなに共通する話題の投げかけからはじまり、おたがい言葉数は多くはないが、身近な話題を通じて一体感が生まれ、職場に着く頃には「さあこれからヤルゾ!」という気持ちになる。また田中さんからみると、一人ひとりの当日の体調などがわかるという。
業務援助遂行者の2人は「彼らに対してごく普通に接している」が、知的障害者は自尊心が強い人もいるので、一人ひとりの性格に応じて接すること、また、失敗は隠さずに堂々と言える雰囲気づくりを心がけている。
(8)作業工程の工夫・改善
 格子状に仕切られた
ビニールケース |
「品質は工程で作り込む」という言葉があるが、例えば数量の確認作業を解消することや作業の進捗状況を一目でわかるようにすることなど、工程の各所で工夫・改善している。
代表的な事例を以下に2件あげる。
1)箱詰め作業の改善
[工程の内容] 収穫したほうれん草を5株(100グラム)単位にビニール袋詰めして、30袋を一つの段ボール箱に格納して梱包する。
[改善前] 一次作業者が箱詰めした個数を途中で忘れてしまい、数え直したり格納個数を間違えるケースが時々発生した。不良品の社外流出防止のため、業務遂行援助者が梱包数の再確認作業を行っていた。
[改善後] 標準規格のビニールケースを活用して内側を格子状に仕切りを入れて、30か所に区分しそこへ袋詰め品を一旦格納することとした。その結果、不足数が一目でわかり、一次作業者のムダな作業時間を解消し、かつ業務遂行援助者の再確認作業を省くことができた。

調整棟へ

台車で苗抜き作業場へ
2)苗抜き作業の進捗状況の目でみる管理・台車の活用による積み替え運搬時間の短縮
[工程の内容] 定植直前に育苗パネルの各穴から苗を抜く(穴に固着した苗を抜き易いように、治具を使って苗の根を穴から浮き上がらせる)。
[改善前] 苗を浮上させた育苗パネルは一旦任意の場所に積み重ね、定植する場所へ移動させるときに台車に載せ換えして運んでいた。
[改善後] 所定の定植数に見合った育苗パネル数が見分けられるように台車を改造し、苗抜き作業が完了した育苗パネルは直接台車に搭載し、育苗パネルの所要数を充足たした時点で、台車をそのまま定植位置まで移動するようにした。その結果、育苗パネルの積み下ろしの時間が半減し、また、業務遂行援助者が苗抜き作業の進捗状況を遠方から一見して判別できるようになった。
上記に類似する改善は、定植パネルを洗浄する工程など随所に生かされている。
(9)障害者雇用に係る各種助成金の活用
障害者雇用に係る助成金についての情報収集のため、積極的に労働関係行政各機関の指導を受けた。これまで活用した助成金は以下のとおりであるが、経営の安定にたいへん役立っている。
| ①富山県知的障害者雇用奨励金 ③トライアル雇用奨励金 ⑤通勤バス購入助成金 ⑦障害者雇用奨励金 | ②特定求職者雇用開発助成金 ④業務遂行援助者助成金 ⑥通勤バス運転従事者助成金 ⑧障害者雇用設備資金(申請予定) |
4. 改善の効果
先の取り組みを行ってきた結果、当社の過去2年間における障害者の出勤率は100%である。
営業業績は下表のとおり。
| 期 決算日 | 第1期 13・3 | 第2期 14・3 | 第3期 15・3 | 第3期 16・3 | 第5期 17・3 |
| 出荷数(袋) (100g) | 104,782 (157,173) | 180,845 | 223,708 | 210,040 | 161,962 |
| 出荷数伸び率 | 100 | 115 | 142 | 133 | 103 |
| 売上高(千円) | 9,786 (14,680) | 16,634 | 21,745 | 24,707 | 19,610 |
| 売上高伸び率 | 100 | 113 | 148 | 168 | 134 |
| 助成金(千円) | 956 | 2,358 | 4,046 | 7,155 | 5,335 |
5. 今後の課題・目標
経営規模を拡大して障害者雇用者数の増員をはかることを最大の目標にしている。第3期・第4期は単年度で黒字計上できたが、まだ、日照時間や気温などの自然条件に生産性が左右される面が大きく、それを克服するために、更に栽培技術の改良をすすめなければならない課題が残っている。
しかし、遠赤外線照明、循環液肥の温度調整、遮光ネットの活用などといった技術改良の効果が徐々に表れているという。現在400万円の累積赤字を残しているが、これを克服して第8期までには現在のビニールハウス工場(約400坪)と同程度規模のビニールハウス工場の増設を当面の目標にして、すでに隣接した土地を確保している。

(後方の稜線は立山連峰)
また、後継者の育成も視野に入れ、長女を県外の障害者施設で勉強させており、将来への準備も怠りない。
経営状況は順風満帆ではないが、創業以来、社長夫妻は朝7時までに出社し、従業員が出勤するまでに生育状況の確認、当日の気象条件に見合った計器類の調整やその日の段取りなどを済ませ、従業員の退勤後は技術改良に時間を当てるのが日課である。
ちなみに、全国各地から障害者の雇用を目的に創業を計画している人々の工場見学希望や講演依頼も多いが、信念と行動力をもってできる限り対応し、培ったノウハウを惜しみなく提供するなど、障害者の雇用増大に繋がることに協力を惜しまない。
高年齢者雇用アドバイザー 大代 武
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











