施設と連携し知的障害者雇用に取り組む
- 事業所名
- 山一食品株式会社
- 所在地
- 福井県勝山市
- 事業内容
- 油揚げ製造業
- 従業員数
- 40名
- うち障害者数
- 10名
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 0 内部障害 0 知的障害 10 揚げ生地投入、運搬 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の概要
当社は、平成9年4月に設立(旧社名は昭和食品)、40人の社員(うちパート社員30人)のうち10人の障害者を雇用している。詳細は以下のとおり。
(1)生産設備及び能力
1)工場面積 2,300平方メートル
2)設備
・自動成型機・プラント :時間処理能力 3.5俵 / 時間
・自動フライヤー(15m)3台 :処理能力 1俵 / 時間
・自動フライヤー(5m)5台 :処理能力 0.5 / 時間
・自動裁断機 2台
・自動計量器 1台
・自動シール機 1台
・手動シール機 3台
(2)事業所組織図
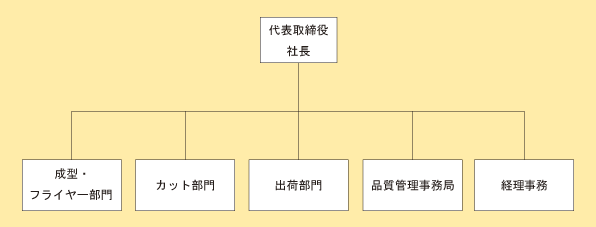
2. 障害者雇用の経過及び理念
(1)経緯
1)知的障害者更生施設からの受け入れ
同市内の知的障害者更生施設「大日園」において、利用者の日中活動の中での仕事は就労と比べ模擬的な側面があり指導・訓練の枠を超えない状況のなか、能力的に事業所での就労が可能な利用者を施設外で働かせたいと言う職員の思いについて、当社(当時社名は昭和食品)で相談を受けた結果、施設外実習、職場適応訓練という形で実現したのがきっかけである。
障害者雇用の方向性について、試行錯誤を繰り返しているうちに彼らを少しずつ理解し、障害者も健常者と同じ仕事をこなせることができるよう取り組んできたが、当初の施設外実習を行った人の中から、2人が施設からグループホームに移行し正規社員となった(うち1人は体調を崩し施設に戻った)。
「大日園」との15年間の付き合いの中で延べ15人の施設利用者を施設外実習として受け入れた。転職や、地元の福祉施設に戻ったり、また年齢的な理由など、様々な理由から退職者も出ているが、施設外で働く機会を設けた当社に対する「大日園」及び本人からの感謝の念は大きい。
2)居宅知的障害者の雇用
当社の取り組みが評価され、勝山市社会福祉協議会からの相談を受け、在宅生活していた知的障害者を雇用し現在に至っている。
なお、障害者雇用にあたっては、公的な補助金を活用し、生産性のマイナス面について軽減を図っている。
(2)障害者雇用の理念
当社は、障害者雇用が事業主の共同責務であるという社会連帯責任の理念に立って、積極的に障害者を雇用していきたいと考えている。また、障害者が職業に就きその能力を十分に発揮することができる体制を整え、健常者とともに社会参加できるノーマライゼーションの理念の実現を目指して地域社会全体の利益に繋がるよう努力している。
3. 具体的な取り組み
(1)送迎体制の構築
出勤に自家用車・自転車・自動二輪が使用できず、電車・バス等の公的移動機関の利用についても時間的に都合の良い便が無い大日園利用者の受け入れにあたっては、施設と連携して送迎体制を構築した。現在、施設利用者は、社員の対応を受けながら出勤時には契約制のタクシーを利用、退社時には施設の公用車を使用し出勤をしている。契約タクシーの費用については、1回の利用額1,500円のうち、本人負担額を100円、残金は当社と施設が負担している。
また、居宅の障害者については送迎用の車を配備し送迎している。


(2)指導補助体制の構築
障害者にとって新しい環境での作業は困難を伴うことが多かったため、当初は施設から支援者を派遣してもらい、本人が慣れるまで傍につき安心して仕事ができる体制を整えた。その後は連絡ノートにて健康・就業状態等について連絡・報告のやりとりを行うようにした。
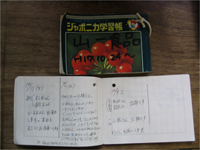
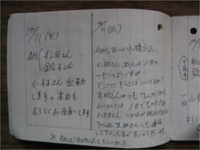
(3)作業工程と障害者の配置
・障害者は油揚げに9人、冷却に1人従事している。
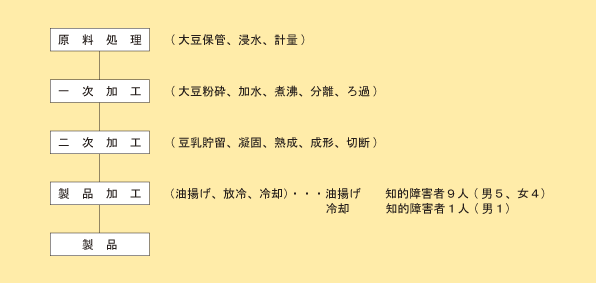
(4)作業服の着用
食品工場のため、常に衛生的な作業服の着用を社員全員に義務づけている。作業服が、障害のある社員が自力で着用することが困難であったため、当初は特例として当社指定以外の服装でも許可していたが、落下毛髪等混入のクレームが多発してきたため、施設における個別指導により指定の帽子を着用するようにした。居宅の障害のある社員には社内で担当者からかぶり方等の指導を行った。
(5)入室時の衛生管理表の記録
健常者・居宅の障害者は体調の不調等の申告や、作業前の入室時に体調等を各自記録表に記入することができるが、施設利用の社員は健康管理の状況等自ら告知することが困難であるため、作業日の朝の体調を施設で記入し毎朝提出してもらうこととした。
現在では、社内に入室するときに自分で記録するよう取り組むとともに、「午前・午後」など記録場所が分かりづらい部分を色分けすることにより記入ミスを減らすことができた。
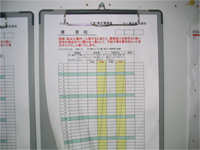
体調表
(6)豆腐工程中の揚げ生地入れ手順
軽度の知的障害者は一度の説明で生地の入れ方を理解するが、重度の知的障害者は理解が困難な部分があり、入れ方に不備があると揚げの仕上がりが悪くなるため、理解しやすい方法として絵で表現し、フライヤーの近くに掲示することにより、正確に作業できるようになった。

判りやすいように説明

(7)作業環境の見直し
障害のある社員の中には、体調の自己管理が困難で、夏季期間暑さによる体調不良など訴えることができない人が多いことから、熱が彼らに届かないよう、助成金等を利用し断熱シート及び作業場の冷却エアコンを設置した。また、身長の低い社員が生地の投入位置が高い機械のフライヤーに対応できるよう足台を用意した。



(8)作業効率の見直し
揚がってきた油揚げを冷蔵庫へ搬送する際には、当初はコンテナを持ち上げ運搬していたが、社内の連絡通路の幅が狭く、また重量があるためコンテナを倒してしまうことがあったことから、コンテナにキャスターを付けた。

(9)活用した公的な助成金制度
・障害者雇用納付金制度(報奨金・重度障害者等通勤対策助成金)
・職場適応訓練制度
4. 取り組みの効果
(1)通勤面
送迎体制を整備整えたことで、安全に通勤し遅刻することなく出勤ができ、社内的にもスムーズにローテーションができるようになった。
(2)職場環境への適応
施設利用者が社会経験の少なさから感じることが多い不安感に対しては、就業当初は施設職員を傍に付いてもらい作業を見守り励ますことで職場環境にいち早く適応することができた。
(3)食品衛生のための作業服の着用
自力で着用が困難であった作業服について、施設にて着用の支援を時間をかけて対応してもらった結果、着用が可能となり、衛生面に支障なく作業できるようになった。
(4)衛生意識の喚起
当初は、施設職員が起床後の体温、手の爪の長さや汚れの確認及び体調管理チェック表への記入を行っていたが、清潔面の意識付けが進み、現在では当社で確認を行うようにしている。
(5)正確な作業遂行
知的障害のある社員が理解することができるよう図を用いて説明することにより、正しい揚げ生地の置き方を理解できるようになり、不良品は激減した。
(6)体調の維持
夏季に生地入れ作業場の気温が40度を超えることがあり、水分の取り過ぎや体力的な問題から体調不良を起こす人が出てきたが、作業環境を改善した結果、体調を保ちながら作業することができるようになった。
(7)作業の効率化
コンテナ本体にキャスターを付けたことで、幅の狭い通路でも運びやすく、作業効率も上がったほか、力仕事の負担も軽減された。
(8)その他
知的障害のある社員と一緒に仕事をするようになってから、社内の空気が柔らかくなり笑顔が絶えない雰囲気が出て、社員が朗らかに仕事ができる環境になった。
5. 今後の展望・課題
職場環境の見直しとして更衣室の完備やレクリエーション施設等の拡充など福利厚生を充実させる計画を持っている。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











