支援機関と連携し全社員で障害者雇用に取り組む
~「ナチュラルサポート」の実践~
- 事業所名
- 株式会社奥井海生堂
- 所在地
- 福井県敦賀市
- 事業内容
- 昆布の製造・卸
- 従業員数
- 45名
- うち障害者数
- 7名
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 1 昆布はたき、ほぐし、品物の移動、袋のシール貼り 肢体不自由 1 パソコン入力、事務 内部障害 0 知的障害 3 昆布はたき、ほぐし、品物の移動、袋のシール貼り 精神障害 2 シートヒーラ - 目次

1. 事業所の概要
当社は、廃藩置県の行われた明治4年に松前船でにぎわう敦賀港を中心に大量に荷揚げされている昆布を扱う昆布商として創業し、後に大本山永平寺の御用達を受け、京都や全国の有名料亭、百貨店の高級昆布を収める業者として140年余のれんを守り続けてきた老舗である。
また、平成7年4月には「株式会社奥井海生堂」と組織を変更し、平成16年9月には新社屋が完成し、さらなる発展を目指している。


2. 障害者雇用の経緯(精神障害者の雇用)
昭和61年当時、近隣にある精神障害者小規模作業所の利用者を職場実習として受け入れたことがきっかけとなる。
その後、職場実習者を雇用することとなるが、病気の再発や入院などを繰り返しながらも、現在も2名が継続雇用しており、彼らも社員として活躍している。
雇用が継続できたのは、一度や二度再発して欠勤しても、良くなったら「また会社へおいで」と声を掛け、再出勤したときには温かく迎え入れられる態勢ができていたことが要因として考えられる。
3. 知的障害者の雇用の取り組み
(1)職場実習の受け入れ
1)職場実習(就職)希望者の確認
現在まで約21年間障害者雇用に取り組む姿勢を構築し、新たな障害者雇用を具体的に検討している当社について、平成15年に、ハローワークの担当者から市内の知的障害者施設に紹介されたところ、職場訪問を経て3人の知的障害者から職場実習や一般就労の希望を確認した。
2)支援体制の構築
具体的な取り組みを開始するに当たり、ハローワークを中心に障害者職業センター・所属施設が加わり支援体制について検討を行った結果、本人や家族・職場を中心として、作業面に関する支援は、障害者職業センターのジョブコーチ制度の利用を軸に、生活面に関する支援は所属施設の就業担当者を軸に支援全体に関する体制を構築し、まずは短期間の職場実習を開始することとした。
また、支援体制の構築と同時に、社内においても職場実習を受け入れる体制を検討した。
3)作業内容・担当者の設定
効率のよい機械に頼らず手作りにこだわる老舗であり、手作業が多種多様に点在している当社において、作業内容に関して検討を行った結果、製品のシール貼り等の単純な作業から開始することとした。
また、社員の中に職場実習受け入れ担当者を配置するとともに、全体の把握・調整等を奥井専務が行う体制を構築した。
(2)職場実習から雇用へ
1)ジョブコーチと作業ジグを開発
職場実習が開始され、最初は製品のシール貼りから作業を始めたが、予想よりも作業効率が上がらず、ジョブコーチによる検討・提案によりシール貼り専用のジグを作成するなどの環境面への工夫を積極的に取り入れるなどの支援を進める。
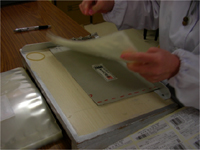
検討・提案により導入した
シール貼り専用のジグ」
2)実習生のステップアップのための作業選定
受け入れ担当者は作業の習得状況を確認しながら、社内の業務の中から新たに実習生が従事する作業を選定し、ジョブコーチと検討を行いながら、職場実習におけるステップアップを実施していくこととなる。
3)施設職員からの協力
長期間の施設利用者に対しては、職場実習の期間中、所属施設職員に以下の内容について協力を受けた。
①公共交通機関を利用しての自主通勤の方法に関する支援
②職場での基本的な挨拶や服装に関する支援
③金銭管理に関する支援
④職場と本人・家族間の連絡及び協力関係
また、実習開始直後は、仕事に従事する時間が急激に増加するために生じる体力面や集中力低下を考慮し、午前中は職場実習、午後は所属施設で作業及びカウンセリング等を実施することとした。
短期間の職場実習実施後に6ヶ月間の職場適応訓練に移行、3名の実習者を雇用した。



4)障害者雇用が進んで
職場実習の開始当初は、社員から知的障害者と共に働くことに対する不安の声があったが、彼らの仕事に取り組む姿勢を見て不安が解消された。また、自分達も一生懸命やらないといけないと初心に返ることで自然な形で社員教育ができたことは、思わぬ効果であった。
また、当社を見学に来た人からは、「障害者を区別することなく雇用している」「非常にいい事をされていますね」。との言葉をもらっている。
3人が社員となり、各個人のステップアップの状況に対応した配置場所や職務内容については、奥井専務を中心に受け入れ担当者による検討を進めた。また、各部署においても主となる担当者が配置され、どの部署でも「誰に」指示を受ければよいのかを明確化したことで、当初の限られた部署での単純作業から、従事できる作業の枠を拡大することができた。
この取り組みは、3人の社員の働くことに対する「自信」や「やりがい」、「働く意欲」の向上へと繋がった。
また、ジョブコーチが訪問した際には、社員から「みんな頑張っているよ」、「私達も大変助かっている」と言葉をかけている。
【新たに設定した作業】





4. 新たな取り組み
全国10ケ所のハローワークで実施されるモデル事業「地域障害者就労支援事業」にハローワーク敦賀が指定され、当社が委託事業所となった。
「地域障害者就労支援事業」では、新たに2人の障害者を職場実習で受け入れた。実習期間の基本は2ヵ月間、週に3日程度実施する。
この職場実習では、聴覚障害者が1人対象となっていたことをきっかけに、奥井専務が提案した朝礼の時間に手話を取り入れることを実施するなど、障害者雇用の経験を活かした対応が随所にみられる。
すでに各部署においては、実習受け入れ担当者が配置されていることや、作業におけるステップアップの流れも確立されており、新たな実習者が比較的容易に実習を開始できる体制が整っている。
現在、職場実習を終えた2人のうち、聴覚障害者の1人については引き続き職場適応訓練に移行することにより一般雇用を目指し、もう1人は当社での職場実習の経験をステップに、他の事業所にて職場適応訓練を受け雇用を目指さしている。

経て職場適応訓練にて雇用を
目指す実習者
5. まとめ
(1)社長の方針
最後に、全国各地を飛び回っている奥井社長からの話を紹介する。
社長は過去に体調を崩されたことをきっかけにマラソンを始めたが、国内外の大会に出場するなかで、視覚障害者や自閉症、下肢や上肢に障害のあるハンディキャップランナーとの出会いから、彼らの並々ならぬ「努力」を感じ取り、事業所経営に対する「努力」の大切さを改めて考えたと言う。
社長は、障害者雇用の取り組みのポイントは「経営者よりも現場で一緒に仕事をする社員の理解」という現場を最重視した方針を持っている。また、『「障害もひとつの個性」という美しい言葉があります、それを自然体で話し合える企業を目指していく中で、弊社の新しい企業としての姿が見えてくるような気がしてなりません』と語っている。
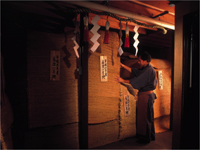
(2)ナチュラルサポートの形成
当社の取り組みで大変特徴的な点は、「ナチュラルサポート」が実践されていることである。 障害のある社員が安心して悩みを相談でき、新たな業務の取り組みに対する不安等を解消してくれる担当者の存在は、彼らにとって欠かせない存在となっている。
また、担当者が不在であっても、他の社員が担当者の役割を把握・代行する様子も見ることができる。
なお、ジョブコーチ支援制度を有効に活用し、障害者雇用に関する各関係機関との緊密な連携を重視しており、課題が発生した場合には積極的に関係機関への協力を要請している。
奥井社長の経営方針により、全体調整を行う奥井専務、担当者をリーダーとした全社員、ジョブコーチ、各関係機関がそれぞれの役割をしっかりと果たしている体制が構築されている。


(本社工場前にて)
平吹 威一郎
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











