助成金を活用し障害者のための工場分室を設置
- 事業所名
- 伊南電器株式会社
- 所在地
- 長野県駒ヶ根市
- 事業内容
- ワイヤーハーネス、多芯ケーブル、モールド成型品等製造業
- 従業員数
- 92名
- うち障害者数
- 12名(うち5名はトライアル雇用中)
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 7 ハーネス組立作業 内部障害 0 知的障害 3 ハーネス組立作業 精神障害 2 ハーネス組立作業 - 目次
 本社社屋 |
1. はじめに
紅葉が色づいた10月の中旬、伊南電器株式会社駒ヶ根工場にある「駒ヶ根工場分室」にて障害者委託訓練の実践訓練コースを受講中のNさんの仕事ぶりや顔の表情は、「作業は速くはないが確実な仕事ができる。でも無表情なのが気になるし、彼の意思がつかめないので…」という職場での評価も変わっていないが、本人はこの職場や仕事は気に入っているようであり、執筆者が訪問したときには嬉しそうな表情を見せる。「風邪を引かないように、あと少しだからがんばろう!」と帰り際に話しかけると、彼が右手を上げるではないか。
職場の責任者である川上さんに聞くと、最近彼が始めた意思表現の方法とか。思わずもう一度戻り、「また、来るから」。右手が上がり、わずかに“ニコリ!” 成長の跡が実感できる。
こうして3ヶ月が過ぎ、トライアル雇用に移行しても、無遅刻・無欠勤で黙々と作業を続けているが、最近は分室内だけでなく本工場内での作業も増えてきている。それだけ戦力になりつつあると期待を膨らませるとともに、川上さんをはじめ、周囲の先輩たちの理解と協力・指導の結果であろうと思うのである。
2. 事業所の概要
当社は、信州伊那谷の南部にある駒ヶ根市に昭和44年に設立され、モーター関係の部品組立からスタートしたが、すぐにハーネス製品の製造を開始し、それ以降現在まで主力製品となっている。 この間、平成6年には中国国内に1000人規模の現地法人“INAN中国”を設立してハーネス製品の製造を開始するなど、国内2工場と合わせてワイヤーハーネス製品の専門メーカーとして順調に業容を拡大してきている。
3. 障害者雇用の経緯~分室の設立~
(1)分室の設立計画
平成15年に当社は、本社機能の管理部門並びに駒ヶ根工場の移転に伴い、市場からの要求が増えてきていた多品種・短納期・小ロットに対応するための社内組立工場の設立を検討した。
この社内情報を聞いた小杉顧問は、次の提案をトップに行った。
「組立工場であれば仕事の内容から見て、障害のある人にも門戸をひらき、障害者雇用の拡充を図れるのではないか。しかも、ちょうど当社の創立35周年に当たる年なので、その記念事業として実現できれば、日頃からお世話になっている地域に対する社会貢献への度合いをより高める絶好のチャンスではないか」
当社は、創立当初から内職者を活用し、最多時には200人前後活用したこともあるので、地域貢献への経営層の理解度が高かったことや、すでに1人の障害者を雇用し、職場や仕事への対処や指導についても社内では理解されていたこともあり、8月上旬に「早急に具体的な検討をする」意思決定をした。

(2)分室の建設
内職者の窓口も担当している小杉顧問は、内職の現場で障害者が作業している様子を見ており、実現にはかなりの自信を持っていたため、早速、製造担当の星野工場長とともにハローワークへ相談を持ちかけた。
その結果、長野県雇用開発協会との3者で具体的な検討が進み、「第1種作業施設設置等助成金」による「駒ヶ根工場分室」を設置し、障害者の働く新しい職場を創ることとし、社内検討ののち「駒ヶ根工場分室建設プロジェクトチーム」を設置した。
駒ヶ根工場分室建設プロジェクトチーム
・リーダー 田中社長
・メンバー 星野工場長
高木部長
小杉顧問
9月には、採用活動と工場建設、助成金の申請書類の作成などが、30回を越えるハローワークや雇用開発協会との折衝や打ち合わせにより同時併行して行われ、12月の「助成金承認前着手の承認許可」を待って、信州特有の寒さの中での工場建設工事が予定通りに進行された。
こうした短期間での作業の末、平成16年3月22日に、下肢障害者2人、知的障害者4人、精神障害者1人及び管理者1人の計8人による分室が操業を開始した。

4. 取り組みの具体的な内容
製造全体を所管する星野工場長は次のように述べる。
(1)障害者雇用に当たっての考え方
①人それぞれの考えに違いがあるように、障害の度合いによる対応を十分に配慮しなければならないが、本人の作業に取り組む姿勢を一番大切にしたい。
②日常の作業の中では思わぬ所でミスが生じたり、何でもない様な行為が見落とされる場合もあるが、これを障害者だからという考えで看過してはいけない。良いことは褒め、悪いことはその場で指摘するなど、社員として当然求められる品質の確保と作業能率の向上を目指すためのキチンとした指導が必要である。
(2)雇用管理上の工夫
①採用に際しては、健常者と同等の待遇で臨むことを前提に考え、選考時にはハローワークに協力をお願いして雇用特性を学び、作業編成も能力が発揮しやすいよう工夫したほか、障害のない社員と交わってできる作業がないかを常に模索している。
②賃金等労働条件についても、障害のない社員と同等の給与を得ている社員もおり、通勤その他の処遇・福利厚生等についても同条件としている。
③職場内の配置については、計画段階から下肢障害者(車いす使用者)を意識したので、スペースに余裕のある職場づくりができ、空調設備も設置した。
④職場運営や作業管理については、工場長・業務遂行援助者・分室管理者による「改善チーム」を設け、保護者を含めての懇談会や生活環境の改善、作業レベルや職場環境の向上に取り組んでいる。

(3)作業編成と適正配置
7人のうち5人は面接のみで採用を決定したため、分室の責任者である川上さんは各人の力量は全くわからず、障害者雇用は未経験のなかでの作業であった。以前から勤務していた1人の身体障害のある女性社員に、一時的に助手代わりになってもらい、まだ職場ができていないなか、外注先の仕事場を借り実習を行い、彼らに仕事の内容やポイントを知ってもらうよう取り組んだ。
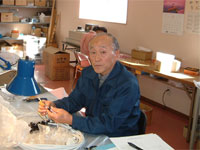
身体障害のある社員は、職場や職務に慣れるにしたがい、従事できる範囲が広がり、少しずつ戦力になっていった。一つの機種の操作を皆で一斉に取り組んでもらい、その様子やできばえで技量や適性を把握することも行った。

また、様々な障害のある社員が同時に入社し、しかもハーネス加工の職務については未経験者ばかりであったため、仕事が出来るようになるためにはまず居心地のよい職場をつくらなければいけないと思い、次のようなことをはじめ、今でも続けている。
①朝会の時は、職場・事業所・仕事・社会等さまざまなテーマの話題を話し、意識や意欲の向上を促したり、指導・教育を行った。
②最初から自分たちの職場の清掃は当番を決めて取り組ませた。
③休憩時間には指導員も一緒にお茶を飲みながら話の中に入り、できるだけ多く話ができるよう努めた。
④事業所から福利厚生の一部として補助を受け、月1度、自分で選んで注文できる昼食会を行うこととした。現在では毎月のお楽しみ会として定着しており、その日の昼食はいつもよりも賑やかである。
(4)支援・助成制度の活用
当社では、各種の支援・助成の制度が、職場づくりや戦力化へのツールのひとつとして積極的に活用しており、それが効果を表している。
活用した支援・助成制度は以下のとおり。
①第1種作業施設設置等助成金のほか
②重度障害者介助等助成金(業務遂行援助者の配置)
③特定求職者雇用開発助成金
④トライアル雇用制度・ジョブコーチ支援制度
⑤障害者民間活用委託訓練
⑥障害者職業生活相談員 など
5. 今後の課題と対策・展望
分室が操業開始して1年半が経過した。「個々人の技能もアップし、なかには組立以外の新しい作業に挑戦する社員も出るほどになったり、組織の一員としての自覚も増してくるなど、分室全体としての能力も着実に向上してきているので、一日も早く障害のない社員との差をなくせるように指導や工夫を重ねて行きたい」と工場長は語る。
また、分室における彼らの仕事ぶりや成果が評価され、機械加工を中心とする“第2分室”設立の計画が新たに具体化しており、委託訓練を受講しトライアル雇用を実施中のNさんは、そのための人材とのことである。
他にも、“第2分室”設立のための人材が採用されて仕事を始めており、半年後には新たにスタートする計画の“第2分室”に向けて職場の活気が感じられる。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











