障害者の作業指導と生活指導の取り組み
 事業所外観 |
1. 事業所の概要
明治30年の創業以来、一般機械部分品の機械加工を営んできた当社は、昭和30年に鋳造部門を設立し三菱重工業株式会社三原製作所の協力工場として、鋳造から加工完成品までの一貫作業の特色を活かし全国各地からの受注生産を行っている。
現在、機械部門13人・鋳造部門5人(うち障害者4人)・管理部門2人により、少数の社員が作業に一貫して従事している。
2. 障害者雇用の理念
障害があっても人は必ず「光るもの」を一つは持っている。本人の努力と併せて、根気強く指導しながら見守って行けば「人は育つ」信念に基づき、現在4人の障害者を雇用し、勤務意欲を持続させるため、生活指導や職場教育を社長・部長が中心となり取り組んでいる。
彼らが従事する鋳造に関する作業は、鋳物完成までの混練・造型・注湯・砂落し処理といった反復工程の中から、職務遂行が可能な作業を見出している。
3.取り組みの内容
(1)能力開発
障害者の採用に際しては、生産性を高めるために能力開発を図る必要があるため、トライアル雇用を利用し、その人の持つ「光るもの」を見極めたうえで、社長・部長が指導者となり、個々の社員に適した指導方法を決め人材育成を進めている。
(2)職場環境の改善
鋳造は高温、騒音、ほこりが舞うといった職場環境であるため、過去に、手が汚れる、目に砂が入るなどの理由で退職した障害者もいたが、7年前に造型作業を省力化するための自動砂処理装置・自動造型機を設置することにより、重労働の作業を障害者が対応できる軽作業に転換できたため、平成15・16・17年と障害者雇用を進めることができた。
(3)職場でのルールに関する指導
①採用当初は、まず遅刻をしないこと、作業に取り組む前と終了後に職場を清掃、整理することを指導した。
②職場内のコミュニケーションを図るため、朝夕のあいさつや返事が適切に行えるよう指導した。あいさつや返事が困難な知的障害者に対し、社員全員が率先して笑顔でのあいさつや話しかけを行い、職場の雰囲気を和らげるように努めた結果、2~3週間ほどで彼らから元気にあいさつや返事が聞かれるようになり、職場への適応がうかがわれた。
③傘を借りたら返すなどの約束事、作業服の洗濯、整髪や爪切り等の身だしなみ、落とし物や忘れ物をしないといった細かな内容についても指導した。
(4)知的障害に対する取り組み
1)勤続17年のAさんの採用時は、ジョブコーチ支援やトライアル雇用の制度はなく、全て手探りで指導した。当初は作業ができないため、指導者は時間を取り、作業を一緒に行って手本を見せ、繰り返し指導を行ったほか、小さな事でもできれば褒めることによって、少しずつ自信を持たせた。今では、混練・鋳型作り・グラインダー処理作業、鋳造部門の大概の仕事を任せることができるようになった。
2)入社半年のBさんは、「一定時間内に○○個仕上げる」といった、設定された目標に向けての作業に対しては、怠けている様には見えないが注意を受けないと取り組むことができないため、3ヶ月経過後も毎時間確認と注意を喚起し、職場定着につながるよう繰り返し指導する状況が続いている。
(5)聴覚障害に対する取り組み
Cさんは相手を呼ぶのに「オイ」、返事は「ウン」と、適切なコミュニケーションがとれないため、職場にとけ込めなかったが、聴覚障害の特性や本人の性格など全社員に説明し理解を求めたところ、明るい性格と気くばりができるなど長所もある本人は、みなに可愛がられるようになった。
また、言葉では意思が伝えにくい点については、作業日報により、本人は作業内容や反省点等を、指導者からは適切な返事を交換することで、失敗をしても次は成功させたいという気持ちにさせるような指導をしている。
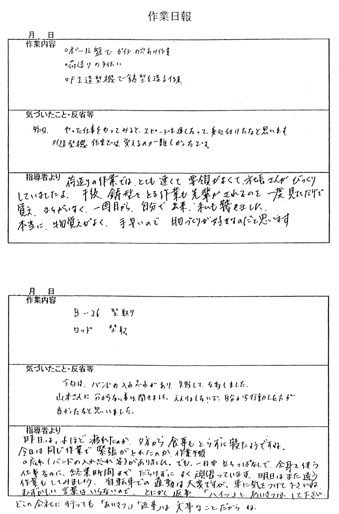
(6)全社員が従事する作業に対する指導
1)鋳造部門工程(混練から鋳物完成まで1週間の工程)
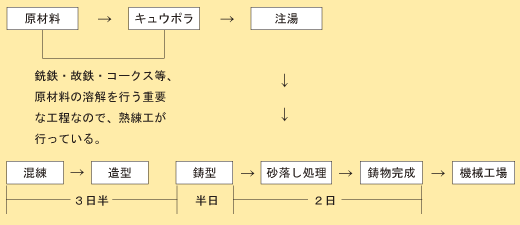
2)混練・・・ 砂・粘土・石炭粉・水を、混練機にて練る。
混ぜる分量が障害者にも一目で分かるよう、はかりに印を付けている。
3)造型・・・ 混練した鋳物砂を使って、自動造型機や手作業で鋳型をつくる。
鋳型の種類が多いので型番を間違えないよう指導し、でき上がった後は必ず責任者の
検査・確認を受け、不良品に対しては何度も繰返し作り直す。
1時間の数量で上達度がわかり、次の目標にもつながる。

4)鋳型・・・ 造型機で作った製品
注湯作業を安全に素早く行うためには鋳型の配列が重要であるため、
鋳型番・数量別等を考え、障害者に置く場所を指示する。
5)注湯・・・ 広い作業場に並べられた多くの鋳型に高熱で溶解した鉄を杓で流し込む作業。
的確に素早く行わないと溶けた鉄が固まるので、社長はじめ従業員全員が神経を
とがらせて作業している。
また、危険度が高いため、手袋・安全靴・長袖シャツ等を装着させ、いつも社長自ら
自らが先頭に立ち、溶湯の扱い方や注湯の仕方などの手本を見せて作業の指導をしな
がら、障害者の作業を見守っている。

6)砂落し処理・・・ 翌日、冷却した鋳型の砂を落とし、グラインダーを使って鋳物のバリを取り整
える。
バリを削りすぎると不良品になるので、バリを削りやすくするためには、鋳物
のどの部分から削るのが良いか、グラインダーの安全な使い方等を細かく指導
する。
7)鋳造完成・・・

(7)安全管理
1)毎朝、社長が障害者一人一人のあいさつや顔色からその日の体調や健康状態等を確認したうえで、安全に作業ができるよう指示する。
2)事故防止について具体的な内容の理解が困難な障害者に対しては、各作業を進めていくうえでその都度、現在従事している作業の危険な部分を具体的に説明する。体が覚えこむまで反復して指導を行う。
(8)家族との連携
職場定着を図るため、家族との連絡を頻繁に取り、家族の理解、協力、本人への励ましを促す。
4. 取り組みの効果
1)障害者雇用の取り組みから、繰り返し指導することで作業遂行力が伸びることを理解した。説明した内容を忠実に守り、単純な仕事なら任せられるようになり、当初の期待以上に作業をこなせるようになった。
2)特別扱いをせず、健常者と同等に作業するなかで集中力や緊張感を体験してもらうとともに、自分がこの職場に必要とされる人間であることを自覚してもらった。このことにより、元気なあいさつや返事、乱れのない服装、清潔な髪型など、生活面でも向上が見られた。
5. 今後の課題・展望
彼らがこれから先、継続して勤務し、職業人として自立するためには、経済面においては、自活できるだけの収入が得られるよう、当社の一員としてこの仕事は任せられると評価できるよう更に指導に取り組むとともに、生活面においては、障害者就業・生活支援センター等関係機関との連携を深めていくことが重要になる。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











