本人のやる気を受け入れ段階的に作業を設定
- 事業所名
- 有限会社制電工業
- 所在地
- 島根県出雲市
- 事業内容
- 電気設備の配電盤の製造及び販売等
- 従業員数
- 18名
- うち障害者数
- 2名
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 1 工程管理、在庫管理 内部障害 0 知的障害 1 塗装、組立、納品、製品補助 精神障害 0 - 目次
1.事業所の概要
(1)事業内容
当社は、昭和53年9月1日、社長が35歳でサラリーマンから独立し創業した。電気設備の配電盤の設計・製造を中心に県内全域に渡って取引がある。
また時代に合わせオリジナル商品も開発し、県外にも売り出そうとホームページも準備中である。

(2)経営方針
人の和を大切に,従業員同士で力を合わせて仕事に取り組んでいる。社長自身11人兄弟であり、人の「和」の大切さや人に対する気遣いなども自然と身に付け、誠実な性格と合わせ経営にも活かすことで、従業員との信頼関係も良好で働きやすい職場環境になるよう努力している。
(3)組織構成
従業員18人のうち障害者2人を雇用している。20代から60代まで幅広い年齢構成である。
2.障害者雇用の理念と現況
(1)理念
障害のない人でも10の仕事があるとすれば全てできるわけではなく、8つできれば良いほうである。障害のある人でも10のうち7つの事ができる人もいれば、2つしかできない人もいる。しかし、2つしかできない人でも、その部分では障害のない人に負けないような仕事ができればいいのではないか。できないことができるようになるのは本人の努力次第だが、障害のためにどうしてもできないこともある。そのことは理解した上で、自分にできることで仕事をしてもらえるように配慮している。障害のある人の側から甘えが出ると雇う側としては大変難しくなる。障害の有無にかかわらず、メンタルな面で強さを持って欲しいと思っている。
(2)障害者雇用状況
創業当初から社長も障害に気付かない形で雇用した精神障害者について、障害について把握した後も継続的に約20年間雇用したこともある。また、周囲や知り合いの両親から雇用を依頼された問題のある若者についても、「本人のやる気次第」とできる限り引き受けてきた。採用当初は問題も起こしたこともあるが今は立派に成長し勤めている。現在は、軽度の知的障害のあるNさんのほか、62歳になる身体障害のある従業員には工程管理など業務のまとめ役として活躍の場を提供し雇用している。
3.知的障害者雇用の取り組みの内容
(1)経緯
Nさんは、ハローワークに通っていたがなかなか仕事が見つからず、はじめ社長夫人の知り合いであった両親から相談を受け、両親の何とか仕事に就かせてやりたいという思いを感じた。その後しばらくしてハローワークからNさんの雇用にについて相談を受けた。当時求人は出していなかったが業務は多忙であったことから、意欲のある人ならと面接することとした。
(2)雇用に至るまで
面接時は両親が同伴した。本業の配電盤の職務は複雑であるため、本人も最初からは無理なのではと素直に気持ちを伝えてきたが、職務は複雑なものばかりではなく、当社としてもできることがあれば障害の有無は関係ないと考えていたので、やる気があるなら少し考える猶予をもらった。

面接終了時、Nさんは、当時大学などと共同研究し社長が考案した、屋外の廃棄物を利用したリサイクルハウス栽培機器を見て質問してきた。リサイクルが成功すれば、退職した高齢者や障害のある人の仕事になり得ると考えていた。従業員は誰も興味を示さなかった機器を、興味深げに見ているNさんを見て、「雇ってみよう。見所がある。」と思った。
しかし、雇用するには金銭的な面や内部の理解など考えなければならないことがあった。障害があるからといって安い賃金で雇えないと考える一方で他の従業員とのバランスに苦慮した。雇用援護制度については関心がなかったが、ハローワークからトライアル雇用について説明を受け、双方の話し合いで制度を利用し採用することとなった。
障害のない従業員に対しても面接時に色々な話はするが、できることも判らないのにいきなり賃金の話をする人については、結局長続きしなかったり、やる気のある仕事に繋がらなかったりするため、最初から受け入れないときっぱり社長は言う。
本人のやる気次第とも話す社長の考え方と、Nさんの仕事を希望する気持ちがうまくかみ合い、また、当社の取り組みを素直に自分で見て、自分なりに考えを話せたことが結果的に好印象に繋がった。また、Nさんはリサイクル機器について学校で勉強したことがあったそうで、健常者でもなかなか気付かない所にも目を向け、意欲的に自分をアピールできたことが雇用の機会をつくり出した。
ポイント
1.自分の現在のスキルを素直に評価
2.意欲的な自己アピール
3.事業所としての明確な方針と積極的な理解
(3)雇用後の取り組み
1)試用期間を使った評価
雇用後、3ヶ月間の試用期間を設けている当社では、Nさんの場合は、仕事が合わなかったり嫌なことがあれば必ず休みがちになれば継続的な勤務に支障が生じるほか、休めば「障害者だから」と思われがちであるため、はじめは決まった仕事を任せるよりも休まずに出勤できるかを見た。

Nさんは、雇用後1年半経過した現在まで休みが無い。人柄もあるが、他の従業員とのマッチングもうまくいき、職務も他の従業員の手伝いや雑務といった本人にできることから取り組んだことが継続勤務の要因となっている。他社で従業員からいじめを受けていたNさんは、コミュニケーションの大切さを自分なりに感じており、今では製品の納品や、スプレー塗装、配電盤の組立補助と、徐々に仕事を覚えて任せられるようになり本人の自信に繋がっている。
ポイント
①メンタル面、健康面を整え欠勤のない勤務状況を作る
②コミュニケーションの大切さ
③本人に対応できる作業から導入する配慮

2)トライアル雇用制度の利用
ハローワークから紹介のあった雇用援護制度の利用に対しては抵抗感があった。今まで何人か障害のある人を雇用した時にも、障害があるから受け入れたわけではないため、制度利用は考えたこともなく制度自体あまり知らなかった。
Nさんについては、知的障害のある人の採用は初めての取り組みであり、仕事量と賃金のバランス、また事業所として利益を追求しなければならない立場、継続的に雇用できるかについての不安といった問題点があったため、ハローワークの強い勧めと本人との話し合いで利用することになったが、「障害のある人を雇うから何かしてくれという気は全くないしそう思われたくもない。受け入れるからには責任を持って受け入れたい」と社長はきっぱり話す。
3)他の従業員との関係
以前は彼らの雇用に対し、障害のない従業員から反発もあった。退職した精神障害のある従業員の時も、当初は「仕事にならず、辞めてもらった方がいいのではないか」との意見も受けた。
同じ立場で働く従業員としては、同じ仕事を同じようにこなしてもらわなければ自分の負担が増えると考え、雇用主とは立場が異なる。
それに対し社長自らが「ここまでの仕事で彼は十分」と考えを従業員に話すことで、従業員も納得して従う場面が何度かあった。その都度原因をはっきりさせ、従業員からの意見を参考にしながらより良い方向性を示し問題解決を図ってきている。
現在Nさんは、先輩の従業員の指導のもと、いろいろな仕事を覚えている段階である。先輩従業員に指導を任せることで周囲とのコミュニケーションを取りやすくし、同じ従業員として問題解決に努めるようにしている。社長は一歩下がってその状況を把握しながら必要なときにアドバイスしたり、厳しく接したりとNさんをメンタル面で支えている。Nさんも持ち前の明るさで従業員とのコミュニケーションも良好で、毎日のあいさつなども大きな声で行い、特に今まで大きな問題もなく真面目に勤務している。社長夫人も気を遣い「少々失敗しても叱られてもがんばらんといけんよ」と激励しながら採用された初心を忘れないよう努力して欲しいと願っている。
ジョブコーチ支援制度を利用しなくても、社長と従業員の信頼関係がNさんに安心感を与え、安定して仕事ができる環境が自然にできている。Nさんも採用から1年経ち、自信をつけ明るい表情で作業に取り組んでいる。
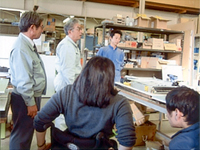
ポイント
①雇用主と従業員の信頼関係による働きやすい職場環境づくり
②初心を忘れない明るさと謙虚さの指導
③あいさつなどの基本的なマナーの徹底
4)家族との信頼関係
Nさんの家族からは、採用時から現在も「預けるから任せます。色々あるでしょうがお願いします。」と言っており、苦情も無い。職場で本人に何かあっても一方方向で苦情を言うのではなく、家族との信頼関係も築かれている。
4. 今後の課題、展望等
社長は、夢のような内容ではあるが、開発したリサイクル機器は比較的簡単な操作で作業ができるため、障害者雇用にも大きく貢献できると話す。
事業所としては資金面などの懸案事項が残されており、障害者雇用がなかなか進まない状況もあるが、できることなら更にいろいろと障害者雇用の可能性を広げていきたいと考えている。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











