コミュニケーションを取りながら、相互の様々な工夫により実現した障害者雇用
- 事業所名
- 日研総業株式会社出雲出張所山方作業所
- 所在地
- 島根県雲南市
- 事業内容
- 業務用冷蔵、冷凍庫等の鉄板加工から組立までの完全請負による業務
- 従業員数
- 45名(事業所全体で400名)
- うち障害者数
- 3名
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 2 ピッキング作業、管理職 内部障害 0 知的障害 1 組立 精神障害 0 - 目次
1.事業所の概要
(1)事業内容
当作業所は、島根県内で製造関連企業への人材派遣を含め400人以上の従業員で構成されている日研総業株式会社において、業務用冷蔵、冷凍庫をはじめ家庭用玄米保冷庫など鉄板加工から組立まで完全請負で業務を進めている。請負先については、ホシザキ電機株式会社の工場業務を請け負っている。

(2)経営方針
「良い製品は、良い環境から」という方針のもとに、作業環境の安全性や効率性の確保については様々な工夫がなされている。また従業員同士のコミュニケーションを大切にしており、一方通行ではない話し合いにより良い職場環境が築いている。
2.障害者雇用の理念と現況
(1)理念
障害者雇用については、2年前から本格的に取り組んでいる。当初は彼らとどのように接すればいいかといった不安もあったが、経営方針に基づきコミュニケーションをじっくりと取りながら良いところやできることを見つけ仕事を任せることで、他の従業員と変わりなく接することを心掛けている。
また作業面の工夫については、ジョブコーチなど専門的な視点からのアドバイスも受けながら、事業所として工夫することを怠らず、雇用した従業員に良い環境で仕事に取り組んでもらおうと取り組んでいる。
常駐している責任者が「雇用した以上、従業員としてできる仕事をしてもらうことが義務」と話すなかに、実際に障害者を雇用し育てていくことで事業所の障害者雇用への手応えと自信が見受けられる。
(2)障害者雇用状況
当作業所の従業員45人のうち、身体障害者2人(Bさん、Yさん)、知的障害者1人(Fさん)の計3人を雇用している。
3.取り組みの経緯と内容
(1)背景
全社的に障害者雇用を進めていく方針から、当作業所においても障害者求人を出した。法定雇用率への対応も念頭に置いていたが、仕事がこなせればやる気のある人に仕事に就いてもらいたいという、ごく普通の考え方で取り組んだ。
(2)経緯
当作業所は、もともとYさんを雇用していたが、現在管理職として勤務しているYさんは、障害が非常に軽度であったため障害を意識したことはなかった。その意味では、障害者雇用は初めてとも言え不安もあった。事業所全体の方針もあり、職務を限定して求人を出したところ、ハローワークから紹介がありジョブコーチ支援や各種援護制度について説明を受け、平成15年8月にBさん、平成16年9月にFさんを受け入れた。
(3)取り組みの内容と効果
1)聴覚障害と視覚障害の重複障害への取り組み
難聴で視覚に障害のあるBさんは、当初の研修期間中、ジョブコーチ支援を受け作業習得に取り組んだ。
当作業所においても、障害者雇用に初めて取り組むことから、Bさんに対しどのように仕事を教えるのが良いか判らないことが多く、感じ方や理解の仕方も違うことで戸惑いもあったが、ジョブコーチ支援制度を利用することでコミュニケーションの取り方や指導面での工夫など参考になった。
例えば、Bさんがピッキング作業を行うにあたっては、1回の説明ではなかなか理解が困難であったため、部品の写真や図を使用することで部品の形などを理解してもらうほか、作業工程を図示したツールを作成することで、Bさんの仕事がスムーズに流れるようにした。
なお、この件については、ジョブコーチが当作業所と本人と協議することにより問題解決に取り組んだことで、本人はもとより当作業所においてもその後の取り組みの自信に繋がった。当作業所もジョブコーチに全てお任せではなく、一度経験した工夫を勉強し取り入れることでノウハウの蓄積が自然にできるようになった。
また、Bさんには毎日自主的に作業日記を付けながら作業内容を覚える努力や工夫が見られた。自ら従事した作業の内容や数量など、誰に言われるわけでもなくデータを取る前向きな仕事への取り組みに対し、従業員の信頼を得ている。「今では全然心配ない、よくやってもらっている」と太鼓判を押されている。
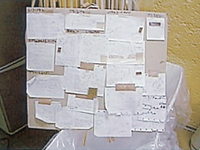

ポイント
①当作業所と本人をつなぐジョブコーチの工夫
②ジョブコーチ支援を通じた当作業所の障害者雇用のノウハウ蓄積と努力
③Bさんの職務に対する姿勢(仕事に前向きな気持ちと自分なりの工夫)
2)知的障害に対する取り組み
Bさんの後に雇用したFさんは、軽度の知的障害があり、数が10までしか理解できなかったが、当作業所も2人目の雇用ということでジョブコーチ支援は利用せず雇用に取り組んだ。
多少でも作業内容が変わるとFさんは1回では理解が困難であったため、当初は、数を数えたり組み立てる簡単な作業を何回も反復し覚えるまで続けた。また、当作業所では10個以上数える作業は少なかったので、最低でも10個ずつ数えるように指導した結果、Fさんは克服することができた。Fさんは年齢も若いせいか、作業よりも社会性に気を遣った。工程リーダーとよく話し合いながら根気よく作業に取り組むことでハンデを克服し、今では組立作業も慣れ戦力の一人と言われている。
当作業所の理解と適切な指導、環境整備など、一度経験したことでノウハウを蓄積し、戦力として受け入れることができたことは、障害者雇用に真剣に取り組んでいることの表れであり、また、特別な扱いを行わないことで本人のやる気も引き出している。

ポイント
①メンタル面や社会性への気配り
②障害特性を理解し、反復指導による作業習得への工夫
③本人のやる気を引き出すことで更に向上に繋げる取り組み
④経験した雇用ノウハウを活かした取り組み
3)他の従業員との関係
常駐のM責任者は、Bさんを受け入れる際自分よりも周囲がどう受け入れるのか気になった。些細なトラブルで本人が傷ついたりすることが心配で、事前の見学や全社ミーティングを行い、その場で「障害者の方を雇用します。初めての試みですが、心ない言葉や偏見で見ることなく同じ仲間として受け入れていきましょう」と呼びかけた。
当初は、本人の感じ方により、何気ない一言が本人にショックを与えたこともあったが、その都度工程リーダーと話し合い、フォローしながら相互が理解する努力をした結果、大きなトラブルもなくうまくいくようになった。
何よりもBさんもFさんも仕事に対し前向きで、自らも努力して取り組んでいることや、工程リーダーが相談相手としてメンタル面や技術面について適切なフォローを行っていること、当作業所全体で良い職場環境づくりに取り組んだことで、周囲の従業員も彼らを一社員として受け入れることができている。特別扱いせずに自然体で受け入れる当作業所の体制が本人にとって強い励みになっている。
ポイント
①従業員の信頼関係による働きやすい職場環境
②工程リーダーを中心とするコミュニケーション体制
②特別視しないこと。感じ方の違いは話し合いで解決する取り組み
4. 今後の課題、展望等
当作業所は、今後も機会があれば障害者雇用に取り組む意向である。一方通行でなくコミュニケーションが取れれば受け入れが可能だということを、これまでの経験で自信を持つことができた。もちろんジョブコーチの専門的なフォローも非常に有効であるが、良い職場環境を作り出そうという職場全体の取り組みにより実現されている。
現在のBさん、Fさんについては、当初の職務よりも仕事量が増えている。当作業所は「本人のやる気と努力された結果です。できるから任せる。障害のない人と何ら変わりません」と述べる。また、初めての障害者雇用にあたり、良い人材に恵まれたとも感じている。「辞められたら困りますよ。それくらい良くやってもらっています。そこのところは、もっと自信を持ってもらっていいと思っています。」
2人は職場の一員として必要とされ、さらに努力を続けている。「仕事は厳しいときもあるけれど楽しい」と話す姿は自然でどこか自信にあふれている。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











