教育分野において視点を変えて障害者の雇用の場を確保
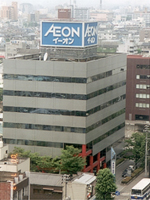 事業所外観 |
1. 事業所の概要
株式会社イーオン・イースト・ジャパンは、「英会話のイーオン」として全国展開しているイーオングループの1社である。岡山市に本社があり、3本部(東部本部・首都圏本部/東京・関西本部/大阪)で構成され、その下に約150校の英会話学校を運営している。(グループ全体では約310校)
2. 障害者雇用の経緯
当社が本格的に障害者の雇用を検討することとなったきっかけは、当社で働いている外国人講師に対し、平成14年3月から日本の雇用保険制度の適用が拡大されたことで、彼らは被保険者となり常用雇用労働者数として数えられるようになったことである。
一度に700人被保険者が増えたため、様々な影響を受けたなかで障害者雇用率が著しく低下したイーオングループとしては、教育を業務としている性格上、「これでは良くない」と、経営トップ自らその対策に心をくだき、早急に障害者の雇用を行うよう指示し、各部門でも連日会議を開いて検討を続けた。
当時学校の組織は、その運営にあたるマネージャー、ティーチングスタッフ、そしてそれらをバックアップするロジスティック部門と多岐にわたっていたが、障害者雇用対策としては、特にマネージャー部門やティーチング部門へ注目しており、つまり英語を教えられる障害者がいれば採用するという考え方があったが、その事が硬直化した考えになっているのではないかと気づき、障害者雇用だけではなく、業務の効率化、全体の組織の機能の活用について見直すこととした。またコンセプトとしては、どこの職場でも障害者を受け入られることは可能、という前提で職務の創出に取り組んだ。
当社が立てた二つの大きな目標は、次のとおり。
①障害者を受け入れる為には職場改善を積極的に行う。例えば通路の確保、床面の整理、スロープ等の設置、また手摺などの取り付けによる環境面の整備と、仕事を効率的・補助的に進めるための新しい機種・機械の導入などの設備投資も前向きに行う、というハード面における取り組み。
②採用のエリアを幅広くし、合同就職面接会等へも積極的に参加。求人条件(当社が求める能力)も漠然としたものではなく、よく検討して定着してもらえるような条件や処遇を考え、積極的に行動を起こすといったソフト面における取り組み。
3.取り組みの内容
(1)設備改善や機器導入のための施設の見直しと助成金の検討
ハード面の工夫・改善については、「どの職場、どんな仕事でも障害者と共に働ける場を創ろう」を念頭において、職場内パトロールをスタートし、作業場・廊下などの床面の凹凸、平滑度のチェック、手摺の必要な箇所等を点検した。
また、車いす用のスロープやトイレの検討、自販機はユニバーサル・デザインの機器への入れ替えを検討した。これらの設置については障害者作業施設設置等助成金の活用に向けて、障害者雇用促進協会やハローワークと相談し進めた。
雇用に関しては、先ずハローワークの障害者担当窓口と相談し、情報収集を行うと共に、紹介された国立吉備高原職業リハビリテーションセンター(岡山県)を訪問し相談した。
これら支援機関との連携の結果、障害者雇用が具体的なものにつながっていった。様々な試行錯誤の中で、国立吉備高原職業リハビリテーションセンターの訓練生をはじめ、この5年で10人の障害者を採用することができた。
(2)人材の確保と必要な設備改善及び機器導入
どこの職場でも障害者を雇用できるように考えていたので、各々の部門に必要な設備や機械を導入することで障害に応じた職場ができると考え、設備の機能や助成金の研究を徹底的に行った。
設備や機器の活用について、具体的には、国立吉備高原職業リハビリテーションセンターからの紹介で、Web作成の経験がありデザイン系の訓練を修了した、幼い頃から心臓にペースメーカーをつけている内部障害1級のAさんを、情報システム部門のコンピュータ要員としてホームページなどのデジタルコンテンツ作成部署に採用する際に、助成金を活用しマークシートリーダーを購入した。また、コンピュータ機器のメンテナンス要員も同時に採用した。
また、教材倉庫管理・発送部門においては、右上肢2級の障害者の雇用にあたっては、半自動梱包機を導入し、配送業務に配置した。
一方、事務部門について、学校の経理を担当する事務センターには、上・下肢の1級・2級及び聴覚障害2級の障害者3人が、帳票のチェック、データ入力などの業務にあたることとした。
その他、全体的に車いすが使用できるよう、スロープ・手摺・トイレなど施設改善した。


(3)新たな印刷センター部門の創出
当社が全体をあげて取り組もうとするコンセプトに基づき、既存の組織にとらわれず、効率を目的として新たに印刷センター部門を創りあげ、従来各学校において作成していた「手配りチラシ」を、企画から印刷まで一元的に管理することとした。
この印刷センターに印刷技術の経験のある障害者を雇用することとし、早速ハローワークに求人を出したが、簡単には進まず難航するなか、ようやくBさんを採用することができた。
Bさんは、手堅い仕事振りで順調に期待通りの成果を上げ、この部門の取扱量も増加するようになったため、その都度人数も増やし、現在では4人でチラシ等の印刷に従事しており、また、チラシに加えて自動名刺切断機を導入し、名刺印刷も手掛け、当社の経費削減にも大きく貢献している。
更に、助成金を活用し、大型ポスター印刷機を導入し、従来外部の印刷会社へ発注していたものが、今では当社内部できめ細かい迅速な注文に対応できるようになり、この印刷センター部門は当社に欠かすことのできない存在となった。
(4)障害者作業施設設置等助成金活用による施設の改善・機器・備品の設置内容
| 【施設の改善】 | ・手摺(構内) |
| ・簡易スロープ(構内) | |
| ・障害者用トイレ(1ヶ所) | |
| ・自販機ユニバーサル・デザイン型(1ヶ所取り替え) | |
| ・駐車場の確保 |
| 【機器・備品の設置】 | ・マークシートリーダー |
| ・半自動梱包機 | |
| ・自動名刺切断機 | |
| ・大型ポスター印刷機 |

(5)職場内交流と技能向上のための取り組み
現在、当社内の関連部署には10人以上の障害者が勤務しているが、全く健常者と変わらない仕事をしている。勤務修了後などには聴覚障害者による手話講座が開催されるなど、お互いが理解しようという気持ちが現れ、交流も盛んに行われている。
当社としても、障害者に対し少しでも負担が少なくなるような施設や設備を提供し、最終目標である心のバリアフリーの達成に向け、障害者と語らい同じ目線で取り組み、“身体のハンディーは、仕事のハンディーではない”をモットーに笑顔の絶えない職場づくりを目指している。
その一環として、年1回開催される地域の「アビリンビック岡山大会」にも積極的に参加してもらい、本人のスキルアップと更なる飛躍を図るべく意識の高揚に役立てている。
4. 取り組みの効果
デジタルコンテンツ部門については、一括外注による時間的・経費的なデメリットの問題があったが、当初予想された以上に迅速に処理ができ、しかも低コスト化を図ることができた結果、外注の割合を低く抑えることが可能となった。また、コンピュータ機器のメンテナンスに1人配置することで、現在1,500~1,600台あるコンピュータのメンテナンスを内製化することができ、十二分に費用をしのぐ効果を上げている。なお、近々新たな人材の受入れに向けて検討しているところである。
情報システム部門に勤務するAさんは、「入社3年目ですが、毎日が楽しく充実しています。月1回の定期検診も異常ありません」と笑顔を絶やさず話す。
Aさんだけではなく、他の社員全員にもマナーが感じられ、笑顔の多い職場を印象づける。
新しく創出した印刷センター部門の効果であるが、当初は全くの手探り状態であった。各学校で作成する「手配りチラシ」を如何に効率よくニーズに応じることができるかといった課題があったが、時間の経過と共にクリアーされ、今では殆どの学校の印刷に支障なく対応している。配属スタッフの技能も向上し、かなり高度な要望にも応えることが可能とり、現在ではポスターの印刷も可能である。
5. 今後の展望
印刷センター部門の今後の展望として「当社グループ内にとどまらず外部企業からの軽印刷も受注できるような組織に変えていきたい」と創出者の総務の山内課長は語る。
「教育を事業としているので、社会貢献・責務を果たすべくより多くの障害者の受入れが将来的な課題ではあるが、」と山内課長は前置きし「特例子会社の設立についても模索しているのです」と話す。
障害者雇用が、当社に新たな活力を生んだと言っても過言ではないだけに、このまま邁進していくことが期待できる。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











