障害のある職員が、障害者支援事業に取り組む
~職員・利用者ともに利用しやすい施設づくり~
- 事業所名 :
- 特定非営利活動法人アス・ライフサポート
- 所在地 :
- 山口市大市町
- 事業内容 :
- 身体障害者・高齢者へのデイサービス、訪問介護サービス、障害者スポーツなどへの支援事業
- 従業員数 :
- 13名
- うち障害者数:
- 3名
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 3 デイサービスでの企画運営、経理 内部障害 0 知的障害 0 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の概要と理念
(1)概要
平成15年に設立した当法人は、翌年に山口市内の中心商店街に近い空き建物を借り、ほぼ全面改修し活動拠点とした。1階は展示会などが開けるユニバーサルスペース、2階はデジタルシューティング(デジタルのライフルで的をねらう競技)やボッチャ(テニスボール大のボールを用い、的ボールの近くに止める競技)などのスポーツ、カラオケなどを楽しめるスポーツジムと事務室、3階はパソコンやゲームを楽しめるデイルームがある。全て障害者や高齢者への支援スペースである。

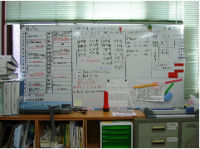
(2)理念
「アス・ライフサポートのアスには、英語のUS(私たち)と明日(あした)のふたつの意味をこめています。私たちの明るい未来の実現を支援する法人、との意味です」と藤田英二理事長は話す。
6歳時に小児麻痺にかかり下肢が不自由となった藤田理事長は、山口県内の養護学校高等部を卒業後、大学に進学。その後、自動車ディーラーで勤務しながら、車いすマラソンに熱中する。車いすマラソンでは日本記録を保持した時期もあり、2000年にシドニーで開催されたパラリンピックでは日本代表として3種目に出場した。事務室の壁には、理事長が用いた競技用車いすの実物と記念写真が飾られてあり、練習に打ち込んだ熱い日々が伝わってくる。
「僕は、車いすマラソンで人と競うことにより、貴重な体験をすることができました。人と接する経験が、自分自身を成長させてくれたように思います。ここの利用者には、スポーツなどを通して目標をみつけてほしいと願っています。デジタルシューティングやボッチャなどは、工夫次第で、障害の有無を問わず誰でも取り組める競技種目になりますから、目標をもつきっかけになってくれるとうれしいですね。また、障害のある人は、人と接する経験が不足しがちです。街への外出も少なくなります。だからもっと街へ出て、人と接する生活を送ってほしいし、その支援をしたいという思いが、アス・ライフサポートの設立につながりました。」
障害者や高齢者は、もっと気軽に街に出て、地域と交流してほしいとの熱い思いが、当法人の活動拠点を、市内中心商店街の近隣に定めることとなった。
この地は、利用者がショッピングを楽しむことができる。また、活動を通して商店街の人々との交流が可能である。さらに、近隣には美術館や散策ロードなども整っており、利便性に優れた地である。当事業所では、そのデイサービスの一環として、ほぼ毎日、利用者は職員とともに商店街でのショッピングや近隣の散策を楽しみながら、地域の人々との交流を積み重ねている。

2. 取り組みの内容
(1)職員同士の相互理解を図る
事務室では理事長のほか、車いすを利用する職員が3人いる。障害者や高齢者と同じ目線で助言し、また必要な支援内容を企画し実施しており、当法人の活動に無くてはならない戦力となっている。
「職員採用にあたっての判断の鍵は、“この仕事はこの人にしかできない”と強く思わせてくれるかどうかでした。そして採用後は、一人一人の障害特性について法人内の一般職員の全員に周知させました。特性について正しく知ることにより、仕事上の誤解を防ぐことができます。」
例えば、障害ゆえにトイレの使用時間を長く必要とする職員については、その理由を皆に正しく周知させておくことにより、「トイレに長く入っているけれど、それは仕事をさぼっているのではない」ことを共通理解でき、日々の業務はスムースに進む。
職員同士の相互理解を進める取り組みが、当法人の経営のベースにある。
(2)施設改修
1)引き戸
小児麻痺により上下肢機能障害(1級)があるAさんは、電動車いすを利用している。当初Aさんは、事務室入口のドアを、電動車いすに乗った状態では開けることができず、その都度、職員の助けを必要とした。そこで、障害者雇用助成金制度を利用しドアを引き戸に改修した。これにより、Aさんは出入りがスムースと同時に、職員の仕事もはかどることとなった。
Aさんはデイサービスの管理者として、利用者の個別計画書の作成、サービスメニューの企画、相談やアドバイスなどの業務を引き受けている。明るく穏やかな人柄ゆえ、職員や利用者からの信頼は厚い。また、当法人の職員になる前には、画家として活動していた時期もある。絵画を県美展に入選させたこともあるその才能で、利用者への絵画指導にも意欲を燃やしている。


2)トイレ
従来のトイレについては、Aさんが電動車いすから便座に乗り移るまでに職員の介助を必要としていたため、トイレの手前に広い台を設置した。Aさんは車いすのアームレストを外してこの台に乗り移り、台の上で脱衣し向こう側の便座に乗り移る。車いすの床、台、便座のそれぞれの高さは同一にしてある。この改修によって、Aさんは一人でトイレを使用できるようになった。また、同じ障害のある利用者にも使いやすいトイレとなった。トイレの入り口は引き戸である。

(3)3階にトイレを増設
交通事故により下肢機能障害(1級)があり車いすを利用しているBさんは、上肢には障害がなく、事務室では主に経理事務を担当している。Bさんは排便の感覚に障害があるため、トイレの使用に約1時間、体調が思わしくない時は数時間を必要とすることもある。
1階の車いす対応トイレを長時間使用すると他の利用者に不都合が生じるため、3階に車いす対応トイレを増設した。これによりBさんは気兼ねすることなくトイレを使用できるようになった。
なお、市内に居住するBさんは、障害者雇用助成金制度を活用して購入した車いす対応の車両を使用して通勤している。

4)事務室のレイアウト
事務室のデスクや機器類等については、車いすを利用する職員が能率よく動けるようにレイアウトしてある。例えば、Bさんのデスクの両側には手を伸ばせば届きやすい位置にコピー機と書類ロッカーを、背後には電話とパソコンを設置している。通路も車いすが通行しやすいように幅広くしている。

5)エレベーターの設置
障害者雇用助成金制度を活用しエレベーターを設置したことにより、車いす利用者だけでなく、高齢者や一般職員にとっても2階事務室や3階への移動がスムースになった。
エレベーターの内部には、奥面に鏡を取りつけている。これにより、車いす利用者は前向きのまま後方の扉の開閉を知ることができる。また、車いすの金属部分の接触による破損を防ぐため壁の下部にはアルミ板を取りつけている。扉の開閉時間については一般の機種よりも長めに設定しているほか、操作スイッチの位置も低くしてある。

6)オストメイト対応のトイレ
1階のトイレはオストメイト(人工肛門)対応となっている。現時点では当法人にオストメイトの職員はいないが、職員や利用者の障害の有無、部位、程度等を問わず、あらゆる人が利用しやすいユニバーサルデザインを念頭においている当法人の取り組みにより、市民が気兼ねなく衛生的に利用できるよう設備を整えた。
(3)介助体制
上下肢機能障害(1級)のあるCさんは、電動車いすを利用しデイサービスの企画や営業などの業務にあたっており、同じ女性の利用者の立場に配慮した相談や自立支援制度の説明などに活躍している。通勤と営業に使う自家用車への車いすの出し入れなどには介助を必要とするため、当法人が介助者をつけている。
Cさんの雇用は、AさんとBさんの雇用にあたって行った引き戸やトイレの改修、エレベーターの設置の後であったため、Cさんの就労生活はスムースに展開することとなった。
3. さいごに~就職の希望を叶えるための挑戦~
「明日に向かってチャレンジしたいと思います。僕は障害者を“神に選ばれ、試練を与えられ、挑戦する人”ととらえてきました。それゆえ、障害のある人のことを“チャレンジド”(challenged)ということばで表現しています。」と理事長は語る。
養護学校での生活体験、そして車いすマラソンの競技体験を通し、理事長の人生観と支援観が形づくられたことが伺える。そこからは、自らの運命を嘆くのではなく、明日に向けた爽やかな挑戦を通し、地域と交流することでもっと豊かな人生を楽しもう、とのメッセージが伝わってくる。
障害のある人にとって、就労は究極の社会参加であろう。当法人は、障害者からの「働きたい」「地域と交流したい」「もっと豊かな人生を楽しみたい」という熱い願いを受けとめ、社会参加への道を開くことを通し、一人一人にとっての自己実現を支援する取り組みを今日も続けている。
松田 信夫
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











