職場環境を整えることによって、障害者の職場定着を図る
- 事業所名
- TDK株式会社甲府工場
- 所在地
- 山梨県南アルプス市
- 事業内容
- 最先端のエレクトロニクス分野における電子部品製造
- 従業員数
- 410名
- うち障害者数
- 5名
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 1 機械オペレータ 肢体不自由 2 看護士、生産管理 内部障害 2 安全衛生、施設管理、製造管理 知的障害 0 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の概要
当社は、世界初の磁性材料フェライトの工業化を目的として1935年に設立し、「創造によって文化、産業に貢献する」という創業の精神に基づき、電子材料、電子デバイス、記録デバイスおよび記録メディア等の製品の研究開発と商品化に取り組んでいる。
当社の電子部品は、パソコンや携帯電話、自動車等、現代社会を支える数多くのIT製品に使用されており、現在は、カーエレクトロニクス、情報家電、高速大容量ネットワークの3分野に特に力を入れている。
当工場は、1977年には、現在の組織の礎となるヘッド事業を山梨県で活動開始し、1982年に現在地に工場を建設、今日に至っている。CSR(企業の社会的責任)とその説明責任を果たすことが求められている昨今、当工場としては、各種の社会貢献活動の展開の一方、環境問題を重視し、2006年3月に発電量300KWの太陽光発電システムの導入を行っている。
(1)主要生産品目
光ヘッド・薄膜デバイス製品・薄膜サーマルヘッド・機能性材料、アモルファスシリコン太陽電池(フレキシブルタイプ)、可視光センサー用セル等
(2)経営方針
社是:創造によって文化、産業に貢献する
社訓:夢 勇気 信頼
夢 ・・・常に夢をもって前進しよう。
夢のないところに、創造と建設は生まれない。
勇気・・・常に勇気をもって実行しよう。
実行力は矛盾と対決し、それを克服するところから生まれる。
信頼・・・常に信頼を得るよう心掛けよう。
信頼は誠実と奉仕の精神から生まれる。
社是は、当社の創業の精神そのものであり、事業は勿論のこと、社会貢献活動や環境活動にもストレートに反映されている。
当社は、活力あふれる事業所であり続けるために、常に新しい発想とたゆまぬチャレンジ精神によって、より高い企業価値を株主、顧客、取引先、従業員、地域社会という全てのステークホルダー(利害関係者)に提供し、心からの感動や良質な興奮を創造し続ける企業でなければならないと考えている。
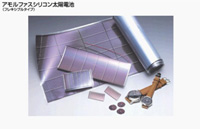

(3)組織構成
当社は、先の重点分野の事業展開を担うビジネスグループ(主要7つの)組織を有しているが、当工場が属するヘッドビジネスグループは、記録デバイス製品および電子部品の製造・開発を行っている。
また、ヘッドビジネスグループには、4つのビジネスディビジョン組織があり、当工場にはそのうち3つのビジネスディビジョン組織が存在している。各々の組織は、開発・設計・技術、製造、品質保証、生産計画、企画機能を有し事業推進を行っているが、それら以外にも事業が円滑に進められるよう共通スタッフ機能を有している。
2. 障害者雇用の理念・経緯
(1)理念
“創造”という行為を成し得るのは、“人”であるとする当社は、個の尊重を礎においている一方、自己責任の原則をもって自立(自律)を促す人事制度を有している。
したがって、障害の有無にかかわらず発揮される能力に見合った、あくまで“個”に視点をおいた制度の運用が原則になっている。
能力開発においてもOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング:日常業務を通じた教育)、OFF-JT(オフ・ザ・ジョブ・トレーニング:日常業務を離れた教育)、自己啓発を軸に個人の主体性をベースにし、意図的な育成も合わせ能力開発を行い、結果、適材適所への最適配置、人材活用に結びつく人事教育理念を有している。
当社は、市場の激しい変化に迅速に対応しながら、当社が得意とする独自のモノづくりに努め、また地球との共生を目指して価値ある技術と製品を開発し、さらなる成長を続けていきたいと考えており、当工場としても経営理念を具現化する事業展開とCSRを果たすことで、社会発展の役に立てることと認識している。
(2)経緯・背景・きっかけ
当社全社としては、“個”を尊重する諸活動に脈々と取り組む一方、CSR(企業の社会的責任)を果たすべく、身体障害者雇用促進法制定(昭和35年)以来、法律の変遷に伴った対応を行ってきた中、当工場においては、昭和63年に、事業の趨勢で約900名もの常用従業員を抱える拠点にまで急激に成長を果たし、必然的に聴覚・言語障害のある従業員も増えたが、そこであらためてコミュニケーションの円滑化が課題となり、障害者が講師となり手話講習を開催してことを機に、障害者雇用に対する取組みが定着した。
3. 取り組みの内容
(1)労働条件
当社では、事業活動のための組織、職務構成に応じた従業員の構成(社員、嘱託、パートタイマー等)としている。障害者雇用においても適性配置の考えを踏襲しており、雇用期間、場所、時間、賃金等の労働条件は障害から決定するものではなく、障害の有無にかかわらず公平・校正に、必要な能力や適性に対する発揮度や適応度に見合った条件としているが、配慮が必要な場合は、彼らが対応できる職務に応じた形態、処遇をとっている。
(2)職務内容
当社は、海外拠点との協業体制により国内外の各拠点の強みを活かしつつ、分業で事業展開を図っている。
当工場は国内拠点として、付加価値を創出しうる工程、効率を最大限とした工程を追及しており、物作りの工程においては従前の一貫した形態(物の流れが目で見えるライン)ではなく、合理化や海外分業(シフト)も相まって、必要な従業員数は減少してきている。
一方で、個々に求められる仕事の質は、製造工程では高技術・技能化し、スタッフ機能では高度専門化が一層高まっており、この状況下で障害のある従業員を各々の持ち場、立場に配置している。
なお、障害のある従業員への作業面における配慮については、作業分析等の工夫や作業標準の整備のほか、目で理解できる実作業指導(やってみせる。やらせてみる)を徹底している。
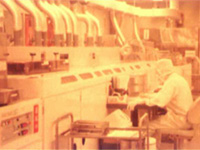

(3)労務管理
労務管理の工夫を一言で表すと、「能力を生かせる道を探る」である。障害の有無や障害状況にかかわらず、発揮される能力に見合った人事制度を適用する、つまり障害内容によって職場環境への配慮は行うが、個人を差別しないことを原則としている。
能力開発においてもOJTやOFF-JT、自己啓発を軸に、個人の主体性如何により能力開発を行い、適材適所への配置や人材活用を行っている。
なお、安全面においては、特に聴覚障害のある従業員用として、目で見える警報器(パトライト)を設置するほか、日常での安全衛生活動にも取り組んでいる。
また、従業員としての一般常識は、円滑な業務遂行のため障害の有無に関係なく遵守を従業員に強く求めている。
1)雇用管理面
ノーマライゼーションを基本に、個々の障害に応じた配慮を行っている。
①聴覚障害
朝礼時等の伝達事項の円滑化を図るため、筆談やメール(パソコン、携帯電話)、掲示板を積極的に活用するほか、ミーティングの内容を文書化して提示している。手話による会話もあるが、伝える側がゆっくり丁寧に話すように心掛けることによって、理解度が向上した。
最初は仕事の与え方等に気を遣ったが、現在は障害があることを意識しないように対応できており、周囲の従業員は自然体での声掛けを行っている。
聴覚障害のある従業員は、嘱託からスタートし正社員に登用した。職場環境面での安全確保の配慮は行っているが、業務遂行において能力や実績評価は、他の従業員と同一基準としており、障害の有無に関係なく確実にキャリアアップが図られている。
②肢体不自由
中途障害を負った従業員について、従前の業務の継続を積極的に働きかけたところ、本人の努力もあり中途障害をバネとして国家資格を新たに取得したケースもある。このことにより職域が拡がり、現場での中心メンバーとして活躍している。
また、入社以来効率の高い業務を遂行していたが中途障害を負った従業員に対しても、従前の業務の継続を積極的に働きかけることによりモチベーションも維持され、業務遂行レベルが以前にも増して高まった感がある。
③内部障害
荷重労働は避けるよう配慮している。受障前に習得した知識や技能の経験を活かす職務に配置し、月2回程度の定期検診を優先させている。
2)設備・職場環境
障害のある従業員が安全で快適に職業生活が送れるよう、基本的な部分での整備を心掛けている。
①段差を避けて円滑に移動できるよう、スロープを設置
②移動による負担を軽減するため、建物まで最も近い場所に駐車スペースを設置
③全ての階段に手すりを設置
④機械の状態が一目でわかるよう、パトライトを設置
⑤移動の負担を軽減するため、障害者用のトイレを職場の近くに設置
⑥スポーツへの取り組みを支援するためのトレーニング設備を設置
(障害のある従業員においては各種の大会で優秀な成績を納めている)






3)メンタルヘルス体制の整備
昨今の社会環境および企業を取り巻く厳しい環境の中では、健康管理面は従業員や事業所にとって重要な課題となってきている。また、中途障害を負った従業員などにおいては、不安や悩みによるモチベーションの低下は非常に大きな問題となるため、メンタルヘルスへの取り組みは、円滑な障害者雇用の継続には必要不可欠である。
メンタルヘルスについては、昨今ようやく注目され、行政サイドの推進もあり加速感を伴いつつも実際には試行錯誤で取り組まれつつあるのが今日の趨勢である中、当工場では平成15年から本格的に取り組み、メンタルヘルス体制を体系的に運営しているが、この体制作りのプロセスにおいて、管理職を中心としたラインケアのための研修と従業員個々を対象にしたセルフケアの研修を2年間かけて行い、厳しい環境の中でも、元気にはつらつと個人の持てる力を最大限に引き出し、発揮できる土壌をさらに耕すことができた。
(4)障害者雇用助成金等の活用
障害者雇用に際しては特定求職者雇用開発助成金を活用した。今後については、必要に応じて障害者職業センターでの相談やジョブコーチ、また手話通訳の活用等を検討している。
4. 取り組みの効果
(1)職場の雰囲気の改善
昨今様々な観点から事業所に対し、コンプライアンス(遵法)が要求されているが、創業以来“個の尊重と社会貢献”の考え方を取り入れている当社においては、義務感や受動的ではなく、自然かつ能動的に行動できる土壌が形成されている。
当社は、企業のあり方の理念の一つに“企業は道場である”と考えている。道場とは道を修める場である。社会における一人の人間として、会社の一員として、育て上げる使命が企業にはあり、同時に己を磨く場所である。常に事業所も個人も切磋琢磨し続けられる関係でありたいと考えている。
(2)職場の活性化、モチベーション等の向上
公平公正な評価プロセスの運用に加え、職場での情報や課題から実績(業績達成)の喜びまで共有化を図ることにより、仕事への参画意識、仕事感の醸成が認められる。
精皆勤継続について事業本部長表彰を受けた従業員もいる。
(3)生産性の改善
作業標準の整備や作業分析等の工夫等により、生産性の向上につながっている。
例えば、聴覚障害のある従業員に対して目に見える管理を徹底することにより、全ての従業員にとっても把握可能であり、また、スロープや専用トイレの設置など安全で快適な職場環境作りは、高年齢者や女性にとっても作業効率を向上することになり、職場全体を働きやすい環境にすることにつながっている。
5. 今後の課題等
(1)課題
当工場は、今後の厳しい経営環境に対応していくためにも高付加価値、高効率運営が、また特に製造工程では連続操業体制の継続のための高度の技術や技能が、スタッフ機能ではより高度な専門性が求められることとなる。
一方で、実態としては、従業員の平均年齢の高齢化と、高齢法対応による継続雇用制度の運用といった課題がある。これは今後の様々な施策策定の根源となる理念を大きく左右ものである。加えて、障害のある従業員を含めた全従業員個々のライフスタイルや価値観の変容への対応にも迫られる難しい課題があり、人事制度、労務管理(勤務体制の検討)、安全・健康管理体制等、総合的な視点とアプローチが必要になってくる。
事業所・個人・社会との共生を目指す有機的な人事制度の探索と構築は、終わりのない課題かと思われるが、創造的かつ発展的な“個の尊重”の理念がある限り、活路は見出せるものと信じ、取り組んでいく意向である。
(2)さいごに
「今回あらためて気づくことは、労務管理の工夫の真髄には、創業の精神として、社是に『創造によって文化、産業に貢献する』を抱き、その理念が事業は勿論のこと、社会貢献活動や環境活動にもストレートに反映されているというところにあります。“個の尊重と社会貢献”のDNA(遺伝子)を継承し、個の尊重と自己責任・個人の自律に向けて個人と会社が共生する土壌作りを継続的に行っていくことが大切なのだと再認識しました。」とは話す。
また、障害のある従業員は「張り合いがあって働いています。必要とされているのが嬉しい。」と感想を話す。
当社の障害者雇用の取り組みは、事業所全体の労務管理を考えなければ決して実りあるものにはならない。言い換えると、事業所全体として“個の尊重と社会貢献”を基本とする労務管理を目指し工夫・改善することが、障害者雇用の充実につながっている。
経営理念に基づく人材活用がしっかりと根付いている当社は、今後も意欲的に障害者雇用を含めた労務管理全体の工夫・改善に取り組んでいく意向である。

アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











