一人の知的障害者雇用の取り組み成果を、次の障害者雇用に繋げる
- 事業所名
- 株式会社サンデーサン
- 所在地
- 山口県周南市
- 事業内容
- 各種レストランのナショナルチェーン展開と経営
- 従業員数
- 1,176名
- うち障害者数
- 25名
障害 人数 従事業務 視覚障害 1 事務管理 聴覚障害 0 肢体不自由 1 調理補助 内部障害 5 店長、事務管理、課長、仕入購買、工場内作業 知的障害 18 工場での出荷補助、店舗での調理補助 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の概要
山口県周南市に本社を置く当社は、昭和46年に第1号店を周南市内に開店以来、35年間で全国に334店舗を構える規模を有するに至った。
設立当初は、幅広い世代のニーズに応じることのできるファミリーレストランとしての経営が進められていたが、その後の時代の変遷の中、消費者の嗜好の変化や各世代の味覚のニーズに柔軟に応じるため、現在では数多くの種類の店舗を全国に展開しつつある。イタリア料理を提供する「ジョリーパスタ」や「フラカッソ」、ステーキやハンバーグ専門店の「ジョリーオックス」などは、若い世代からも支持も受け、その躍進がめざましい。
2. 障害者雇用の経緯
障害者法定雇用率が1.6%から1.8%に上げられ、障害者雇用が企業の社会的責任として強く認識され始めるとともに、企業に対する行政指導も活発となり、当社にも公共職業安定所から訪問指導を受けた背景から、平成11年から障害者雇用に積極的に取り組み始めた。
神代信孝人事チームリーダーは、平成11年当時を次のように振り返る。
「障害者の仕事を会社内に探すのではなく、障害者が仕事をする場所を会社内につくるのですよ、と職安の方からアドバイスをいただきました。私はそのとき、障害のある人を隔離するような職場ではなく、一緒に働くことのできる会社にする必要性を感じました。当社の店舗は全国にたくさんあるのですから、まず山口県内で1店舗1名の障害者の受け入れができるなら、と想像は膨らみました。」
当時の管理本部長の前向きな理解もあり、企業の社会的責任としての障害者雇用の取り組みに、当社は力を入れることとなった。
3. 製造工場における取り組み
(1)徹底した衛生管理
全国334店舗で使用するソース、スープ、ドレッシング類を製造する、本社敷地内の工場では、入室者は全員、工場入口で衛生管理用の白衣と帽子を着用後、風力機で白ゴム長靴を洗浄、毛髪除去ローラーで埃などを入念に除去し、自動手指消毒器で手指を洗浄する。その後、別室でエアシャワーを全身に浴び、ようやく工場内へ入室する。
工場には知的障害のある従業員を2名配置しているが、衛生的で安全な食品を製造することが顧客からの信用と収益につながるため、彼らを含め従業員全員に対し、衛生管理の指導を徹底している。

(2)知的障害者雇用の状況
1)Aさん
私立高校を卒業した中軽度の知的障害のあるAさんは、現在週30~40時間勤務のパート職員として雇用され、自宅から電車を2本乗り継いで通勤している。
Aさんは、工場ラインから出てきたソースや野菜スープ類の袋を手で取り上げ、セイロ様のチルドコンテナに並べる作業に主に従事している。チルドコンテナが袋で満たされると台車の上に24段積み上げ、冷凍庫に運び込む。24段の高さを既に勘でつかんでいるAさんのムラのない作業は、スピード感にあふれている。




Aさんを採用した理由について、神代人事チームリーダーは、「採用を決める面接の時、Aさんには大きな声と明るい笑顔がありました。これが採用決定の一番大きな理由でした」と話す。
他の従業員と円滑な関係を築くことは作業効率が上がることにもつながるため、従業員一人ひとりの明朗さは職場に不可欠な要素である。なお、Aさんは、勤労を通した規則的な生活習慣によって心身が鍛えられ、いたって健康である。
2)Bさん
養護学校を卒業した中軽度の知的障害のあるBさんは、半年間の職場適応訓練を実施した後、Aさん同様、週30~40時間勤務のパート職員として雇用され、自宅から電車で通勤している。
Bさんは、①折りたたまれた状態の段ボール紙を箱に組み立てる、②箱をローラーに乗せて送る、③箱に冷凍されたソースや野菜スープ類の袋を詰める、④詰め終えた箱をローラーに乗せて送る、⑤箱に封をする、⑥箱を運搬用パレットの上に積み上げる、といった一連の作業プロセスを手慣れた迅速さで作業を進めている。



気持ちのよい挨拶ができ、まじめに仕事に取り組むBさんは、退社後に家族のために夕食の材料を買って帰宅している。BさんもAさん同様、当社は高く評価している。
(3)知的障害に対する指導
1)指導マニュアルの作成
AさんとBさんを雇用するにあたって、工場では作業工程毎に具体的な作業内容を段階を追って記載したB4サイズ1枚の指導マニュアルを個別に作成した。また指導マニュアルは、毎日の作業習熟状況も記載することができる。なお、現在では二人とも作業に十分習熟し、このマニュアルは現在活用されていない。
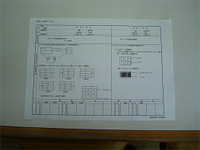
2)連絡ノートの活用
家庭との情報交換のために連絡ノートを活用している。2人は出社時にこのノートをそれぞれのレターケース内に提出する。忘れ物や体調などについて特筆すべき事柄があれば、現場責任者がノートに記入し、これを2人は持ち帰り、家庭でその日の情報を見てもらう。なお、現在では2人とも就労生活を支障なく送りつつあり、記入される特記事項は減少している。
文字を介した連絡は地道な根気が必要とされるが、この取り組みを継続することによって、職場に対する家庭の信頼を高め、ひいては従業員の安定就労を支えるベースになることが期待できる。

3)変動の少ない従業員体制
職場の人間関係は、作業意欲や作業能率などに大きく影響する。工場で2人をよく知る46人のパート職員の多くは女性であるが、勤務時間が柔軟に対応できることにより職場定着状況は良好であり人事異動が少ないため、2人と長く接し続けることのできる職場環境が、彼らの安心感につながり継続雇用を促している。
4)通勤時の配慮
電車を使って自力で通勤している2人に対して、台風等により天候が極めて悪化した時などは、上司が車で最寄りの駅まで送っているこのような配慮の積み重ねがお互いの心の絆をつくっている。
5)時給アップの可能性
AさんBさんとも、現時点ではパート職員であるが、今後の勤務に応じて時給アップの道が開かれている。
4. 店舗の厨房における取り組み
(1)身体障害者雇用の状況
イタリア料理店ジョリーパスタ山口店では、身体障害のあるCさんを厨房に配置している。
17歳の時、交通事故で右手の機能を失い身体障害者手帳2級を取得したCさんは、別事業所で勤務した後、公共職業安定所の合同面接会に参加、当店舗が週30~40時間勤務のパート職員として雇用され、自宅から自家用車で通勤している。
Cさんにはピザ、ドリア、グラタンなど、オーブン機器を使ったイタリア料理全般を任せている。ピザづくりでは、まず生地を丸く伸ばし、チーズなどの具材を乗せ、背後のオーブンに入れ、タイマーを設定し、スイッチを入れ、数分後にオーブンから引き出されたピザの上にさらに具材を乗せ、完成させる。これら一連の作業を、Cさんは左手のみで迅速に進める。グラタンなどの料理の迅速さについても同様である。
料理の知識や技術は、全て雇用後の研修で習得してもらったが、Cさんは新入社員教育も担当し、料理や接客の仕方はもとより、社会人としての心得の指導にもあたっている。当店舗のCさんに対する期待は大きい。




店舗内で高い実力を発揮するCさんに対し、上司は他の従業員と同様に接している。
山本裕一店長は、Cさんについて次のように語る。「私にとって障害のある人と一緒に働くのは、Cさんが初めてなのですが、Cさんの明るさ、責任感の強さ、人一倍働く姿に感銘を受けています。これからも、Cさんに長く働き続けてほしいですね。」
なお、当社には、「キャストストアマネージャー」という「パート職員の立場での店長」を意味する役職である。こうした昇進の道を用意することにより、障害のある従業員にとっても、そのチャレンジ精神が鼓舞されることが期待できる。
(2)知的障害者雇用の状況
イタリア料理中心のフラカッソ防府店では、中軽度の知的障害のあるDさんとEさんの2人を厨房に配置している。1店舗につき障害者1名雇用という原則だが、末嶋和則店長の理解によって2人を雇用した。

1)Dさん
高校を卒業したDさんは、公共職業安定所の紹介により、週30~40時間勤務のパート職員として雇用され、自宅から自転車で通勤している。
雇用当初はジョブコーチ支援を受け、他の従業員と変わらぬ作業をこなすまでになった約3年前から、時給を一般従業員と同額に昇給した。
Dさんの作業内容については、原材料や食器類の洗浄から調理までの一通りをこなしている。当店舗では調理メニューが70~80種類あり、しかも季節に応じたメニュー改正が年2回ある。Dさんはこれら全ての調理手順を正しく習得するため、当初はこまめにメモをとり、わからないところについては周囲の従業員に質問しながら覚える努力を続け、現在、末嶋店長は全幅の信頼をよせている。

2)Eさん
養護学校高等部在籍時に当店舗で職場実習を行ったことがきっかけで、卒業後、週30~40時間勤務のパート職員として雇用されたEさんは、自宅から徒歩で通勤している。
Eさんの作業内容は、当初は原材料や食器類の洗浄が中心であったが、末嶋店長の判断により、調理に取り組み始め、現在、折にふれてジョブコーチ支援を受けている。
末嶋店長は、「Eさんは、挨拶がとてもきちんとできる男性です。職場実習で出会った時にもそのように感じました。従業員は皆、彼を見習うべきだと私は思っています。」とEさんについて語る。

3)知的障害に対する支援
Eさんの調理への取り組みにあたっては、本人に緊張やとまどいが生じるため、周囲の従業員が、その日の様子や課題として見えてきたこと等を手帳に記すこととした。この手帳をEさんが家庭に持ち帰ることで、家族はその情報を共有するとともに、Eさんの思いに共感し支援することができる。このように手帳のやりとりは、Eさんの情緒面の安定に大切な役割を担っている。
また、業務内容変更の構想については、店長が事前にEさんの保護者と相談を密にすることで本人への適切な対応を心がけた。
なお、調理のオーダーが次々に入る時間帯では、厨房内は大変慌ただしくなり、DさんからのEさんへの語りかけや態度が厳しくなることがあるため、2人が互いにうまく関われるようになるための対応を現在検討している。
末嶋店長は、「Eさんには調理の仕事に挑戦させているところですが、この仕事をやり遂げられるようになってほしいと期待しています。従業員同士が互いの力を認め合えるようになることが、解決への道のひとつになると思うからです」と話す。
5. 今後の課題・展望
現在の厳しい経済事情において全国の事業所は独自の営業戦略を打ち立て、未来を切り開いていかねばならない状況のなか、当社は障害者雇用を今後も推進していく意向である。
例えば、山口県内の店舗を中心に障害者雇用を円滑に展開させるため、山口県雇用開発協会が主催する障害者職業生活相談員資格認定講習会を複数の店長が受講している。
神代人事チームリーダー、山本店長、末嶋店長はともに、障害者雇用について次のように話す。
「障害のある従業員と接するようになってから、周囲の従業員がこれまで以上にやさしくなり、気配りするようになりました。このことが、店舗での接客の場で発揮されています。また、障害のある従業員が私たちにしてくれる元気な挨拶については、私たちのほうが見習わねばなりません。」
障害者雇用を通してサービスの原点に立ち戻ることができた、と考えている。
当社が障害者雇用を推進することで、障害のある従業員とともに働く経験により彼らの働く力を正しく理解する店長が増え、今後、全国の店舗に配属することで、さらに障害者雇用が展開し、アメニティ(快適さ)あふれる店舗が増えることが期待できる。
当社は、障害者の「働きたい」という熱い願いを叶えることを通し、企業の社会的責任を果たしつつ、アメニティを創造すると同時に業績も上げていく企業経営を今日も続けている。
松田 信夫
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











