定着の秘訣はない。けれど、定着の事実の重みがある。

1.事業所の概要
(1)たすけあいの精神と「笑顔の種」
生活協同組合コープしがは1993(平成5)年3月、県内4つの生協が合併し設立された。その後、全国的な流れを受けて1998(平成10)年6月には個配事業をスタート、共同購入を利用しにくい方の声に応える仕組みづくりを進めている。
また、2006(平成18)年10月には、独自事業として福祉ネットワークセンター「ゆめふうせん」を開設し、ささえあいサポートとして組合員の暮らしのなかでのちょっとした困りごとをサポートしている。もちろん専門的な知識や経験をもつスタッフ(=コーディネーター)も在籍しているが、あくまで基本は組合員どうしの助け合い活動(有償ボランティア)にあり、サポートをする側(事前にサポーター登録を行う)も受ける側もともに組合員およびその家族が対象となる。日々の暮らしの中で「困った」ことがあれば、まずは電話。たとえば、こんなこと……
【コール1】
子どもの具合が悪いんだけれど、小児科や耳鼻科って混んでいるから大変! 診察の順番取りをお願いできないかしら?
【コール2】
出産後、実家が遠いので里帰りも難しい。体力が回復するまで、家事などを手伝ってくれる方はいないかしら?
こうした助け合いの精神は福祉の分野だけでなく、障害者の雇用に際しても理念として、さらには自然なかたちでのサポートとして結実している。何よりも変化する時代のなかで、地域のニーズ、そして組合員一人ひとりのニーズに沿って「笑顔の種」を届けていきたい。
(2)理念から事業へ
協同組合は、共通の経済的・社会的・文化的ニーズと願いを満たすために自発的に手を結んだ人々の自治的な組織であり、自助・自己責任・民主主義・平等・公正、そして連帯の価値を基礎とする。これは原則であるが、そこに盛り込まれた価値を実践に移すために各種の事業を展開している。
もちろん障害者雇用は事業ではないが、雇用あるいは定着を進める上で、こうした理念が効用を及ぼしていることは疑うまでもない。
ただ、理念に代表される原則と情勢が変化する現実との間に矛盾というか齟齬が生じる場合もある。その時は原則に立ち返りつつ、けっして固執はせず、いかに現実に対応できるか。その柔軟で漸次的な姿勢がこれまでの/これからの障害者雇用を支えてきた/支えていく土壌であり、裾野の広がりではないだろうか。
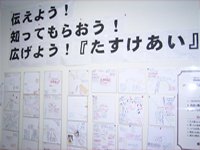
2.障害者雇用の経緯
(1)過去の事情よりも現在の姿が語るもの
合併により設立されたという経緯もあり、当初は新規での採用ではなく、すでに雇用されていた人を継続して雇用することのウェイトが大きかった。その時点において、障害者雇用の経験があったかと訊ねられれば、おそらく経験として語ることができるほどのことはなかったであろう。しかしながら、採用年月(表1参照)からみれば、1993年の合併以前に採用し現在に至っている人が6名いる(肢体不自由3名、体幹機能障害1名、知的障害2名)。なかには中途で障害者手帳を取得した人もいるが、みな勤続年数は長い(最長は32年、最短は15年)。
この事実が、障害者雇用について語るべきことをやんわりと教えてくれているのかもしれない。つまり、定着の事実の重みということである。定着とは安定した就労と言い換えることもでき、何よりも仕事をする上で安定ということは大きな前提となることがらでもある。安定は安心につながり、安心は安定へつながり戻り循環を形づくる。確かにホッとする空気が流れているのかもしれない。その目には見えない安心感を再認識する意味でも、2007(平成19)年、「障害者雇用優良事業所労働大臣表彰」を受賞できたことに深い意義を感じている。
(2)障害者の雇用状況
コープしがには、障害のある人が9名働いている(うち1名は短時間の知的障害者)。
従業員のうち法定雇用率の分母になる常用雇用労働者数は379名で、2007年6月時点での雇用率は2.63%となっている。
これら9名のうち、身体障害者が4名、知的障害者が4名、精神障害者が1名であり、その具体的な雇用の状況は表1のとおりである。
先にも述べたように勤続年数を見てみると、それぞれが自分の経験を踏まえて仕事をしていくには十分な時間が経過してもいる。しかし、それは単に時間だけの問題ではなく、それぞれの人にとってのやりがいの「効用」ということもあるのではないか。もちろん、それは「誰かがやらなあかん仕事」としての「責任」が伴うことではあるが。
表1 障害者の個別雇用状況(2007年5月1日現在)
|
3.取り組みの内容
(1)基本としていること
1)「ありがとう」の関係
安定した就労のためには、「あるべき仕事(作業)」が何よりも大切であると考えている。そうであれば結果として、仕事のやりがいへとつながり、「ありがとう」の関係が自然とでき上がってくるのではないだろうか。本人と周りの人とが互いに「ありがとう」を言い合える環境づくり。それは、むりやり仕事を作り出すことからは生まれない。同じ場所で、同じ仕事を、同じやりがいをもってすることができる、それはいわば協同(共同)の精神であり、生活協同組合の理念が具現化された姿でもある。
2)それぞれの事情と適性
人それぞれに事情があり、働きたい(働くことのできる)時間も人によってさまざまである。そうしたさまざまな事情が障害の故に生じることであれば、できる限りその事情が仕事の支障とならないように配慮、応えていく必要がある。もちろん、本人の能力(職業能力)と適性については随時把握しながらではあるが。
たとえば雇用形態としては正規職員、嘱託、パート等があるが、ここでいう嘱託とは全体のなかでははかることのできない特別な事情をかかえていたり、ある種特別な能力を発揮している人を含めて考えている。当然、賃金は本人の能力をみて決定し、ベースアップもあれば一時金も支給している。また、勤務時間は週30時間以上とし、一日6時間、あるいは7.5時間と、ある程度フレキシブルなものとしている。
たとえ雇用形態が違っても、「誰かがやらなあかん仕事」を誰かが/誰もがしているとの実感がある。
(2)店舗での仕事
現在、中核的な店舗で2名の障害者が働いている。ここでは、より長く仕事をしている重度知的障害者の仕事ぶりを簡単に述べる。
まず、一般的な雇用管理の観点から重度の知的障害と軽度の知的障害を比較すれば、後者のほうが業務を遂行する上では困難なことが少ないだろうと考えられる。しかしながらそれはあくまで一般的なことがらであって、個別の要素の重なりあいにおいてどう変わっても不思議ではない。
仕事は各種商品の陳列・補充(雑貨・菓子・食品等定番ドライ商品)だが、午前と午後では扱う棚が変わり、商品の置き場所をしっかりと把握していることが業務の上では大前提となる。午前はパートが休んでいる棚の陳列を、午後は定番ドライ商品棚全般の陳列を担当している。しばしばお客さんからの問い合わせに戸惑ってしまい十分に対応できないこともあるが、その時は周囲の誰かに話を伝えるようにと言っている。過去にはトラブルがなかったこともないが、お客さんは組合員でもあり、比較的理解を得やすい環境ではある。
現在、彼女が休むと周囲の誰かが残業しなければいけないほど、彼女が担当している仕事は「やりきらなあかん仕事」であり、「責任」ある仕事である。でも、「責任」が過剰なプレッシャーになり、ストレスを抱え込まないように過大なことは求めないようにしている。そのためにも日常的な声掛けと一緒に働いているパートさんからの情報は大切なものだ。
共通の認識として、彼女には常に何を優先して仕事をするのかが分かるようにしている。一日の段取りとしては①休んでいるパートの担当分、②午前中のみのパートからの頼みごと、③棚全体の補充、と優先順位の高い仕事から始め、もちろん優先順位の高い仕事についてはやり終えることが前提でもある。
一日のなかで、1週間のなかで、そして1年のなかで、繰り返される仕事。そのそれぞれの時間の幅のなかで「頼み」-「引き受ける」関係が成り立つこと。それは別様に言えば、同じ場所、同じ仕事、同じやりがい=協同(共同)の精神の具現化でもある。

(3)配送センターでの仕事
現在、共同購入センター(商品の配送センター)は県内に10か所ある。そこでは配送業務と倉庫業務が中心になるが、うち障害者が仕事をしているのは倉庫業務であり、4名の障害者が働いている。
仕事の内容は、商品の仕分け作業・倉庫整理が主であり、障害の種別であったり、不自由さの程度によって、あるいは経験の年数等により求めることは変わってくる。ここでは共同購入センターで働く1名の知的障害者を紹介する。
まず、単に倉庫業務といっても、基幹的な仕事と補助的な仕事がある(もちろん、ともに「誰かがやらなあかん仕事」である)。たとえば段ボール整理の仕事ならば、もしミスがあったとしても事後的な修正はできる。しかし、積荷の商品の配置を間違えば、そのままトラックに積み込まれてしまい、「届けるべき場所」に「届けるべき商品」を届けることができなくなるかもしれない。つまり、事後的な修正ができないことはないが、修正するとなるとかなりの負担と労力が求められる。これが基幹的な仕事と補助的な仕事の違いでもある。
だからこそ、長い目で仕事の習熟を見極める必要がある。もちろん一緒に仕事をすることを通じてである。仕事の変化という面をとらえれば、補助的な仕事は変化に対して少ないレクチャーで可能となり、基幹的な仕事は変化に対してより多くのレクチャーが必要となる。いずれにしても仕事上での成長は環境に左右されると考えている。リーダーをはじめとした同僚のサポート、目には付きにくい細かい支援の有無などナチュラル・サポートの意味合いはとても大きなものがある。


そうしたサポートが可能になったのは、職場の共通した理解とともに本人の働きぶり(意欲を含め)に負うところが大きい。
現在担当している仕事はドライ商品の前出し作業で、トラックの配送の都合から午前中は忙しさが際立っている(一日のなかで午前11時30分までがピークである)。商品の配送は、まずは物流センターである程度区分けし、その後配送センターで配送ルートに従った位置に順番に並べる。まさに、この配送ルートに従った位置と順番にきちんと並べることが求められる仕事でもある。
この作業を担当する本人は、仕事のなかでしんどい事と楽しい事について、「しんどいのは火曜日から木曜日までは夕配の積み込みがあるし(つまり忙しさのピークが2度あるということ)、楽しいのは金曜日の午後の作業(ホッチキス留め)です(自分のペースでできる仕事でもある)」
傍ではセンター長が「そやな~」とうなずきながら彼女の言葉を聞いていた。「責任とプレッシャーは紙一重ですから。バランスが大事です」。センター長の言葉である。
(4)事務の仕事
職場では人やモノが動けば、前にも後にも事務仕事が生じる。電話もかかってくれば、注文を受け付けたら伝票を起こし、時間がある時はデータの入力や書類の整理もしなければいけない。
現在2名の障害者が事務仕事を担当しているが、障害故の不自由さの程度はそれぞれである。誰でもできること/できないことがあり、障害故の困難さは工夫や改善でどうにかできることもあれば、一方ではどうにもできないこともある。これまでしていた仕事が過剰な負担を強いるものとなれば、結果として、仕事は別の仕事に取ってかわらざるを得ないだろう。けれど、考えようによっては別の仕事なら十分にやれるのである。それは職場での存在価値であり(につながり)、役割を担っている/担ってもらっているという関係をつくりだす。そして、その先に目指すべきこととしては、より仕事がしやすいように自分から発信していくことが大切である。そうした積極性は仕事での積極性にもつながる。
事務所内には数名のスタッフがいるため、電話の呼び出し音が鳴れば誰かが受話器をとる。もちろん誰がとってもいいわけだが、これまでの経験が電話応対に活かすことができるのであれば障害の有無に関係なく遠慮することはなにもない。
電話の内容は定型的なものから、個別的なものまでさまざまであるが、経験は「何を、せなあかん」という判断を可能にする。発揮された経験は周囲に「頼り」とされ、コミュニケーションが生まれる。それは「責任」と「安心」のコミュニケーションでもある。

4.まとめ・今後の課題
しばしば言われることであるが、「効率」の功罪というものがある。そのことは障害者雇用を進める上でも無視できるものではない。障害者雇用が企業活動にもたらす影響については、「第14回職業リハビリテーション研究発表会論文集」でも述べられているが、プラスと思われる影響もあれば、逆にマイナスと思われる影響もある。
具体的にマイナスの影響としてあげられている上位3項目を見てみると、①指導者の不足と負担増、②作業効率の低下、③従業員間の職務のアンバランス、となっている。
しかし、コープしがでは、「誰かがやらなあかん仕事」との共通した思いが醸成され、ホッとした空気が流れている。それが、すべての前提でもあるのだろう。確かに今後は、時代の趨勢もあり、「効率」ということで「作業幅の減少」や「作業精度のup」ということを一層考えていかないといけないのかもしれない。それでも「効率」の前段階にあるもの、「共同・協同」の価値が消えることはないだろう。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











