皆が働きやすい職場を目指して~在宅勤務を取り入れたフレキシブルな勤務形態への取り組み~
- 事業所名
- 有限会社奥進システム
- 所在地
- 大阪府大阪市
- 事業内容
- 業務管理システム開発(Webアプリケーション開発)
- 従業員数
- 4名
- うち障害者数
- 2名
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 2 プログラマー 内部障害 0 知的障害 0 精神障害 0 - 目次
1.事業所の概要・障害者雇用の経緯
(1)概要
当社ではインターネットが持つ可能性を最大限に活用し、お客や利用する人々が便利な社会になるように貢献していきたいと考えている。具体的にはWEBアプリケーション開発(業務管理システム)、ECサイト製作・運営、UNIX系システム開発、システムコンサルティング、WEBプロモーションなどに取り組んでいる。
【基本理念】皆が平等で、幸せな社会環境作りに尽力する
【経営理念】進取・自立・奉仕
【行 動 指 針】
・インターネット技術を活用し、社会に対し貢献できる企業を目指します。
・お客様の立場で、奥深く進んだサービスが出来る企業を目指します。
・社員、一人一人が自立する企業を目指します。
・オープンソースプロジェクトを尊重する企業を目指します。
(2)障害者雇用の経緯
基本理念にある、「皆が平等で、幸せな社会環境作りに尽力する」の中に含まれることになるが、雇用機会の少ない就労困難者(専業主婦、母子家庭、障害のある人等)のサポートを起業当初から考えていた経緯がある。
インターネット技術を活用した在宅ベースでの雇用による就業困難者のサポートの可能性を探ることからスタートしており、障害者雇用についても情報収集し、特例子会社、障害者職業訓練校、作業所などへの見学、各セミナーへの参加をすることによって当社での雇用も可能であると考えるようになった。
そして、大阪市職業リハビリテーションセンター情報処理科の見学をした縁から、訓練生の就職に向けた実習の依頼を受けることになった。当時はとても新規採用を考えられる状況ではなかったが、Fさんと出会い共に頑張ってみたいと思い、2ヶ月間、Fさんの実習の受け入れを行い、採用に至った。
約1年後、仕事の状況から新規採用を検討中のところ見学に訪れたKさんについても、採用前に1ヶ月の実習を受け入れて採用に至った。
2.取り組みの内容
(1)環境整備
大阪Officeでの受け入れにあたり、配慮した点は、バリアフリーのオフィス環境を整えた点である。
今後の受け入れを考えて、障害者作業施設設置等助成金を活用して事務所内のトイレ、スロープ、机、引き戸などの改造(入口にはスロープ、引き戸など設備を整えることによって自由にアクセスが可能となった)や電動リフト、簡易ベッドの設備も整え、体調不良時にはベッドで横になることができるようにした。また、雇用についてもトライアル雇用、特定求職者雇用開発助成金を活用した。



(2)勤務形態
現在、週3日(月、木、金)は出勤、週2日(火、水)は在宅という形態をとっている。
在宅勤務は勤務管理が難しいと言われているが、それに対する取り組みとしては、Skypeという音声通話ソフトを使って朝礼を行っている。朝礼では、「昨日の報告」、「今日の予定」、「困っている点」について各自が報告し、困っていることがあればその対策を話し合うようにしている。それに加えて各自が日報を作成して、他の人の作業状況などを確認できるようにして情報共有に取り組んでいる。
なお、情報共有の工夫や取り組み以前に、各自が責任をもって仕事をしており、お互いの信頼関係がある。逆に、一人で仕事に行き詰って悩んでいないだろうかと心配になるくらいである。大切なのは、日々お互いを思いやり、お互いが働きやすい職場環境を作ることである。そういった形でフォロー体制がしっかりしており、今はそのバランスがとても良い状況である。
3.障害のある社員の勤務状況
(1)Fさん(頚椎損傷1級)
平成18年4月にトライアル雇用を経て採用したFさんは、インターネット技術を活用しWEBシステム(業務管理システム)をPHPというプログラミング言語で開発している。
当社のメインプログラマーであり、現在までに注文管理、顧客管理、ショッピングサイト、通販システムなどの開発に携わっている。プログラミング作業だけでなく、顧客との打合わせからシステムの設計、電話でのトラブル対応に至るまでを行っている。
また、「交渉力」が高いFさんは、営業SEの様な幅広い業務も担当している。業務上の必要な環境としては、パソコン操作にトラックボールを利用、また電話対応時にヘッドフォンを使う程度である。
雇用1年目は、週1日出勤、残り4日が在宅勤務という勤務形態が中心であった。
顧客との打合わせなどには積極的に参加して業務経験を積む間、一度仕事に行き詰まり、落ち込んでしまう事態もあったが、しかし、このことをきっかけに、ミーティングを中心に、仕事の進行管理やお互いの様子を気に掛ける等の情報交換をより丁寧に行う良い雰囲気を構築することができた。
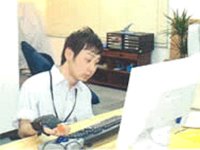
(2)Kさん(頚椎損傷1級)
平成19年5月にトライアル雇用を経て採用したKさんも、Fさん同様、インターネット技術を活用しWEBシステム(業務管理システム)をPHPというプログラミング言語で開発している。
採用して間もないが、技術力が高く、採用後すぐに1つの案件を担当して設計、プログラミング等を中心に業務を担当し、即戦力として活躍している。また、社内のパソコンやサーバーの運用管理や技術動向の移り変わりが早い業界での調査・研究なども行っている。
業務上の必要な環境としては、パソコン操作にトラックボールを利用する。
Kさんを受け入れるにあたって、今後の受け入れのことも考慮して事務所にバリアフリー環境を整えることになった。それに伴い、週3日出勤、2日在宅という勤務形態を開始した。
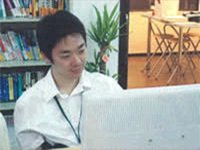

4.障害者雇用の効果・メリット
当社が掲げている基本理念「皆が平等で、幸せな社会環境作りに尽力する」が、車いすを使用している社員がいることで理解者が増えてきたことが挙げられる。以前は、なかなか当社のポリシーや目指していることが伝わり難かったが伝わりやすくなった。
経営者の中には受け入れをするためにはコストがかかると危惧する人も多いが、コストが全てではないと考える。まず組織は人と人との係わりであること、障害者雇用によって回りの人への気遣いができ、コミュニケーション、チームワークが強化され、強い組織へと成長を遂げることが可能である。実際にお互いが働きやすい環境を作ろうと考えることで、仕事にやり易さを感じられるようになった。
また、2次的効果として営業効果の向上にも繋がっている。小さいシステム会社がたくさんある中で、車いすを使っているということで印象が強く、相手に覚えてもらうことができる。顧客から、たくさんあるシステム会社の中からどこに依頼をしようかと迷った状況で印象を残せておけば選択してもらうことが可能である。
5.障害のある社員のコメント
Q1.会社の良い点について
Fさん:融通がきく、病院や体調が悪い時など、時間をずらすことが可能、在宅でもできるので働きやすい。
Kさん:やりたいと思っていた仕事なので、いつも以上に頑張れる。そして、責任感も出てくる。
小回りがきき働きやすい、自由な気風のとても風通しのよい会社です。
Q2.今後の展望について
Fさん:働く目的として、社会と関わっていたいという想いが強かったので、今後も働くことを通じて色々な人と知り合っていきたい。
Kさん:ちょっとでも微力だがみんなの役に立っていきたい。ひたすら頑張って将来的には独立もしたい。
Q3.今後、障害者雇用を考えている事業主へ一言
Kさん:特別に考えるのではなく、普通に扱ってもらえた方がうれしい。ただ、上の物を取れないことや手伝ってもらうことは必要、特別だと思って欲しくない。
Fさん:普通の人と同じ仕事をしてもらうことも可能なので、実際にふれ合ってもらって認識を持ってもらいたい。
Q4.就職を目指している方へ一言
Fさん:私は、社会とつながっていたいという想いが人一倍強く、そのためには、「絶対に就職しなければいけない」と考えました。そのため、就職につながると信じたITの勉強を、大阪市職業リハビリテーションセンターで2年間懸命に行いました。そのおかげで、今の私があります。皆さんも、ぜひ目標意識をもって頑張ってほしいと思います。
Kさん:最初は出来る事が少ないかもしれませんが、好きなことを続けていくことが大事なのではないかと思います。障害があっても世間は甘くないので、お互いに努力することを大切にしていきましょう。
※開発をとりまとめている社員のコメント
彼らは社会とつながっていたいという想いが強いためか、仕事に対する姿勢がとても熱心です。そして、今や、この職場でいなくてはならない存在です。
正直なところ、彼らを受け入れる前、何か心構えや特別な配慮等が必要なのだろうかと少し心配もしました。しかし、実際に受け入れてみますと、彼らが出来ない部分(ファイリング等)のお手伝いは必要ですが、特に障害があるから仕事上での支障があるのではと心配していたようなことはありませんでした。
6.まとめ
当社は、それぞれ持ち味が違うので、皆で協力することで、お客が求めるレベルにとどまらない仕事をしている。
障害者雇用の観点から雇用しているように見えるかも知れないが、募集時に縁のあった人がたまたま障害のある人であったというだけである。
中小企業では特例子会社のような、充実した設備、待遇、形態を整えることはできない。しかし、誰でも働いてもらおうと思ったら、相手を理解しようとするし、働きやすい環境を作ろうと取り組む。障害のある人を特別視して、その人達の聖域を作るのではなく、配慮が必要な部分を個性の一つと捉えている。
また、支援できる人が支援する職場の中の心配りが、社内の良い関係を作りあげることができる。そしてそのような部分は、障害のある人にかかわらず、誰にでもあることである。
今後、障害者雇用が特別なことではなく、職場の同僚がお互いに理解するという自然な形で進んでいくことが大切であり、就業するための環境さえ整えば、本人の持つ得意分野を発揮しITを道具として働くことが可能である。
桒田 大輔
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











