人材ビジネス業界で精神障害者を中心に障害者雇用に取り組む
- 事業所名
- 株式会社エイジェック
- 所在地
- 東京都新宿区
- 事業内容
- 人材派遣、人材紹介、業務請負などの人材ビジネス
- 従業員数
- 2,343人(雇用率の算定基礎となる労働者数)
- うち障害者数
- 37人(45人カウント)
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚・音声障害 3 文書データ化・軽作業 肢体不自由 6(1) 総務事務補助 経理事務補助 内部障害 3 営業サポート、事務全般 知的障害 12(12) 文書データ化、名刺印刷、オフィスサポート 精神障害 13(7) 文書データ化、名刺印刷、オフィスサポート ( )内は特例子会社「エイジェックフレンドリー」の内数
- 目次
1. 事業所の概要
エイジェックは人材派遣、人材紹介を中心とする人材ビジネスを手掛ける企業として2001年に創業した比較的若い企業である。現在、主力の事務部門以外に技術・建設・製造分野など多種多様な職域にも対応するとともに、人材の採用から未経験者の教育まで、多彩なプログラムで人事コンサルティングを提供し、人材派遣、アウトソーシング、人材紹介などで総合人材サービスを提供している。業容は拡大する一方であり国内拠点82か所以外に海外にも7拠点を有し、従業員数は派遣社員を中心に急増し現在7千名を上回っている。
2. 障害者雇用の経緯および特例子会社設立
(1)単体での障害者雇用の限界
一般に人材ビジネス業界では派遣社員を多数雇用することになるが、派遣先企業での障害者の受け入れは極めて少ないのが現状である。同業界では営業業務や事業所内で総務、経理など管理業務に携わる内勤従業員に障害者を受け入れるにしても、内勤従業員自体の数が限定されることから、すべての従業員に対して障害を有する従業員の割合を示す障害者雇用率が低くなる傾向にあり、障害者雇用面では深刻な問題を抱えている。エイジェックもこの例に漏れず、内勤従業員として総務、経理などの職域で身体障害者のみならず精神障害者を積極的に採用したものの法定雇用率達成の見通しが立たなかった。
(2)特例子会社設立
1) エイジェック単体では法定雇用率の達成が困難視されるため、人材ビジネス業界の大手企業が先行して取り組んでいる特例子会社における障害者雇用を検討することとなった。2006年8月に特例子会社エイジェックフレンドリー社を設立し、障害者の中でも特に一般就労が困難といわれる精神障害者と知的障害者を中心に採用し障害者雇用を推進した。精神障害者や知的障害者を雇用対象とした背景には、エイジェックがフレンドリー社設立前から本体で採用していた精神障害者や知的障害者が高い能力を発揮して事務作業に従事していた事実があり、彼らの雇用を推進することに不安を感じなかったことにある。なお特例子会社設立と同時にエイジェック本社(東京)にいた精神、知的障害者はフレンドリー社に転籍することとなったが、地方拠点にいる精神障害者はエイジェックに残留している。
フレンドリー社では、障害を持つ人々が各々の特性を活かしながら安心して働ける環境作りをモットーに、メンバーの自主自立を尊重しながら、互いに切磋琢磨を重ね、業務水準の向上と職場環境の充実に努めることを理念に掲げている。
2) エイジェックでは単に受け身で自社内の障害者雇用を推進するだけでなく、人材ビジネス業者である特徴を活かし積極的に障害者の人材紹介を事業として手掛けている。すなわちフレンドリー社設立前の2005年に障害者を職業紹介する専門の障害者就労支援事業部を設立し障害者の職業紹介を開始した。障害者就労支援事業部では、職業能力を見極めるのが困難な障害者の採用に躊躇する顧客企業が多いことから、障害者の受け入れを容易にする方策としてエイジェックが直接雇用しOJTで就労能力を高めた障害者を顧客企業に対して人材紹介、或いは紹介予定派遣(将来的には派遣先企業の直接雇用となることを前提に一定期間人材派遣するもの)する手段も講じている。
エイジェックの取り組みがユニークなのは、障害者就労支援事業と特例子会社フレンドリー社で働く障害者を結びつけたところにある。フレンドリー社の従業員の中には企業での就労に自信をつけた後に、今以上にやり甲斐があり、より良い労働条件を求めて特例子会社と異なる一般企業に転職したいとの希望を持つ者もいる。同社では彼らの希望に応じてフレンドリー社での就労状況を掌握し、一般企業での就労能力が十分にある者を見極めた上で、顧客である企業に障害者を人材紹介する考えを持っている。フレンドリー社自体が設立後間もないため未だ実績には至っていないが、就労能力を見極めた上で障害者を採用したいと考える顧客のニーズに沿ったアプローチであり今後の成果を期待したい。
3. 障害者雇用の現状
エイジェックでは本体で雇用する障害者の数は身体障害者10人と精神障害者6人の合計16人に過ぎず、障害者雇用推進の中核となっているのは精神障害者7人、知的障害者12人(療育手帳を取得する発達障害者を含む)、身体障害者(療育手帳も重複所持)1人の合計20名を雇用する特例子会社エイジェックフレンドリー社である。
フレンドリー社を含めたエイジェックの雇用率は2007年6月現在で1.92%と法定雇用率を満たしている。
フレンドリー社が雇用する障害者の採用方法、労働条件、担当業務などについて以下に述べる。
(1)募集と採用
募集はハローワークを通じて障害者手帳所持者を求人する。設立当初は中途採用が中心であったが、その後は養護学校の実習生を受け入れ、実習期間を通じて就労能力を見極めた上で新卒採用につなげるケースも出ている。
中途採用による選考では書類選考および面接によるが、特に面接選考を重視している。フレンドリー社の従業員は全員が障害者である。採用面接には精神障害の当事者でもある同社のマネジャーが同席し、面接で応募者に対する質問(例:①発症する前の状態を100%とすると今の体調は何%程度の状態ですか、②当社に入社した際には具体的に何の仕事をしたいですかなど)と応答とのやり取りを通じて精神障害などの病状の安定状況や仕事に対する意欲などを見極めている。精神障害者については自身の体調を把握でき体調の悪い時に休める人であるか否かをチェックする必要がある。
面接段階で採用の見極めが困難な場合には2週間の委託訓練を実施する。さらにトライアル雇用を通じて就労能力や病状を確認するケースもある。なお障害者の受け入れに際しては、原則として特定求職者雇用開発助成金を活用しているほか、必要に応じて作業施設設置などの助成金を申請している。
(2)労働条件
給与は時給制であるが全員が常用労働者として社会保険および労働保険にも加入している。就業時間は原則として午前9時から午後6時の1日8時間フルタイム勤務であるが、各自の体調などを判断して最短で6時間までの短時間勤務を認めている。毎年のベースアップがある他、能力評価による昇給もある。賞与、退職金についてはいまだ未整備であり今後の課題となっている。精神障害者の多くが定期的な通院を必要とすることから、2週間毎に1回の半日休暇を認めている。
障害者の年齢構成は、10歳代が3人、20代が10人、30代が4人、40代が3人となっている。独身者が多く親元から通勤しているため、月例給与に障害年金を加えた月額18万円程度でも生活できる水準にある。
(3)担当業務
フレンドリー社の業務の約85%は親会社であるエイジェック社から業務委託を受けたものであり、3つの業務をチーム制で担当している。最初に手掛けた業務は文書データ化であり親会社の紙媒体文書をドキュメントスキャナーで読み込み電子データ化するものである。各種の帳簿類・伝票から業務にかかわる記録文書までさまざまな形態の文書をデータ化処理している。
2つ目の業務は名刺印刷であり、名刺以外に封筒やポストカードなどを内製している。資材調達、工程・品質管理、検品、発送までのすべてを障害者が担っている。将来的には販促ツール、パンフレットなどの印刷業務も手掛けたい考えである。3つ目は親会社総務・経理事務受託のオフィスサポートであり、ドアを隔てて同じフロアに隣接する親会社に駐在してデータ入力、ファイリング、書類発送など多岐にわたり総務・経理事務をサポートしている。
一般に知的障害者や精神障害者の場合は軽作業に携わる職務が多いが、フレンドリー社では障害者全員がパソコンを使用して事務作業に携わっている。また新たに入社する障害者に対する教育訓練はOJTで行われ、上述の複数職務を経験させて適性に沿った職務への配属を考えている。
(4)職場環境
職場では仕事を統括管理するマネジャーや各チームのリーダーを含む全員が障害者であるが、知的障害者と精神障害者との相性が良い模様で障害種類の別をほとんど意識することなく皆が笑顔を交え会話しながら仕事を楽しんでいる様子であった。フレンドリー社で働く障害者には身体障害者(知的との重複障害者を除く)が存在せず、一般には雇用管理上ソフト面で様々な配慮が必要と考えられている精神、知的、発達障害者のみで構成されているにもかかわらず、アットホームな雰囲気には驚かされる。ストレスに弱い精神障害者にとっては周囲が全員障害者であること、また仲間同士によるピアサポートが期待できることから最適に近い職場環境になっているものと思われる。なおマネジャー及び3人のチームリーダーはいずれも精神障害者である。
障害者の中には、職務命令ではなく自発的に名刺発注の遅れている部門に対して電話で注文を取ったり、フレンドリー社が実施しているコーヒーサーバーによるコーヒー販売でも昼時間に親会社社員に積極的に売り込みをする障害者がいるとのことであった。また親会社駐在のオフィスサポート要員が、所属部門の親会社社員が不在や多忙で電話を取る者がいないときに自ら電話を取り社外のお客に応対するケースも生じている。障害特性から見れば営業活動や電話応対が困難とみられる障害者であるにもかかわらず、強制されたのではなく自発的にこのような対応をするまでに成長しているのは職場環境が優れていることの証左と言えよう。
(5)その他雇用管理
同社では障害者の雇用推進について、自社の法定雇用率達成という枠にとどまらず、「障害者の職域開拓」という視点から、メンバー個々のスキルアップ、人材紹介事業を通してのキャリアアップまでを視野に入れており、採用の段階で 「自発的な取り組みが期待される者」「社会人としての意識・責任感が認められる者」を精査して採用している。そのため雇用管理上での問題は起きにくい体質になっていると思われ、これまでのところ大きな問題に直面したことはない。また障害者の多くが地域にある就労生活支援機関のサポートを受けているため会社側では生活面に関与せずにすんでいる。過去に休みがちの障害者が出て問題が生じたケースもあったが支援機関との連携で雇用継続に成功している。
精神障害者の体調管理面に関して、主治医や産業医との間で特段連絡を密にしているわけではないが、問題発生に備えて主治医の連絡先を把握するとともに、当事者には診察券を常時携帯することを義務づけている。また常駐しているエイジェックOBの高齢者が顧問としてカウンセリングを担当しているほか、親会社でフレンドリー社を管理する女性担当者が女性障害者の個別相談にも応じている。フレンドリー社内の人には相談しにくい事柄には外部者が対応できるカウンセリング体制が構築されている。


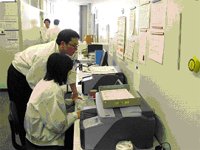

4. 今後の取り組み課題
現在エイジェックでは法定雇用率を達成しているものの今後に派遣社員の増加が予想されることから、障害者の受け入れをさらに増加し継続して法定雇用率達成することが最大の課題となる。そのためには何よりも仕事量の確保が必要である。また経営面で親会社への依存度の高い特例子会社フレンドリー社を独立採算のとれる会社に育成することも今後の課題となる。
同社では障害の種類・様態ともに多様化している現状をふまえ、障害者各自の適性に合った仕事を確保するためにエイジェック本体からフレンドリー社に受託可能な仕事を発掘することを常に心がけている。さらにグループ企業以外からも仕事を受託できないか検討を始め、エイジェック本体の社員に協力を求め顧客企業に営業をかけた結果、2007年4月頃から多種にわたる仕事を受託することに成功しており、今後にその成果の拡大を期待したい。
なおフレンドリー社の従業員からは、社外からの受注を通じて新しい仕事に挑戦することができ、さらに仕事にも幅が広がり自分の可能性を発見できたとの自信の声も聞こえている。
5. まとめ
(1)エイジェックの特徴は2006年4月から障害者雇用促進法の改正により新たに雇用率の対象となった精神障害者の雇用促進に積極的に取り組んでいることである。大都市圏、特に首都圏では新興のIT系企業を含む多くの企業が集中しており、OA事務職域や専門職域を対象とする障害者求人のニーズが高くなっている。しかしながら少子高齢化、医療技術の進歩などにより企業ニーズの高いパソコンを使える若手で軽度の身体障害者の数が少なくなっているのが現状である。軽度の身体障害者は数が限定されるだけでなく、学校を卒業する段階や、いったん就職した企業を離職し再就職先を探す段階でも障害者枠でなく一般採用枠で就職活動をするケースも多いため、雇用環境の厳しい地方都市と異なり大都市圏においては事務・専門職域での身体障害求職者は極端な供給不足に陥っている。
(2)他方、2006年4月から新たに雇用率対象となった精神障害者には、いったん就職したものの在職中の発症により離職を強いられた者で年齢的にも比較的若い層も多く、離職後に投薬、カウンセリングなどを通じて症状が緩和するとともに支援機関のサポートを受け再度就職活動をはじめた者が存在する。これらの当事者にはOA事務職、専門職の経験者も多く企業にとっては即戦力となりえる能力を有する者も存在する。
精神障害は、投薬を怠ったり過剰なストレスを受けることによって再発する恐れがある。また一定規模の企業は、うつ病を始めとする精神障害を発症し長期休職を強いられる従業員を抱えているケースが多く、雇用管理上ソフト面で様々な配慮を要する精神障害者を新規に採用することに二の足を踏む企業が多いのが現状である。しかしながら上述の通り大都市圏で働ける身体障害者が供給不足に陥っている現状では、一定期間安定して事務職域などで企業内就労を維持している精神障害者に対して、企業側が即戦力としてその採用を前向きに検討することも可能と思われる。この意味でエイジェックの取り組みは精神障害者が一般就労にステップアップするための養成機関的な存在となりえるものであり、障害者雇用施策上の緊急課題である精神障害者の一般就労への道を拡大する可能性を持つものとして、その成果を見守りたい。
執筆者:独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構東京駐在事務所障害者雇用アドバイザー 名田 敬
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











