戦力としての採用方針と職場定着のための取り組みについて
- 事業所名
- NECネクサソリューションズ株式会社
- 所在地
- 東京都港区
- 事業内容
- 情報サービス事業およびアウトソーシング事業
- 従業員数
- 2,862名
- うち障害者数
- 35名
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 10 SE、人事、購買、一般事務 肢体不自由 17 SE、営業、購買、一般事務 内部障害 7 人事、総務、経理、一般事務 知的障害 0 精神障害 1 経理 - 目次
1. 事業所の概要
当社は、平成13年4月にNECグループの情報サービス事業およびアウトソーシング事業を有する5社が統合して発足した企業である。
現在、社員数2,862名、活動拠点として、本社(東京都港区)、3支社・6支店、その他にデータセンター7ヶ所(中国上海を含む)を有する事業体である。
当社は、システムインテグレーション事業(システムのコンサルテーション、分析、設計、開発など)、プラットフォーム事業(ハードウェア、ネットワークなどの事業基盤を支える商品・サービスの提供)およびアウトソーシング事業(お客様業務の代行)の3つの事業を担っており、お客様へワンストップでトータルサービスを提供している。
また、経営理念として「いつもお客様とともに すべてはお客様の満足のために」を掲げており、お客様の満足度を常に意識し、お客様の目線で全ての物事を考えるスタンスは今や社員のDNAと言っても過言ではない。こういった成果は毎年実施される外部のCS(顧客満足)調査で常に上位を占めていることに表れている。
2. 障害者雇用の経緯、背景
当社はNECグループに属するが、NECグループは以前からグループ全体として障害者雇用に積極的に取り組んできた。
当社もNECの指導の下、当社なりに取り組んできたが、なかなか成果実績が伴わない状況が続いた。
これは、採用ノウハウの不足によるところも大きいが、採用スタンスとして次のような点を考慮した結果とも言える。
それは、「採用するということに留まらず、当社に於いて永く、納得できる仕事生活を送って欲しい」(=ご本人および受入れ職場双方が不幸にならない採用)ということである。
すなわち、採用段階に於いて、応募された方をやみくもに採用するのではなく、応募された方の特徴・特性、経験、希望などを総合的に勘案し、受入れ職場側の態勢や仕事内容も加味して弊社事業遂行の継続的な戦力となっていただける方を採用したいということである。
つまり、ご本人が定年まで活躍される、ヤル気を持続されることこそが真の障害者雇用だという観点を強く意識し、活動してきている。
このような点から、弊社の採用状況は次に示す通りに推移してきた。
| H13年 | H14年 | H15年 | H16年 | H17年 | H18年 | H19年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用率(%) | 1.56 | 1.52 | 1.45 | 1.48 | 1.66 | 1.74 | 1.84 |
尚、現在の障害内容別人員は次のとおりである。
| 肢体 | 聴覚 | 内部 | 精神 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 7 | 1 | 35 |
3. 障害者の従事業務、職場配置
現在の職種別の状況は次の通りである。
| 技術職 | 営業職 | 事務職 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 9 | 3 | 15 | 27 |
| 女性 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 計 | 11 | 3 | 21 | 35 |
先ほども述べた通り、当社の採用スタンスはご本人のスキルや人柄を重視していることおよび事業遂行の戦力となって頂く、という点から、極力職場の通常所管業務の中から、障害の内容や度合いを考慮し、適職をアサインするよう努めていることは言うまでもない。
このような観点から、現在従事している業務内容としては次のようなものが一例として挙げられる。
- SE・・・顧客案件のプロジェクト管理、客先支援、プログラミングなど
- 営業・・・提案書作成、既存ユーザーへの深耕策企画、客先訪問など
- スタッフ・・・予算策定/管理、施策企画/運用、現場支援など
- 一般事務・・・各種データ入力/管理、部門ホームページ作成、各種庶務など
この例からも分かるように、健常者と大きく異なる業務内容とはなっていない。
4. 取り組みの内容
(1)採用活動
選考時点で、可能な限り同様の障害を抱える社員と触れ合う機会を設け、具体的な働き方などをイメージして頂き、応募された方に安心感を持って頂く様努めている。
また、障害者の方が学んでいる学校とのパイプ造りやハローワークにて開催されるNECグループ合同就職面接会へも積極的に参加している。
(2)職場定着活動
受入れ職場の理解促進や職域開発を目的として、新入社員研修、新任主任/マネージャー研修や管理職研修などにて啓蒙教育を実施しているほか、社内ウエッブ上にて全社員に対しても人権教育を実施している。
これとは別に、障害者が配属されている職場上司に対しては、年1回程度勉強会を実施し、東京障害者職業センターのカウンセラーなどによる講義や情報交換、意見交換を行っている。
こういった取り組みは、それぞれの職場で抱える問題などの解決に一役買っているのみならず、気づきや反省を通して、障害者の立場に立った社内環境の整備・向上にも結びついている。(EX.聴覚障害者に対して、社内放送の内容をEメールにて配信したり、連絡用携帯電話の貸与、全社行事での手話通訳対応などを実行)


また、年2回程度、本人及び職場上司とのヒアリングを実施し、課題や不安/不満の解決に役立てている。
尚、聴覚障害社員が企画し運営しているものとして、手話サークルがある。このサークルは「シュワちゃんの会」と命名され、聴覚障害社員が講師となり、月2回の手話勉強会を行なったり、各職場にて昼休みに10分程度の手話講座を行なったりして、健常者とのコミュニケーション向上に大いに役立っている。

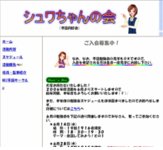
5. 取り組みの効果
前述の取り組みを実行したことにより、受入れ職場の課題解決促進が図られたことは言うまでもないが、それよりも職場の理解が進み、障害者を受け入れる空気が従前に比べて格段に良くなったことが大きい。
また、障害者も事業遂行の戦力であることから、結果として働き易い職場・企業環境の創造にもつながったことも大きいと言える。
この他、企業としての活動成果によるものとは必ずしも言えないが、社員が東京都障害者雇用促進協会から「優秀勤労障害者」、その他表彰を受けるなどの栄誉に浴することができた。
しかしながら、障害者の雇用・定着に向けて、課題がまだまだ数多く存在しているのも事実である。
一つは、受入れの空気は広がっているものの、職場によってはまだまだ濃淡がはっきりしており、啓蒙機会とその内容の工夫は大きな課題として残る。
また、ご本人の担当している仕事の変更や、職場上司が変わった際の対応については、より丁寧な対応が必要であると考える。
これらの解決には、更なる工夫と一定の時間が必要とは考えるが、当社は次の観点が土台にあるものと認識している。
①ダイバーシティの視点
これは多様化する価値・サービス需要に対応するためにも、障害を抱える方だけでなく、これまで以上に女性や高齢者・外国人の活躍機会の創出など、これまでのあり方・価値観を再度見直し、多様性を受け入れる企業風土/文化を造り上げなければ、今後弊社の発展はあり得ないのではないか、という考え方である。
このことにより、様々な事情を持っている方々の活躍の場が広がり、絶え間ない成長につながっていくものと確信している。
②職場主体の受入れ環境づくり
「障害者雇用は人事部がやるもの」という意識を払拭し、「良き人材を受け入れ、職場の成長につなげていく」という意識に完全に変革させていきたい。
職場理解が進んだとしても、戦力として位置づけられなければ、本人のモチベーションダウンは必至であるし、本人の甘えにもつながりかねない。
③ナレッジの活用
ITを提供する当社に於いては、社内ITツールを最大限に活用し、障害者および職場関係者がともにナレッジを共有し、様々な課題解決への有効ツールとして活用できれば、これまで以上に障害者雇用に対する理解促進が進むものと確信している。
最後に、昨年やっと法定雇用率に達したばかりではあるが、創意と工夫により、世間から障害者雇用の面に於いてもエクセレントカンパニーとして認知頂ける存在になれるよう今後も努力していく所存である。
執筆者 : NECネクサソリューションズ株式会社 人事部人事マネージャー
石田 俊浩
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











