トップの一言でゼロからすすめた障害者雇用
- 事業所名
- 株式会社アリエ富士宮工場
- 所在地
- 静岡県富士宮市
- 事業内容
- 化粧品の製造
- 従業員数
- 246名
- うち障害者数
- 12名
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 1 包装仕上げ作業 内部障害 0 知的障害 11 包装仕上げ作業、清掃作業、資材搬入・整理作業 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の概要
本部を横浜に置く化粧品のOEMメーカー。富士宮工場は、富士山麓に湧き出す清冽な水と澄んだ空気に囲まれて良質な製品を生み出す環境に恵まれている。
障害者の職場配置とも関連するが、この事業所の「主張」は高度の品質管理と環境の維持、改善である。業界初のISO9002をはじめ、9001、14001の認証を取得している。
このため厳格な品質管理、環境改善の目標を確保することが必須なのである。
ここの事業所の障害者雇用の始まりは、取引先化粧品会社にある障害者の製造ラインを実際に見た社長が、「当社でも製造ラインを計画せよ」というその一言であるという。
今から8年ほど前のことで、1988年10月に新設された比較的新しい工場とはいえ、それが障害者雇用のスタートで、200人を越える企業でありながら障害者雇用の経験は全く無かった。
ISO基準に基づく有資格者の配置が会社のルールであるため、現在は障害者だけの製造ラインの構築には至っていないが、障害者の雇用は毎年続けられて製品包装仕上げ工程の各部署に配置され、現在7年以上の就業者が5名、3年以上が4名と、確実に定着化がすすみ、業務上欠かせない戦力として活躍をしている。
ゼロからスタートをして、欠かせない人材として育ててきた企業のスタンスといくつかの取組事例をランダムな視点で紹介する。


2. 取り組みの内容
●採用基準
ここ数年、静岡県立あしたか職業訓練校の訓練を経て入社のケースが多い。一年間の作業訓練、ジョブコーチの助言、3ヶ月のトライアル雇用で採用しており、現在はこの制度を利用した採用がほぼ定着している。みんな挨拶や礼儀、コミュニケーションの基礎が出来ており社会生活への適応が早い。
採用にあたっては、バス、自転車、徒歩等自分で往復通勤が出来ることを必須条件にしている。親の送迎は不可。仕事の能力より、「人と交わって何かをしてみたい」という意欲と、なにより「自立」を重視している。
●作業指導、生活指導、日報、月報、年間評価
経験豊富なベテラン生活指導員の2名が、本人、両親・家族との相談にあたり、所属現場責任者とも連携して日常的に障害者へのフォローを行っている。
トライアル中は毎日「日報」を交換してきた。業務のためというより、「生活記録日誌」の表題どおり、一日の起床から就寝までの出来事・感想記録で、毎日の目標や健康状態のチェック、家庭生活での整理整頓、家事手伝いの様子が書き込まれる。トライアルが終了するまでの健康状態の把握と、「普段の生活の確立こそ職業人の第一歩」と考え、担当者、保護者が連携して自立を支援していく大事な役割を担っている。
「月報」は障害者が配置されている現場ごとに全員分が定期的に作成されている。健康状態や家庭生活の問題点など、家庭や本人との話合いの結果なども含めて記録され、指導や自立支援の資料として活用されている。
「障害者評価表」が毎年一回社内用に相談員・所属長から作成される。これは、基本的ルール、コミュニケーション、行動意欲、作業遂行能力の基本事項をさらに25項目に分けて各々7段階で評価をしている。生活も作業上の能力も皆それぞれ異なっており、目標に対して何が足りないか、相談員を中心に、それぞれの障害者の到達度を把握し会社全体として支援をしていく資料となっている。

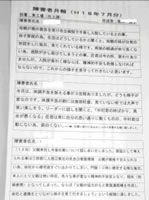
●社長の一言と社内の変化
「社長の一言」とはいえ障害者の配置に対しては、当初職場の抵抗があった。現場リーダーをはじめとした社員から、障害者雇用に反対する意見が出された。全員を集めて「賛成できないものは辞めてもらう」という強い会社の方針を示し、それでも意見を変えないものは個別に説得もした。背景に社長の強い意志があったことが、社内をまとめる大きな支えとなった。そして本気で障害者との作業を追及させてきた。
はじめは、定着を優先して極端に言えば「何もしなくていい」という時期もあったようだが、むしろ本人が社員のやりたがらない後片付けをすすんでやり始めた。その仕事は、薬品会社のGMP※や5S(整理整頓)に該当している大事な仕事であったが、本来業務でないことから社員が後回しにしていた事情のある業務であった。
その後、障害者との共同作業を継続する中で、「多様な仕事をこなすという器用さ」はなくても、ひとつの仕事に集中して「専門家」として習熟し、社員の嫌がる単調な仕事もすすんでやる彼らの姿と、お互いのさまざまな努力が継続する中で、「辞めさせては困る、いなければ仕事が回らない」と言わせるまでに周囲が変化している。
※GMP:医薬品の製造管理及び品質管理規則(Good Manufacturing Practice安心して使うことのできる品質の良い医薬品、医療器具を供給するために、製造時の管理、遵守事項を定めたもの。
●自閉症の女性
彼女は職業訓練校での一年間の研修で、職業能力は「大変優秀」との評価を得ていた。仕上げ作業のラインに配置して適性や順応性をみていたが、職場の作業者との連携が取れず業務の停滞がみられるようになった。本人は一生懸命がんばっているものの結果の良否の判断が付かないようで、周囲の人にいじめられているような誤解も生まれ、仕事への興味も半減し、半年経過後は遅刻早退が常習化して、会社も休みがちとなった。
ラインから構内の清掃作業に仕事内容を変更したが、親は「ウチの子は」という期待を持っていたようで、本人は親と会社の間に立って社内評価にも半信半疑となり、仕事への愛着を失っていった。
親との突っ込んだ話し合いの中で親の見栄や外聞、過度の期待を取り除き、本人のことを中心に考えた結果、フルタイムから9:00-14:30に就業時間の短縮を行った。
この結果、帰宅後好きな絵を描く時間が持てたこともあり、今まで受身だった仕事への取組みが意欲的に変化してきた。その「絵」を生活指導員や総務担当者に見せに来るなど周囲の人と接する態度も変化した。そしてISO環境ポスターコンテストに応募した作品が入賞するなど評価も得て、現在は生き生きと仕事に励んでいる。
3. これからの方向(いま考えること)
●精神障害者の雇用
ISOの厳格な規格の中で必要なことは、器用さではなくて目視による判断力である。現状、知的障害者に苦手な分野でも精神障害者は可能ではないか、と考えている。
うつ病などその特性から、拘束時間—インターバルをもたせて3時間交代で他の仕事に回る、とか、数を競うのではなく余裕を持った就業環境を整えていくことで雇用の範囲を広げようとしている。
●自立した人間を育てること
会社では知的障害者に対して、仕事を覚えることも大事だが、それよりも自分で生きていく-自立する自信を身につけることを会社で学んで欲しいと考えている。将来何らかの理由で転職したような場合、この事業所で習得した「技能」は他では通用しない。むしろ周りの人に喜ばれる生き方、社会で役に立つことの自信を持つ、それを肌で感じてもらうことを会社は目標にして指導している。
●「障害者」の評価を変えること
働いている障害者は、みな仕事はもちろん生活面でも成長している。
3年前、道路交通法改正で運転免許が取得できる道が開けた結果、3名が免許を取得した。
●働く者に必要なこと
健常者にとっても全く同じことが言えるが、障害者が社会に出て働く場合一番大事なことは、「時間の感覚」を身につけること、だという。
ハンディキャップからくる周囲への影響、仕事習熟の遅れなどそれは問題ではなく、それよりも大切なこと-それが時間の感覚を身につけることで、それが出来れば社会人として大丈夫、と総務担当者は言っている。学校にもお願いして、早速「3分間スピーチ」などを取り入れて実践してもらっている。
障害者は、それぞれの持分で仕事に携わり戦力となっている。トップ主導による企業の方針を確立して、総務担当、現場担当、指導員それぞれの職分にあるものがその考え方をキチンともって対応すれば、障害者は安心して能力を発揮できる、ということが足掛け9年で培われた経験の結果である。
執筆者 : 社団法人静岡県障害者雇用促進協会
障害者雇用推進技術顧問 中島 義夫
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











