合併により従業員数が約2倍に!行政からの働きかけを受け採用実績ゼロからの取り組みと担当者の思い
- 事業所名
- 株式会社ファインシンター
- 所在地
- (本社)愛知県春日井市
(滋賀工場)滋賀県愛知郡 - 事業内容
- 自動車用部品、鉄道車両用部品、産業機械用部品等に使用される粉末冶金製品の製造
- 従業員数
- 1,020名
- うち障害者数
- 15名
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 3 金型製作・プレス作業 肢体不自由 1 事務 内部障害 7 金型製作・製品検査 知的障害 4 箱洗浄・トレー清掃 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の沿革・概要・理念
(1)合併で誕生した会社
株式会社ファインシンター滋賀工場は滋賀県湖東地域にある。工場のすぐ近くには国道307号線が走り、北は彦根から南は甲賀、さらには大阪の枚方へと続いている。国道307号線は湖東三山として有名な寺院へのルートにあたっており、ことに秋の紅葉シーズンには東近江市、愛荘町地域にはたくさんの人たちが訪れる。
株式会社ファインシンター(2008[平成20]年1月7日より本社・愛知県春日井市)は二つの会社、ともに日本における粉末冶金業界のパイオニアとして戦後間もない頃に相次いで設立された旧・東京焼結金属株式会社と(旧)日本粉末合金株式会社との合併により発足した会社である。発足は2002(平成14)年10月1日であり、もともと滋賀工場は(旧)日本粉末合金株式会社(本社・京都市)の滋賀工場として1973(昭和48)年に開設されたものである。
株式会社ファインシンターの主要製品は自動車用部品(86.8%)、鉄道車両用部品(4.3%)、産業機械用部品(2.8%)、油圧機器製品(6.1%)となっており、大部分が粉末冶金製品である。
会社の基本理念は、『ものつくりを通し、すみよい社会と人々の幸せに貢献する』であり、長期方針として以下の3点を掲げ理念の実現に向け邁進している。
1.21世紀に勝ち残る企業基盤を確立する
・品質第一に徹し、魅力ある商品・技術の実現
2.良い社風を築き、地域に信頼される企業を目指す
3.明るく働きがいのある職場を築く
2. 障害者雇用の経緯、そして現在の雇用の概要
(1)採用実績なしから始まった取り組み
合併という出来事は障害者の雇用という意味においても大きな出来事であった。というのも合併後、従業員の数が約2倍になり、それにともない法定雇用率算定の基礎となる常用雇用労働者の数も2倍になったからである。2002(平成14)年に法定雇用率は未達成であったため行政から雇入れ計画(3年計画)を作成するように指導を受けた。その後、計画は立てたものの具体的な取り組みには至らず、2006(平成18)年になるまで、結果としては法定雇用計画に対し未達成状態となり、年月だけが過ぎていった。
そして2006年に入り、これ以上放っておくことはできないとの判断から、具体的な取り組みに向けての一歩を踏み出すこととなった。しかし、その時点では障害者の採用実績はまったくなく、何から始めればいいのか、あるいは何をどうしたらいいのか、すべてが未知数であった。もちろん障害者の雇用数がゼロであったわけではなかったが、在籍の障害者はいずれもが入社後に病気やけが等で手帳の取得となった中途での障害者であった。
(2)始められた具体的な取り組み:本社でのケース
2006年の1月、会社として、まず初めに出向いた先は埼玉障害者職業センターであった(当時、本社は埼玉県の川越市にあった)。そこで素直に訊ねた。「障害者の方を雇用するために何をどうしたらいいのでしょうか?」と。センターの担当者からの答えはシンプルで、それでいて的確なものだった。「まずは障害者の方を知りましょう。雇う側が勉強しましょう」と。そこである種のイメージ作り(「知る」ことを通じて「知らないこと」から生じる先入観や偏見に気付き、より実際の姿に近いイメージを喚起すること)を兼ねて、近隣の特例子会社と所沢市にある国立職業リハビリテーションセンター(以下、国リハと略記)を見学することとした。見学は管理部部長をはじめ、人事室長、人事担当者2名の計4名と限られたスタッフではあったが、見学をしたことによって認識は変化することとなった(それは後日、効果として現われることになる)。本社人事担当者は当時を振り返って、つぎのように語った。「見学させていただいた会社では知的障害者の方が多かったのですが、実際、黙々と仕事をされていました。これまで身近に接したことがなかったので本当に仕事ができるのかな?という[不安な]思いもあったのですが、きちんと教えることができれば、できるのだなと思いましたね。また、会社には手話のできる方もいて、[聴覚障害者の方が]一人で孤立しないように配慮もされていて、また車いすを使用している方もいて、扉は引き戸ではなくスライド式のもので、きちんと[環境を]整えれば、雇用できるんだなとも思いました」([ ]内は執筆者が内容を鑑みて、適宜補いました。以下、会話文中等の[ ]は同様)。
また、国リハを見学した印象についても、つぎのように語った。「会社で使用している機械と同じような機械、機器がありました。金型を造る機械もあれば設計で使用する機器もあったので、ここで勉強をして来られた方なら、すぐにでも雇用できるんじゃないかという感じを受けました。それ以上に、実際ここで、これならいけるんじゃないかという具体的な採用ができるイメージが湧いたのです」。そのイメージは後日、国リハからの3名の採用というかたちで一つの実を結ぶこととなる。
(3)始められた具体的な取り組み:滋賀工場でのケース
一方、滋賀工場としても本社から採用を進めて欲しいとの話があったが、その時点(2006年11月頃)では何をどう進めていいのか分からない状況であった。そこで近隣のハローワークに連絡を取り、まずは仕事場を全部見てもらうことにした。実際に「隅から隅まで」見てもらった。製造現場、廃棄作業、清掃作業、事務所等、それは雇用の可能性を探すことであった。その後、ハローワークの担当者から連絡があり、障害者職業センターで訓練している方(以前の会社を退職。知的障害者)と面談することとなった。面談の場で、実際に作業をしている様子を見ることもでき、また本人の自宅が工場からごく近いことも手伝って、話はスムーズに進み、結果、ハローワークの担当者に連絡をしたのが11月で、1月程の期間を経て仕事に来てもらうようになった。
(4)障害者雇用への思い—担当者として当時を振り返って:At That Time—
具体的な取り組みを開始した当時の思いについて、本社人事担当者・滋賀工場採用担当者はそれぞれつぎのように語った。
〔本社人事担当者〕
とにかく[雇用率の]数字を上げなければという思いで、あちこち走り回って、可能性のある方を紹介してもらおうと必死の思いでした。
〔滋賀工場採用担当者〕
とにかく初めてのことで、とくに最初から知的障害者の方で、どう対応していいのか? 本当にふつうに会話ができるのか?突然パニックに陥って暴れたりしないか? といった不安がありました。とくに面接の時、まったく無表情だったので本当に大丈夫かな? と。もちろん、今は一年を通して同じ部署にいますし、そういう違和感はありませんが……。
いずれの言葉からも、必死さ、あるいは経験がないことでの戸惑いのようなものが感じられるのではないだろうか?
(5)現在の雇用の状況
株式会社ファインシンターは滋賀工場を含め国内に5工場をもっているが、それぞれの工場で障害者を受け入れている。以下に工場および営業所での雇用の状況について記す。
◆川越工場(埼玉県)=7名
→聴覚2名(ともに重度) 内部3名(いずれも重度)
知的2名(うち1名重度)
◆山科工場(京都府)=3名
→内部2名(うち1名重度) 知的1名
◆春日井工場(愛知県)=1名
→聴覚1名(重度)
◆玉川工場(埼玉県)=1名
→肢体[下肢]1名(重度)
◆滋賀工場(滋賀県)=2名
→内部1名(重度) 知的1名
◆名古屋営業所(愛知県)=1名
雇用人数の合計としては15名となり、ちなみに2008(平成20)年1月末現在の雇用率は2.4%となっている。
3. 募集・採用活動の実際
(1)偶然の幸運
2006年1月から始められた具体的な取り組みのなかで、偶然の幸運が大きなきっかけ、そして当初の支えともなったようである。それは当時の本社から近い場所に国リハがあったということである。国リハの存在は採用活動においても実効性のあるものだった。国リハの紹介から採用へと至ったことも大きいことであるし、ある意味それ以上に、見学することを通じて身体障害者の方に限って言えば、一般の中途採用(正社員)と同じかたちでやっていけると判断できたことが大きい。今後のことについても、採用の際、求められる能力に劣ったところがなければ、一般の中途採用と同じ条件で雇用していく予定である。
また、採用選考の際に企業としての一線というか、譲ることのできない要素として自立通勤が可能であること」と基準を設けた。それは障害の種類は問わずに同様とした。
さらに知的障害者の方に関しては、こちらが言うことを理解できて、ある程度職業訓練ができている方とした。設けられた基準がゆるいものなのか、あるいは逆に厳しすぎるものなのかの議論はここでは不要であろう。大切なことは一般論ではなくて個々の事情を理解しようとすることであり、企業として求める基準を譲ってしまうことは採用後の定着を考えた時にあまりにも負担が大きいということである。なぜなら、「受け入れることの責任」以上に「受け入れた後の責任」はより大きなものとなるのだから。
(2)仕事の見直しから見えてきたこと
先にも書いたように、滋賀工場での具体的な取り組みの一歩は職域をつぶさに検討することであった。なかでも出荷の段階で製品は「通い箱」という専用の箱で出荷されるが、ユーザー(自動車メーカー)から戻って来る時には、箱はビニールに入ったまま、油もついたまま、ラベルもついたままの状態で戻って来る。そのためビニールを外して、油をきれいに拭いて、ラベルを剥がすという作業(箱清掃)を誰かがしなければいけなかった。しかもボリュームがかなりあり、それでいて作業自体がきわめて単純な作業でもあったことから特定の専任者が決まっていたわけでもなかった。この二つのこと、一つは誰かがしなければいけない仕事という意味で必要性の高い仕事であったこと、他一つは作業自体がきわめて単純な作業であったことが、知的障害者の方に向くのではないかという話につながることとなった。
また、作業の内容自体は単純でも環境は厳しい(屋外であり、夏は暑く冬は寒い)こともあり、この環境に見合う方がいるのかどうか不安な思いもあったが、障害者職業センターのカウンセラーに詳しく話を聞くことができて不安は杞憂に終わった。面接の場で、カウンセラーが言った「彼は内心喜んでいますよ」という一言で不安は払拭された。

(3)全社的に行った仕事の見直し
採用活動と平行しての仕事(職務)の見直し(トップダウン方式)は、本社および各工場それぞれで行った。具体的には全部門で、たとえば聴覚障害者であればこういった仕事、知的障害者であればこういった仕事というふうに仕事の洗い出しをした。その際、見直しが単なる便宜上の見直しになってしまわないように障害の内容によって、さらには最低でも一人は雇用するという方向で洗い出しを行った。結果は難しかったが、なかには「こうした仕事ならできるんじゃないか?」という声も聞かれ、いずれにしても企業トップからの指示が幅のある見直しを可能にした大きな理由ということになるだろう。
4. 取り組みの実際
(1)受け入れの状況
■川越工場:その1
滋賀工場とは事情がことなり川越工場では元々、「箱清掃」をする特定の専任者がいたが、あまりに量が多過ぎて仕事量に対して仕事が追いつかないという状況が続いていた。しかし、今では知的障害者(重度)との二人作業となり、追いつかないというような状況はなくなった。
一般的に知的障害者の作業効率を高いものとするためには単独作業よりはペア作業が適していると言われることがあるが、それは互いの関係性が良好である場合にしか当てはまらず、どちらかが過剰な無理や我慢をしてしまえば、ストレスの悪い影響が生じてしまう。
当初、すでに居られた方は年配者ということもあり温厚な性格で、この方であれば上手に指導してくれるんじゃないかという期待はあったが、知的障害者の方が賑やかな性格で話好きな上に、時にはじけてしまうようなところがあるにもかかわらず、懲りずに指導をしてくれている。そのお陰で定着もできており、ペアの組み合わせとしてはたまたま上手くいっている。採用当初はジョブコーチの支援を受けてもいたが、ジョブコーチは年配者がストレスを溜め込みすぎないかとの心配をしてもいた。
しかし、親子のような年齢の差が幸いしたのか、対照的な性格が幸いしたのか、指導というよりは一緒に仕事をするといった態度が幸いしたのかどうかは定かではないが、大きなトラブルもなく会社としては本当に助かっている、と本社人事担当者は語る。

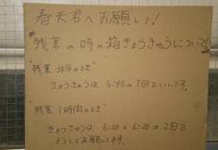
■川越工場:その2
金型製作の部門で二人の聴覚障害者(ともに重度)が仕事をしている。二人とも国リハの卒業生であり、雇用して半年が経過した時点で(時期は同時期ではない)ともに選考(正社員に登用するかどうかの選考であり、障害の有無による区分けはない)を行った。ところが後に選考を行った人の成績は芳しいものではなかった。それは国リハの職員から聞いていた様子とは違いが大きく、正社員には難しいだろうとの評価があがってくるようになった。それで「後々の採用にひびいてくることがあるかもしれない」との思いから何が問題になっているのか、それを理解しようと職場の同僚、さらには国リハの職員とも継続して話をしてきている。よくよく話を聞いてみると、やはりコミュニケーション不足——それは教え方の問題であったり、理解できているとしてきたことのすれ違いだったり、ほかにもいろいろとあるが——に起因することも出てきた。
会社の事情もあって、本人の周囲にいた人たちが別の工場に異動になり、指導者は新しい担当者に代わった。結果、これまで関わりがまったくなかったこともあり、コミュニケーションのステップはまた初めからとなってしまった。ゼロからのコミュニケーションは積み重ねられたコミュニケーションよりも緊張を強いることが多いが、「お互いに理解できていないところもあるし、いろいろ話をしながらやっていきましょう」と新たな関係づくりを模索している。
■滋賀工場
知的障害者を雇用するに際して、けっして大掛かりなことではないが、安全に作業ができる環境を整備することとした。まずは移動ルートを決めた。通勤用の車はこの場所に停めて、ここを通って入口を抜けて、タイムカードはここで押して、トイレに行く時はこの道を通ってというふうに。それというのも工場内はフォークリフトが頻繁に行き来しているので、接触のないルートを選ぶ必要性があったのだ。
当初はルートを覚えてもらうために指導員についてもらったが、今ではその必要はない。ただし作業場所は出荷場所でもあり、フォークリフトやトラックの出入りが激しいので、作業スペースを示す黄色いラインから外に出ないように話をしている。また、業者の方にもラインの内側に入らないようにお願いもしている。
しかし、本人も慣れてくると、悪気があるわけではなくても時に走ってしまうようなこともあり、周囲のものはそれとなく気にかけている。「過去に一度、接触しかけたこともあり、ヒヤッとしたことがあるので」と工場採用担当者は言葉を結んだ。

(2)接することを通じて学んでいく
採用後の定着に関して思うところを本社人事担当者に訊いた。
これまでにも障害者を雇用する際には、本社人事部として受け入れ部署の担当者に「この人」の特徴や、配慮が必要な点等について事前に話をしてきましたが、実際は、話を聞いているだけでは理解できないことも多く、ともに接してみて理解が深まることがほとんどの場合ではないかなとも考えていました。
やはり経験からしか学べないことはあるわけで、そのことができるためには受け入れを進めていくことが近道であるだろうし、今のところはそれ以外の道はないのではないかとも思っています。
滋賀工場採用担当者はつぎのように言う。
[知的障害者を]受け入れて間もない頃は従業員にも抵抗感というか、どう接すればいいのかわからないところがあった。朝、着替えるためにロッカーに行くと、いつもそこに立っていて、表情も無表情で、ちょっと困ったなと思っていた。しばらく経って、理解のある管理職の二人が話しかけるようになり、冗談で「副工場長!いつも早いですね」なんて調子で話をするうちに打ち解けていったのです。まぁ、彼はこういうタイプなのだろうと。話しかけてみると普通ですし。最初のイメージよりは馴染んでいけると思いました。それから半年、一年経ってみんなと打ち解けて、今では違和感なく「おはよう」という日々です。
今でも、朝は一番に来て立っています。雪の日は喜んで雪かきをしていてくれたりする。そういう姿がいっそう理解を深めていると思います。
始まりは理解している少数の人から、そして徐々に周りに広がっていく。やはり[定着に向けての取り組みは]人間関係が大前提です。
5. さいごに(何も特別なことじゃない)
(1)「これから」のこと
法定雇用率を達成しているからといって、それで終わりではないだろう。「これから」のことについて本社人事担当者・滋賀工場採用担当者がそれぞれに語ってくれた言葉を引こう。
〔本社人事担当者〕
未だ、知的障害者を受け入れているのは工場だけであり、そろそろ本社でも知的障害者の受け入れを考えていかなければいけない時期に来ているようにも思います。本社が移転したこともあり、それを契機にして、受け入れをしていきましょうという話はしています。活躍してもらえる場があるなら、活躍してもらうほうがいいに決まっていますから。
〔滋賀工場採用担当者〕
正直、箱の清掃はまだまだ人が足りていません。屋外の作業でもあり、環境は必ずしもよくはないのですが、環境の整備も考えつつ、[知的障害者を]受け入れていければと考えています。
(2)障害者雇用への思い—担当者として今、時点での思い:Now The Time—
これまで行ってきた取り組みを経た今、障害者雇用に対する思いを本社人事担当者・滋賀工場採用担当者はそれぞれつぎのように語った(当時と現在との変化をみるには2-(4)「障害者雇用への思い—担当者として当時を振り返って—」の項を参照)。
〔本社人事担当者〕
まず何よりも職場の雰囲気が変わってきたということ。ある人を受け入れることで、全然違う職場の人が話しかけてきたり、今までとは変わって、違う部署にいる人同士が話をする機会が生まれたり、雰囲気が明るくなったと思う。
不適切な表現かもしれないけれど、マイナス面だけじゃなくプラスの面もいっぱいある。従業員の気持ちが変わることで、それが自分たち自身の活力になっていけたらいいと思うし、雇用は義務だからという訳ではなく、その人が来てくれてよかったと思えるような雇用に変えていけたら嬉しいです。何よりも障害を持つ人への無理解が、身近で一緒に仕事をすることで解消していった。この事が人としての成長にもつながるのではないかと思います。
〔滋賀工場採用担当者〕
彼が入ることによって周囲の人(年配者や派遣社員)の負担になりはしないかと思うこともありましたが、面倒をみることが楽しみでもあるようです。職場が明るくなったということでしょう。冗談もよく飛び出すようになり、刺激にもなっているのではないでしょうか。結果としてはいい方向に向かったと思っています。
知的障害者を受け入れるまでは、受け入れることが初めてのことでもあったので、先入観(偏見)がなかったと言えば嘘になりますが、実際、徐々に理解が広まったと思います。もちろん職場の全員というわけではありませんが。そうした理解は外国人労働者と接することも多いので、同じように感じることもあります。
トラブルはないわけではないが、刺激がプラスというか、自分たちにもできる、けっして特別なことではないと思えるようになりました。
以上、これまで述べてきたように株式会社ファインシンターでの取り組みは偶然のきっかけから大きな効用へとつながってきたように思う。その経験はこれからも受け継がれていくであろうし、それが企業としての文化になっていくのかもしれない。

執筆者 : 社団法人滋賀県雇用開発協会 障害者雇用アドバイザー 緑川 徹
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











