雇用管理の担当者の配置と責任者による定期的な業務評価
~Aさんの雇用から今までの関わりを通して~
- 事業所名
- 株式会社ラウンドワン新御堂緑地店
- 所在地
- 大阪府吹田市
- 事業内容
- ボウリングを核として、アミューズメント・カラオケ等を複合させた総合レジャー施設の運営
- 従業員数
- 55名
- うち障害者数
- 1名
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 0 内部障害 0 知的障害 1 店舗内清掃 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の概要
当該事業所は、ボウリング場経営を中心とした複合型大型レジャー施設である。1980年に杉野興産株式会社として設立し、大阪府泉大津市にローラースケート場をオープンしたことが始まりである。1994年に株式会社ラウンドワンに社名を変更して以降は、関西を中心に店舗を拡大、郊外の道路沿いや繁華街の中心部に出店を続けている。現在では北海道から九州までの全国各地に約80店舗を展開している。
事例で取り上げるAさんは、大阪府吹田市の新御堂緑地店で勤務をしている。業務内容は営業中の店舗内外の清掃である。ボウリング場だけでなく、卓球場、ビリヤード場、メダルゲーム機等を設置しているアミューズメントコーナー、個室がならぶカラオケコーナーといった具合に、同じ建物の中に様々な娯楽施設が配置されている。そのため、建物外観から想像する以上に清掃作業の時間は必要である。ところが、Aさんが配属されるまでは専属の清掃スタッフがおらず、各施設のスタッフが接客作業の合間で清掃をする状況であった。Aさんが全ての施設の清掃を担うことで、店舗のクレンリネスが高まり、他のスタッフにとってもゆとりをもって接客に徹することができるようになったのは言うまでもない。
2. 取り組みの内容(業務内容の習得まで)
Aさんが当該事業所で雇用されるきっかけとなったのは、障害者を対象とした合同面接会である。長年にわたりパン製造補助業務やスーパーマーケットの商品陳列業務を休まずに出勤していた真面目さと、面接でのはきはきとした受け答えが採用の決め手となった。
Aさんの採用前には、1週間の職場実習の機会を設けることにした。清掃経験がないAさんにとっては、当該事業所の業務内容を把握し、配属先店舗の雰囲気に慣れるとともに、当該事業所で働きたいという思いを強く持つきっかけになる期間となった。また、障害者雇用を受け入れる配属先店舗にとっては、職場実習期間を通して確認したAさんのスキルを踏まえた上で、雇用開始までにAさんの職務内容を整理することにもつながった。さらに、Aさんと配属先店舗との間に入る支援者にとっては、事業所内でのナチュラルサポートにつなげるための支援計画を検討するためのアセスメントの場面にもなった。就職までの『回り道』にはなったものの、配属先店舗でAさんが無理なく働けている現在の状況を考えると、最初の段階での職場実習の機会は有効だったと考えられる。
前述のとおり、Aさんは清掃業務に従事することは初めてであった。そのため、当初は来店者数の多い土曜日、日曜日を休日として、比較的ゆとりがある平日を勤務日として、Aさんに時間をかけて確実に作業を習得してもらうこととした。必要に応じて支援者も現場に入っていきながら、段階的に作業を覚えていくことができた。
3. 雇用管理体制(Aさんとの『ホットライン』の構築)
(1)管理スタッフとの『すれ違い』を解消するために
当該事業所の店舗は、年中無休かつ深夜までの営業形態となっている。配属先店舗においても営業時間は午前10時から翌朝6時までとなっており、支配人を含めて店舗の責任者クラスは、Aさんの勤務終了時刻である午後5時から出勤することも多い。そのため、Aさんと『すれ違い』になり、Aさんの業務の習熟状況や作業上での疑問点を確認する等のコミュニケーションが不足しがちとなってしまう。
そのため、日中に受付業務を担当することの多いXさんが、Aさんの指導担当者としての役割を担うこととなった。Aさんにとっては、日々の作業場面で気付いたこと、疑問点などをその都度Xさんに報告して、確認が取れるようにしたのである。もちろん、Aさんの担当業務である清掃は店舗内外に及ぶため、業務の全てがXさんの目配りが行き届く状況ではない。だが、Xさんが定期的にAさんの作業状況を確認する等で作業全般を把握するようにしたり、他の施設スタッフからAさんの作業状況をXさんに伝えるようにする等の支援体制を作るようにしたのである。この取り組みによって、各施設のスタッフがAさんの作業状況にも関心をもつことにもなり、今まで以上にAさんが安心して業務に取り組む職場環境にもなっていった。
(2)付かず離れずの関係
こういった店舗内での支援体制は、仕事が慣れてきたAさんに対する働きかけでも効果を見出すことにもつながった。
Aさんが就職してしばらくたった後のこと、清掃作業に集中していたAさんは、そばを通りかかるお客さんに対して「いらっしゃいませ」の言葉かけができない、ゴミ袋の回収作業のときに、お客さんの横で作業をするときも何も言わない等の場面が目立つようになってきた。Aさんは「自分は接客業務に従事しているわけではないので、挨拶をする必要はない。お客様に挨拶をしても返事がないから声をかけないのだ」と、自分の考えをXさんに伝えていたのだという。それ以降のXさんは営業中の店舗での清掃作業ゆえ、お客様への挨拶の重要性を繰り返し伝えるようにしている。Aさんは当該事業所に就職する前に働いていたスーパーマーケットの商品陳列作業の際も、目の前の陳列棚の商品補充に集中するあまり、来店客と接触しても謝罪をしない等のトラブルが頻発していた。そういった同時に二つのことに気配りをすることが苦手なAさんの障害特性を支援者からXさんに伝え、現在の職場でのAさんに対する繰り返しの声かけに活かしている。
当初、Xさんからの注意があったときは、Aさんも意識して挨拶をする等の接客姿勢の改善がみられるものの、暫くするとどうしても担当業務である清掃作業を優先してしまう傾向があった。しかし、現時点では作業現場から付かず離れずで見守っているXさんからの繰り返しの声かけの成果もあって、Aさんの作業中での挨拶等の接客対応も随分と改善がみられている。


(3)無理なく作業をするための業務量の調整
小さなトラブルはありながらも、確実に作業に慣れてきたAさん。そういった作業への取り組みが評価されるにつれ、店舗が繁忙となる土曜日、日曜日が出勤日となる等、業務量も増え、配属先店舗の中での期待も大きなものとなっている。これはAさんにとっても仕事に対する責任感とやりがいに結びついているようである。
しかし、業務量が増えることによって、勤務時間内に全ての場所の作業を終えることができなくなっていった。全ての場所を限られた時間内で清掃しようとするAさんの焦りにより、作業全体が雑になってしまう状況にもなっていた。色々な作業をしたいというAさんの前向きさが、かえって全ての作業が不十分になってしまっていたのである。そのため、清掃作業の全ての『棚卸し』を行い、毎日二回清掃する場所、毎日一回清掃する場所、一日おきに清掃する場所・・・、といった具合に職務内容の整理を行い、Aさんが確認しやすいような『作業スケジュール表』を作成することにしたようである。営業中の店舗での清掃なので、混雑具合によっては、予定通りに作業ができない場面もある。そのため、その日の時間内にできなかった部分は、翌日に必ず行う等の作業現場の実態に合わせたものとなっている。『作業スケジュール表』をもとに、XさんはAさんの日々の作業状況を把握することができ、Aさんが無理なく作業ができるように作業量を調整する判断材料にもなっている。

(4)支配人による業務評価の設定
配属先の店舗は、アルバイト従業員が多く働いているが、全ての従業員に対して4ヶ月毎の雇用契約の更新時に支配人との評価面接機会が設けている。Aさんが就職する以前からの当該事業所での取り組みではあるが、障害者雇用の取り組みとして採用されたAさんも、他の従業員と同様に評価面接を受けることとなっている。面接の中では、これまでの4ヶ月の本人の業務状況を振り返るとともに、次の4ヶ月に向けた業務の取り組みのテーマについて支配人と意見交換を行っている。
Aさんにとっては、普段は接することの少ない支配人と面と向かって話をすることで、自分の仕事に対して見つめ直し、改めて初心に戻って業務に大切なことを確認する貴重な時間である。支配人による業務評価は、よい意味での緊張感を持続させることができる取り組みにもなっている。
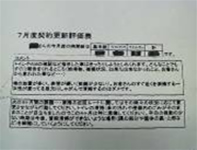
4. 今後の展望と課題
仕事に対する責任感は強く、一生懸命に作業に取り組むけれども、焦りや注意力の不足等からトラブルを起こしたり、やる気が空回りしてしまうAさん。これまでの長年の就労経験でも同じような失敗を繰り返してきた。今後も、真面目に取り組むあまりについ周囲のことまで気付かずに・・・といった小さなトラブルはあるかもしれない。ただ、当該事業所のような担当者による日々の声かけに加えて、責任者による定期的な面接機会を設けるといったしっかりとした支援体制があることで、Aさんによるトラブルを防ぎ、結果として長きにわたる安定した就労へとつながることも期待できる。
執筆者 : 財団法人箕面市障害者雇用支援センター 支援係 永田 祐子
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











