有能な医療スタッフの経験・知識は障害者雇用にも存分に活かせる
~ジョブコーチ支援事業の導入が契機~
- 事業所名
- 医療法人錦秀会阪和第二泉北病院
- 所在地
- 大阪府堺市
- 事業内容
- 患者様の「やさしく生命(いのち)をまもる」ために質の高い医療・福祉サービスの提供
- 従業員数
- 780名
- うち障害者数
- 18名
障害 人数 従事業務 視覚障害 1 マッサージ師 聴覚障害 2 介護 肢体不自由 3 一般事務・介護 内部障害 1 介護福祉士 知的障害 10 清掃 精神障害 1 清掃 - 目次


1. 事業所の概要
(1)理念
阪和第二泉北病院は医療法人錦秀会の「やさしく生命(いのち)をまもる」の基本理念に基づき、
一、患者様の人格と尊厳を最大限に尊重し、自立支援、社会復帰に向けた医療を提供します。
一、地域住民の皆様の健康維持・増進のために、質の高い医療・福祉サービスを提供します。
一、患者様、家族様に満足頂ける医療・介護サービスを提供し、快適な療養環境づくりに励みます。
一、職員一同、よりよい医療サービス提供のために常に自己研鑽に取り組みます。
以上の理念と基本方針の下に、四半世紀にわたって地域の高齢患者様に対する医療・福祉サービスを継続して行ってきた。
そして、大規模なケアミックス型の病院として、今後も地域の医療機関、介護施設等と密接な連携を取りながら、予防医学、急性期治療、慢性期療養、終末期医療と幅広い分野で「やさしく生命(いのち)をまもる」という法人理念のもと、ご高齢の患者様ならびにご家族の皆様の信頼にたる病院づくりをこころがけている。
(2)沿革
| 昭和55年11月開院 | 内科・外科・整形外科等各種診療科 |
| 平成16年10月 | 日本医療機能評価機構の認定 |
| 平成18年4月 | 阪和インテリジェント医療センター(HIMC)開設 |
最新鋭のPET-CT2台、全身MRIの導入による「がん」の早期発見、診断を行う。
現在、入院ベッド数は、療養病棟(医療保険適用)が514床、療養病棟(介護保険適用)が335床、障害者施設等一般病棟が60床、急性期一般床が39床、緩和ケア病棟が21床となっている(平成19年8月21日現在)
2. 障害者雇用に対する考え
「阪和第二泉北病院には、高齢者や加齢による障害を併せ持った方々が多数入院されている。この中で、対象者(患者様)の看護・介護にあたる看護師や介護士は、その方の目線に立ちつつ、病状や精神状態あるいは回復状態を的確に観察・分析した上で次への的確な対応を判断するという能力を充分に兼ね備えている。その能力を、当事業所で雇用する障害のある従業員への職務指示を行なう際や、職務経過を見守る際にも活用することで、職務に従事する障害者の個性や適性と作業能力等の把握及び理解を得ることができ、さらに愛情を込めた指導も行なうことができる」としている。
そのような高い能力を持ったスタッフの下での障害者雇用には、少しも不安を感じていないとの「自信」が窺われ、かつ雇用する障害者に対しても、病院のスタッフとして期待を抱いているとの思いが充分に読み取られる。
3. 障害者雇用の経緯
(1)障害者雇用の背景
法人による業務改善計画として、職員数の増加と業務の抜本的な見直し策が図られ、それまで外部委託していた業務を内部職員が行なう体制に移行する案が打ち出された。
具体的には
①8対1、6対1であった患者数対職員数の割合が、4対1に変更。
②病室の清掃なども介護職員が行なう体制である。
しかし、この体制によって職員が掃除に時間を取られ、病院の主たる業務である看護や介護サービスの低下につながる恐れが懸念されていた。
この改善策を実行する上にあたり、個々の病院だけではなく、法人全体の問題として取り組んでいた所に、「障害者を雇用することで課題解決策を検討」の話が持ちあがる。
障害者雇用に関し、法人が主導して業務改善計画を策定したことにより、各病院で障害者雇用に取り組む体制作りが加速した。各病院内では、看護師・介護士が行なうと看護・介護サービスの低下につながりかねない、「掃除の仕事」について、障害者が従事することで課題の解決策が図られることから、清掃業務に対する雇用に向けた検討が行なわれた。
(2)障害者雇用の始まり
障害者雇用は最初に、阪和第一泉北病院から始まる。職務内容の指導はもとより、一般的な職務遂行上の指導ポイントなど試行錯誤の後、大阪障害者職業センターとの相談により、ジョブコーチ支援事業を活用した障害者雇用体制を構築した。
それを受けて、平成18年の春、阪和第二泉北病院では最初からジョブコーチ支援事業を利用した、障害者雇用形態をスタートさせた。
雇用開始初年度は、ジョブコーチまたはその他支援者(障害者施設職員、関係機関職員)(以下「ジョブコーチ等」という。)のコーディネート等に時間がかかり、採用目標の11人を雇用するまでに1年の年月を要したが、ジョブコーチ支援事業の活用で、病院スタッフによる指導・清掃の時間が少なくなり、介護サービスに専念できるというメリットもあり、看護・介護スタッフからは歓迎されている。
今回、知的障害の従業員が1人、配置転換されたことにより、新たにもう一人の雇用を予定しており、合計12人になる見込みである。
4. 障害者雇用の実態
(1)知的障害のある従業員の職務内容
職務内容は、病室の清掃(拭き・掃き・ベッド等柵の拭き掃除)、ゴミ集め、食堂の清掃(拭き・掃き)に限定される。
障害のあるAさんに対し、雇用に向けてジョブコーチ等による指導の下、最初に取り組んだ時の清掃手順は別紙の通りである。(ただし、本人の習熟度・作業スピードの向上により時間・場所・手順が変更になる可能性もある。)

(2)雇用形態と労働条件
他のスタッフは看護師等の資格を持っているため、給与体系は清掃勤務を行う知的障害者と他のスタッフとは別体系になっている。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 勤務日数 | 4週8休 | |
| 休日 | 基本的には土・日休み(週休2日制) | 担当課長の判断等で変更の場合あり |
| 勤務時間 | 午前9時~午後5時(休憩1時間) | |
| 給料 | 時間単価750円 | 時給月給制 |
| 保険等 | 雇用・労災・健康・厚生 | |
| 契約期間 | 1年更新 | 更新日3月20日 |
(3)障害者採用のプロセス
(ⅰ)選考方法
ジョブコーチ支援事業等を利用する為、障害者求人情報は必ず、公共職業安定所を通して行われる。
公共職業安定所での求人を基に就労を希望された方は、まず、大阪障害者職業センターで、障害者職業カウンセラー(以下「カウンセラー」と略す。)による、病院での清掃作業、手順・注意事項などの説明を受ける。一方、カウンセラーは、希望者の職業評価を行い、その希望者がどの程度の能力を持ち、どの程度まで仕事ができるかを見極め、ジョブコーチ等の支援体制をコーディネートし、公共職業安定所及び事業所に報告する。
それを受けて事業所側は、公共職業安定所および障害者職業センターからの紹介順に、事前に順番を決めていた各病棟の清掃場所、勤務場所への配置を決める。
(ⅱ)指導の方法
障害者の配置場所が決まれば、担当のジョブコーチ等と各病棟の責任者が相談の上、詳細な作業手順・方法・タイムスケジュール・必要物品(複数枚の雑巾・ピッチ等)の準備の依頼等、作業を進める上で必要な事項を決定する。また、病棟責任者とジョブコーチが相談しても処理できないことが起こった場合は、採用担当部長に相談し決定する。
ジョブコーチ等は病棟責任者に配置を予定している人の特性や性格、考慮すべき点などについて説明し、人的な面も含めて、働きやすい環境を作り出すように努める。さらに、障害者が作業する上で支障が生じた場合、本人・病棟責任者と相談した上で問題解決に取り組むこととしている。
阪和第二泉北病院では、障害者雇用に関してはジョブコーチ等が大変重要な役割を担っており、採用担当部長も「ジョブコーチ等の支援がなければ、障害者雇用はかなり難しかっただろう」と話しておられた。
以下に障害者雇用のプロセスを図式で紹介する。
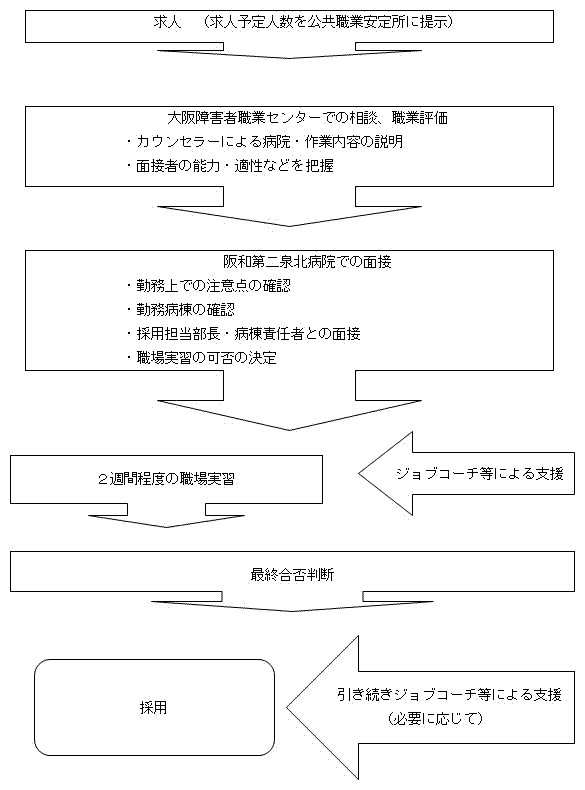
5. 障害のあるスタッフの就業安定のために
(1)ジョブコーチ等による支援
阪和第二泉北病院では、2週間程度の職場実習時にジョブコーチ等と実習生との関わりを通し、病院スタッフが実習生の性格や関わり方を理解する期間としている。
職場実習中は実習生の障害特性や性格をよく理解しているジョブコーチ等が、実習生の動きや環境面で配慮すべき点を観察しながら、職務遂行上必要な助言を行う。そして、支援を行う上で必要と思われる点(ソフト・ハード両面での環境整備)について病棟責任者と話し合う。途中で問題が発生した場合、実習者・病院側が納得できる一番良いと思われる解決点を見つけ出し、双方に提示し納得・了解してもらう。
それと並行して、実習生の作業能力に応じて、一日のタイムスケジュール・一週間の流れを作成し、病棟責任者にも提示する。協議の上問題がなければ、そのプログラムが行えるよう支援していく。
一方、病棟責任者は、実習期間中、ジョブコーチ等と実習生との関わりを観察しながら、本人の特性、性格を的確に把握して、ジョブコーチ等がいなくなった後のアプローチの仕方を理解し、考えていく。この実習期間は、本人が病棟で作業・環境になれるための重要な期間であり、病棟責任者にとっても、本人の様子を観察する為の重要な期間である。
阪和第二泉北病院では現在障害のある人が11人雇用されている。それぞれにジョブコーチ等が支援している関係上、アフターケアー等で訪問する機会が多い。その際、担当以外の障害者とも関係作りを行い、その様子を観察するなかで、問題点があれば本人に助言を行うこともある。それでも解決しない場合には、担当のジョブコーチ等に連絡し改善に向けて調整をはかるように努めている。
(2)就業生活上の課題解決に向けて他機関との連携
障害のあるスタッフは、施設・訓練校を経て就労された方がほとんどである。家庭や日常生活上の問題点がある場合、ジョブコーチ等を通じて出身施設の支援者に連絡・協力を依頼し、病院スタッフとも連携をとりながら、問題解決に取り組む。
6. 総括
人事担当部長(以下「部長」という)は「障害者雇用に関して、特に理念はないし、配慮もしていない」と話しておられたが、あるジョブコーチは「部長のその様な話は謙遜である。何もないところから、部長は11人もの障害者雇用を実現させた。その為にジョブコーチ等の制度について研究をし、安定した雇用につながるものは積極的に取り入れた。また、雇用現場から上がって来た必要なものについても、出来るだけ取り入れようとする姿勢を示し、働きやすい環境を作りあげてきた。このような事例は、今まで障害者雇用をしてこなかった企業にとっては、大変参考になるものであるし、このような事例は他の機関・企業にも、もっと理解されるべきものと思われる」と話していた。
一方、障害のある人を受け入れている現場責任者は「現在雇用されている人の性格や特性に合わせて指導している。本人の状態・性格を見ていて、厳しく指導しても効果が現れないと思われる場合は、本人が一番理解しやすいような、言葉掛けや態度で接する。また、言葉ではなかなか理解できない所もあるので、実際に私がやって見せて、理解させるようにしている。その後、本人が出来ているかどうかの確認は、きちんと行っている」と話しておられた。その様な姿勢・指導方法は、ジョブコーチ等による支援を利用する中で確立されたものであるが、忙しい業務の間をぬって、障害のある人たちの職場定着に努力している姿には、頭が下がる思いがある。
この阪和第二泉北病院の事例は今後障害者雇用を考えておられる企業にとって、参考になると思われる。また、このような優秀なスタッフを持っておられる病院では、障害者雇用に充分に対応できると思われる。
執筆者 : 大阪市職業リハビリテーションセンター 指導員 吉田 浩巳
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











