みんなが主役のイキイキした職場
- 事業所名
- NTNテクニカルサービス株式会社岡山事業所
- 所在地
- 岡山県備前市
- 事業内容
- 親会社(NTN株式会社)へのテクニカルサポート事業や業務請負事業
- 従業員数
- 180名
- うち障害者数
- 4名
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 1 工場内のレーン作業 内部障害 0 知的障害 3 仕上げ・梱包作業 精神障害 0 - 目次
1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯・背景(夢の発信地を目指して)
「これからの企業は売り上げの拡大、利益はもちろん大切なことであるが、地域、社会との共生、地球の環境保護をしていくことも大事である」と親会社であるNTN株式会社の長期ビジョンの中で“人を活かし、社会貢献するグローバル企業の考え方”が打ち出された。その具体的な社会貢献の施策の一つとして「障害者、特に知的障害者の経済的な自立の支援をするようになったのです」とNTNテクニカルサービス株式会社岡山事業所(以下「NTS株式会社」という。)のウェルサービス部の高津部長は雇用の動機を話してくれた。
ここで、NTS株式会社の会社概要と障害者雇用の取り組みの経緯を追ってみると、NTS株式会社は、NTN株式会社の中高年齢者の受け皿会社として発足し全国に5事業所がある。従業員約680人で、機械装置の製作・改造・治工具管理のテクニカルサポート事業や業務請負事業等を行っている。障害者雇用については、2004年に静岡県の磐田製作所で、障害者主役の職場を目指してミニ福祉工場“夢工房”を立ち上げたのを皮切りに、続いて2005年には、三重県の桑名製作所、そして、この岡山製作所は3つ目の工場となる。岡山製作所でのきっかけは、2005年10月から実習生として受け入れていた隣接の養護学校の生徒Aさんが2006年に卒業するということで、会社が引き続き採用して3月27日に正式に職場を立ち上げたという事である。
言うまでもなくNTN株式会社岡山製作所は、障害者雇用には大変理解を持っており、障害者雇用率も2.37%と法定雇用率を大きく上回っている。しかし、社会貢献というには、障害者雇用に対し受け身の姿勢ではなく更に一歩踏み込んでという思いから、グループであるNTS株式会社において、働く場が制限されている知的障害者の経済的な自立を支援するようにと方針が出され、それを受けての取り組みである。そして、“夢工房”というネーミングは、働く障害者にとって夢の職場であり、NTN株式会社グループにとっても一つの夢でもあるので障害者雇用の発信地になれたらいいなあという思いで名付けられた。
2. 障害者雇用の方針(夢工房の運営ルール)
運営を担当しているNTS株式会社の方針は、実に明確で分かりやすい。今後、障害者雇用に際しての方向性として、他の企業でも大いに参考となるものと思われる。
つまり、「障害者を雇用するのだから赤字はしょうがない」では、これからの雇用の拡大は望めないし、維持運営も途中で息切れしかねない。何とか部門赤字を出さない工夫をして「障害者職場はお荷物職場」という風にはしないようにとの考え方である。数字の目標は直接人件費、直接経費ベースで収支トントンを目指している。障害者の雇用は、「ボランティア活動ではない」さりとて「障害者を雇用して儲けようとも思っていない」との位置づけである。
3. 取り組みの内容Ⅰ(障害者が主役の職場づくり)
障害者雇用の先進企業を数多く回り、研究してきただけに、高津部長は「障害者が主役となって働ける職場を目指しています」とも語ってくれた。障害者が、ただ働いているだけでは主役ではない。現在では、補助作業やお手伝いという要素が強く、これから生涯イキイキと働いて自立してもらう為には、責任を持って仕事をしていく場が必要なのではないかという思いからである。それゆえにいままでの障害者雇用とは変わった形で職場を提供したいと、ラインに組み込むのではなく、専用の職場としたのである。主役である以上、障害者だから作業能率が低いのはしょうがない!品質が心配だから健常者がダブルチェックするという事では信頼性の向上につながらない!その為には、従来の発想を転換しなければならない。いままでの様に障害者を健常者の作業レベルに強引に合わせるのではなくて、障害者の不足している能力を個々に見つけて、それを補助する道具づくりをする。健常者の仕事のやり方を決して無理強いしてはいけない。それでは生産性向上に限界があるとの結論に至ったのである。そうでないとこの職場に仕事が獲得出来ないことになるからである。また、本人にもちょっとした補助をすることで、”ちゃんと仕事が出来てますよ”という声掛けで仕事における達成感を感じてもらっている。出来たら褒めることを一番心掛けているところであり、それによってモチベーションを高めてもらい、結果「生産性向上と品質保証面の信頼性向上」につながると確信しているからだ。写真①にある“完成品通い箱”のビニール掛けが上手く広がらないので、ビニール袋の底の大きさと同じ底板を作成した。写真②“バーコード貼り治具”については、身長や箱の大きさで角度や幅調整が可能となった。これはNTS株式会社の技術者が夢工房の生産性をあげる為にAさんをはじめ障害者の身体的特長を考えて作った代表的なものである。



4. 取り組みの内容Ⅱ(家庭との交流ノートで定着支援!)
備前市のNTN株式会社岡山製作所の正門を入ると、目の前に“夢工房”の建物が見える。室内に入ると作業中であるが、元気の良い声で「いらっしゃいませ、ようこそ」と3人の障害者の方と2人のサポーターの歓迎をうけた。気持ちがシャキッとし、背筋の伸びる思いであった。目に飛び込んできたのは、従業員が着ている白い作業服であった。製造会社では汚れが着きやすいので、大変珍しい。見るからに清潔で安全な作業環境であるという事がすぐに想像出来た。さほど広くはない作業場だが、整然と片付けられ、床面には通路ラインが引かれており、4S(整理・整頓・清掃・躾)もきちんと守られていた。又職場の壁には手作りポスターで、そこでの作業上の注意や心得、又片付け、清掃のポイント等がわかりやすく書かれて掛けられていた。作業工程版(連絡版)には一際鮮やかに、カラーで視覚に訴えていた。出勤者や休暇者、今どの作業が行われているかの進行状況、又達成したのかを、リボンを貼り付けてリアルタイムに一目で分かるようにしている。働きやすい、分かりやすい工夫が随所に施されていた。丁度、作業中のところを見ることが出来た。NTN株式会社で製造された軸受を、出荷用にセットしているところであった。まずバラ荷の製品コンテナから軸受を5個ずつ木の棒に差し込み、形を整えて保護シートの上に置き、そして、棒を抜き、製品を包み込んで一つのブロックにし、ビニール袋を下敷きした「完成品通い箱」の中に入れる。4ブロック入れると一定形成にする為にビニール袋の覆いをかぶせ、バーコードを貼れば、これで一工程となる。この作業をAさんを始め3人で役割分担して行っている訳である。慣れてきたので前後の工程まで理解できて、仕事をしているとの事であった。以前は、健常者のパートの女性がこの作業を行っていたが、写真②にあるようなAさんやその他の障害者の個々の能力に応じた治具・工具の補助具をNTS株式会社の技術者が作ることによって、いまではパートの従業員を超える生産性を誇っている。「よくぞここまでになった」と高津部長は目を細める。
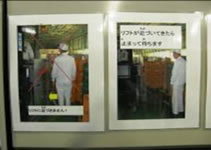

【知的障害者の不安を解消する工夫】
知的障害の従業員はサポーター2人が出勤なのか休暇なのかがわからないと不安になって仕事ができないことがあるので、出勤者・休暇者が一目でわかるようにこのボートに従業員の顔写真を貼っている。

【障害者の業務管理と雇用管理の工夫】
仕事の内容と、作業個数についても構造化されている。表の上部に障害者の氏名が書かれており、今日の作業の内容、数量等がすぐわかるようにしている。また、作業が終了するとマグネットを裏返し作業の進行状況も一目でわかるようになっている。
Aさんはコミュニケーションが取りにくい発達障害を持っている。「今日まで会社で仕事を続けられてきたのは、ご家庭の支援のたまものですよ」とも語ってくれた。働くことによって被雇用者となっても障害が無くなった訳ではない。会社へ全部任されても十分なことは出来ない。Aさんの家庭はその点、会社ときちんと連絡をとり、障害に向き合って何とか自立をさせていこうと努力をされていた。そこで、息子であるAさんのことを少しでも知ってもらおうと、定着支援の為に協力して欲しいと会社に願い出て、家庭と会社の間で交流ノートをつけることにした。会社は、最初Aさんのことが分からないことばかりなので、体調のことや気分など色々質問を書いて、答えをもらっていた。最近ではご家庭の方から働き方や会社での生活などについて継続して情報提供とご提案をいただきながら、コミュニケーションを図っている。との事であった。
一般企業へ就職するだけでもなかなか難しいものであるが、定着していくとなると、一歩も二歩も踏み込んで家庭も会社も支援していく必要があるのではないだろうか。Aさんの家庭との交流ノートは現在数冊にもなっている。障害者本人の就労意欲も必要だが、ここら辺りが継続就労をしていく一つのポイントとなるのではないかと感じた。
会社では、障害者とのコミュニケーションを図る為、誕生会・花見・家族を含めた忘年会などの福利厚生にも力を入れており、カラオケは大の人気だそうである。又、Aさんはマラソンが得意で蒜山マラソンには連続して出場しており、あのオリンピック選手の山口衛里(天満屋)さんに伴走してもらったそうだ。(ハーフマラソン自己ベスト1時間25分10秒)
5. 取り組みの効果(社員に与えるメリットも大きい)
この“夢工房”から、社会貢献以外に企業が得られるものは?との問いに・・・働く姿勢と道具づくりですネ。ひたむきな働き方、作業姿勢に感動し、物づくりの原点に気づかされ、忘れかけていたものを思い出させてくれる。職場に入ると背筋がピーンと伸びますネ。又、道具づくりも金をかけ、エネルギーを使った自動化改善ではなくて、原点に返った知恵と工夫で簡単な道具を作るだけで、生産性・品質が向上するというのが示せるようなものを再認識させられました。と答えが返ってきた。
NTN株式会社グループが理念としている「新しい技術の創造と新商品の開発を通じて、国際社会に貢献する」との考え方にピタッと合うものとなっているとの事。まさにこれが障害者雇用のメリットと言えるのではなかろうか。
6. さいごに(スタッフの夢)
Aさんの雇入れから始まった夢工房岡山、仲間も増えてきて現在3人となった。現在サポーターを2人付けているが、今は慣れていなくてもそのうち運営のノウハウも身に付けていくと思われるので、現状スペースで5名ぐらいまで雇用しても今のスタッフで十分サポートできるのではないかと思っているとの事。「やがては特例子会社が出来ればいいなと思っています」と夢を語ってくれた。特例子会社があるとどんな良さがあるのか?との問いに・・今のままだと社会・地域の人にそんなにアピールする訳ではないので、「ここに障害者専用の職場がある」っていうことが分からない訳ですね。特例子会社にすればいちいち宣伝しなくても、NTN株式会社グループからも認知され、世間からも認知される。そして、障害者のお子さんを持っている親御さん達にとっても、「うちの子もあそこで働かせたいなあ」と就労に向けて希望を持って養育していく、そのきっかけになればとの思いからです、との答えであった。広い工場の一角にある“夢工房”であるが、まさにNTN株式会社グループの夢の発信地となる日もそう遠くないのではないか。4つ目の夢工房“夢工房金剛”も施設に仕事を提供するという形で進んでいる。又、事務部門においても障害者雇用を積極的に進めたいと、本社事務所では現在検討しているとの事。近日中にインターン制度にのって雇用にトライアルする予定である。
最後に高津部長から「夢工房岡山の2周年を目前に、企業の社会貢献のあり方を、単に障害者を雇用していくだけでなく夢工房を通じ、地域企業経営者の方へ障害があっても健常者と変らない作業が出来ますよ。保護者の方には、頑張って自立に向けた養育(基本的生活習慣の自立)と、働きたいという動機付けをしていれば就労のチャンスが広がるんだ」というメッセージを発信していかなければならないと話してくれた。
素晴らしく、新しいこの取り組みが順調に進んでいくよう期待をしている。

執筆者 : 人事労務コンサルタント 山本 豊郎
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











